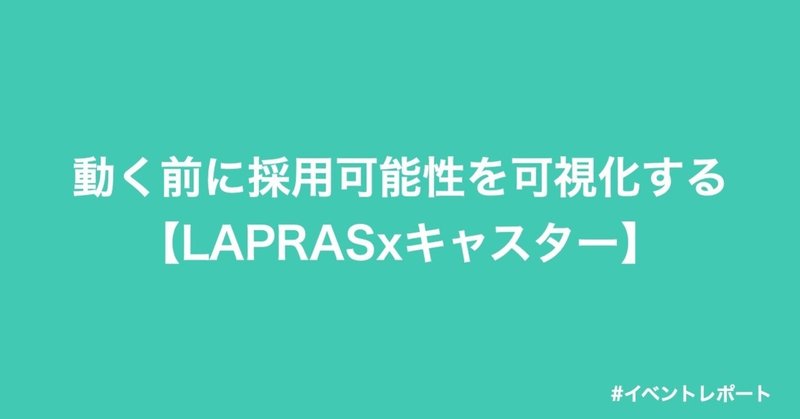
動く前に採用可能性を可視化する【LAPRASxキャスター】
概要
日時:2020/05/21 16:00〜
場所:Zoom
ターゲット:エンジニア採用の担当者、など
・LAPRAS株式会社 取締役COO 二井雄大
・株式会社キャスター/CASTER BIZ recruiting 事業部長 森数美保
内容
進め方
アイスブレイクのあと、それぞれがLTを行い、最後に主に参加者の質問に答える形でパネルディスカッション、という流れで進みました。
(文中敬称略)
アイスブレイク
「コロナの影響で採用活動に変化はありましたか?」
・企業の採用スピードが上がっている(森数)
・スカウトで今まで動かなかった人が動いたことがあった(二井)
採用要件定義のやり方(二井)
現場が本当に必要としている人材が本当に必要な人材と限らない。そのため、人事主導で行ったほうがよいこともある。
どういう事業フェーズ、どういう課題がある、どういう点を強化したい?などをしっかり考える。
求めるスキル感をmustとwantで仕分けする。
どういう切り口だとその候補者に刺さるか?自社の何を強みにして、候補者に訴求出来るか?
・言語、ジュニアが成長出来る、デザイナーと働ける、顧客と近い、著名なエンジニアがいる、など…
→ 採用競合に対し自社が勝てるところはどこか?をまとめる
要件定義後はレビューをしっかりする。
・すぐに採用する必要があるか?その場合要件は下げることができるか?など
採用難易度に合わせた採用戦略(森数)
・市場
欲しい人がどれくらい市場にいるのか?競合はどれくらいいるのか?
→ 数が多く、競合が少ない、市場で戦う必要がある
・入社時期
緊急度がどれくらいか?
・会社の状態
候補者を引きつける材料があるか?採用に対応出来る人数はどれくらいか?
どうすれば難易度が下がるか、を考える。
市場の部分では、積み上げると、スーパーマンが欲しい、になってしまう。しかし、そもそも採用で解決したい課題ってなんなのか?を考える必要がある。実は採用以外にも解決する方法があるのではないか。そうなると採用したい要件も変わるかも。
競合が少ない場所で戦う必要がある。母集団がどれくらいいるか?はなかなかわかりづらいので媒体の担当者などと連携する必要がある。
自社で戦える武器があるならそれを磨くことが大切。ないなら増やさないといけない。とにかく社員を巻き込み、協力者を増やす。
パネルディスカッション
・例えばピンポイントでRailsのテックリード人材が欲しいとした場合にどう動くか?
(森数)1名のみ、なら、エージェントを使う。最初は10社程度に声をかけ、よいところ2,3社に絞っていく。
(二井)Ruby会議に参加している社内エンジニアに声をかけ、リファラルを狙う。その後、ダイレクトリクルーティングを行う。
・社内の巻き込み方はどのようにすればよいか?
(二井)同じ目線にもっていく。立場としてイーブンな関係性を築く。採用を成功させる、という目的は同じはずなので。ポジション毎にチームビルディングが必要になるが、その方がよい。
(森数)エンジニア全員とディスカッションをしたことがある。どんな人と働きたい?なぜそう思うのか?を聞いた。それによりポジションへの理解が深まり、エンジニアにも自分ごととして受け止めてもらいやすくなる。
・高い選考体験を与えられる選考フローとは?
(二井)採用に関わる人が全員同じことを言っている必要がある。どういう人がなぜほしいのか?が正しく一貫していると、本当に欲しいと思われているということが伝わり、辞退率も減るのではないか。
(森数)どうすれば会社を好きになってもらえるか?を考える。その会社で一番会社を好きな人や、キーマンとなる人を見つけて関わってもらう。(代表や役員であることが多い)
→ 役員を巻き込めない、のなら、最終面接まで役員には関わらないでもらいたい(二井)
・6〜12ヶ月後に採用したい、など長期的に考える場合にはどうすればよい?
(森数)採用をしない時期にも採用活動は続けるべき。どんな時期にどんな人がほしいのか、を考えて発信を止めないことが大事。
(二井)後のためにコンテンツのストックを作っておく。また、時期がわかっていればそれを見越して早めにターゲットに声をかけておく。半年後だとその人の状況も変わり、転職に前向きになっているかもしれない。
・企業の認知度が低い場合はどうアプローチすればよいか?
(森数)優秀なエンジニアがいる、などテックに強いと印象づける。そのためにどうするか?を考える。
技術ブログに力を入れる、勝てるフィールドを見つける、など。とはいえ武器がない、と思った場合は、直近で入社した人がなぜ自社に決めてくれたのか、を聞くと優位性が見えるかもしれない。
・SNSでのスカウトについて
(二井)得意な人がやればよいと思っている。普段からどれくらい自然に発信しているか?慣れていなと大変になる。
・オンラインで採用活動を完結することは可能か?
出来るはず。
企業側よりも、候補者から見た時の情報量が減るはず。オフィス訪問がない、など。それを踏まえたりして、気持ちよく選んでもらうためにはどうするか、が重要になる。
感想
LAPRASさんはほとんどスカウトによる採用を行っていることもあって、どうすれば候補者にちゃんと選んでもらうようにするか?を考えて設計している気がする。ミスマッチが起こらないように詳細な情報を公開したり、社内のエンジニア全員と話す機会を作ったり、とか。それを作る、要件定義をする過程で、「本当に必要な人材」が見えてくる、ということかな、と思ったりした。
冒頭に出されてた、顧客が本当に必要だったもの、の有名なイラスト。
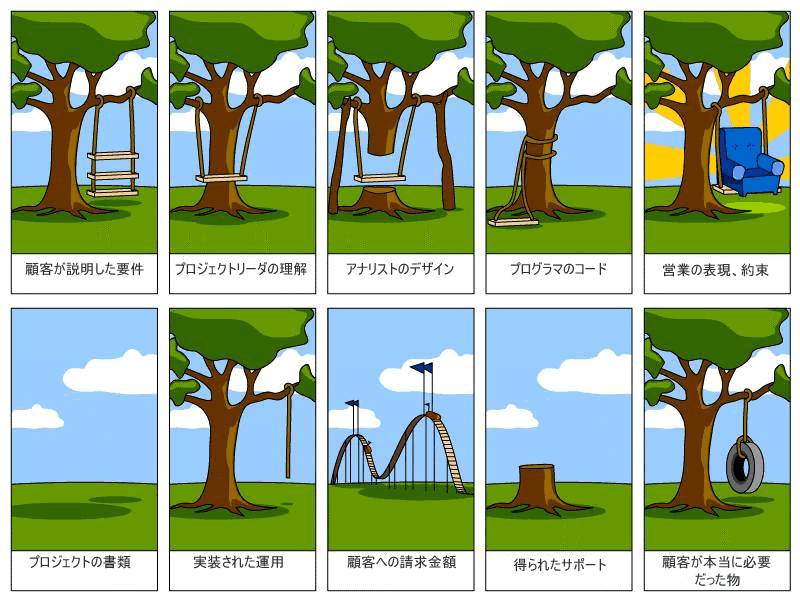
(元ネタとかはここに詳しく載ってるよう)
https://www.businessballs.com/amusement-stress-relief/tree-swing-cartoon-pictures-early-versions/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
