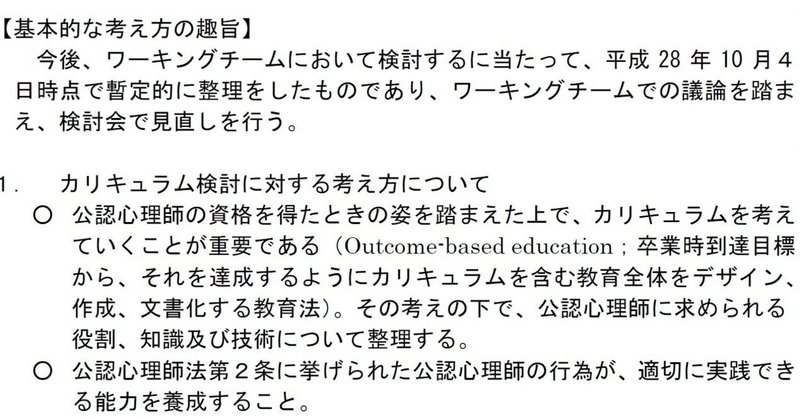
公認心理師カリキュラム等検討会を振り返る(第2回:平成28年10月4日)ー検討の骨子ー
さて、第1回の検討会から2週間後の2016年10月4日、航空会館7階大ホールにて第2回目の検討会が開催されました。今回は、ワーキンググループを設置するにあたり、そこでどんなことを検討するかという議論です。
議事録や資料は以下のURL(厚生労働省:公認心理師カリキュラム等検討会)で見ることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_380707.html
公認心理師のカリキュラム等に関する基本的な考え方
前回の検討会ででた意見を基に、公認心理師のカリキュラムに関する基本的な考え方を事務局が作成しました。資料の趣旨としては、今後ワーキングチームでカリキュラム等を検討するに当たり暫定的に整理したものとのこと。ワーキングチームでの議論を踏まえて、今後この基本的な考え方についても、検討会で見直しを行うことも事務局から説明されていました。
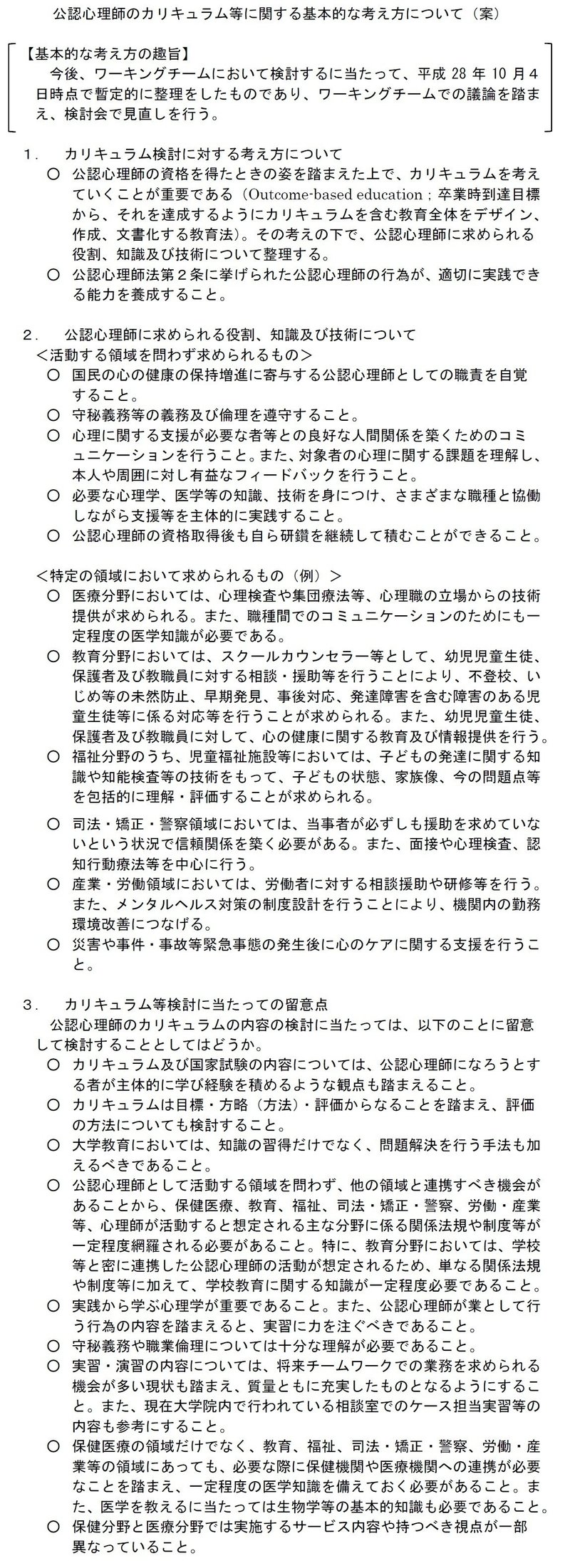
「カリキュラムに対する考え方について」への意見
川畑構成員 カリキュラムを考える上で重要なポイントは、どこに比重を置くのかということに結局なってくる。全ての領域についての実務的知識をなるべく盛り込むのか、全てに通用するような共通の能力を高めることを目標にするのか。そのバランスの取り方でカリキュラムの方向性が変わる。
北村座長 2.の所にどこの分野に行っても求められるものと各特定の分野が書いてあって、その重さみたいなものは人によって感じ方が違うかもしれない。国家資格ですから、ある一定の基準を、自分はもう就職は小学校に決まっているんだといっても、医療のことはそれなりには勉強しないといけないとは思います。だから国家資格として必要な各専門分野の知識、経験というのは、あるのかないのか、どの程度かというのは後で議論したい。
子安構成員代理長谷川氏 この資格は汎用資格ですので、心理学について幅広く学ぶことが求められる。法第2条には「心理学に関する専門知識及び技術をもって」と書いてある。現代の心理学は、心理学を大きな柱とし、その両側を生物学的な考え方と、人文社会科学的な考え方がしっかり支えるという、Bio Psycho Socialというモデルが標準になっているので、そういう方向でカリキュラムを考えていただければ。
北村座長 国家資格ですので、学者を作るわけでもないという面もあり、学問と実学のバランスというのも難しいとは思う。
林構成員 医学教育のカリキュラムがOutcome-based educationという形で変更になったと聞いた。どういう変更が、これまでの医学教育の中で加えられたのか。
北村座長 今まではプロセス重視、Process-based education。内科学、外科学、整形外科、などの単位を集める。それでいい医者になるかというと、そうではなかった。話を聞けない、人の顔を見て言えない、十分説明できない。国家試験を通る知識は持っているけれど、患者さんにとってはいい医者ではなかった。社会が進歩し、科学も進歩し、社会のニーズも変わる、それをちゃんと取り込んでいける。あるいは生涯にわたって勉強していける能力がある。いろいろな能力を考えると、内科、外科、整形外科という、いわゆる今までの学問体系だけで教えていてはいけない。コミュニケーションも教えなければいけないし、実習では学問ではなくて態度ですね。お辞儀の仕方みたいな、そういうことも含めて、人の話を聞くとか、そういうことも教えて、全体として国民に望まれる医者を作ろうという形に変わりました。
大野構成員 (公認心理師には)非常に総合的な能力が必要とされ、その養成に力を注ぎたい。ただ、特に臨床心理士養成大学院において、公認心理師の受験資格を提供できるカリキュラムの内容を備えることが望まれる。今回議論されているカリキュラムにおいて、スーパービジョンやケースカンファレンス、あるいはケース指導、そういうものをかなり綿密にやっている内容を、そのまま移すというのは非常に厳しいものがある。公認心理師養成においてそういう 緻密なスーパービジョン必ずしも必要としないのではないか。 総合的な臨床心理アセスメントとか、全人格的な個人心理療法の習得に関しては、従来の臨床心理士試験によって判定されるべきものではないかと考えている。そういうことも考えて、従来の臨床心理士養成の訓練が徹底されるということが、非常に重要だと思う。それぞれの特性をどのように生かすか、互いに連携することが、質の高い臨床心理サービスが提供できると考えている。共存共栄と我々が呼んでいる、そういう体制が出来ることを願っています。
川畑構成員 スーパービジョンの下での継続的な相談面接の教育が公認心理師の中に生かされないというのは非常に残念である。Outcome-basedで考えたときに、しっかり相談ができる、コミュニケーションが取れるというところの研修をしっかり積んでもらうためには、今の臨床心理士の大学院でやっている教育はミニマム。それすらないカリキュラムの編成については、このあるべき姿という点から考えると、少し問題があるのではないか。
大野構成員 どういう形で協力できるかということを念頭に置きながら、高度の専門職を育てるためには必要な部分もあるだろうということです。例えば、施設について基本的な学習、特にロールプレイとか、そういう内容については十分に活用できる話。
北村座長 医者は、医師国家試験を通って医者という資格は持つが、社会は一人前とは全然思ってない。せめて研修を2年間ぐらい終わって、やっと1人でやれるかというイメージ。公認心理師、臨床心理士の感じもそういう雰囲気に行くのかなと。やはり国家資格は最低の資格です。それがなければ患者さんにお話を聞くこと自体も本来は駄目。業務独占ではないので、法律上は問題ない、イメージとしては、やはり国家資格は最低限それを取ってもらって、そこの中で技を磨き、信頼されるようになるには、それなりの国家資格を取ってからのトレーニングが要ると思う。だから、住み分けはできる。
【ここまでの感想】
今回は最後にまとめて感想を書こうと思ったのですが、我慢できずにここで一旦書きます。
一つ目は、汎用資格ということで5分野想定されている。共通のスキルもあれば、ある分野で特に求められるものもあるので、そのバランスをどうするか。これをこれからワーキングチームで検討するという事ですが、個人的には、国家資格は最低限のスタートラインと考え、養成期間は共通項目をしっかりと身につけて、分野ごとに特化した部分は現場に出てからOJT等で身につけるのがスムーズだと思っています。養成時の分野ごとの教育は、OJTへスムーズに繋がるためのプラグ作りのようなイメージで。
二つ目、なぜOBEなのかという医学教育の経緯も面白いですね。国家資格なので、国がわざわざ法で定めて作る資格なので、高度な専門技能を保証する訳です。ただ、あまりに専門の所ばかりやっていても上手くいかなかった。話を聞けない、人の顔を見て言えない、十分説明できない、対人援助の基本的なところを見落としていた感じでしょうか。上ばかりを見ていると足下をすくわれる的な。公認心理師の場合はどうなのだろうか、ワーキングチームで検討されるのでしょう。
三つ目、また臨床心理士がでてきました。何ですかね、私の色眼鏡のせいでしょうか、カリキュラムを検討するための方向性を議論している段階で、「そのまま移すというのは非常に厳しい」とか「緻密なスーパービジョン必ずしも必要としない」とか、どうして言えるのかなぁ。これはこの後検討していく事じゃないのかなぁ。ここでは川畑構成員の意見の方が、これまでの議論を踏まえた上で妥当のようにも思います。資格認定協会と養成大学院協議会、どっちも臨床心理士関連の団体ですけど、そこでこれだけ意見が食い違う。どうも認定協会としては“臨床心理士は今のまま残す、という前提で、差別化できる形で公認心理師を作りたい”という意図があるように感じてしまう。つまり、臨床心理士のためには公認心理師の質があまり高いと困ると。臨床心理士の下位資格として公認心理師を作りたいと。私が穿って見過ぎなんでしょうか。まぁ、この辺りもカリキュラムの内容含めて議論されていくでしょう。
「公認心理師に求められる役割・知識及び技術について」への意見
活動する領域を問わず求められるもの
鉄島構成員 守秘義務等も当然重要だが、所見などが当事者なり関係者から開示を求められる場合も今後は多々あると思う。根拠に基づいた説得力のある文章なり所見をきちんと書けるという能力は、等しく重要な専門性かと思う。
佐藤構成員 他職種協働ということでいけば、いわゆる古典的な守秘義務では対応できない。ましてや先生がおっしゃったような開示要求、特に精神科の場合には非常にデリケートな秘密を扱う。守秘義務については義務及び倫理としないで、是非この辺は鉄島先生がおっしゃったことも含め、細かく丁寧に議論していただきたい。
米山構成員 子どもの虐待防止の中で、守秘義務を超えて、いわゆる家庭の背景だとか、お子さんのことについてというのは、情報を共有すべきというものが出ている。これは法律のことも含むのかもしれないが、その辺りもきっちりと学んでいただきたい。仕組みはあるが、地域ではまだまだ使われていない、オフレコでというようなことになっていることが多い。学校にもそれが全部入っているので、そういうものを使うと、きっちり法的な中で情報交換が行えるようになっている。
北村座長 守秘義務と言っていて、かえって命を失ったりする事例があるので、こういうのこそプロフェッショナリズムで教える。原則守秘義務が当たり前でが、それを超えるようなことがあるということも理解してもらう。
川畑構成員 災害や事件、事故等の対応というところ。通常の業務でのクライアントの危機的な状況であったり、普段の自分の職場でない、いろいろな場所に行って仕事をすることも多いという点で言うと、緊急事態、危機事態に柔軟に対応できる力を持っているというのは、かなり心理師に求められる能力かと思う。特定ではなくてジェネラルのほうに載せていただくのも1つかも。
北村座長 仕事でないオフで、医者だと怪我人を見て対応しなかったら怒られそうな気がする。心理にもそういうのはあるのか。
川畑構成員 倫理上の問題が少し絡んでくる。そういう職業的な関係を持つべきなのか、同僚あるいは地域の同じ市民として関わるべきなのかという部分の線引が非常に微妙。
北村座長 でも緊急事態であれば、例えば自殺企図が明らかだというようなときは、仕事でなくても然るべき人に通報して、然るべき保護をお願いするというのはありますよね。災害も含めて、緊急事態のほうは、領域を問わずの方向に移しましょう。
佐藤構成員 「必要な心理学、医学等の知識、技術を身につけ」。精神医学というのをこの段階で入れていただけるものかどうか。
北村座長 当然、医学の一分野の精神医学という理解でよろしいか。
佐藤構成員 今後どこの心理の先生方が、どこの現場に行かれても、これはもしかしたら精神疾患かもしれない、あるいは場合によったら薬物依存かもしれない、そういうことは大変多いと思うので、基本的なところで枠組みとして認識して、精神医学というのをもう少し位置付けていただけないか。
北村座長 「心理学・医学・精神医学」と書くと、精神医学と医学が違うかなと思われる。取りあえずここでは医学にして、その次の特定の所、あるいはワーキンググループで、どれぐらいの精神医学を必要なのかというのを議論したい。
村瀬構成員 この心理職というのは人の生き方の根本に関わっていくような仕事かと思う。例えば家族の問題、これは全て教育からいろいろなこと、病気になったときにはどうという、そうした生きることの根幹というのは、社会の仕組み、つまり行政についての基本的な知識。それから法律、例えば家族の問題についても、4年ほど前に長らくそれがもとになっていた家事審判法が、家事事件手続法に変わり、家族というものに対して、もう少し国が積極的に関わるべきではないかという理念が盛り込まれている。
そういうことを学びながら、しかし手続でここは法律家が判断する所、ここは家族療法の中で考えていくという、これまでモヤモヤとしていたところを、別のセンスとしてきちんと勉強することが必要。知識とか技術の中に、行政とか法についての勉強が要る。
北村座長 それはもっとも。自分が心理学が面白いからと特定のことばかりやっていても仕方がない。公認心理師は社会のニーズを捉えてほしい、そんなところも含めて、言葉を何か考えましょう。
釜萢構成員 公認心理師がいろいろ業務に携わる中で作成された記録が、診断とどう関わるのか。共通の認識の下にカリキュラムが作られなければいけないので、その辺りで特に精神科医が行う診断と、どのような整理になっているか。
林構成員 診断は医師の専権事項。診断が付いた患者さんに、心理職に心理面接あるいは集団療法等の依頼を出すという手続。治療の過程の中で情報が心理に伝わったときに、診断の見直しということはあり得るが、積極的に診断に関わるということは今のところない。
川畑構成員 診断は医師の専権事項だが、医療領域では、そうした診断が共通言語として使われないといけない部分もあるので、それについての学習は今後必要。精神医学的な意味での診断とは別の側面からクライアントのいろいろな状態について把握する。それがまた逆に診断に生かされるとか、そういう貢献の仕方は今後あるべきではないか。
釜萢構成員 心理のアセスメントというのはどういう意味を持って、法的な責任がどのように生ずるのか整理されないと、公認心理師が業務をする上で、非常に問題になってくるのかなという危惧を抱いた。
北村座長 第2条には「心理状態の観察とその結果の分析」までで、診断ということは書いてない。あとは助言とか治療です。これを、カリキュラムにしっかり反映させていくことが大事。教育の分野では診断とは言いませんよね、自閉症などという診断はしないのですよね。
米山構成員 学校では診断でなく、やはり特性で。そういう疑い・心配があるというところで見立ている。全てが診断をということではない。見立てという中で、診断名を求められることが医者としてはある。ただ、対応についてはその特性をということで済んでいる。
小児保健のレベルでは、診断がまだ付けられないお子さんたちがたくさんいます。見立ての部分で、傾向とか特性がありますというレベルで、心理師と御家族の支援にそれで当たっている。病院レベルでの診断と、領域ごとにその辺りの見立てたときの伝え方というのは異なる。
特定の領域において求められるもの
米山構成員 医療という所の中に保健分野というのは全然違った形での領域だろう。医療の下でもいいと思うが1項目加えて。
福祉の分野の「児童福祉施設等」という所に、障害児施設がいつも統計上抜かれてしまうことも多いので、「障害児施設を含む福祉施設等」と。
北村座長 1点目は福祉も関係しますね。逆に福祉の方に子どもしかなくて大人が抜けている。
佐藤構成員 障害福祉サービスという大変広大な領域があります。
渡邉構成員 福祉というと、児童相談所の今の仕事は子ども虐待対応が中心。連携として、お医者さん、ワーカーさんと言うか福祉司と。児童指導員、保育士さん、子どもの生活に直接関わる方たちとの連携を学んでもらうのも大事。
北村座長 年寄りの虐待もあるので、虐待に対して連携を取って適切に対応できるという文言があってもいいか。
佐藤構成員 福祉の所は、児童もあれば虐待も高齢者の問題もある。先ほどの障害者の問題もよろしくお願いします。
子安構成員代理長谷川氏 医療分野なのですが、欧米での心理療法の主流が認知行動療法。集団療法もありますので、併せて認知行動療法もキーワードとして是非。高齢者に関連して、認知症の問題が現代社会では極めて大きい。認知症に関して、福祉分野になるかと思いますが追記して。
石隈構成員 教育分野では、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを将来的には正規の教職員として規定する方向で検討が進んでいきます。スクールカウンセラー等の前に、「チーム学校」と入れて「チーム学校」の一員であるスクールカウンセラー等という表現に。
山中構成員 「不登校、いじめ等の未然防止」となっていますが、中学校ですと暴力とか非行とかもあるので、そういう側面も是非。
「発達障害を含む障害のある児童生徒に係る対応等」と書いてあるが、対応と広がりすぎて、もう少し限定できないか。
診断ではないが、個別の指導計画を作るときに心理職の方が心理検査をして、この子はこういった特性がありますということをとても参考にしている。心理検査というものは教育のところにはないのですが、そういう側面も強くなってきている。
学校の場合は学校組織全体にいろいろ協力していただくこともあるので、組織へ介入していただくこともある。
北村座長 ワーキンググループにはそのとおりしっかり伝えて、組織に対する介入とか、心理検査のこととか、そういうものを盛り込んでもらうようにしたいと思います。
栗林構成員 産業領域の所で、メンタルヘルス対策の「制度設計を行う」というのは望みすぎ。企業におけるメンタルヘルスケア活動は、軸足がかなり個人のパフォーマンス向上、ひいては企業業績の向上に移っている。それを阻害する要因として不適応問題。そういう問題を解決するのに、心理的視点以外に、マネジメントスキル、人事労務的な問題、組織論が必要。メンタルヘルスケア活動全体の制度設計という所を要求するのは望みすぎ。
北村座長 確かにそう思う。他には。
佐藤構成員 特定領域の扱いが大変難しい。汎用性との絡み。当面は、汎用性のベースを充実させて、それで司法であれ福祉であれ医療であれ、それをある種のサブスペシャリティ的にやらないと、なかなか教育でも医学の問題が必要だという話にどうしてもなってしまう。
北村座長 ワーキングではその点を是非議論したい。試験で各分野にとんがった細かいことを聞いても仕方がない。職場に入ってから勉強することで。かと言って、総論だけで済むわけではなく、医療、教育、福祉等々の分野ごとの問題も当然出てくるが、それほどとんがった細かいことは聞かないという感じではないか。
「カリキュラム等検討に当たっての留意点」への意見
大野構成員 カリキュラムの内容によって大学、大学院の在り方が非常に影響を受ける。学部卒5年という受験資格を得るための内容を、しっかり検討する必要がある。学卒者について、所属する分野以外についても知識を習得し、現場実習をする必要がある。心理業務の能力習熟に加えて、他の分野と連携するために、他の分野に関する基礎知識を習得し、現場実習をするために、勤務しながら他分野で実習し、週末に講習を受けるというようなことを、職場ごとに保障していただけるような環境の確保が必要。
もう1つは、それなりの心の専門家としての専門性に秀でた人材をしっかり養成するという、ある意味モデル事業に一致するような内容が臨床心理士養成の大学院の中にある。特に臨床心理分野専門職大学院について、臨床心理士師受験資格に加え、公認心理師受験資格を持つ教育課程として制度化され、幅広い領域を包含した即戦力としての人材を輩出することができるという点からも、国民の心の健康に寄与するものと期待される。そういう意味で、臨床心理分野専門職大学院がより発展的な方向に進むことができるということで、是非考慮をお願いします。
北村座長 専門職大学院は幾つぐらいで、定員は。
大野構成員 6大学院。20~30人ぐらい、大学院によって違う。
北村座長 受験資格に関しては、いろいろな意見がある。落とし所も全然ないが、ワーキングでしっかりと議論したい。ただ、附帯決議があるので、それだけもう少し確認。
付帯決議の確認
1.『臨床心理士をはじめとする既存の心理専門職及びそれらの資格の関係者がこれらまで培ってきた社会的な信用と実績を尊重し、心理に関する支援を要する者等に不安や混乱を生じさせないように配慮すること。』
2.『公認心理師が臨床心理学をはじめとする専門的な知識・技術を有した資格となるよう、公認心理師試験の受験資格を得るために必要な大学及び大学院における履修科目や試験の内容を適切に定めること。』
3.余りカリキュラムには関係ないので割愛
4.『本法第七条第一号の大学卒業及び大学院課程修了者を基本とし、同条第二号及び第三号の受験資格は、第一号の者と同等以上の知識・経験を有する者に与えることとなるよう、第二号の省令の制定や第三号の認定を適切に行うこと。』
※第1号…大学と大学院卒業者
第2号…大学の卒業者で実務経験を積んだ者
北村座長 附帯決議は医者の臨床研修のときも付いていて、附帯決議だから聞いても聞かなくてもいいのかと思ったら、とんでもない。法律と同じぐらいの重みがあり、結構痛い思いをしました。衆議院と参議院で同じ決議がされているので、しっかり遵守したい。その心は、大学を出て大学院を出るというのを主とし、それと同等の実力がある大学プラス実務経験、あるいはそれ以外のルートを従とする。従とは書いてないが、それと同等の実力をある者とするということで、大学院を出るということが主。
今、大野委員がおっしゃった、そういう大学院がまだ少ないが、しっかりあるり、附帯決議もある。大学院で何を教えて、何を学ぶかということをまず決めて、それと同等の資格は実務でどうやって得るのだという話になる。それでよいですか。
林構成員 大学院課程がある国家資格が果たしてあるのか存じませんが、四大卒後実務経験を得るコースもあるということは、大学院課程において医学部における五年生、六年生のように、実習、実務経験を十分に積むことを想定すべきではないか。特に医学領域の実習を重視していただきたい。
なぜかと言うと、かなり多数の方が医療領域で仕事をされると思う。医療のことを大学院の実習の中で学ばないというのは不都合。
四大卒後実務経験が、主ではなくて従であるとおっしゃられて非常に残念。現場の中で学ばなくてはいけないことが心理職には多くあると思う。実務現場で学ぶ実務経験の時間数と、大学院で学ぶ実務経験の時間数を勘案して、年限を決めていただく形にしていただきたい。
北村座長 かつては、大学院といえば研究者を育てる組織。今は専門職大学院という実学を学ぶ所。当然現場に出て学ぶことが多くなると思うので、先生がおっしゃったことは十分反映されると思う。
それから、卒前と卒後が両方つながって、公認心理師の資格を取ってからも、また医者でいう研修医のような時代にもっと経験を積んでもらう。資格を持った上でやることと、資格を持っていないでやることでは、話を聞くのは同じようだけれども違うと思う。資格のある人の頷き方と、資格のない人の頷き方では、クライアントに与える影響も違うので、それをシームレスにつなげていったらいいと思う。こういったところを、ワーキングでやる。
川畑構成員 大学院での実習は大事だと私も思う。もう1つ、実習を実際に心理的に役に立つ形にするために、それを橋渡しする理論の勉強もとても大事。大学院ではそこのバランスをきちんと取った形でのカリキュラムを整備し、2号に関してはそれに同等であることがきちんと保障される人に与えられる制度設計をすることが重要。
北村座長 実習、実務経験のときも指導体制は当然問われる。単に実務をやって何年だけでなく、指導者は誰がどういう形で理論を教えたかということが大事。
石隈構成員 附帯決議の臨床心理士をはじめとする既存の専門職は、極めて重要なところ。どこで線引きするかはとても難しい。大学院レベルで心理職についていろいろな検討運動をしてきた3団体等の意見を参考にすると、(臨床心理士の他に)学校心理士、臨床発達心理士、特別支援教育士、それからガイダンスカウンセラー等が大学院レベルの資格。これはワーキンググループ等で検討の1つに入れていただければ。
北村座長 移行措置、現在活動している方に対して公認心理師の資格を与えるのは当然のこと。そんなに難しいことをして仕事を失うようなことをやるものではない。知識でマルバツ試験をやるという無茶はやめて、経験や実績を十分評価できるような移行措置があって然るべきとは思っている。ただ、名前だけ臨床心理士で長いことやっている人は、やはり排除をしないといけない。しっかり実務をやっていることが担保されないと。
佐藤構成員 大学院教育が問題になっていますが、実務経験ですとどうかということで、要は今後の体制カリキュラム、学部教育が今までとは様変わりするはず。従来の教育制度であれば、学部は様々な分野の方が指定大学院に入られて受験資格を取られて臨床心理士になること自体が問題ではないかという議論がずっとあった。今度学部教育でカリキュラムがしっかりすれば、大学院の意味合いは大分変わる。そうなれば、大学院における実習と四大卒でそのまま実務に入ったことと、十分に肩を並べられる。それを、旧来の大学院の研究者養成のカリキュラムと比べたら、それは少し落ちるかもしれない。しかし、国家資格の職能としての公認心理師として必要条件は十分に満たすだろう。
北村座長 ところで資料を見ると、臨床心理士の試験合格率が6割ぐらい。公認心理師の試験も皆さんはそのようなイメージですか。医師国家試験は、新卒者が95%。ところが、95%も合格するのに、多くの大学は最後の6年目の半分ぐらいは、国家試験対策であったり、予備校がはびこったり。せっかくカリキュラムで実習をたくさんやろうと、現場に出ようと、実務をやろうと、大学院でそのようなカリキュラムを作るにもかかわらず、もし大学院の2年目は国家試験対策でマルバツの試験ばかりをやったら何の意味もない。国家試験対策はしないで、実習を思い切りやってほしい。ですから、国家試験は実習をやった人は通るけれども、机の上の勉強をした人は落ちるみたいな、そんな問題を作ってみたいなと思う。
村瀬構成員 大事なことはサービスを受ける当事者がどう体験しているか。体験した人がその人の状態の改善にそれがどう反映していくか。カリキュラムや科目を考えていると、提供する自分の視点にウエイトをおいて考えがち。受ける人がどうかという視点を持っていることが必要。
こういう議論をすると、もう少しこういうものが必要、この科目が必要だと。どれが要らないということはないが、大事なことは受ける当事者にとってどうだろうかという原点。細かい技術論ばかりに走らない。私は、ある種の専門分化した力量をしっかり身に付けながら、しかしバランス感覚をもって、何が必要かという基本がしっかり身に付いている公認心理師が生まれるようなカリキュラムを、ワーキンググループで作っていただきたい。
カリキュラムというのは箱を並べたようなもので、それをどう教えるか。同じカリキュラムでも、誰がどのようなことを配慮して、どういう工夫をするかによって全く中身が違ってくる。教える人、研修を指導する人をどうするかということを、どこかいつも念頭に置きながら、こういうことを考えていくことが必要。
大野構成員 臨床心理士は60%、大体一定の合格率を維持している。試験のは、100問のマークシート、小論文、面接という3つの独立した指標で評価。1つでも問題があれば評価が低くなることも含めて、結果的には60%。しかも、修士課程の2年生になっても実践をやっている。2年生の段階から、実際に外から来るクライアントに対して対応している実態があり、しかもきちんと報告書までしていないと受験資格を認められない大学院もある。今後も臨床心理士養成に当たってはこの試験体制を堅持していきたい。
公認心理師について、そのような特色をうまくいかすような試験制度を確立していただければ。
北村座長 国家試験ですが、医師のときにはあったが、情報公開を請求され、正解まで書いて、判定基準まで公開している。ですから、論文や面接をどういう客観的根拠をもって判定しているのかということも、情報公開で請求されるので、ある程度科学的なものでないと辛い。論文や面接はかなり難しいように、個人的には思う。しかし、入れたいなと思う一面もある。
それから、○の2つ目にあるように、広い意味でカリキュラムは方法も含む、場合によっては方法も指定したい。ケースカンファレンスで学ぶこととか、単なる黒板で学ぶのではないということまで指定はできると思う。
米山構成員 3条の欠格理由には、いろいろな障害の方についてはもちろん入っていない。裏返してみると、4月からの障害者差別解消法の合理的配慮のカリキュラム実践、実習、試験についても、是非そこも組み込んだ形で入れていただきたい。
子安構成員代理長谷川氏 心理学がほかの学問とどこが違うかというと、非常に総合的な学問。基礎科学としての側面も、応用科学すなわち社会に貢献するという側面もある。自然科学的な部分も、人文科学的なところもある。学部教育においては4年間の学びの集大成として、できる所では卒業論文、卒業研究、あるいはグループでも構わないと思うのですが、今まで座学で学んだことを実際に応用して総合的に自分で問題を発見して解決していく能力を、是非カリキュラムの中に組み込んでいただければ。
学部のほうで総合人間科学の基礎を満遍なく学んで、大学院では実践に関して十分な実習時間、特に学外での十分な実習時間を取っていただければ。
北村座長 正におっしゃるとおり。
釜萢構成員 四大卒で実務経験を積んで受験資格を得る場合に、指導者はどのような形でそこにおられるのか。そして、四大卒で実務経験を積んだ方は、どのぐらいの人数を考えておられるのかを教えてください。
松本主査 実務経験などの指導者のレベルについては、現時点では決まってない。ワーキングチームで御議論いただければ。人数も現時点では分かっていない。
佐藤構成員 資料に日本精神神経学会の要望書があり、先生がおっしゃったようなことについても検討している。精神科領域については、精神科専門医を指定されている医療機関で何とか対応したいという議論がある。大学院の場合の実習先は、今、地元の医療機関で既存の大学院の実習を受けている。これからは、やはり一定の施設基準、指導者の基準は、これからは専門医制と同じように必要になってくるのではないかとは思っている。繰り返しですが、精神科についてはそのような議論は出ている状況。
村瀬構成員 実は日本心理研修センターを立ち上げたときに、幾つかの役割として、これから心理学のスタンダードというものを定めていく。そして、その上に実践をしていくときの実力をステップアップしていく段階を、公共性のあるものにしなくてはならないだろうということで始めている。2年計画で、指導者としてどうことが必要なのか、何が課題になっているのかというような実態調査。現場ではどのような能力を持った人を必要としているかを調査し、そのようなデータを基にしながら、今話題になっているような指導者をどのように、質はどれぐらいで、どう決めていくかということの基礎データになるようなものを研究しているところ。2年計画で、来年の9月頃にまとめができる予定。
北村座長 医者の研修の場合は、厚生労働省の局長の判子のある研修終了証を持っていないと、指導者として認めてくれないという制度もある。ただ、それは義務化されている制度ですから、ここで言う実務経験とは質が違います。ただ、やはり指導者の資格みたいなものは必要かな。
川畑構成員 現在日本の大学は少子化の中で生き残りのために大変な状況。学部卒で現場に出る人たちの心理士としての資質保障に関して、これはかなり危惧すべき部分もあることを御理解いただけたら。
北村座長 深い話で、反応しにくいです。
ワーキングチームの設置について
ワーキングチーム開催要綱(案)に沿って松本主査から説明が行われました。タイムスケジュールとして、ワーキングチームを年内に6回くらい、そして年明けから検討会に戻って2、3回おこなって素案を整理する方向性も示されました。
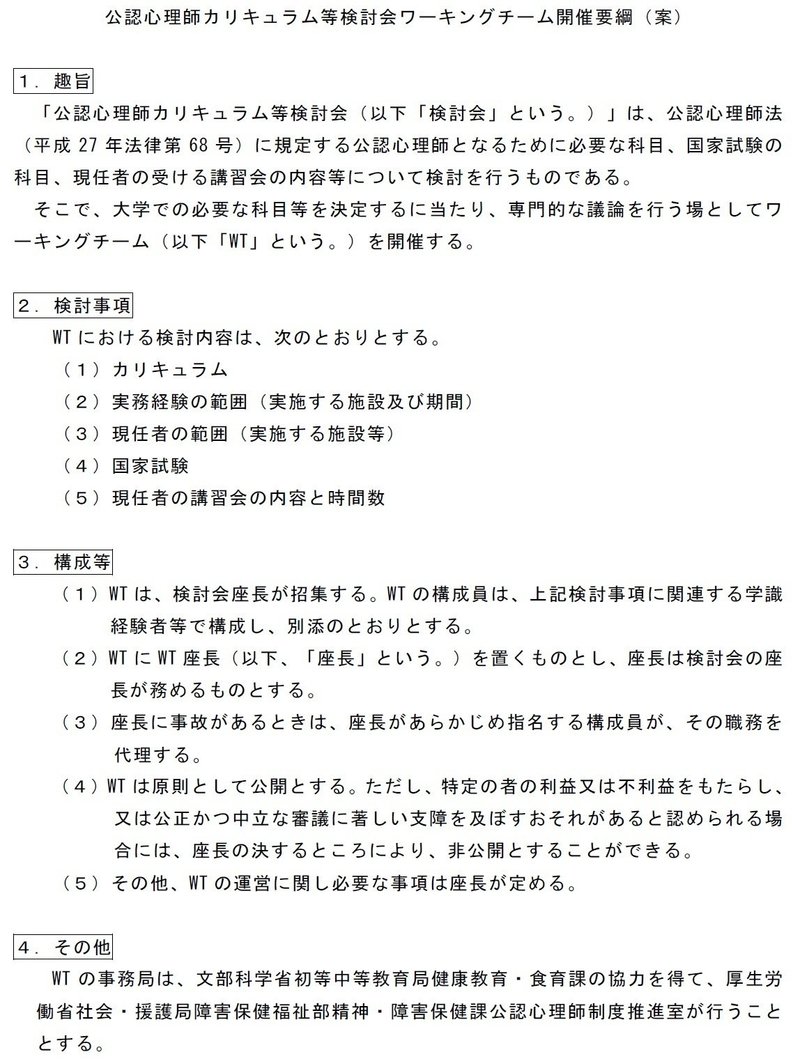
WTで検討している間は、この本検討会はしばらく休みになるということも確認され、WTの議論は逐次本件当会の構成員にも共有されることを確認し、閉会となりました。
第2回検討会のふりかえり(私的雑感)
次からはしばらくワーキングチームでの検討になるとのことで、いろいろなことが議論されました。「カリキュラム等に関する基本的な考え方」の部分については途中で感想を書きましたので、その続き。
「公認心理師に求められる役割・知識及び技術について」の所、領域を問わず求められるものについては、倫理の問題、ベースとなる知識、医師の診断と公認心理師のアセスメントの違いなどが議論されたように思います。この段階ではそんなに揉めることのなかったように思います。法律や制度について、心理職がどうしてそこまで知っていないといけないのか、と思う向きもあるようですが、村瀬構成員のいう所、つまり、社会の中で生活しているクライエントを支援するために、その社会という枠組みを抑えておく、ということは確かになぁとも思います。
その次の特定の領域において求められるものについては、いろいろ意見が出ますね。まぁこれは皆さん各団体や分野を代表して出席しているので、そうなるのは当たり前とも思います。
「カリキュラム等検討に当たっての留意点」では付帯決議についても改めて確認されました。付帯決議の重要性、1号の大学院が「主」で、2号、3号は「従」の関係、との北村座長の考え方に、異議のありそうな構成員もいましたが、『第一号の者と同等以上の知識・経験を有する者』なので、やはり大学院のカリキュラムが基準になっている、そういう意味でやはり1号が「主」と考えるのは妥当のように思います。
移行措置については北村座長が「知識でマルバツ試験をやるという無茶はやめて、経験や実績を十分評価できるような移行措置があって然るべき」とこの時は言っていました。また、「実習をやった人は通るけれども、机の上の勉強をした人は落ちるみたいな、そんな問題を作ってみたい」とかなり野心的な事も言っています。ただ、この辺は実際にはそうはならなかった訳なので、この点の議論がどう整理されていったのか、今後また振り返っていきたいと思います。
試験については、情報公開というのも求められるので客観的な基準が求められる。なので小論文や面接を導入する際には、そうした基準の設定をかなり精緻にしないといけないという難しさがあるということですね。確かにペーパーテストだけの試験でいいのか、技能面の評価をどこで行うのか、というのはありますが、そこをどうするのか。そこは試験前の養成課程でしっかりチェックされておかなければならないのだと思います。
日本精神神経学会の要望書は、仕事が早いなぁと思いますね。公認心理師という資格ができる、それに伴って制度もできる、今までやってきたことをその制度にどう活かしていけるか。そういうことを議論してこの時点でまとめていたということですね。こういう所は心理の団体にも頑張ってもらいたいと思います。
村瀬構成員の心理研修センターの調査の話。これってどこかで公表されていますかね?ぜひ見たいのですが、センターのHPには何もなかったので、どうなったのかな。いろいろ探し回ったけど、コレのことかな?どうなのかな。
https://www.my-kokoro.jp/books/research-aid-paper/50th_2015/pdf/mykokoro_research-aid_paper_50th_01.pdf
今回も検討会のまとめのつもりが長くなってしまいました。まとめ方を変えた方が良いかな。多分色々検討しながらWTの振り返りも書いていくと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
