女性支援等に係る開示請求への対応に当たって中央省庁・自治体が留意すべき事項
中央省庁・自治体が留意すべき事項
中央省庁と自治体が女性支援等に係り開示請求を受けた場合、その請求は悪用、濫用である恐れがあり、上のnoteで述べたリスクに鑑み、下記の通り慎重に判断すべきである。
また、情報公開法を所管する総務省は、不開示基準の解釈や権利濫用法理の適用基準について、速やかに検討を行い、指針等を策定し、及び必要な場合には法改正を検討すべきである。
①開示文書がネット殊にSNS を介して公開、共有されオープンに弄ばれる事態は情報公開法・条例が想定しておらず、現状を放置することは民主主義の基盤たる情報公開制度を掘り崩すことになるため、速やかな検討と対応が必要であると考えられる。
②情報公開法・条例上は基本的には請求者の目的、動機は問われないこととなっているが、女性支援等に係る開示請求を巡る状況に鑑み、また支援対象者が性暴力、DV、虐待等の被害者をはじめ、安全の確保と心身の健康に敏感な配慮を必要とする人たちであることから、請求者からの聞き取り、SNS等発信の確認、過去の開示文書の使用の仕方の確認等一定の調査を行って、開示・不開示や開示範囲の判断を行うべきである。
③特に、若年被害女性、DV・虐待被害者、ひとり親、LGBTQ+、外国人など困難女性支援法に関わる支援等に係る事業等、それらを含め男女共同参画分野において民間団体が関わる事業等、及び女性支援に限らず困窮者支援、マイノリティ支援が関わる事業等について、特に注意が必要である。
④情報公開法5条1号及び対応する条例規定の適用については、特定の個人が識別される部分に限らず、「個人の権利利益を害するおそれ」のある情報が開示されないよう慎重に判断すること。その際、SNSを含む公開情報との突合せにより生じ得る危険や家族や知人等による特定の危険を十分に勘案すること。また、「権利利益を害するおそれ」には当該個人への誹謗中傷等の攻撃のリスクを考慮すること。
⑤同5条2号及び対応する条例規定の適用については、「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」について、請求者の発信、行動等及びその背景や文脈などを十分勘案して、開示した場合のリスクを慎重に評価すること。特に当該団体等が誹謗中傷等の攻撃に晒されている場合にはその事情を十分に勘案すること。また、団体の提出・提供情報には独自のノウハウ・経験が多く含まれており、かつ一般への公開や他団体との共有を前提に整えられたものではないことに留意し、適切に保護=不開示とすること。
⑥開示請求に係る団体には必ずその旨を通知し意見聴取し、適切に反映すること。
⑦開示文書を正当な理由なく一般公開するなど不適正な使用がされていることが確認された場合には、請求者及び関係者にデータの削除・消去をはじめ使用の中止を求めること。不適正な使用に係る通報、情報提供には速やかに対応すること。
⑧不適正な使用を繰り返す者、民間団体等へのバッシング、嫌がらせ等に利用することが明らかな者、自らの理論・主張を通すために利用することが明らかな者(注)などからの請求に対しては権利濫用法理の適用を検討すること。
(注) 法令等の独自解釈に基づき、「こういう文書がなければおかしい」として開示請求を繰り返し、文書不存在も我田引水に解釈し行政を誹謗している者がいる。
⑨以上につき、関係部局と情報と認識の共有を図り、整合的な対応がなされることを確保すること。
⑩悪意や歪んだ動機のある開示請求に効果的に対処できるよう、不開示基準の解釈や権利濫用法理に係る解釈等につきさらなる検討を行い規程等を整備すること。
開示請求と権利濫用法理
総務省
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準
第1 開示決定等の審査基準
2 開示しない旨の決定(法第9条第2項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(6) 開示請求が権利濫用に当たる場合。この場合において、権利濫用に当たるか否かの判断は、開示請求の態様、開示請求に応じた場合の行政機関の業務への支障及び国民一般の被る不利益等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲を超えるものであるか否かを個別に判断して行う。行政機関の事務を混乱又は停滞させることを目的とする等開示請求権の本来の目的を著しく逸脱する開示請求は、権利の濫用に当たる。
内閣府
内閣府本府における情報公開法に基づく処分に係る審査基準
第1 開示決定等の審査基準
2 開示しない旨の決定(法第9条第2項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(7)開示請求が権利濫用に当たる場合
第7 権利濫用に当たるか否かの審査基準
権利濫用に当たるか否かの判断は、開示請求の態様、開示請求に応じた場合の行政機関の業務への支障及び国民一般の被る不利益等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲を超えるものであるか否かを個別に判断する。行政機関の事務を混乱又は停滞させることを目的とする等開示請求権の本来の目的を著しく逸脱する開示請求は、権利の濫用に当たる。
判決
佐賀地裁判決(平成19年10月5日)
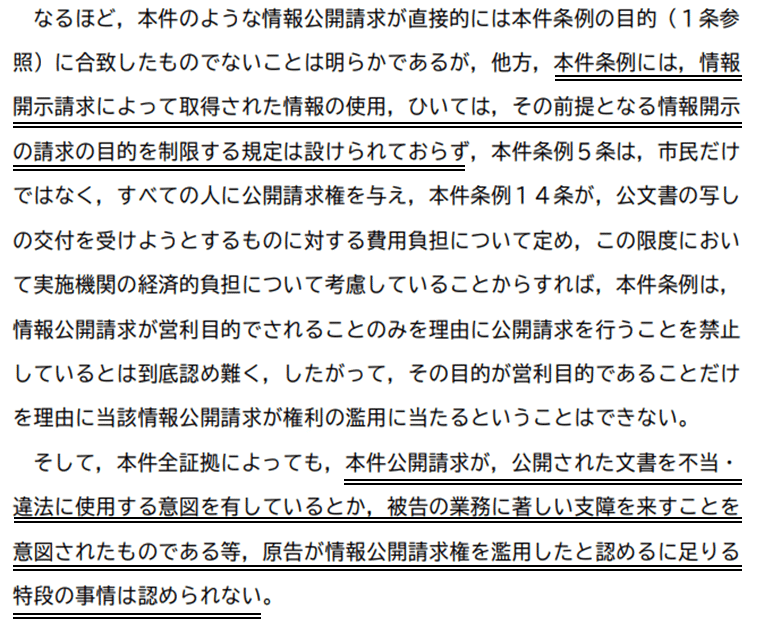
⇒反対解釈として以下のいずれかの場合には不開示とすることが認められる。
① 取得情報の使用若しくは開示請求の目的を制限する規定がある場合、又は
② 情報公開請求権を濫用したと認めるに足りる特段の事情が認められる場合
東京都
情報公開条例
第4条(適正な請求及び使用)
この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
情報公開条例施行通達
第4条関係(適正な請求及び使用)
第2 運用
1 適正請求及び適正使用の要請
⑴ 実施機関は、不適正な請求をしようとするものがある場合は、そのものに対して、適正な請求をするよう要請するものとする。
⑵ 実施機関は、公文書の開示によって、その情報が不適正に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる場合には、当該使用者にその中止を要請するものとする。
⑶ 著しく不適正な請求及び使用については、権利濫用の一般法理により対処する。
他県の情報公開条例の例
・開示によって得た情報をもとに違法又は不当な行為を行うことが明らかに認められる場合(栃木県、愛知県)
・特定の個人を誹謗、中傷、又は威圧することを目的とするなど、明らかな害意が認められる場合(群馬県、三重県)
・過去の開示請求により得た情報を不適正に使用して第三者の権利利益を不当に侵害した事実が認められる場合であって、同請求者から同種の内容の請求がなされ、不適正な使用が繰り返されると明らかに認められる場合(群馬県、静岡県)
・開示請求により得た情報を不適正に使用し、又は使用するおそれがあると認められる場合において、実施機関が、当該情報の使用者に対して、その情報の使用の中止を要請したにもかかわらず、なお、不適正な使用を繰り返すなどした者から改めて開示請求がなされた場合(千葉県)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
