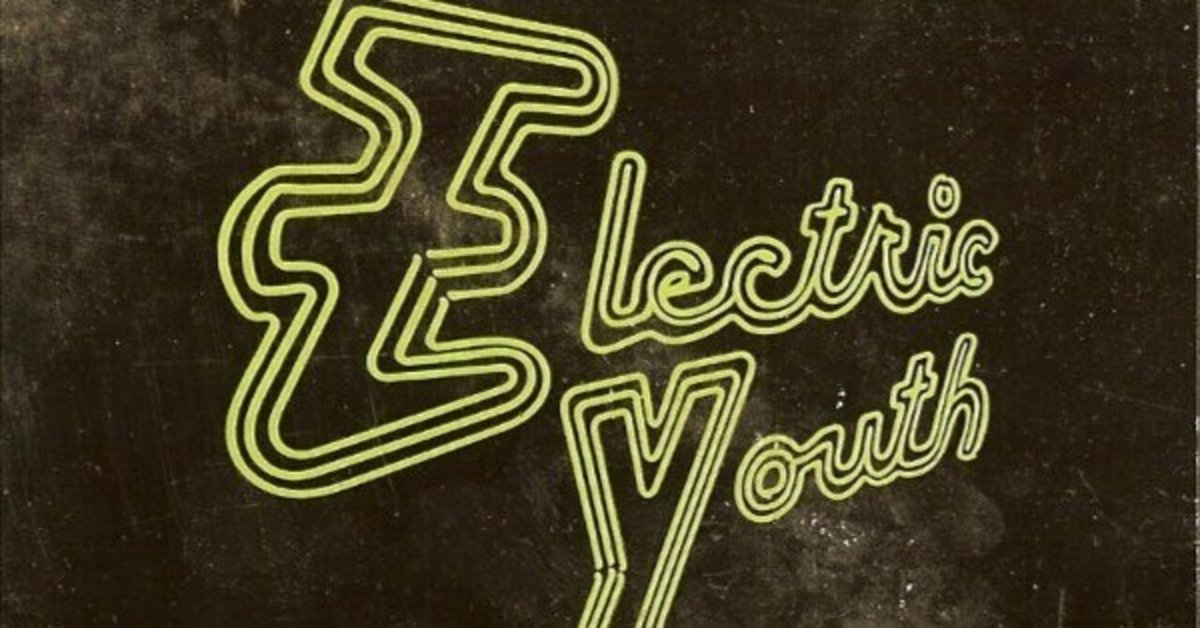
エレクトリック・ユース
エレクトリック・ユースとは、1989年の春にヒットしたデビー・ギブソンによるポップ・テクノ調のダンス・ナンバーである。このころの日本はまだ平成になったばかりで、長かった昭和がついに終わり新しい年号が決定されたものの、まだみんなあまり馴染めずにいて、妙にふわふわしたどうにも落ち着かないような毎日が続いていたように記憶している。昭和の最末期はどこもかしこも自粛ムードに包まれていて、表向きにはみな大人しくしおらしく日々の生活を極めて重苦しく送っていた。しかし、昭和が終わり平成になったからといって、すぐさま自粛ムードをかなぐり捨ててぱっと大騒ぎして大喜びしてもいいのかというと実はそうでもなく、今度は国民として喪に服さなくてはならないということであった。元号が変わって、何か完全に改まって新たに始動するという雰囲気はほとんどなく、まだだらだらと昭和が続いているような気分であった。どうも平成は存在感が薄い。「へひせひ」なんていうふうに発音すると、どうにも気が抜けまくっている。そんな表向きには大人しくしおらしく過ごさなくてはならない妙に重苦しい毎日がたらたらと続いていたころ、わたしは当時はまだ大学生でモラトリアム期間ということもあり、のんびりと学生生活を送っていた。夜の街をふらついて地下のダンスフロアに潜り込んだり、あちこちのレコード店を巡ってみたり、学校のない日の昼間は暇にまかせて家でひとりで録画したMTVの番組を見たりしていた。時折、アンダーグラウンドのクラブでもかかっている最新ヒット曲のビデオなども流れたりするので、一応そういうものもチェックするようにしていたのだ。いつものように何かおもしろいものはないかなと物色していたときに、そこで初めて「エレクトリック・ユース」を見たと記憶している。
このとき、デビー・ギブソンのことはもうすでに知っていた。カイリー・ミノーグやリック・アストリーがポップなダンス・ヒットでアイドル的な人気者となり、セカンド・サマー・オブ・ラヴのあおりを受けてほとんどアシッド・ハウスだらけとなっていた英国インディ・チャート(ラジオ日本「全英トップ20」の番組内で紹介されていた)に紛れ込むようになっていた87年後半から88年初頭にかけての時期に、弾けるようにポップな「シェイク・ユア・ラヴ」を全米・全英のチャートでヒットさせて鮮烈な印象を残していたのが当時まだ十七歳だったデビー・ギブソンであった。ちょうどブレイクのタイミングが重なっていたこともあり、最初はストック・エイトキン・ウォーターマン(PWL)関連のアイドル・シンガーなのだと思い込んでいた。ノリがよくサビが覚えやすい「シェイク・ユア・ラヴ」は、いかにもそんな曲調のポップ・ソングだったから。
だがしかし、よーく聴いてみると、デビー・ギブソンの「シェイク・ユア・ラヴ」は、小気味のよい跳ねるダンス・ビートが特徴的な楽曲であり、キーボディストのフレッド・ザールのプロデュースによるラテン・フリースタイルにも近しい王道の八十年代ニューヨーク・ダンス・サウンドとなっていることがわかる。とてもパーカッシヴで骨太で据わりのよいプロダクションは、まさにニューヨーク的な香りのする実に主張の強い音なのである。これに対して、ストック・エイトキン・ウォーターマンが次々とほぼ金太郎飴状態で送り出していたヒット作品のサウンドは、のっぺりとしたベースラインと単純化されたダンス・ビートを軸とするユーロ・ディスコであり、そこに華やかさを付け加えているラテン・フレイヴァーはまさに取ってつけたような装飾であって、ダンス・リズムの根幹から湧き出してきているものでは決してない。同じようなダンス・ポップ曲であってもデビー・ギブソンのそれは、明らかにストック・エイトキン・ウォーターマン印のものたちに備わっていた如何ともしがたい軽さとは、まさに一線を画していたのである。
そして、やはりなんといってもデビー・ギブソンをその他のポップ・シンガーたち、アイドルたちとは決定的に異なる存在にしていたのは、楽曲の作詞と作曲を自分でこなしてしまう自作自演歌手(シンガー・ソングライター)であるという部分が非常に大きかったのではなかろうか。これはレコード会社やプロデューサーが用意した曲をロボットのようにただ歌うだけの、ヒット・チャートを賑わせているアイドル歌手とは異なる個性の獲得につながっていたと思う。デビー・ギブソンには、自ろの手で書き下ろした自ら歌いたいメロディと言葉(歌詞)があったのだ。ただそれだけで、ただの職業歌手よりは少し格上であるかのように思えたし、「シェイク・ユア・ラヴ」のプロモーション・ヴィデオでぴょんぴょん跳ねるように歌い踊っている姿にもなんともいえない非凡さが垣間見えてくるようにさえ見えた。十六歳でデビューし、老舗アトランティック・レコードによるプロモーションの後押しもあり、ティーンエイジャーでありながら次々と世界的なヒット曲を飛ばす大スターにして、その音楽的才能も認められるアーティストとなった。その音楽性や歌の内容には、ある意味で子供っぽく無邪気なところや未成熟で青い部分も所々に見受けられるのだが、そこがまた等身大のデビー・ギブソンという女性の人物像を素直に表しているようで概ね好意的に受け取られていた。その変に背伸びしすぎないありのままの十代の若者の内面や主張を投射した音楽と歌は、多くの人々に新鮮味をもって受け入れられ、発表するシングルは常にヒット・チャートの上位へと送り込まれることとなったのである。
「エレクトリック・ユース」はセカンド・アルバム『エレクトリック・ユース』からのシングルとしてリリースされた。デビュー・アルバム『アウト・オブ・ザ・ブルー』で大成功をおさめた若きスター歌手の二作目だけに、とても大きな期待の中で発表されたアルバムであったが、デビー・ギブソンは軽々と二台目のハードルもクリアしてみせた。アルバム『エレクトリック・ユース』からはタイトル曲の「エレクトリック・ユース」だけでなく、ビルボード・ホット100で三週連続一位を記録したデビー・ギブソンにとってのキャリア最大のヒット曲となったピアノ・バラード曲「ロスト・イン・ユア・アイズ」やアダルト・コンテンポラリー調のバラード「ノー・モア・ライム」などの世界的なヒット曲が続々と生まれた。当時、まだティーンエイジャーであったデビー・ギブソンが、恐るべき子供たちであるところのX世代の(最若年層の)若者たち(当然、デビー・ギブソン本人も含む)について歌ったものが、この「エレクトリック・ユース」となる。
1970年8月31日にニューヨーク市ブルックリンに生まれたデビー・ギブソン(デボラ・アン・ギブソン)は、日本でいえば大阪の吹田市で開催されていた日本万国博覧会(大阪万博)の開催期間中に生まれた、ばりばりの万博世代・エキスポ世代に属する人物である。そんなデビー・ギブソンが、自分も含めた同世代のティーンエイジャーたちのことをエレクトリックな若者たち(電気的で/電動の/衝撃的な/若者たち)「エレクトリック・ユース」と歌った。そして、それが世界的なヒット曲となった。MTVでプロモーション・ヴィデオが流れ、ラジオでもヘヴィ・プレイされ、多くのデビー・ギブソンと同年代の若者たちがそれを目にし耳にした。それは、それまで少し宙ぶらりんな存在であったエレクトリック・ユースに「エレクトリック・ユース」がエレクトリック・ユースであるという自覚をうながした瞬間でもあった。
エレクトリックな若者たちであるところの万博世代は、六十年代生まれのX世代(ジェネレーションX)どまんなかな常に時代に先行していた世代と、後にやってくるY世代(ジェネレーションY)やミレニアル世代の走りである常に時代に先行している世代の狭間に生まれ落ちた、厳密にいってXでもYでもどちらでもない中間地帯の空白の世代(ブランク・ジェネレーション)であった。いわゆる第二次世界大戦後のベビーブーマー世代を親にもつ団塊ジュニア世代であり世代人口は突出して多く、世界的に人口減少が急速に進む中にあってはこのような分厚い層をなす世代はもはや二度と出現することはないであろう。基本的な頭数が多い分だけ世代(全体)が表出させつ色合いが薄れ、それにより確固たる色をもたない空白となってしまっているという部分もあるとは思われる。だが、実際にこの万博世代が生まれた時代というのは、まさに時代の狭間であって、大きな時代の変わり目のときでもあった。明らかに1968年までとそれ以降とでは、世界は大きく変わったのだ。六十年代末と七十年代初頭の間にはっきりとした切断線があることは、近ごろ「よみがえる新日本紀行」と題して再放送が行われている当時の「新日本紀行」の映像を見てもよくわかる。昭和四十年代の後半から(七十年代以降)どういうわけか見るからに小さな子供たちの様子ががらりと変わるのである。つまり、一気に服装がカラフルになるのである。真っ赤なスカートや緑色のズボン、レモンのように真っ黄色のシャツ。七十年代以前にも色鮮やかな服装をした子供たちはいただろう。だが、同じカラフルでも、この大きな時代の境目の前と後ではかなり違っているのだ。以前の時代の色物の服というのは、日本らしい景色や木造の家屋の茶系の色合いになじんだ落ち着いた色であり、悪目立ちすることのないやや退色したカラフルが基本であった。子供たちも昔ながらの素朴で日本らしい色合いの服装をしていたのだ。そこに眩しいくらいに鮮烈な色の服を着た子供がちらほらと混じるようになる。目の覚めるような原色のヴィヴィッドな色合いの服をベビーブーマー世代の若い親たちが小さな子供に着せるようになるのが、明らかに七十年代初頭以降のことなのである。そこで何かが決定的に変化していることが、小さい子供の着ている服装の色の鮮明さからも見てとれる。共同体内での周囲との調和よりも服装のレヴェルでのひとりひとりの他者との差別化が優先され始める。伝統的な村落共同体・地縁共同体が内側から解体され、ばらばらの個人が参加する資本主義の原理と精神が浸透した市場経済・自由主義経済を最優先する社会が、最後の軛から解き放たれて加速しはじめたのが、この変革の時期ではなかったか。そして、その捻れて捩れた切断線の狭間で、時代の亀裂とひび割れの落とし子のような、新旧の時代どちらにも属さぬ空白のジェネレーションが、この時期に誕生した。それが、ちょうど1970年生まれの万博世代であり、1970年生まれのデビー・ギブソンが歌ったエレクトリック・ユースなのである。
1989年当時のティーンエイジャーは、まさしくエレクトリック・ユースであった。フォーク・シンガーのボブ・ディランがアコースティック・ギターをエレクトリック・ギターに持ち替えたのが六十年代後半のこと。万博世代は、もうすでにボブ・ディランがフェンダー・テレキャスターを抱えて「ライク・ア・ローリング・ストーン」を歌っている「ノー・ダイレクション・ホーム」な世界に生まれてきた。成長とともに身の回りに新しい電化製品が増えてゆき、いつしか朝から晩まで電化製品に囲まれた生活を送るようになる。八十年代前半、つまり万博世代がティーンエイジャーになったころに、その名もエレクトロという、まさにエレクトリック・ユースのためにあるような音楽が出現する。ニューヨークのトミー・ボーイやセルロイドといったストリートのカルチャーに近しい新興のレーベルから、アフリカ・バンバーターのソウル・ソニック・フォースやタイム・ゾーンなどのヒップホップ系のアーティストたちが、次々とエレクトロな音楽作品をリリースした。押韻詩のラップを巧みに歌うことを目的としたヒップホップとはまたひと味違った、エレクトロニックなビートに着目し、ヒップホップの音楽的土台やサウンド面を前面に出して展開したものがエレクトロであった。ファンキーで強烈なビートが特徴であるエレクトロは、まさにダンスするための音楽であった。エレクトロなヒップホップにおけるラップは、主役のダンスに花を添える脇役としてあった。機械的にジャストなタイミングで刻まれるエレクトロニックなビートに合わせたダンスは、自然に電気仕掛けのような動きとなりロボット・ダンスと称されたりブレイク・ダンス(ブレイキン)として発展してゆくようになる。ドラム・マシーンを使用したエレクトロニックなビートは、万博世代にとっては最初から身近なところでごく当たり前に鳴っているサウンドであった。ハービー・ハンコックの「ロックイット」にしても衝撃的なエレクトロ・サウンドというよりも、ニューヨークで流行している八十年代の新しい音楽のひとつとして「ナルホドネー」といった感じで受け止められていた。年長の人々は「ロックイット」のあれやこれやで大騒ぎしていたが、まだ若くて無知な万博世代にとってはなぜこの曲だけ特別に騒ぎ立てられているのかがわからなかった。もっと他にも本格的なエレクトロの楽曲は山ほどあったはずだから。少しも違和感を感じずにドラム・マシーンの打ち込みのビートに耳親しみ、エレクトリックなダンス・ビートに合わせて体を動かすのが当たり前の世代と、その少し前のディスコ時代のバンドの奏でるディスコ・ビートで踊っていた世代では、ビートというものに対する感覚の差が大きくある。機械的なリズムに対する拒絶感や生理的な距離感というものが、あの時代のある年代以上の人々には確実にあった。かつてはよくエレクトロなどのドラム・マシーンのビートは、冷たく無機的だといわれた。同じダンスのビートであっても人間が身体を使って叩き出しているリズムではないので、そのサウンドに血肉が通っておらず無機質だと感じられたのであろう。もともとエレクトリックなビートに好意的ではない世代の人々は、そのように感じることが多かったように思われる。人力で叩き出されたリズムと同等に機械に打ち込まれたエレクトリックなビートも身近なサウンドとして感じられていた万博世代にとっては、気分的にノリノリになれるビートかどうかという部分こそがすべてであった。逆に万博世代としては、ひと昔前のフワフワフワフワいっている軟派な感じのディスコ・ミュージックに対して拒絶感や生理的な距離感を感じることの方が多かったようだ。そういう新しい電化した時代に育ってきたティーンエイジャーであったからこそ、この世代の若者はエレクトリック・ユースとなった。ニューヨークのブルックリンで生まれ育ったデビー・ギブソンも学生時代にラジオなどから流れるエレクトロのマシーナリーなビートをよく耳にしていたはずである。幼い頃からピアノを弾いていたデビー・ギブソンにとってメトロノームのように正確にジャストに刻まれるエレクトロニック・ビートは、もうすでに血肉にしみ込んでいるとても親しみのもてるリズムであったのかもしれない。
シカゴ・ハウスやデトロイト・テクノに新時代のダンス・サウンドの曙光を聴き取り、その世界に率先して頭からのめり込んでいったのも、やはりエレクトリック・ユースであった。四つ打ちのビートとパーカッション、ハイ・ハット、ベースライン、シンセサイザーのフレーズによって奏でられる電子音楽。もはやエレクトリック・ユースは、ビートのテクスチャーやベースのうねり具合などの電子音の音色とその微かな動きを聴くだけで、そこに深い情感の表現を感じとる感性の準備が整っていた。わざわざヴォーカルの歌詞によってくどくどと説明されることまでを、もはや必要とはしなかったのである。そして、そのエレクトリックなサウンドそのものが、世代の共通言語として機能するまでになる。世界中のクラブのダンスフロアで、同じダンス・トラックで踊っているエレクトリック・ユースが、同じように電子のサウンドに深い情感を感じ取りそれぞれに身体を躍動させてリアクションしていた。電子音の表情の様々な変化に喜怒哀楽のうねりを聴き、それをエレクトリック・ユースの間で相互に共有し、さらにはそれをグローバルな共感にまで押し広げることができた。例えば、リズム・イズ・リズム(デリック・メイ)の「ストリングス・オブ・ライフ」がプレイされれば、ダンスフロアのダンサーたちはそのピュアなデトロイト・テクノ・サウンドを聴きながら、人間の生命や人生の連なりや広がりなどのどこまでも拡大してゆくイメージを内面に思い描きながらダンスする。それは、ニューヨークでもロンドンでもパリでもリミニでもナイロビでもメルボルンでもブエノスアイレスでも北京でも京城でも東京でも変わらない。そして、エレクトリック・ユースのダンサーたちは、世界各地に無数に点在する大小のダンスフロアにおいて同じイメージや感情や感覚が感じ取られていることを確かに感じ取っている。まさにグローバルなエレクトリック・ユースによる共有と共感のネットワークである。エレクトロニックなダンス・サウンドによって目に見えないワールド・ワイド・ウェブ状の空白の世代の繋がりが形成された。それが88年のセカンド・サマー・オブ・ラヴである。デビー・ギブソンが「エレクトリック・ユース」を発表する前年の夏のことである。このことからも「エレクトリック・ユース」が、セカンド・サマー・オブ・ラヴのアシッド・ハウスをはじめとするハウスやテクノなどの新しいエレクトロニック・ダンス・ミュージックやその文化から大きな影響を受けているであろうことは疑いようがない。また、ダンスフロアでのエレクトリック・ユースの共有と共感のネットワークは、後に訪れるインターネット時代のコミュニケーションを先取りするようなものでもあった。万博世代とはエレクトリック・ユースであり、MTV世代やネット世代のフロントランナーでもあった。
「エレクトリック・ユース」は、エレクトリックな時代を生きるエレクトリックな若者たちの時代が到来したことをポップに高らかに宣告するようなヒット曲であった。89年は、実際に大きな変革の一年であったし、まさに時代の変わり目であった。その遥動の連続の最中にあって、新時代が到来していることを実感・感覚させる動きもまた多々あった。そのうちのひとつが、デビー・ギブソンがヒットさせた「エレクトリック・ユース」である。日本では昭和が終わり、ソ連がアフガニスタンから撤退し、中国では天安門事件が起き、サンフランシスコは大地震で揺れ、ドイツではベルリンの壁が崩壊し、東欧に革命的な民主化ドミノが起こり、冷戦が終わって、日本のバブル景気は天井を打った。たった一年のうちに、予想だにしていなかったことが、いくつも立て続けに起きた。人類史上最も騒々しい一年であったかもしれない。68年以来の世界的な地殻大変動であった。溜まりに溜まっていたものが一気に吹き出したようなところはある。世界は激動していて、あっちにこっちに大きく揺れていた。これからの世界がどうなってゆくかなんて、まだ誰にもはっきりとは見えていなかった。しかし、エレクトリック・ユースにとっては、すべての出来事はみんな輝かしい未来に向けてのポジティヴなサインのようにも見えていた。人々を分断し押さえつけ堅固にそびえていたベルリンの壁が、人々の手によって呆気なく打ち砕かれ崩れ落ち倒れた。かつて壁があった場所で歓喜に沸く人々の晴れやかで誇らしげな表情をニュース映像で見て、新しい時代が到来したことをこれっぽちも実感しなかった若者が、はたして当時いただろうか。デビー・ギブソンの「エレクトリック・ユース」は、そんな十代の若者の心持ちを代弁するかのような楽曲であり、新時代到来のテーマ・ソングであるかのように新時代の主役となる世代のティーンエイジャーの耳にも琴線にも大きく響いた。
あのころ、まだ十代だったエレクトリック・ユースたちは、古い世界と新しい世界の激しいせめぎ合いの中で、明らかに新しい時代の幕開けの兆しが自分たちの身近なところにまでおとずれつつあることを確かに感じ取っていた。それは自分たちのためにあるよう(に見えるよう)な時代だ。新しい世界に適合しうる、新しいエレクトリックな若者たち。エレクトリックな世界を味方につけて、どこまでもどこまでも行けると信じていた。デビー・ギブソンの「エレクトリック・ユース」を聴いて、実に単純な発想ではあるがエレクトリック・ユースはこれからの時代において無敵であるようにも思えていた。エレクトリック・ユースは輝かしくも華々しい(はずの)前途に目を向けて、何の保証もないにもかかわらず青くて若い無敵感に満ち満ちていたのである。
91年の春、デビー・ギブソンはシングル「エニシング・イズ・ポッシブル」をスマッシュ・ヒットさせている。なんだって可能で、不可能なことなんてひとつもない。まさにそれは、エレクトリック・ユースが、あの当時に感じていた気分そのものであった。時代と時代の狭間の空白の時代に生まれたエレクトリック・ユースが、激動と揺籃におおわれた世界をひとつの巨大なダンスフロアに見立て、言葉にならない言語を共有しまるでデータ通信でもするかのように共感しコミュニケートしながらダンスした。そんな時代が確かにあった。つるつるの器官なき身体となって踊るエレクトリック・ユースの瞳に映る世界は、もはや怖いものはなにもない無限の可能性に開かれた場所であった。
(2021年、春〜夏)
〈付録〉
「中国 “革命”の血と涙」。最後の天安門事件の映像で、期せずして涙がこぼれ落ちてしまった。これまでにも事件の映像は、何度となく見てきたはずなのに。どうしたことだろうか。これが歳をとるということなのか。そのうちにアホみたいに涙もろい老人になりそうで怖い。めそめそ。あのころ、世界も、社会も、時代も、すべてがものすごい勢いで動いていたことを思い出した。ただただ毎日うだうだと遊んだりしていただけだったけど、ぐんぐんぐんぐん前に進んでいるような感覚があった。激動とか変化というものは、そのただ中にいると、あまりいちいち実感をもって感じられるようなこともないようだ。ただ、自分を取り巻く世界が社会が時代が轟々と移り変わり行きすぎてゆくだけで、ぐんぐんぐんぐん猛スピードで前進しているように感じられる日々であったのだ。目まぐるしさに疲れるというよりも疲れているひまさえもなく、次々となにかに背中を押されるように新しい扉をくぐり抜けつづけるという感じであった。そういう激した時代のうねりや流れの中で、あの天安門事件は起きた。毎日のように、天安門広場の様子はニュース番組でも報じられていた。それもまたテレビの画面越しに見る、轟々とすべてがうねり動いていることを実感させる世界の景色のひとつであった。あの当時の中国の学生や若者たちも猛烈なスピードで前へ前へと進もうとしていたのだろう。世界も時代もそういう動きや流れの中にあったのだから、間違いなく天安門広場もその例外ではなかったというだけだ。おそらくは自分の足で進むことのできる速さを大きく超過して、大きなうねりや流れに飲みこまれてしまい、あっぷあっぷしながら猛スピードで前進していたようなところもあったのではないか。同時期に学生生活を送っていた同年代の日本人の若者たちと同じように。いや、来る日も来る日もネナ・チェリーやリサ・スタンスフィールドのアルバムを聴いて、来るべき時代のダンス・ミュージックやソウル・ミュージックに胸を躍らせ高鳴らせていた世界中の同年代の若者たちと同様に。だがしかし、あれから三十二年が経って、あの当時に未来への夢と希望で胸を膨らませていたかつて若者であった人々は、今どのように思って世界の景色を眺めているのだろうか。まだ手の中には何ももっていないけれど、科学技術が飛躍的に発展し、過去の過ちを反省し歴史から学び人間が人間性を着実に向上させてゆく、これからの時代はきっともっともっと輝かしく素晴らしいものになるだろうと思っていた。多くのあの日の若者たちは、きっと今ではしみじみとこんなはずじゃなかったと思っているのではないか。あのころよりも、世界も、社会も、時代も、ものすごい勢いで悪くなっていっている。人間が救いようもなく小さくなった。まったく輝かしくも素晴らしくもない。あの日に抱いていた理想はとても高かったのに、あれもこれもすべて潰されて踏みにじられてしまった。東京オリンピックの開会式を見てみても、随所にこの国のだめだこりゃ感は手にとるように見てとれた。あの日の夢や希望を実現できていれば、もうちょっとは輝かしくも素晴らしい底堅さみたいなものやこの世代に備わった胆力のようなものを今ごろは隅々にまで行き渡らせることができていたのではないか。あの式典の場にいた人々の顔ぶれはどうだ。天安門事件が起きたとき、菅義偉は四十歳でもうすでに横浜市会議員であった。小池百合子は三十六歳でニュースキャスターとして華々しく活躍していた。橋本聖子は二十四歳でサラエボとカルガリーの五輪に出場した名の知れたオリンピック選手で社会人でもあった。あの当時、それぞれにそこそこにバブル景気の恩恵も受けたことであろう。そして、三人ともに少なくとも手の中にまだ何ももっていない若者ではなかった。今、あの日の天安門広場の映像を見たとしても迂闊にも目頭を熱くしてしまうようなことはよもやないであろう。これでもかと銃弾を浴びせられ真正面から突っ込んでくる装甲車に追い立てられる何ももたぬ若者たちに、自分の姿(または自分の世代の姿)を重ねて見るようなこともついぞないであろう。あれから三十二年ずっと自分たちの思う通りにできてきたのだからこんなはずじゃなかったなんて思うこともこれっぽっちもないに違いない。反対に、あれからずっとわれわれは挫かれ続けているのではないか。上から頭を踏みつけられたまま、立ち上がれないように押さえつけられている。天安門広場にいた若者たちの姿は、実は自分たちの姿そのものなのではないか。中国の学生や若者たちがわれわれの世代の先頭に立って真っ先に潰されて踏みにじられたというだけなのではないか。こんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかったのだ。銃弾を浴び血まみれになり、突っ込んでくる装甲車の下敷きになる。わたしはもう死んでいるのか。あのころに夢見た輝かしくも素晴らしい未来は、まだ来ないのか。まだ来ないのか。未来はまだか。待ちくたびれた。そんな踏みつぶされた世代の悲哀に思いがいたり、なぜだか自然と涙があふれでてしまった。
(2021年8月15日、フェイスブックに投稿。21年10月/22年3月、加筆)
ここから先は
¥ 100
お読みいただきありがとうございます。いただいたサポートはひとまず生きるため(資料用の本代及び古本代を含む)に使わせていただきます。なにとぞよろしくお願いいたします。
