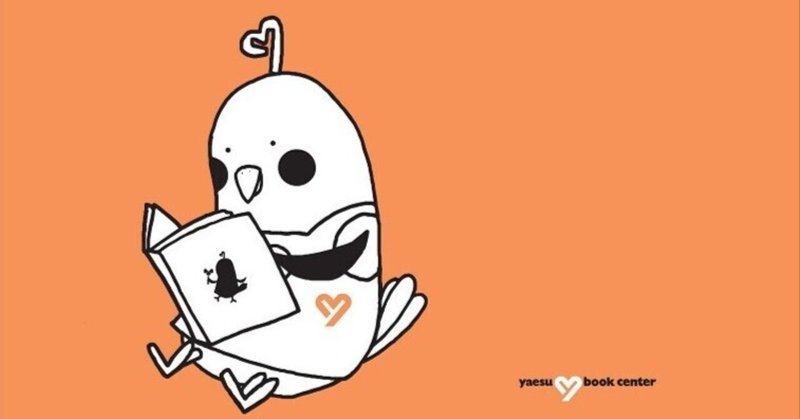
初めてのYBC
八重洲ブックセンターが、2023年3月31日に閉店した。ずっとそこにあり続ける、いつまでもなくならないものなのだと(勝手に)思い込んでいたが、(やっぱり)そんなことはなかったようである。始まりがあれば、終わりがある。いつまでもずっとあると思っていたものが、突然になくなり、その(何となく永遠性そのものであったような)存在がこの世界からすっかり消え去ってしまう。そういうものやことあるいは人との別離を、ここ数年で本当にいくつもいくつも経験している。そして、今回はそれが八重洲ブックセンターの順番であったようだ。ちなみに、そのすぐ次の順番は、流浪の番組「タモリ倶楽部」であった。八重洲ブックセンターは44年、「タモリ倶楽部」は40年、それぞれの歴史に相次いで幕をおろした。(後にわかったことだが、坂本龍一は八重洲ブックセンター閉店の三日前に亡くなっていた。何か本当にここが時代の大きな変わり目であるように感じられてきて仕方がない。)
初めて八重洲ブックセンターに行ったのは、まだ小学生のころであった。おそらく小学生の中学年ぐらいだったはずだ。祖母が連れて行ってくれた。行く前から「日本で一番大きい本屋さん」だと聞かされていたせいで、むちゃくちゃテンションが上がっていたことを記憶している。わたしが本が好きだということを知っていたので、新しくできた八重洲ブックセンターをわたしに見せようと思ったのであろう。生まれたときにはもう父方も母方も祖父が他界していたせいもあって、祖母はわたしが小さいころから色々なところに連れてゆき色々なものを見せ色々なものを実際にその場で経験するための計画を色々と考えてくれていた。(ちなみに、祖母は、銀座生まれの銀座育ちという人であった。そのせいもあり、その界隈の自分とゆかりのある、ひいては孫のわたしにとってもゆかりがあるはずの場所を、あれこれわたしに見せたり案内して回ったりしたかったのであろう。大正の終わりから昭和初期にかけての銀座界隈とは、まったく景色は変わってしまっていたであろうが‥‥)
たぶん、わたしが八重洲ブックセンターに行ったのは開店してすぐではなく、営業を開始して少し経ったころではなかったかと思う。開店フェアのような賑やかさはなく、店内はもうごく普通に本屋らしい落ち着いた雰囲気と佇まいであった。しかし、普通に本屋ではあるのだが、ちょっと考えられないくらいの規模であった。広々として、たっぷりと空間のある店内で、それが上に何階も積み重なっている。ビルが一つ全部本屋だというだけで、小学生の頭ではちょっと追いつけないものがあった。新富町通りの丸広百貨店に入っていた紀伊国屋書店や二階のある駅の近くの黒田書店でも当時のわたしにとっては大きい本屋さんだった。池袋ぶらんで〜と東武の旭屋書店なんてもうだだっ広いし本の数も多くて見て回るだけで疲れちゃうと思っていたくらいであった。ゆえに、八重洲ブックセンターの広さは本当に桁違いであったのだ。
前もって「日本一大きい」と言われていて、実際に見てその通りで、わたしは絵に描いたように面食らっていた。いや、あまりにも規模が大きすぎるし広すぎたのか、小学生の頭では理解の範疇を超えてしまっていてよくわからなかったというのが正直なところであった。頭の中は「これが日本一か!」だとか「本当にすごく大きい!」という実際に見た印象やその場で感じられた空気感からくるイメージでいっぱいになっており、右を見ても左を見ても本ばかりでただただテンションが最高潮に上がったまま持続しているという感じであったように思う。見渡す限りどこもかしこも、上の階もその上の階も全部が本屋なのだという、なかなかない状況に直面し、完全に圧倒されてしまっていた。
そのころ週末に横浜の祖母の家つまり母の実家に泊まりに行った帰りなどに乗り換え駅の池袋で駅の上の旭屋書店によく寄った。そこでも店内をぐるぐるぐるぐる歩き回るだけで、わたしはなかなか欲しい本を「これ!」と決められなかった。あまりにも本の量が多すぎて、どこを見て歩いても本がどんどん次から次へと目に入ってくる。それだけで目が回ってしまって、頭の中をぐるぐると沢山の本が渦巻き続ける状態となり、どの本を選んでいいのかさっぱりわからなくなってしまうのである。母も祖母もいつも根気よくなかなか決められないわたしに付き合って、決まるまで待ってくれていたのだが、結局最後の最後は「決められないなら、また今度ね」ということになる。そんなことがしばしばあった。しかし、そこで変に焦って目についた本をぱっと手に取って「これ」といって決めてしまうと、後で必ず後悔することになるのである。そのことはわたしも経験から重々承知していた。だから、時間切れになってしまったら、本はあっさり諦めるしかないのである。
ただし、広大な八重洲ブックセンターでは、母も祖母もいちいちぐるぐる店内を歩き回って欲しい本を探すわたしに付き合ってもいられないと思ったようである。そこで、このときは店内に入ったところで、まず千円札を渡された。つまり「好きな本を選んで、これで買いなさい」のシステムがとられることになったのである。そして、巨大な八重洲ブックセンターに、いきなり放流である。だだっ広い店内にずらりと本が並んでいる光景に、もうすっかりテンションが上がりまくっていたわたしは、まるで吸い込まれるように本の売り場のど真ん中に突入し、平積みにされていたり面出しにされている本を、片っ端から見て回った。手の中には気に入った本を買うためにもらった伊藤博文の千円札を四つ折りにして握りしめて。
最初から猛烈にテンションが上がっていて、「日本一大きい本屋さんだから、きっと今までに見たことがないようなすごい面白い本があるに違いない」という強い思い込みがあってうろうろしていたものだがら、なかなかにこれといったものが見つからない。どんなに大きい本屋でも、売っている本そのものは、そこらにある普通の本屋とそう違わないのだ。他の本屋には売っていないものばかりがあるというわけではない。よって、いつものようにただうろうろと歩き回るだけになる。ただし、普通はある程度うろうろ歩き回っていれば、また元の場所に戻ってくるというようなことがあるものなのだが、八重洲ブックセンターではそれがなかった。前もって、どこにどんな本があるのかを少し把握してからうろうろすればよかったものの、それをしなかったせいで、ただただ行き当たりばったりで本を見て回るだけの果てしないうろうろが繰り返されるだけとなった。なかなか欲しい本が見つからずに、時間だけが刻一刻と過ぎていった。
しばらくうろうろしているうちに、ふと気がついた。手の中に握りしめていたはずの、四つ折りの伊藤博文の千円札がないのである。右手にも左手にも持っていないのである。どこを探してもないのである。あちこち本を見て回っているうちに、気になる本を手に取って、それを開いて中を見るときなどに、ひょいっとどこかに千円札を置いて、そのままそれをそこに置き去りにしてしまったのだろう。いまだに何かなくしものをするときには、大抵このひょいっとどこかに置くということをしている。何も考えずというか、何か別の考え事をしていて、何も考えずにひょいっとどこかに置いてしまうのである。何か考え事をしていると、何よりもまず今考えていることの方が最優先されてしまうのである。いちどきにふたつのことができないたちなのである。このときも、幼いながらにこれはいつものあれだと気がついたのであろう。どこかにひょいっと置いてしまったに違いないと、平積みにされている本の上に千円札が置き去りにされているに違いないと思い、それまでに見て歩いた店内をぐるぐるまた歩き回るということとなった。もはやこうなると、欲しい本を探すことなど頭の中からすっかり飛んで消えてしまい、なくしてしまった千円札を探すことだけで頭の中はいっぱいになっている。せっかくもらった千円札をどこかでなくしてきてしまったなどと、そう簡単に祖母や母にいえるものでもない。店内をうろうろ歩き回って必死に千円札を探し続けた。
八重洲ブックセンターというと、どうしてもあの千円札のことを思い出す。今からもう四十年以上も前のことだけど、まるで昨日のことのように。散々店内を探し回って、自分の中では何時間もうろうろ歩き回ったような気がしていた。たがしかし、どこかにひょいっと置いてしまったと思われる千円札は、やはりどこにも見当たらなかったのである。「日本一大きい本屋さん」に大興奮して有頂天になっていたわたしとしては、これはとてもショックな出来事であった。とても高いとこまで舞い上がっていた状態から、暗く深い谷底まで真っ逆さまに一気に墜落したような気分であった。あまりにもショックが大きかったのか、焦りまくって探し回ってもどこにも千円札が見つからなかったので諦めたところから先のことは、ほとんど何も覚えていないのである。大切な千円札をなくしてしまったことを、どう祖母や母に話したのか、その後せっかく八重洲ブックセンターまで来たのだからと何か本を買ってもらって帰ったのか、さっぱり覚えていないのである。
おそらくは、生来のすっとこどっこいなわたしのことであるから渡しておいた千円札を、どこかにひょいと置いてそのままなくしてしまうぐらいのことは、祖母も母もある程度は前もって織り込み済みであったのかもしれぬ。その可能性は高い。そこで「やっぱりそんなことだろうと思った」となって、その後どうなったのだろうか。やはり、「なくしちゃったものは仕方がないね。じゃあ、また今度ね」となったのであろうか。きっと、そのときのわたしはもう非常にわかりやすく空気がすべて抜けきった風船のようにしなしなになってしまっていたことであろう。変に調子に乗って、いい気になっていると、必ず手痛いしっぺ返しをくらうことになる。それもまた、いつものことであった。やっぱり、何をやっても駄目なものは駄目なんだなあと、小学生ぐらいのころからわたしはいつも心のどこかで思い続けるようになっていた。
お読みいただきありがとうございます。いただいたサポートはひとまず生きるため(資料用の本代及び古本代を含む)に使わせていただきます。なにとぞよろしくお願いいたします。
