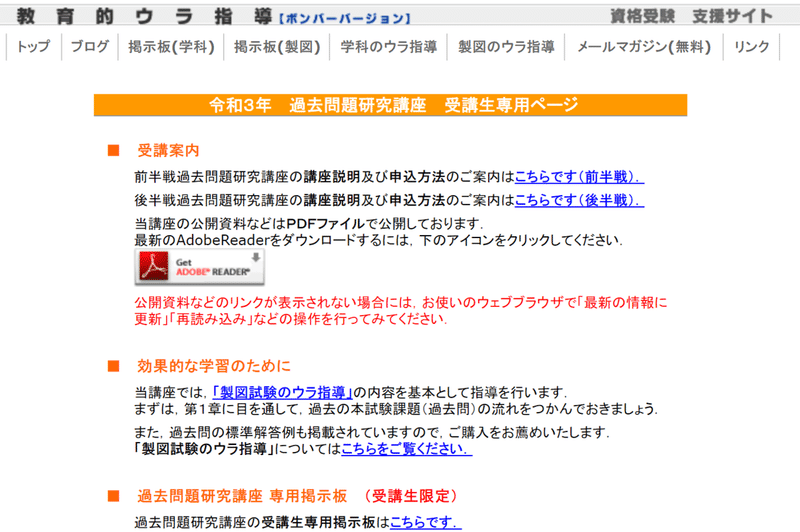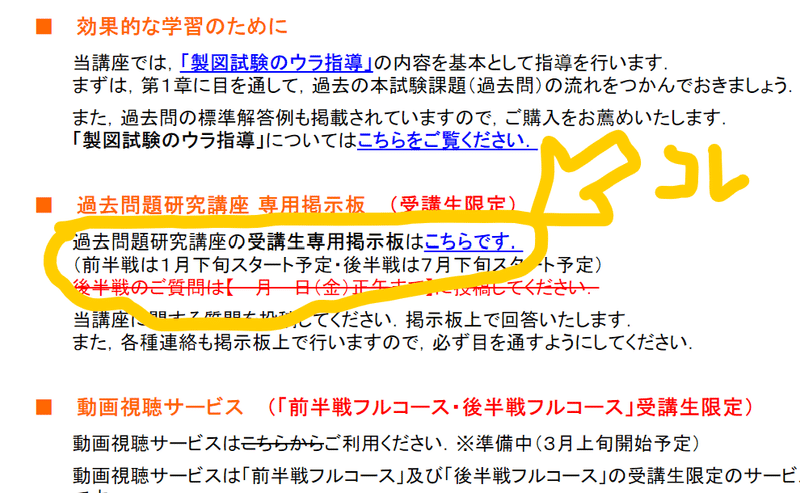【製図】本番で悩んだら過去問に聴け!
学科試験同様に,製図試験も本番で出題者が求めているモノを制限時間内に適切にくみとれるかが勝負です.それが出来ねば,どんなに綺麗で,ミスのない答案を完成させたところで不合格.
例えば,AとBという2つの判断ポイントがあり,Aを満たそうとするとBを満たせず,逆に,Bを満たそうとするとAを満たせない(=相反条件).そんな場合に,AもしくはBのどちらを優先すればよいかで悩んだとしたら,過去の本試験課題ではどのように解決しているのか参考事例を探してみましょう.
ウラ指導の過去問研究講座を受講されている方は,試験制度改革が行われた以降の平成21年からの10年分程度は把握しておきましょう.
課題文,ウラ指導の模範解答例,試験元が毎年,公開する標準解答例(著書「製図試験のウラ指導(学芸出版社)」に掲載)をバインダーにとじておき,それをバイブルとして使い倒しましょう.気づいた点などは,赤ペンでどんどん書き込んでいく.後半戦(7月の課題発表~製図本試験日まで)が始まる前に,過去問マニアとなっておけば合格に大きく近づけます.
自分で判断できなかった場合は,受講生専用掲示板をご利用ください.また,他の受講生の質問とそれに対するウラ指導からの回答についても常に目を通すようにしてくださいね.
自分で過去問を調べる癖をつけることで,様々な気づきがあり,それがアナタの『相反条件に対し,適格に判断できるチカラ』を磨き上げてくれます.
何事も効果的にレベルアップしたいのであれば,本気で向き合い,手を動かし,場数を踏んでいくことこそが成功への最短ルートです.誰よりも過去問を熟知している受験生となることを目指してください.それによって,本番で死守すぺきポイント(条件)と,割り切っていいポイント(条件)の違いを的確に見抜けるようになります.
とりわけ,本番での課題条件の読み取りが苦手な方は必ず,実践してください.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?