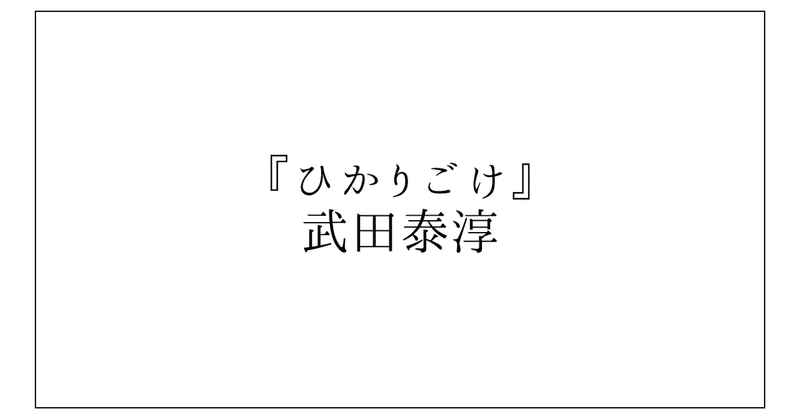
読書記録|『ひかりごけ』
人の肉を喰らった者にしかあらわれない光の輪があるという。
それは、ひかりごけのように光を反射し、発光する。
その者に異端者のしるしを刻み付けるかのように。
実在の事件をもとにした表題作「ひかりごけ」は、食人というショッキングな主題が据えられていることにまず意識がいく。
でも、本当の意味での主題は、そこにはないのかもしれない。
船長は、同乗していた船員を喰らうことを決めたときも、食人の罪で裁判にかけられたときも"我慢して"いたという。
言うに事欠いて、“我慢している”とは。
しかし反抗心でそんな態度をとっているのではないという。
船長はいったい、何を我慢しているのだろう。
それは、人を喰らうだとか、裁判を受けるだとか、具体的な事象一つ一つではなくて、もっと深いところで繋がっていて一所に根ざしているように思われる。他者と違う自分、世間一般の枠組みから外れた自分を認識しながら生きること、そして異端のまなざしに耐えているそのことに。
私はただ、他人の肉を食べた者か、他人に食べられてしまった者に、裁かれたいと申上げているだけです
そう語る船長には、言下にお前は異形なのだと言われている声が聞こえていたのかもしれない。
しかし、船長にあらわれるはずの、異端のしるしである光の輪は法廷にいるだれにも見ることができない。
食人の罪を犯していない者なら見えるはずのその光が、なぜか彼らには見えないのだ。それどころか、光の輪はつぎつぎに法廷にいる人々に浮かび上がっていく。
そして、ゴルゴタの丘で処刑されるキリストと船長の姿とが重ね合わされるラストは象徴的だ。
光の輪がみなに浮かび上がったこと、それは人は誰しも何らかの罪を犯している、ということになりはしないか。
大衆ははじめから相手と自分とは違うものだと切り離し、好きなように品評するが、他者を異端と決めつけた自分自身は、果たして異端ではないと言えるのか。そう問われているように感じる。
極限状態にあっても人は人らしくいられるのか。
しかし、その人間らしさとは何か、誰がそれを裁くのか。
読み終えてからも、しばらく思いを巡らせていた。
表題作のほかに3編収録されているが、いずれもある集団、場において異端とみなされた人間の姿が描かれているように思われる。読めば読むほどに、普通であるということはなんなのか分からなくなってくる。
同じく武田泰淳の『富士』を読んだときも、似たような思いを抱いた。精神病患者とそうでない人間と、いったいどんな差があるのか。自分自身の思う自分の姿は絶対と言えるのか。武田泰淳の作品を読んでいると、そんなふうに自問自答が浮かび、人間存在みたいなことを考えてしまう。
『ひかりごけ』武田泰淳(新潮文庫)
表題作はインパクトの大きいテーマだけれど、ほか3編も重厚で読み応えがある。
「海肌の匂い」は、衝撃的な場面はないけれど自分の中ではとくに印象に残っている。あるコミュニティに外部から身を投じるとき周囲からどことなく感じる好奇の目、少しでも変わった行動をとれば異端視される。そんなまとわりつくような空気にじわじわと追いつめられる感覚がリアルで、こちらまで息苦しくなってくる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
