
教育委員会制度とは?
「学校教育などに関わる事務担当機関」との漠然とした認識はあるものの、実際にはどのような方が選任され、どんな役割を担っているのか知っていますか?
そもそも、「教育委員会制度」はなぜ必要なのでしょうか。
『いまさら聞けない!日本の教育制度』(著:樋口修資さん)という本を参考にさせて頂きます。

そもそも、教育委員会ってどんな組織?
教育委員会は、地方の教育行政において、公正な民意の反映と、教育の政治的中立性確保の観点から設けられている、合議制の執行機関です。中立性を確保するため、地方自治体の首長から独立した形で存在します。
地方自治体の首長から独立した形で存在しているので、『学校の設置・教員の人事や研修・校舎の整備・学校で使用する教科書の選定』など、その街の教育について大切なことを教育委員会の会議で決定しています。そのほかにも、図書館や博物館の設置や、その街の文化財の保存や活用なども教育委員会の仕事なんです。
こうみてみると、教育委員会ってかなり忙しそうに見えますね...
実際にどうなのか、、、
というところは、調べてもなかなか出てこなかったので、今後当事者の方にインタビューしていけたら良いなと思っています!
各地方自治体のホームぺージや、自治体名+教育委員会組織図で検索してみると、実際のもの(例:東京都)が出てくるので、興味がある人はのぞいてみてください!
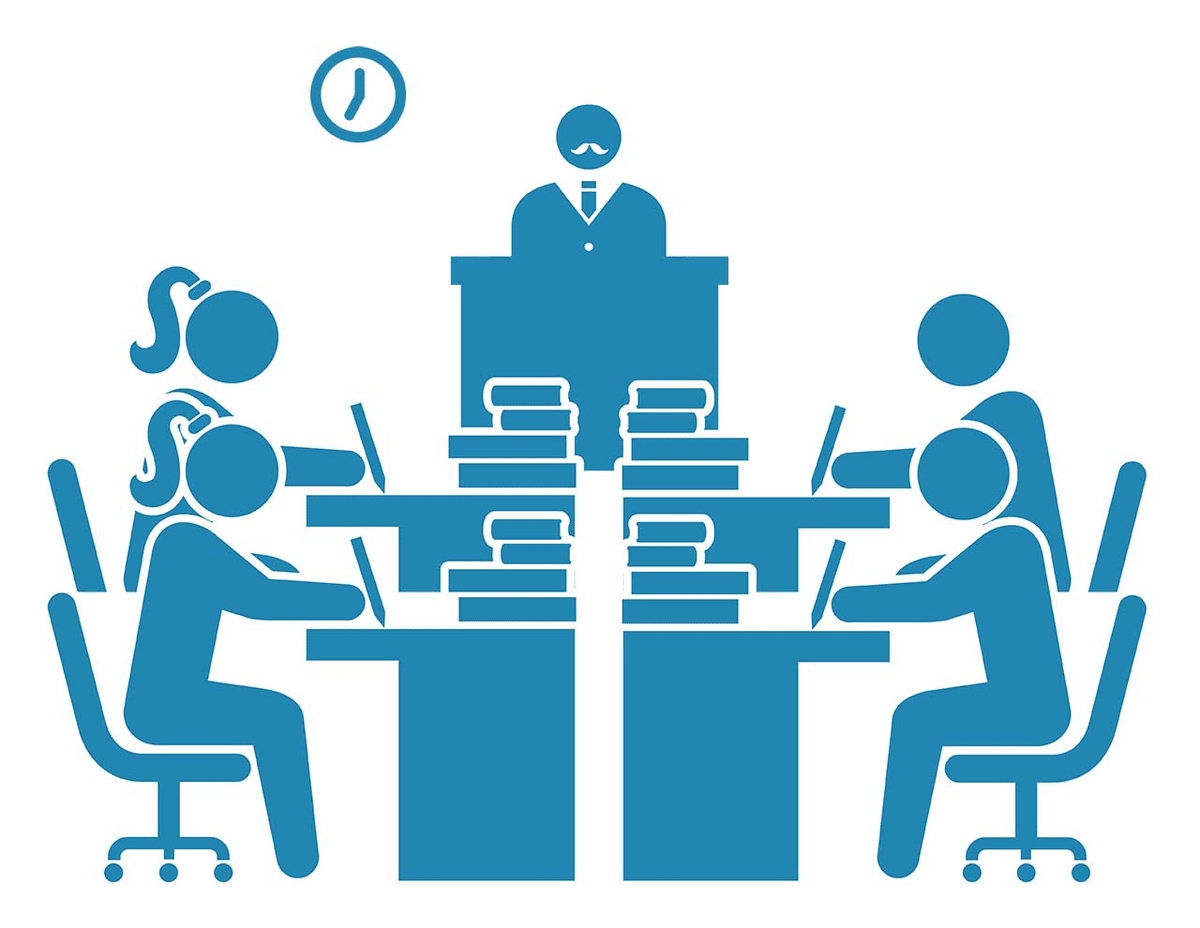
教育委員会制度はなぜ作られたのか?
戦後、教育が政治に影響されないようにと、「教育の民主化」「地方分権化」「教育の自主性の保障」を基本原則に、アメリカの制度を参考に作られました。
戦後、教育改革が進められる中で発足した制度であり、文部科学省はこの制度の意義を3つ定義しています。
①政治的中立性の確保
②継続性・安定性の確保
③地域住民の意向の反映
教育は、どんな人でも関わってくる分野であり、地域でも特に身近で関心の高い行政分野であると考えられます。
☆専門家だけでなく、様々な人が教育に参画すること
☆より『子ども』を主語にした教育を行うこと
☆ある程度一貫した方針のもと、安定的に行われること
☆教育の結果が出るまでには時間がかかるという特性を把握し、様々な改革は徐々に行っていくこと
が求められるのではないかな、と個人的には思っています。

教育委員会制度は本当に必要なのか?
この問いに対しては、おおきな声でお答えします。
絶対に必要です。
子どもたちへの偏ったイデオロギーや価値観の押し付けを防ぐためにも、中立の防波堤としての教育委員会制度は絶対不可欠です。
イデオロギーとは、観念の体系のことを指します。文脈によりそれが意味するものは異なりますが、主に「物事に対する包括的な概念」「哲学的根拠」「社会に支配的な集団によって提示される観念」といった意味で使用されます。
子どもたちには、偏った知識で社会や物事を見てほしくないという気持ちが強いので、制度としてこのような保障がされていることはとても大切なことだと思います。
ここまで読んでくださり
ありがとうございました!
ぜひ他の記事も併せて読んでみてくださいね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
