
Crush CLS(短縮版心肺蘇生コース)
本コースの特徴
ここでは、90分程度の短時間で実施する心肺停止患者に対する蘇生シミュレーション学習の流れについて、一案を共有させて頂きます。1日程度かかる一般の蘇生コースと比較して、「蘇生の流れを歩いてみる」ことを目標として、院内の勉強会等で許容可能なサイズに収めたプランです。また、予習をお願いした上で実施するのが最適と考えますが(予習については、他の記事の教材をご利用ください)、予習なしでも実施が可能できます。
対象と目標
この短縮コースの最適な受講生は、初期研修医及び看護師であると考えています。それぞれ、下記を目標に学習を進められるとよいと考えます。
〇初期研修医
◆リーダーとして、蘇生の最初の10分間に対応できること。
☞それぞれのシナリオにリーダーとして参加します。
〇看護師
◆適切な胸骨圧迫とBLSを実施できること。
☞これを目標に置く場合には、全てのケースにおいて、第一発見者を看護師として、看護師が適切なBLSを実施していることを確認の後に応援の医師が到着してリーダーを引き継いで担当する形が最適と考えます。
◆リーダーを務め、蘇生の最初の10分間に対応できること。
☞病院のセッティングによっては、蘇生のリーダーを務められる医師が即座に到着できないケースも想定されます。このような場合には、看護師だけで蘇生プロトコルを維持する必要があります。
必要物品
最低限必要となる物品
◆胸骨圧迫(とマスク換気)可能なマネキン
◆シナリオや波形提示を行う用紙(下記をA3印刷)
準備可能であれば手配する物品
◆バックバルブマスク(看護師参加がある場合には、手配が好ましい)
◆AEDシミュレーター
◆モニター付き除細動器
◆挿管のシミュレーションキット
◆輸液のシミュレーションキット
また、写真に示すようなボードとマグネットを作成して、蘇生介入を示しながらシミュレーションを進めることも可能です。

各ケースの解説
いずれのケースについても、明らかな高齢傷病者は避けて、一般的な感覚では、挿管も含めたFull Fight蘇生の対象者となるよう設定しています。シナリオについては、前述の資料をダウンロード頂き、以下で指導の留意点と背景設定をご確認ください。
Case.0 BLS

院外で人が倒れているのを発見するシナリオです。AEDの使用を含む一般的なBLSを実施して、到着した消防隊に引継ぎを行うところまでを実施します。胸骨圧迫の質、AEDの使用、バックバルブマスクがあれば換気の技能についても、合わせて指導・評価を実施します。受講生全員がBLS受講済みであれば、省略も可能と考えます。省略する場合には、以降のシナリオで第一発見者となった際にBLSの指導をしっかりと行います。
Case.1 高カリウム血症からのpVT(救急外来にて)

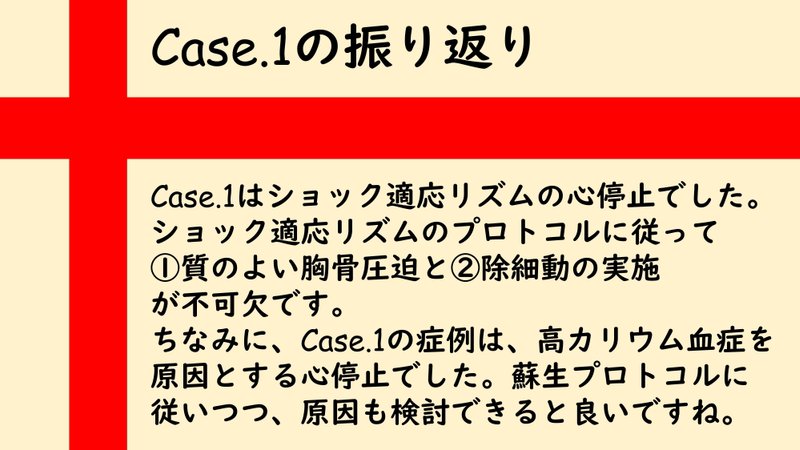
ショック適応リズムでの蘇生です。以降のケースのモデルとなる症例のため、受講生の中で既に蘇生のトレーニングを受けたことのある方がおられたら、お願いすると良いでしょう。場合によっては、初回の電気ショックまではインストラクターが実演した後に、再度最初から、受講生にリーダーとして蘇生を開始してもらうとよいと考えます。
シミュレーションとしては、2回目の除細動と初回のアドレナリン投与まで進んだら、以降適当なタイミングでROSCとして、心拍再開後の治療に進むとよいと考えます。また、実際の除細動器を使用できる状況であれば、3回目の除細動実施のタイミングで、充電後に波形変化してROSCとすることで、内部放電についても取り上げるとよいと考えています。
まずは、プロトコル通りに蘇生を行うことが第一ですが、Case.2への布石として、フィードバックの段階で困ったことに答えていくだけでなく、原因検索についても話ができると良いと考えます。
Case.2 COPD急性増悪で入院中、痰での窒息からPEA


ショック非適応リズムでの蘇生です。本症例では、蘇生中の原因検索が1つのポイントとなります。蘇生中の空き時間に、3つの「か:患者、家族、カルテ」など意識して、どれだけ情報を集めることができるのかが、本症例を進める鍵であると考えます。
シミュレーションとしては、2回目のアドレナリン投与後にROSCとして、心拍再開後の治療に進むとよいと考えますが、呼吸原性の心停止であるため、受講生が挿管を実施した場合には、挿管直後のROSCでよいと考えます。
また、アドバンスな内容として、本症例は一般病棟での心停止であるため、レントゲンや血液ガス分析など、救急外来やICUであれば即座に手配できるデバイスが手元にないことも意識してもらうとよいでしょう。また、ROSC後にICUまでの移動距離があることも念頭にマネジメントを進められるとよいと考えます。
Case.3 心筋梗塞を原因とするVFの継続(救急搬送)


ショック適応リズムでの蘇生ですが、なかなかROSCが得られず、アミオダロンまで使用することとなる症例です。
シミュレーションとしては、救急搬送の症例であるため、受入れ決定から搬入の時間までの時間を想定して、開始前のブリーフィングを行ってもらうと良いでしょう。蘇生開始後は初回のアミオダロン投与後にROSCとして、心拍再開後の治療に進むとよいと考えます。12誘導心電図を撮影した際に、STが上昇している波形を示して、その後の循環器内科への連絡なども実演すると良いでしょう。また、ややアドバンスな内容になりますが、本症例は年齢などを踏まえるとECPRを考慮する症例であるため、最初のブリーフィングの段階で循環器内科に応援要請することも考慮する症例であることをお伝えすると良いでしょう。
本症例は初期研修医にとって、研修終了までにできるようになってもらいたいと考えるケースそのものですので、受講生全員の知恵を合わせて、なんとか対応し切ってもらうことができたらと考えます。
最後に
本コースは時間を短縮して、蘇生のプロトコルを体験する点に重きを置いております。但し、不十分な部分も残るかと考えます。この進め方について、問題点や改善案などありましたら、コメントでご指導頂けますと幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
