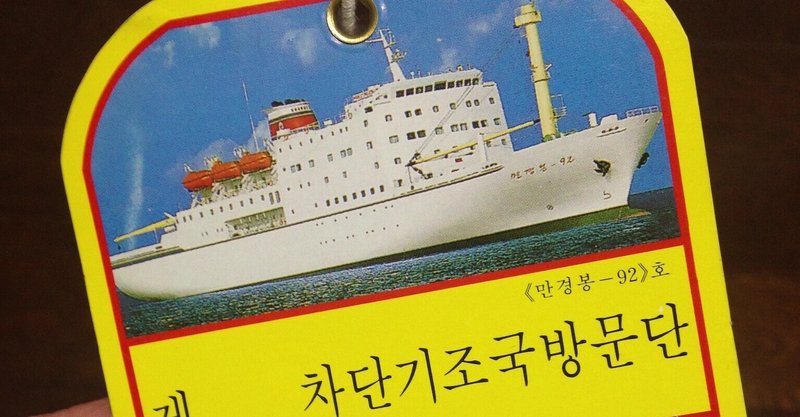
平壌への「留学」について。金元均名称音楽大学 通信受講制度。
記事掲載やイベント登壇で私の経歴を掲載していただく際には「平壌へ留学経験あり」と紹介してもらうことが多くあります。
しかし、正しくは「留学」ではなく「総聯通信受講制度」という制度なのです。説明が長くなるため「留学」という単語を使用しています。今回はその制度と思い出について少し書きます。
金元均名称音楽大学について
作曲家・金元均(キム・ウォンギュン、1917-2002)は『金日成将軍の歌』や国歌『愛国歌』を作曲し同大学の学長も勤めた人物です。国家と指導者への貢献から「人民芸術家」「労力英雄」の称号を授与されました。
日本統治の解放から間もない1946年に平壌音楽学校としてスタートしたこの名門大学は、金日成氏や金正日氏の指導のもと北朝鮮の音楽界を担う学び舎となりました。現在はエリート養成校として名高い金星学院の音楽部門を吸収統合した平壌第一・第二音楽院も傘下に置いています。
私が学んだ当時はまだ平壌音楽舞踊大学という名称で、舞踊部門は分離していませんでした。
総聯通信受講制度とは
日本各地にある朝鮮学校の生徒たちが朝鮮の芸術を本場で学ぶための通信教育制度です。
私は高校の3年間、夏休みごとに訪朝し金元均名称音楽大学(当時は平壌音楽舞踊大学)民族器楽学科の専門部にて学びました。
金正日総書記の親筆書簡による指示で始まった制度で、現地での学費や滞在費は無料、ホテルでは3食昼寝付き、卒業公演ではオーケストラをバックに演奏、毎週末には朝鮮の一流の楽団の公演を鑑賞したり金剛山や妙香山といった景勝地へ観光に出かけられるなど、非常に優遇されていました。
民族器楽科のほかに、声楽科、舞踊科、ピアノ科が設けられていました。
(私が在学した当時の情報です。制度は現在も継続しているようですが、具体的な状況は把握していません)
朝鮮新報の記事へのリンクを貼ります。
在日の学生たちが大学専門部で学ぶ様子が取材されています。

(写真)同じ先生に師事した兄弟子と、音大校舎の裏手にて。
専攻楽器 小奚琴(ソヘグム)
韓国では民族楽器や伝統音楽を「国樂」として、かつての形のまま伝承しています。現代風アレンジを行う際にも楽器はほぼ改良せず、そのまま演奏しています。
翻って朝鮮では西洋オーケストラと同じ音階で演奏できるよう様々な改良が加えられました。奚琴(ヘグム)はもともと2弦の楽器でしたが、より広い音域をもたせるため、ヴァイオリンを参考に4弦に改良されました。弦と弓はヴァイオリンと同じ物を使用します。

恩師との思い出
学生たちは専攻のほかに楽典、チャンダン(朝鮮伝統音楽の基本リズム)、ソルフェージュ、律動(ダンス)などを学びます。
専攻科目は専科房と呼ばれる個室にて専属の先生に付き、少人数制(1~3人程度)のレッスンを受けます。
私がお世話になったのは董(トン)先生。
卒業以来お会いできずにいますが、3年ほど前の朝鮮中央TVに登場していました。

(画像)朝鮮中央TVより。右が恩師の董先生。

卒業時には使用した教本に先生からメッセージをいただきました。
永遠に忘れるな。優れた民族音楽家として育ちなさい。
残念ながら、現在の私は平凡な朝鮮ウォッチャーであり、現在は在日コリアン社会とも音楽演奏とも離れて暮らしています。
先生のことを思い出すたびに胸が少し痛みます。
私の記事に関心を持っていただけましたらサポートをお願いします。サポートいただいた金額は取材費や参考書籍の購入に充てさせていただきます。
