
土屋大輔さん - やりたいことを言い続ける人
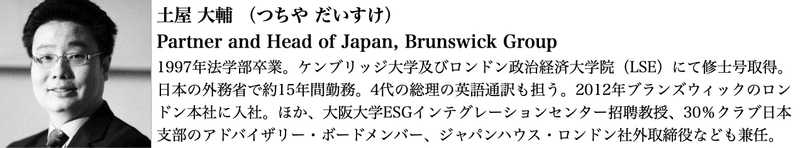
イギリスの居心地の良さに惹かれて転職
私は1歳半から14歳まで、父の仕事の関係でアメリカで育ちました。中学の途中からは日本で過ごし、そのまま日本の外務省に入省しました。
そこで1998年に海外研修先としてイギリスを選び、2年間の留学と在英国大使館勤務で合計4年間のイギリス生活。再び外務省本省に帰任してからの7年間は、沖縄基地問題やWTO ドーハ・ラウンド交渉など、イギリスとは直接関係のない業務に携わってきました。
そして、2009年に、再度、在英国大使館勤務を任じられました。仕事は充実していてやりがいも感じていましたが、3年の任期が終わる際に、自分にとって居心地の良いイギリスに残りたいと考え、転職活動を行いました。
やりたいことは周りに言い続ける
尊敬するある人から「本当に何かしたいことがあるならそのことを実際に言葉に出して周りに言い続けることが大事だ」と言われたことがあります。これは本当にそうだな、と思います。
私の転職に際しても、周囲に「ロンドンにいたい」という話をしていたら、大変ありがたいことに知り合いの知り合いが、ロンドンに本社を置く、今の会社Brunswickを紹介してくれました。企業がM&Aや危機などの重要局面において、NGO・メディア・政府・投資家・従業員などの幅広いステークホルダーとどのように協力するか、そしてときにはどのように対峙するかをアドバイスするコンサルティング会社です。
そんな仕事があるとは当時の私は知りませんでしたが、やってみたいかどうかの前に、イギリスに住みたい、ということが転職の動機だったので、ビサを出してくれるなら受けてみたい、と思い面接に臨みました。
面接では、日本に戻って日本の拠点を立ち上げることに関心はないか、とも聞かれました。しかし、そこで「日本は好きなので、日本関連の仕事は喜んでしますが、イギリスに住みたいので転職を考えています。日本に帰るなら仕事自体が好きな外務省を辞めるつもりはありません、日本への出張なら、いくらでもします。」と言うと、ロンドンでビザ付きのポジションを作ってくれました。
このように、私自身はブランズウィック最初の日本人コンサルタントとして入社したわけですが、世界中に展開している日本企業を様々な局面でサポートするニーズに応えるため、その後、日本人・日本語スピーカーの採用で忙しくなりました。採用は日本に限らず、アメリカ、アジア、欧州でも徐々に進めてきました。最初に宣言した通り、あくまで自分自身の定住地はイギリスに置きながらも日本への出張を重ね、2020年に東京事務所を立ち上げました。世界に散らばる約25人の日本人・日本語スピーカーを束ねて、日本関連の仕事を統括することが私の現在の役目です。
海外展開する企業には様々な苦労があります。各国の規制当局やNGOとの調整、海外の投資家に企業を価値をどう理解してもらうか、現地の従業員が問題を起こしてしまった場合の対処などです。ビジネスを発展させていくためには、こういった問題について、法令に沿っているか、ということにとどまらず、360度の関係者とどう付き合っていくか、が死活問題になってきます。
ブランズウィックはそのために、上記約25名の日本語スピーカーのみならず、世界23ヶ国のオフィスにいる元弁護士、元バンカー、元「物言う株主」、気候変動やサイバー事案のプロ等々、様々なバックグラウンドや専門性をもつ1500人の同僚たちと国境を超えて知識や経験、人脈を共有し、世界中に進出する日本企業のサポートを行っています。

ルールは従うものではなく、つくるもの
法学部の学生だった時「日本は成文法(ドイツ由来の大陸法)であるのに対して、英米はコモンロー(判例法)である」と学びました。当時は全く実感を持って理解していませんでしたが、今は日々の業務の中でその根本的な違いを肌身に感じています。
語弊を恐れずにかんたんに言いますと、前者は「一度作ったルールはしばらく変えないことを前提に、漏れや矛盾がない大方針(成文法)を最初に慎重に作り、それを運用する」という発想です。後者は「ルールは必要に応じて柔軟に変えたり廃止したりすればいいということを前提に、その場その場の状況でルールを作り、それが積み重なり、淘汰されたものが自然と大方針(判例法)となる」というのが私の解釈です。
大陸法と英米法の間でどちらがよくてどちらが悪い、ということではないですが、それぞれの強みは間違いなくあると思います。前者の強みはルールがコロコロ変わらないので、先の見通しがつきやすいことです。一方、後者の強みは前例にとらわれず、新しい状況に対応した新しいルールができやすい、ということです。
現在は、新たなテクノロジーへの対処、地政学的な問題への対処、気候変動への対処などについて、新たなモデルやルールが必要とされているフェーズです。しかし、そういったルールをつくる場面で強みを発揮しがちなのは英米法の国々です。イギリスやアメリカは、まず新しい法律や規制を作ってみて、うまくいかなければあっさり撤回してまた前に進むということを積み重ねていきます。その新しい法律や規制の形成には、政府はもちろん、企業、NGO等も積極的に参画して、衝突を恐れずに喧々諤々の議論を進めています。
日本企業も海外でビジネスを行う以上は、こういったルール形成を傍で見ているだけではもったいない、と感じます。そんなルール形成の議論の中に、日本企業も積極的に加わって、衝突を恐れることなく、プレーヤーとしての自らの主張を響かせていかなければならないのです。そうしなければ、いつのまにか他人が作った三角や四角の土俵の中で相撲をとらされている、ということになりかねません。
素晴らしい日本企業はたくさんあります。しかし、日本企業はその奥ゆかしさからか、他国企業に比べて発言が少なく、損をしてしまっているケースも多くあるように感じられます。日本企業が世界で真っ向から勝負していけるようにお手伝いすることこそが、やりたいことを言い続けることには遠慮がない自分の果たせる役目であると思っています。
