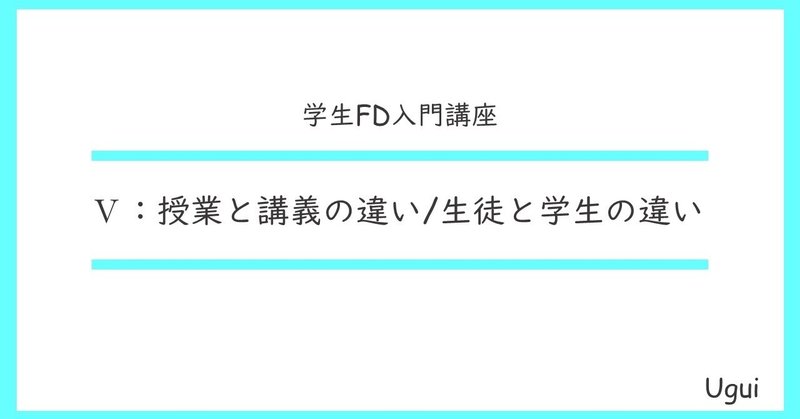
授業と講義の違い/生徒と学生の違い[学生FD入門講座Ⅴ]
〇高校から大学へ進むと……〇
高校を卒業して大学に入学すると、2つの言葉が変化します。
授業が講義になります。
生徒が学生になります。
この言葉の変化がなぜ起きるのか、厳密には分かりませんし、調べても諸説ありと出るだけでしょうが、おそらくこうではないか? と考えていることを紹介させて頂きます。
〇授業から講義へ〇
漢文チックになりますが、レ点を入れると
授業:「業ヲ授ケル」
講義:「義ヲ講ズル」
と読むことができます。
こうすると、
高等学校までの授業は、教員が生徒に対して、生きるために必要な業(仕事や暮らしの手立て)を授ける(さずける)ものである。
対して
大学での講義は、教員が学生に対して、義(どうあるべきか、どう考えるべきか、どう生きるべきか……)を講じる(述べ伝える)ものである。
と解釈することができます。
確かに、大学のすべての講義の本質が”講義”とは言えないでしょう(授業の部分もそれなりにあるでしょう)。
しかし、高校までにまずは生きていくための生業を授けてもらい、大学からはどう生きるのかを講じてもらい、それをもとに自分で思索を深めると考えると、しっくりくるのではないでしょうか?
※この考え方は、私自身のものではなく、教育哲学専門のとある教授が講義で言われていたものです。妙にしっくりきて、5年以上経った今もはっきり覚えています。
〇生徒から学生へ〇
次に、生徒から学生への変化についてです。
ここで注目したいのは、「徒」という文字です。
徒弟という言葉に代表されるように、「徒」という文字を人に対して使う場合には「身分が下で、習う立場にある」というニュアンスがあります。
一方で、「学生」という表現からはこのようなニュアンスが感じられません。
このように考えると、生徒から学生への変化は、教わる立場から自ら学び修める立場への変化であると言えるのではないでしょうか?
〇授業と生徒に必要で、講義と学生に不要なもの〇
このように考えると、高校の教員には必要で、大学の教員にはべつになくてもいいだろうと言えるものが浮かび上がるのではないでしょうか?
そう、教員免許状です。
高校の教員のように、授業として生徒に対する場合には、教員は教える立場ですから、正しいことを最適な方法で教えることが求められます。
しかし、大学の教員のように、講義として学生に対する場合は、多様な考え方を学生に向かってぶつけ、それを学生が1人の大人として判断し、思索の材料にするのですから、むしろ過度な正しさや最適な方法は、多様性を失わせるという意味で、邪魔になる場合もあるでしょう。
逆から極端な例を挙げれば、教員が例え間違ったことを伝えても、それが生徒を相手にする高校までなら大問題ですが、大学においては学生1人1人がそれを吟味し、取り入れるかどうかを決められるわけです。
つまり、大学では、学生が1人の大人として自ら学べるため、免許がない教員でも大丈夫だと言えますね。
※不快感を与えているとしたら申し訳ないのですが、高校生に判断力がなく、子どもだと言っているわけではなく、大学生との相対的な関係でお話している点はご理解ください。
〇学生FDに関わる学生へ〇
学生FDに関わっている学生の大半は、大学生だと思います。
折角なので、講義・学生という言葉の意味をかみしめて活動しては?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
