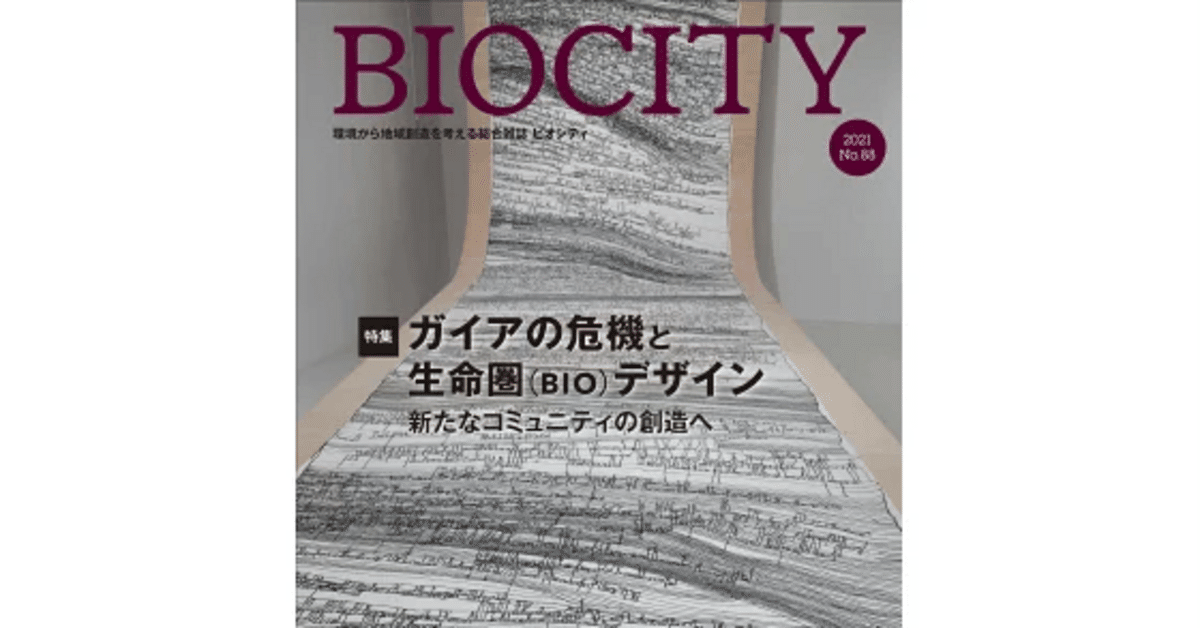
BIO+FORM考 自然と建築の幸せな関係 『ローカル+エコライフからの建築デザイン』(原稿再掲)
総合環境情報誌『BIOCITY』の88号(2021年)に『ローカル+エコライフからの建築デザイン』というタイトルで寄稿させていただいた。このNOTEで書き綴っている内容とほぼ被るが、論考としてある一つのまとまっている文章になっているので、再掲させていただく。
(以下再掲 原稿)
●山積する課題と都市の限界
環境容量の限界、それに伴う気候変動やマイクロプラスチック等の問題、資源枯渇、従来型のエネルギー源の限界などが喫緊の課題としていよいよ露呈している。現在の都市構造は過剰な資本主義に未だ支えられ、消費と廃棄を繰り返すだけの現代のシステムの縮図である。人間の所業の因果応報であることは間違いないわけだが、私たちはその問題に半ば目を背けつつ、緩慢に自殺しつつある。
こうした状況に対する警句はすでに「成長の限界」が発表された五十年ほども前から指摘されてきたことだが、この間さまざまな取り組みはなされてきたものの、未だ根本的な解決ができていない。
私たちはこれからいかに健全に、安心して、永続的に暮らしていく術を取り戻すのか、その源泉としての自然環境をいかに回復するのか、がいよいよ問われている。しかし、現在取られている様々な対策の中には、逆に生きていく人間力をむしろ奪ってしまうのでないか、と懸念される状況もある。
私たちはこの人新世の末期にあって、暮らしのデザインの根本的な転換が求められているのだろう。これまで、環境問題に対する対処はどちらかというと対処療法的な、技術に依存した方法論が主流だったように思う。果たして、問題を起こしてきた人間の「技術」というものを「技術」だけで乗り越えていくことができるのだろうか?人工的な世界認識術がこれまでの問題を起こしてきたとするならば、そのパラダイムを超えた環境認識論の上に立った、新しい方法論が模索されるべきであろう。
●機械的環境主義と生命的環境主義
世界の人口はいまや八十億に迫るが、未だ都市人口は半分を少し超えた程度のようだ。すなわち、まだ半分近くの数十億人の人間が土着的で、自然の力に何らかの形で依存しながら暮らしている割合が多いはずである。私たちも、つい数十年前まで農業などの一次産業的なものが主体の暮らし方をしており、地域の気候風土、それに伴う生業、風習を基本としながら生きていた。里山文化と括られることがあるが、自然にとても近いところで、ときにはその恵みをいただき、あるときは畏怖を抱きながら暮らしていたのである。いかに現代が進歩しようとも、一方では地面に足をつけて暮らしている人々がまだまだいることは認識しておく必要があろう。
かつての時代の環境認識の構造と現代のそれとは根本的に違うのではないか、と思われる。現在の「都市の時代」は、科学的合理性が優先されるので、環境問題に対しても合理的な判断が求められる。それはそれで間違いではないと思うが、一方で自然という大きな宇宙の仕組みに内包されている感覚知のようなものが置き忘れ去られ、それが生命としての人間の内的分裂を引き起こしているようである。
合理的判断による環境問題への対処論を「機械的環境主義」とするならば、今一度、自然をあるがままに理解する「生命的環境主義」的なところへ立ち戻る必要があるのではないか。自然や生態系への深い理解と合一的な意識、すなわち仏教でいうところの「梵我一如:梵(宇宙)と我(人間)の同一化」を取り戻すことができないだろうか。ふたつを上下構造として意識しつつ、両方からの解決のアプローチをとる「全体的解決」をこれからは構想したい。即ち、自然に根っこをもった身体性の回復である。そこまで私たちの意識の幅を拡張しないと、屋上奥を重ねるような対処的解決方法だけでは、いつまでも根本的な解決には至らないだろう。建築のデザインにおいて、機能的側面のみならず、自然との包摂的な暮らしの場を創造する提案が本稿の目的である。
●自然の理解とパーマカルチャー
自然の仕組みを非常に大雑把に煎じ詰めると、「流れ」と「循環」と「ストック」ではないだろうか。太陽のエネルギーを原資として、水を運び屋として、この地球という世界は回っている。水、風、栄養、熱が流れの中にあり、生命はその中でエントロピーを小さくする形でストックとして存在する。
そうした仕組みを見据え、世界中の土着的な暮らしを参照しながら、編集したアイデアが「パーマカルチャー」である。オーストラリアの生態学者 ビル・モリソンらが七十年代に提唱し始めた。
パーマカルチャーが提示するところは、自然界においては、全てが「資源」であり、「廃棄物」がない世界である、ということだ。
生態系や環境を総体的に認識、理解できるなら、周りには「すでに十分ある」のであり、それを活用できていないのは未だ「デザインが未熟」だからなのである。
日本のように、これから社会が縮退する状況においては、「縮小するデザイン」が必要である。より少ない資源でより精神的に豊かな状況を作っていくことは、むしろ「創造的な下降」である。私たちの技術が目先の「部分最適」的な解決を目指していることとは対照的に、自然界は常にバランスをとっており、私たちも「全体最適」を意識したデザインに転換していくべきである。


●環境建築の展望
以上のような認識のもと、これから目指すあるべき「環境建築」の姿を展望してみたい。
まず、建築を生命のメタファーとして捉えるならば、自然界の流れの中における一時的なストックである、と位置付けられる。自然物から生まれ、建築という外皮をまとい、環境と応答しながら新陳代謝を繰り返し、息長い生命力を保ち、解体される場合にはまた自然の中で再利用されるか、腐って還っていくのである。建築はあくまでもその場所に「できる」ものであり、建築外部の環境を排除し、どこからか降り立ってきたような宇宙船やカプセルではない。
近代建築の特質として、建築は設備が作っている、と揶揄されるように、均質な空間を空調技術によって実現し、全世界に拡大することが正義だった。しかしながらそれは環境容量と自然資源が無限と思われていた時代のことであり、現代においては当然のことながらできるだけ機械設備に頼らなくても済む建築を目指すべきであろう。
また、建築を構成する素材は全て地上資源の自然物で作られるべきである。特に住宅のような小規模な建築は、近代的な工業製品の素材を使わなくとも築造技術は確立されており、特殊な性能を備えなくてもよいことから、もともとその地域の気候風土に即した作り方が改めて基本となるべきである。サーキュラーエコノミーの議論が盛んな欧州においては、建築は「資源銀行」である、という捉え方をし始めているという。即ち、自然の摂理のごとく、建築がその寿命を迎えても、捨てるものはなく、次の段階の資源として活用されるデザインを目指そう、ということである。
また、温暖化の原因とされている二酸化炭素の排出量のうち、セメント産業が占める割合は約八パーセントと言われている。近代建築ひいては近代文明を支えてきたコンクリート構造物も見直しが必要な時期に来ているのではないだろうか。特に住宅建築においては、日本の伝統的な作り方は「石場建て」であった。そうした構法も改めて見直されるべきである。
●閉じたエコハウス
環境に配慮した建築を目指す議論は大いに進めるべきだが、現在の「エコハウス」なるものは、建築を機械的なものとして捉え、むしろ近代建築を支えてきた思考の延長上にあるのではないか、と危惧する。現在おもに議論されていることは、いかに建物からの熱損失を少なくするか、ということと、再生可能エネルギーを建築と一体でどう整備するか、ということである。確かに現在の粗悪な性能の住宅事情の省/創エネルギーを図ることは急務である。しかしながら、設備による機械仕掛けとし、断熱をどんどん強化して、建築が徐々にカプセル化していくことにはいささか違和感がある。
そもそも、高断熱や太陽光発電による将来的な弊害への予見や十分なテクノロジーアセスメントはされているのか、などもう少し慎重に議論した方が良いのではないかとも思われる。
建築がむしろこうして「閉じる」ことで、環境との関係性あるいは、自然の一部である、という感覚が阻害され、外部環境との連続性、果ては社会との距離感さえも遮られてきてしまうのではないか。閉じて、「部分最適」を図るのではなく、外部環境まで含めた「全体最適」を意識すべきである。
そもそも、つい数十年前までは私たちはこれほどエネルギーを使わず、しかしながら程よく幸せに暮らしていたはずである。現在の私たちの「高エネルギー体質」な暮らしを転換することからまずは再考すべきである。高エネルギー体質を放置しておいて、建物の性能と装置ばかりがヘビーになっていくのは本末転倒のように感じる。「より少ない資源でより豊かに」ということからすれば、閉じたエコハウスからのパラダイムシフトが必要ではないだろうか。
●関係性のデザインによる、開いた環境建築
自然、生態系はそれを構成する要素の関係性が重層的であることで、いわゆる「総持ち」的な関係を築いている。単一的な仕掛けやシステムに依存するのではなく、小さな「いいこと」の集積がレジリエンスを担保してくれる。
それに倣うならば、環境建築は「閉じた箱」ではなく、建築の外部に目をむけ、外部まで含めたデザインとすることである。できるだけその建築が立つ場所の環境や社会との関係性を多様に保つのが良い。それが総合的な「環境価値」の創出につながり、「社会関係資本」の再構築にもつながる糸口になる。即ち建築が多様な関係性のローカルハブとして機能する、ということである。
住環境が多様な方法で担保されている、ということは必ずしも一様一律な仕組みやシステムに依存しなくても良い健全な暮らし方につながる。即ち「低エネルギー体質」に移行していくきっかけになるように思う。
また物理的な環境性能のみならず、隣人や地域社会との関係性の構築は、将来そこで暮らしていく上での社会的セーフティーネットの確保につながる。かつての地縁、血縁に支えられた共同体の仕組みは現代においては敬遠される中、そうした新しい関係性の構築が必要とされている。
●デザインの原則
以上の観点に沿って、建築のデザインの原則として整理してみた。
一 循環型、再生産型の地上資源である自然物で建築を作る。廃棄物を出さない。
二 再利用が可能な作り方とする。建築は資源のストックであり、「捨てるデザイン」を考えておく。
三 地域の資源で作る。(人的資源も含めて。)
四 地域の気候風土に即し、その自然がもつポテンシャルを最大限に生かすパッシブデザインを行う。
五 建物周辺の微気象を創出し、外部環境を整える。
六 LCA的な評価において全体最適となっているかを意識する。
七 住まいの場に生産的行為を取り戻す。
八 菜園、食べられる空間を近傍に設ける。
九 地域文化を尊重し、技術の継承と風景を整える。
十 地域社会のハブとなるような仕組みを備える、地域との関わりしろを設ける。
こうしてみると、伝統的な建築物は、環境建築という観点からも実は非常に親和性が高い。さもありなん、そもそも空調も新建材もなかった時代は、その土地の資源と気候風土に配慮した作りにせざるを得なかったのであり、現代とは背景が違うものの、温故知新、古来からの建築のありようは改めて拾い上げる必要がある。そこに現代性を継ぎ木しながら、現代の民家を作っていく態度が必要であろう。
が、現実的にはハードルは高い。現代人には自然の素材に対する無理解、住まいづくりに対するコモンセンスの消失、住まいの商品化という状況に晒されており、環境建築が環境的、社会的資産として価値を持つことに人々の想像が及ばない。こうして建築は使い捨ての消耗品となり、いつまで経っても価値が棄損されていくばかりである。
●「里山長屋」:ローカル&エコロジーという生き方
環境、社会的危機の中で、更にコロナ禍が追い討ちをかけているわけだが、それが炙り出したものは「都市的なるもの」の限界であった。そうした状況に気づき、都市からの離脱を始めた人たちが最近は増えてきたようである。
一つの仕事に縛られ、疑問を持ちながら悶々としていた人たちが潜在的に多数いることは想像できる。リモートでの仕事の可能性が可視化され、却って都市における様々な関係性の希薄さが浮き彫りになった。
もはや都会にいなくても良い、自分の手足を確かめながら、自分の食べるものは自分で作り、環境にもできるだけ配慮した暮らしがしたい、仲間とも連携しながら良きコミュニティに属したい。そう考える人たちが増えてきている。
私は元来、物理的な意味での環境負荷の少ない建築のあり方を模索してきていた。しかしながら、生態系の「全体性」を意識したことから、多様な方法論での環境性の回復、暮らしの中における生産的行為の復権、隣人関係の関わりしろの再構築、などのテーマを通して、総合的な暮らしの場の設計を試みるようになった。
ここでは、『里山長屋』という十年前に竣工したプロジェクトを通じて、目指すところをスケッチしてみたい。

●「里山長屋」プロジェクトの背景
中山間地域である神奈川県相模原市の北部にある藤野地区。東京から比較的近いこともあって、数十年前から移住者が比較的多い。先述のパーマカルチャーの普及啓発活動を行う団体がここに拠点を構えたこともあり、環境問題の関心が高い人たちが集まってきている。そうした中、パーマカルチャーを学んだ四世帯が、環境にもコミュニティにも配慮した暮らし方を模索しよう、ということで長屋形式の多世帯による集合住宅を計画し、二○○九年にスタート、二○十一年一月に竣工した。
●環境とコミュニティの課題の同時的解決
生態系の仕組みに寄り添った暮らし方、即ち日本のパーマカルチャー的風景のイメージとしての「里山」という言葉と、良き隣人関係を育む住環境のイメージとしての「長屋」という言葉を掛け合わせ、「里山長屋」という名前のプロジェクトとした。元来、環境とコミュニティの課題は、「関係性の構築」という共通言語で括ることができる同根のものであると考える。このプロジェクトでは「全体性」をキーワードに様々な課題に総体的に取り組むことをイメージした。また、環境配慮型の暮らしは、自立的でもあり、ひいてはそれが災害や環境危機に対するレジリエントな状況を作ることができるのではないか、という試みでもある。
●コハウジングという手法
欧米では長い歴史がある、住人同士が共有して利用できるコモンスペースを備えた集住形態をコハウジング(コレクティブハウジング)という。それに倣い、個々の世帯の居住の独立性は保ちつつ、空間的には別途コモンスペースを確保することで、住人同士の関わる余地を多くしつらえた計画としている。他の多くの事例では二十世帯を超えるような規模が多いようだが、ここでは限られた土地規模から四世帯+コモンハウスの計画とした。
●複合的なテーマ設定
環境と調和する暮らし方を想起した時、単なる断熱性能のみを環境要素とするのではなく、多面的に、多様な方法論で環境建築を実現するアプローチを探っている。
伝統的構法 × パッシブデザイン
先述のように、伝統的に作られてきた建築構法が、地域の気候風土に根ざしたものであることから、元々環境との親和性がある。一方で断熱性能や間取り、明るさなど現代の暮らしにはそぐわない部分も多々ある。そうした部分は現代の技術を付け足しながら、むしろ伝統的構法が備えている環境性能を引き出したい。昔ながらの民家の壁は小舞の下地の土壁であり、調湿性や蓄熱性などの優れた室内の環境制御機能が備わっているが、現代の基準からしたら、断熱性能が劣る。現代の技術である断熱材を土壁の外側に施すことでむしろ土が持っている蓄熱性を確保し、太陽熱を利用したパッシブデザインとのマッチングが良いことから、室内の温度変化を緩やかにしてくれる。冬の昼間は南側の窓から侵入する太陽光と屋根に備えた太陽熱集熱装置により、ほとんど暖房が不要である。また日中土壁が貯めた熱を夜まで持ち越す様子が室内温度の計測で明らかになっている。土壁は全て最終的にはまさに土に還る素材であることからも、こうした手法にはもっと注目して良いと思う。
自然素材 × 地域の材
どの地域でも自前の森林資源がたくさんある。主には杉、檜の針葉樹の類だが、その素材によってしつらえられた空間は、やはり長年その素材を利用してきた人間の感性に刻み込まれている。素材が持つ機能もさることながら、実に清々しく、温かみがあるように感じる。杉などは熱伝導率が低いことなどから、床などがあまりヒヤリとする感覚が少ない。日本の住宅の多くが木造であるが、フレーム架構は木造でもその上に石膏ボードやビニルクロスなどを貼って木材自体は隠してしまう作り方が今やほとんどである。これでは木材が持っている機能やその質感に触れることが敵わず、木造建築の価値を半ば放棄しているように思う。
里山長屋では、地元の材を扱うまちで唯一の製材所の方と組み、地域材にて作ることとした。架構と内外装材には杉、檜を使い、壁は竹小舞+土壁と漆喰。木製建具類は地元の建具屋さんで製作した。竹は地域の山で住民たち自らが鉈をふるって採ってきたものである。大工職人は地域のベテランの棟梁にお願いし、かつての伝統的な構法をたどりながら手仕事で作ってもらっている。こうして、材料が地域の環境の循環の中で作ることと同時に、経済も地域で回ることとなる。
微気象の形成 × 食べられる庭
現代の消費と廃棄の仕組みに楔を打つ試みとして、回復すべきことは自ら食料を生産することに尽きるように思う。ここでは、小さいながらも菜園となる空間を各住戸の前に用意した。各世帯思い思いの方法で土を耕すこととなる。自給率アップとは程遠い収穫量だが、都会で忘れてしまった身体感覚を取り戻す作業としてはうってつけであろう。消費の場からは生産の顔がほとんど見えない。生産の現場を認識することは自立的な暮らしを取り戻す第一歩である。
一昨年からは鶏も四羽飼い始め、毎日卵を供給してくれている。隣家の子供たちが世話をしてくれていて、よき環境教育にもなっている。
菜園、食べられる庭を建物の周辺にしつらえることは、微気象の形成にも寄与する。地面の緑被は夏場の太陽の照り返しの防止になる。また幸い、建物の北側には桧林が存在するが、夏場は冷涼な微気象を形成し、冬は北風から防風林として建物を守ってくれる。南側の隣地には栗林があり、季節になると栗をこちらの敷地に落としてくれると同時に、夏場は良い日陰をも提供してくれていた。(現在は老齢化して、残念ながら伐採)
住まい手 × 地域社会
このプロジェクトのゴールは、環境配慮型の建物を作ることだけではなく、暮らしのありようを探ることである。
設計段階から、町の集会所を借りて、これからの暮らしの理想像を描くワークショップを数回行い、コンセプトを磨き上げていった。毎回二〜三十人ほどの方々が集まり、真摯な議論を重ねることができたように思う。ある回では、建設前の敷地に赴き、食べられる野草を参加者の皆で詰み、料理に仕立てるというワークショップを行った。
こうして多くの人たちと関わりを持ちながら、建設行為をするということは地域の中での仲間づくりであると同時に、建物がそれ以上の意味を帯びてくる。消費財としてのハードではなく、物語をまとった何かに変質するのだと思う。
コモンハウスは住人同士のコミュニケーションの場であるだけでなく、地域の方々との会合の場にもなったりしている。地域との関わりしろをできるだけ多く用意することで建物が地域とのハブ役を果たすことになる。
●その他の事例
また、地方においても行政の意識があれば、地産地消材で地域の職人さんとで公営の住宅をも作ることも可能だ。徳島県神山町ではそうして木造二階建てで、熱エネルギーも地場産の木質エネルギーで供給されている環境配慮型の集合住宅の設計に関わらせていただいた。
また、こうした試みは何も田舎でないとできない、というわけではない。変わらなければならないのは都市そのものであり、むしろ都会の中に生産的な居住環境をインストールしていく試みを今後益々進めていく必要があるだろう。
その原点となった一つの試みは東京の足立区にできた「畑がついているエコアパート」である。里山長屋の下敷きとなったプロジェクトである。


最後に、先に言及した神山町の風景を載せておく。畑/田、石垣、住まい、裏山、山林と人々の生業がシームレスにつながるランドスケープである。自然は分断されて存在せず、人間の暮らしもそこに連続するものであると考える。自然に寄り添うことで身体性を回復することが真の環境建築への道筋ではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
