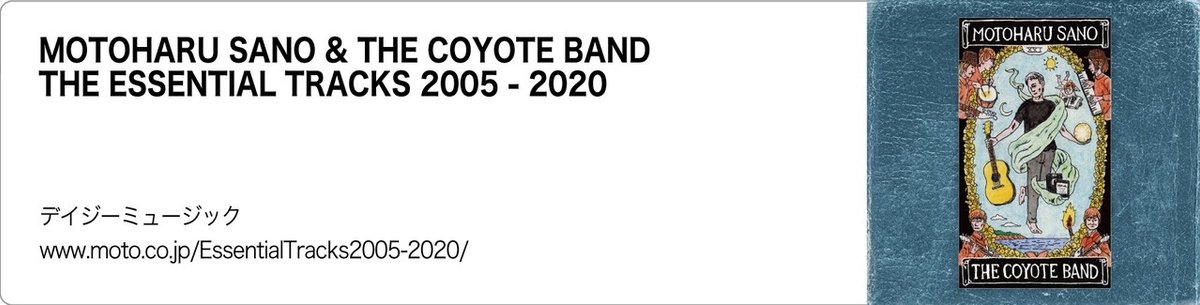【5日連続!佐野元春40周年記念特集】 DAY3:「サムデイ」でブレイク。そしてニューヨークへ
今年、デビュー40周年を迎え、タワーレコード「NO MUSIC , NO LIFE」のポスターに登場するなど、何かと話題の佐野元春。10月7日には40年のキャリアをまとめたベスト・アルバム『佐野元春グレイテスト・ソング・コレクション 1980ー2004』と『ジ・エッセンシャル・トラックス 佐野元春&ザ・コヨーテバンド 2005ー2020』がリリースされる。そこでTV Bros. note版では「佐野元春ウィーク」と題して5日連続で佐野元春のインタビューを配信する大特集を組むことになった。
【佐野元春40周年記念 ベスト盤2パッケージ 2020年10月7日 同時発売】
アルバム『SOMEDAY』『No Damage』の大ヒットで佐野元春を取り巻く状況は好転。下世話な言い方をするなら、ここからが“稼ぎ時”だった83年5月に佐野元春はニューヨークへと旅立ってしまう。
ーーアルバムが大ヒットとなり、すごくいい環境ができたにもかかわらず、佐野さんはニューヨークへと旅立ちます。日本を離れてしまうことで状況は冷えてしまうかもしれない。そんなリスクを負ってのニューヨーク行きは大きなチャレンジだったと思いますが、それでもいくべきだと思ったモチベーションは何だったんでしょうか。
「次のステップに行きたいという強い思いがあった。それは、まったく誰も聴いたことのない日本語のポップ/ロック。それをブチかましたい。これがニューヨーク行きのモチベーションだったし、そこで作ったアルバム『VISITORS』の音楽へと繋がっていった」

ーー『VISITORS』は、まさにブチかましたアルバムでした。当時の最先端だったエレクトロなNYサウンド、ファンク、ヒップホップ…。日本ではまだ一部の音楽ファンが好むだけだったブラック・ミュージック、それもカッティングエッジなブラック・ミュージックが取り入れられていて、びっくりしたものです。で、今回のベスト・アルバム『佐野元春グレイテスト・ソング・コレクション 1980-2004』のDISC ONEを聴いていて、13曲目「グッドバイから始めよう」に続いて「コンプリケーション・シェイクダウン」が始まった瞬間に、サウンドの質感、空気感がガラッと一変するのがめちゃくちゃ新鮮でした。
「そうだね。佐野元春の第2章の始まりって感じかな(笑)」
ーーまるでファンファーレのように。この曲のデジタルなエレクトロ・ファンク的なサウンドと前のめりな日本語ラップが衝撃的でした。まだアンダーグラウンドだったヒップホップにニューヨークで直接触れて、大いに刺激されたんでしょうね。
「否応もなくそのムーブメントに飲み込まれていった。ヒップホップ/ラップをやってる連中と交流するようになったんだけど、彼らが言うんですよ。MOTOは日本語でやってみろよ。日本語でラップをやれば、それは世界で初めてだぜ。クールじゃないか、と(笑)。それで日本語でラップしてみたのが『コンプリケーション・シェイクダウン』であり『カム・シャイニング』だった」
ーーでも、日本のメディアにはヒップホップ/ラップを取り入れたことに否定的な声もありました。
「メディアがどう言おうと関係ない。ファンがどう受け止めるか、ですよ。で、ファンの半分は僕の変化にOKと言い、半分はNOと言っていた。さすがに、これはどうしたものかな、とは思ったけれど」
ーーあ、ちょっと揺らいだわけですね。
「実はね(笑)。ただ、その後のコンサート・ツアーで、否定的だったファンも次第に理解していってくれて、約1年間続いたツアーが終わる頃にはほとんどのファンの人たちは僕の新しい変化を受け入れてくれた」
住むところを探すことから始めたニューヨーク生活
ーーそうした変化を後押ししたニューヨークでの毎日はどんなものだったんでしょうか。
「まず住むところを探すことから始めて生活の基盤を作り、少しずつ友達を作っていった。当時ストリート・レベルで炸裂していたヒップホップ/ラップのムーブメントを肌で感じて、僕の中に変化が生まれていった。その変化がすべて『VISITORS』のアルバムに表れている。それまでの日本の音楽シーンは、どこか鎖国的な状況だった。だから、ある意味、『VISITORS』は黒船に乗って帰ってきたようなものだった」
ーーやはり日本の音楽状況に対する違和感のようなものがありましたか?
「とは言っても否定的な感じではなくて、より楽しい所へ行きたい。そのためには閉鎖的な音楽状況に風穴をブチ開けたい。もっと自由になろうぜ! そんな気持ちが強かった」
ーーそして『VISITORS』は大きな反響を呼び、音楽シーンに風穴をブチ開けた。
「日本の音楽リスナーのほとんどがそれまで聞いたことのない様式をもったアルバムが『VISITORS』。でも、若い聴き手は先入観がないから『VISITORS』の革新性に気づいていた。手をこまねいていたのは評論家たちや洋楽ファンだった」
ーーつまらない大人たち、ですね。
「まあね」
しっかりしたバンド・サウンドを求めてロンドンへ
ーーそして80年代半ばから後半にかけて佐野さんの存在感はどんどん大きくなっていきます。
「僕が実験的な試みをしても商業的に落ち込まなかったのは、ファンのおかげだ。その力を借りて今度はロンドンでプロジェクトを立てた。それが『Cafe Bohemia』と次の『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』だ」
ーー音楽の新しい息吹をニューヨークで吸収し、次に向かったのがロンドン。その意図は?
「ロンドンの音楽シーンのメインストリームでは、若いバンドたちがモータウンに代表されるアメリカ黒人音楽の再解釈から、モダンなダンスポップを奏でていた。また、サード・ワールドの音楽がそれまでの白人の音楽と混じり合って真新しい音楽のムーブメントが起こっていた。おもしろそうだった」
ーーサード・ワールドの音楽というのは、レゲエやアフリカ音楽に代表されるエスニックな音楽のことですね。
「そう。早い時期にレゲエを取り入れたポリスやクラッシュの後に続くミュージシャンたちが、新しくて魅力的なポップ音楽を作っていた」
ーーところが、ロンドンで一緒にレコーディングしたのは、いわゆるパブ・ロック周辺のミュージシャンが中心でした。
「僕はロンドンで、流行り物の音楽ではなくしっかりしたバンド・サウンドを求めていた。プロデューサーのコリン・フェアリーが力を貸してくれて、十代の頃よく聴いていたパブ・ロック周辺のミュージシャンを集めてくれた。ブリンズレー・シュワルツやピート・トーマス。そうした彼らとのセッションを通じてアルバム『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』のレコーディングに繋がっていく」
ーーニューヨークで最先端の音楽を吸収し、今度はロックの基本であるしっかりとしたバンド・サウンドを求めてロンドンに向かう。その振れ幅が興味深い。
「僕はあまり自分のことを、こうだ、と決めつけない。直感が大事だ」
ーーだからどんなサウンドでも身にまとうことができる。
「そうでありたいよね。デヴィッド・ボウイにしてもエルヴィス・コステロにしても、アルバムごとにサウンドが違う」
<DAY3 了>
佐野元春(さの・もとはる)プロフィール
1956年、東京生まれ。1980年、レコーディング・アーティストとして始動。83~84年のニューヨーク生活を経た後、DJ、雑誌編集など多岐にわたる表現活動を展開、1992年、アルバム『スウィート16』で日本レコード大賞アルバム部門を受賞。2004年に独立レーベル「DaisyMusic」を始動し現在に至る。代表作品に『サムデイ』(1982)、『ビジターズ』(1984)、『スウィート16』(1992)、『フルーツ』(1996)、『ザ・サン』(2004)、『コヨーテ』(2007)、『ZOOEY』(2013)、 『Blood Moon』(2015) 、『MANIJU』(2017) がある。
※明日配信の第4回は『スウィート16』などを発表した90年代以降の話題からスタート!
ここから先は

TV Bros.note版
新規登録で初月無料!(キャリア決済を除く)】 テレビ雑誌「TV Bros.」の豪華連載陣によるコラムや様々な特集、テレビ、音楽、映画のレビ…