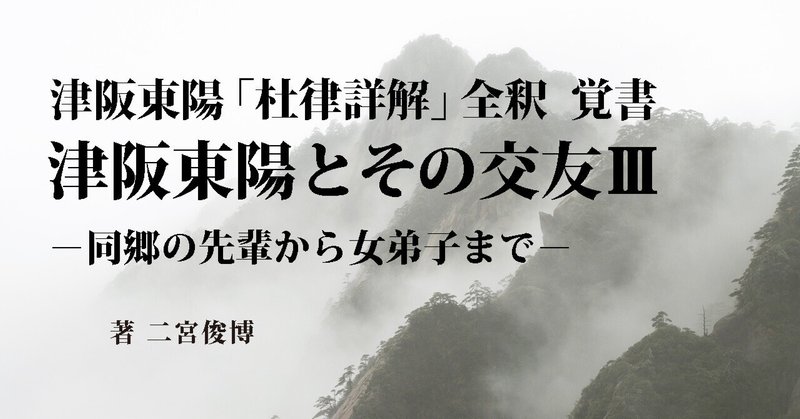
覚書:津阪東陽とその交友Ⅲ-同郷の先輩から女弟子まで-(10)
著者 二宮俊博
おわりに
津阪東陽の交友について、「安永・天明期の京都」「文化十一・十二年の江戸」に引き続き、東陽の詩を中心としてこれを探ってきたが、そのなかで注目すべきは、東陽の生地平尾村に隣接する菰野の学問的風土である。「吾薦野ハ百五十年來多クノ学者ヲ出セル郷ナリ」とは、南川金渓の言(『閑散餘録』巻下)であるが、伊藤東涯に学んだ龍崎致斎が種を播き、南川金渓や久保三水が育ち、その薫陶を受けたのが東陽であり或いは平井澹所であったわけである。菰野の知友先輩に対しては、在京時代、「久保希卿に与ふ」「南川士長に復す」「森子紀に報ず」「平井可大に答ふ」「横山士煥に答ふ」といった書簡(いずれも『文集』巻一)があり、その内容は文章論や学問上の疑義に関する事柄である。
なお、本文中には取り上げなかったが、在京時代に交友のあった人物として、越後糸魚川の邑長(里正)松山茂粛(名は造。通称勇右衛門)がおり、『日本詩選』に一首を載せるが、東陽は彼から蜃気楼について聞いた話を「越海塩山記」(『文集』巻三)としてまとめている。七律に「寄せて越後の松山茂粛の七十の初度を寿す」詩(『詩鈔』巻四)ほかがある。その長子、猷(字は子楨、通称貞吉)は那波魯堂に師事し詩を北海に学んだ。また聞き書きといえば、「水戸の赤水翁、余が為に之を語る」として磐城四倉浦(現、福島県いわき市)の不知火に似た現象を記した「赤井龍燈記」(『文集』巻三)がある。赤水は、地理学者の長久保赤水(名は玄珠、字は子玉。通称源五兵衛。享保2年[1717]~享和元年[1801])。東陽より40歳上。安永6年(1777)江戸の水戸藩邸に仕える以前、安永3年から4年にかけて一年ほど京都に逗留したことがある。
さらに交友について論ずるならば、当然ながら津藩の人々に言及すべきであろう。ただ今回は紙幅の都合もあり、これを取り上げなかった。東陽の人間関係を知る上では必要であっても、詩として読んだ際、興味を引くような作品はさほど多くない。それに関連して、本稿ならびに前々稿・前稿で紹介した東陽の詩のなかには重複表現や月並みな言い方が目につき、格段すぐれたものは少なく、詩人としての高い文学的評価を与えられないかも知れない。まさに「夫れ詩に別材有り、書に関するに非ざるなり。詩に別趣有り、理に関するに非ざるなり」(南宋・巌羽『滄浪詩話』詩弁)である。東陽自身、詩を作るのは好きではあったが、もとより詩人として遇せられるのを望んでいたわけではなく、あくまで儒者としての餘技にすぎない。とはいえ、「伊州雜賦、津城の知友に寄す二十首」(『詩鈔』巻八)や「津城雑詩三十首」(『詩鈔』巻九)のような七絶の風俗詩のなかには、その自注と相まって興味深い内容の作品が存するし、また泥人形を作って遊ぶ我が子の姿や自宅に遊びに来た隣家の猫などを詠出した「春を遺る十首」(『詩鈔』巻八)それに「夜、児に句読を授く」詩(『詩鈔』巻八)などさりげない日常生活の一齣を描写した宋詩風の七絶には佳品もあることを一言申し添えておく。
【資料篇①】
「立恭先生之碑」
天之賦才也、或頴敏或敦樸、而頴敏者、中途而易摧、否則必驚高遠失其實矣。唯其敦撲誠實、能自勉勵、才資益發、修成其業者、吾見立恭先生焉。先生諱世賢、字希卿、一字幸助。世籍於勢州菰野管下黒田村。以其居臨三重川、號三水。考定軒府君諱可久、嘗遊于洛、師事蘭嵎先生。妣久保氏。有二男、先生其次子也。本姓伊藤、奉外祖泰巖君祀、遂冒其姓。幼而不凡、受教膝下、稍長就大夫龍崎子而學。既冠來吾藩、事三角先師、親炙多年、學業大進。明和紀元、師奉君命、巡觀攝河州古戰場、先生從焉。會朝鮮聘使維舟於浪華津。先生與同友長良子軌行見制述官南秋月及成元金三書記。時先生未更姓、韓客或疑仁齋先生族、故筆語詰問其學悖新安先生、答以非其族、而奉其教者。且曰、子讀其書、未得其旨、宜細玩便得。詞鋒峻勵、客不能復詰。時年二十三。己丑還郷、命為里正、移吉澤村。日與同志講経論史、有暇必來就先師質疑、歳々以為常。天明癸卯、為大里正、明年擢爲税官焉、賜禄若干。所職尤劇、尚且教導士庶不怠。文化乙丑、進爵加禄。丙寅、嬰疾辭職不允。戊辰、從所乞。壬申五月十日卒于家。享年七十一。葬江村蓮行寺。私諡曰立恭先生。配伊東氏。子男孝恪嗣家、好文辭善書。女二人、一夭一適桑名田中某、亦先死。先生為人謹厚、廉而有信。其於學也、崇信古學紹述二先生之德、服膺先師之説、平素口其盛恩而不置。在日書牘片言字紙、謹函韞之。其作文也、宗八大家、旁玩宋學士集。詩非其所好、不多作。晩年纂集論孟古義聲援十二巻、備参閲云。余於先生、齢不相若、居不相傍。雖問侍先師、童子隅坐、何言。然先生特延余論道、未嘗以長加。余蒙先生之知、殊渥也。孝恪録状乞銘墓於先師、孫允倩病痱、不能事筆硯、因託余記事且銘。銘曰、
冠山之幽 三水之瀏 鬱々粼々 維其有人 學尚古義 名播異域
士庶稱廉 生徒受澤 事師以誠 有子克家 銘此于石 不朽不瑕
津藩文學 丹比世業謹撰子 孝恪建
(天の才を賦するや、或いは頴敏、或いは敦樸、而して頴敏なる者は、中途にして摧け易し。否らざれば則ち必ず高遠其の実を失するに驚く矣。唯だ其れ敦樸誠実、能く自ら勉励して、才資益ます発し、其の業を修成する者、吾れ立恭先生を見る焉。先生諱は世賢、字は希卿、一の字は幸助。世よ勢州菰野管下の黒田村に籍す。其の居三重川に臨むを以て、三水と号す。考は定軒府君、諱は可久、嘗て洛に游び、蘭嵎先生に師事す。妣は久保氏。二男有り、先生は其の次子なり。本姓は伊藤、外祖泰巌君の祀を奉じ、遂に其の姓を冒す。幼にして不凡して、教えを膝下に受く。稍長じて大夫龍崎子に就いて学ぶ。既に冠して吾が藩に来たり、三角先師に事へ、親炙すること多年、学業大いに進む。明和紀元[1764]、師、君命を奉じて摂河州の古戦場を巡観し、先生焉に従ふ。會たま朝鮮聘使舟を浪華津に維ぐ。先生、同友の長良子軌と与に行きて制述官南秋月及び成・元・金三書記に見ゆ。時に先生未だ姓を更めず、韓客或いは仁斎先生の族かと疑ひ、故に筆語して其の学の新安先生に悖るを詰問す。答ふるに其の族に非ずして、其の教へを学ぶ者を以てす。且つ曰く、子其の書を読む、未だ其の旨を得ず、宜しく細玩すべし、便ち得んと。詞鋒峻勵、客復た詰る能はず。時年に二十三。己丑[明和6年、
1759]郷に還り、命じられて里正と為り、吉澤村に移る。日び同志と与に経を講じ史を論じ、暇有れば必ず来たりて先師に就いて質疑し、歳々以て常と為す。天明癸卯[3年、1783]、大里正と為る、明年擢んでられて税官と為り、禄若干を賜ふ。職とする所尤も劇、尚ほ且つ士庶を教導して怠らず。文化乙丑[2年、1805]、爵を進め禄を加へらる。丙寅[文化3年]、疾に嬰り職を辞するも允されず。戊辰[5年、1808]、乞ふ所に従ふ。壬申[文化9年、1812]5月11日家に卒す。享年71。江村の蓮行寺に葬る。私に諡して立恭先生と曰ふ。配は伊東氏。子男孝恪家を嗣ぎ、文辞を好み書を善くす。女二人、一は夭し一は桑名の田中某に適ぐも、亦た先んじて死す。先生人と為り謹厚、廉にして信有り。其の学に於けるや、古学・紹述二先生の徳を崇信し、先師の説を服膺して、平素其の盛恩を口にして置かず。在りし日、書牘片言の字紙、謹んで之を函韞す。其の文を作るや、八大家を宗とし、旁ら宋学士集を玩す。詩は其の好む所に非ず、多くは作らず。晩年に論孟古義聲援十二巻を纂集して、参閲に備ふと云ふ。余の先生に於ける、齢は相若かず、居は相傍はず。先師に問侍すと雖も、童子隅坐す、何をか言はん。然れども先生特に余を延いて道を論じ、未だ嘗て長を以て加へず。余、先生の知を蒙る、殊に渥きなり。孝恪の状に縁って墓に銘するを先師に乞ふ。孫允倩、痱を病み、筆硯を事とする能はず、因て余に託して事を記し且つ銘せしむ。銘に曰く、冠山の幽、三水の瀏。鬱々粼々、維れ其れ人有り。学は古義を尚び、名は異域に播く。士庶廉を称し、生徒沢を受く。師に事ふるに誠を以てし、子有り家を克くす。此れ石に銘し、朽ちず瑕せず)
◯頴敏 才知が優れる。◯敦樸 質朴。◯高遠失其実 後漢・王充『論衡』説日篇に「平地従り泰山の巓を望めば、鶴は烏の如く、烏は爵の如し。泰山の高遠なる、物の小大其の実を失す」と。◯三重川 菰野を流れる三瀧川のことであろう。◯考・妣 『礼記』曲礼下に「生けるに父と曰ひ、母と曰ひ、妻と曰ふ。死せるに考と曰ひ、妣と曰ひ、嬪と曰ふ」と。◯府君 亡父の尊称。◯蘭嵎先生 伊藤仁斎の五男、蘭嵎(名は長堅。元禄7年[1694]~安永7年[1776])のこと。◯膝下 『孝経』孝治章に「故に親しみは膝下に生ず」と。◯大夫龍崎子 前出、龍崎致斎のこと。その伝は前掲『菰野町史』参照。◯冠 『礼記』曲礼上に「二十を弱と曰ひ、冠す」と。◯三角先師 前出、奥田三角のこと。梅原三千主編『津市文教史要』(昭和13年)参照。◯親炙 直に接して親しく教えを受ける(『孟子』尽心下)。◯摂河州 摂津・河内。◯朝鮮聘使 宝暦14年(明和元年)、将軍家治襲職祝賀のため来日した朝鮮通信使。◯浪華津 大坂。◯長良子軌 津藩の儒医、長良承芳(字は子軌、通称洞彦、号は顧斎。延享3年[1746]~文化3年[1806])のこと。東陽に五排「長良士軌の耳順の寿詞」(『詩鈔』巻三)、七絶「長良士軌道に贈る五首」(『詩鈔』巻八)などがあり、其三の自注に「士軌、京に遊びし日、博物人を驚かし、江北海は呼びて伊勢の張華と為す。家は蔵書に富み、官庫に譲らず」という。また斎藤拙堂に「顧斎先生墓碣銘」(『拙堂文集』巻五)がある。前掲『津市文教史要』も参照。拙堂の墓碣銘に「朝鮮聘使都にに入るに会し、先生之に見ゆ。詩を賦し其の文学南秋月に贈るに、秋月絶倒す」云々という。◯南秋月 制述官の南玉。◯成元金三書記 成大中(龍淵)・元重挙(玄川)・金仁謙(退石)。◯孝恪 字は士愿。通称幸助。蘭所と号す(安永5年[1776]~天保7年[1838])。◯仁斎先生 伊藤仁斎(名は維禎。寛永4年[1627]~宝永2年[1705])。朱子学を非とし、古義学を唱えた。諡は古学先生。◯新安先生 南宋・朱熹のこと。『隠居通議』巻一に「(南宋・葉適の)水心文集中に朱文公を称して或いは新安先生朱公と曰ひ、或いは朱公元晦と曰ふ」と。◯里正 庄屋。◯古学紹述二先生 伊藤仁斎とその長子、東涯。◯函韞 文箱に収める。◯八大家 唐宋の8人のすぐれた文章家。唐の韓愈・柳宗元、北宋の欧陽脩・蘇洵・蘇軾・蘇轍・曾鞏・王安石をいう。明・茅坤に『唐宋八家文鈔』一六四巻、清・沈徳潜に『唐宋八家文読本』三〇巻などがある。◯宋学士集 明・宋濂(字は景濂)の集。◯童子隅坐 『礼記』檀弓上に曾子(曾参)が重篤の病床にあったとき、「童子隅に坐して燭を執る」。その童子の一言によって大夫用の華美な簀を身分不相応なものとして取り替えさせた話がみえる。
◯冠山 鈴鹿山系の鎌ケ岳。◯瀏 水の清いさま。『詩経』鄭風「溱洧」に「瀏として其れ清し矣」と。◯粼粼 清く澄んださま。『詩経』唐風「揚之水」に「揚れるの水、白石粼粼たり」とあり、毛伝に「粼粼は清徹なり」と。◯克家 よく家を治める。『易経』蒙卦・九二に「子、家を克くす」と。『書言故事』巻二、子孫類に「人の子有るを称して家を克くする子有りと曰ふ」と。
なお、久保希卿については江村北海の安永8年(1779)刊『日本詩選続編』に詩一首を載せ、作者姓名に「藤世賢 字は希卿、久保幸助と称す。伊勢菰野の支邑吉澤の人」という。
また、この碑文に言及する朝鮮通信使の南秋月らについては、南川金渓『金渓雑話』巻中から関連する記事を抜き書きしておく。【資料篇②】からもわかるように、金渓も彼らと筆談を交わしている。
学士秋月ハサノミ大ナル男ニハ非レドモ、鬚多ク眼中ヤゝスルドニシテ声音キビシク、スベテ丈夫ナル男也。家寒素ナルヨシヲイヘリ。経学文章、往年ノ諸学士ニ比スレバ大ニ富リトミユ。見識モ尤確乎トシテ、謙遜ヲ先トスレドモ、亦容易ニ人ヲ許サゞリキ。正使ノ書記龍淵ハ予ト同年ニテ、特ニ親メリ。容貌美麗ニテ衛价ガ風アリ。鬚ナク声温也。頴敏ノ才ハ学士三書記ノ中ニ第一ト見ヘタリ。又書ヲ巧ニシテ、子昂ガ法ヲ能写セリ。五歳ノ男子一人アリト自ライヘリ。副使ノ書記玄川ハ大ナル男也。鬚ハ秋月ヨリ寡シ。豪俊ノ才ハナケレドモ、篤行質素ナル人也。人ヲ待スルコトモ忠厚餘リアリ。従事ノ書記退石ハ年五十九歳ナリ。五十八ニシテ進士ニ挙ラレタリトイヘリ。漢ノ馮唐ガ老年マデ郎署ニ有シモ同ジ比ナラン。コノ人ハ性多病ナリ。詩ハ巧ナレドモ、文章ハ巧ナラズ。コレヲ要スルニ、四人トモニ風流ニシテ醞藉アリ。吾邦ノ学者ノ如キ、圭角ヲ先ニシテ優游ノ気象ニ乏シキモノニ非ズ。予相者ノ語ルヲキゝシニ、龍淵ハ大ニ貴相アり、前途頼シキ人也トイヘリ。
※碑文は、志水氏の著書に翻刻されているのによったが、幾つか欠字(太字の箇所)や誤字がある。欠字の箇所は『菰野町史』によって補った。ただし、町史では「崇信古學紹述二先生之德」を「古学を崇信し二先生の徳を紹述して」と訓じており、それには従わない。久保三水の長子、蘭所については前記の両著に詳しい。
【資料篇②】
「金渓南川先生之碑」
君諱維遷、字士長、一字文璞、號金渓。南川氏、勢州菰野人。家世業農圃、以故君之幼時、家無一策子可讀、又無父兄親族訓導勸學、而君好文學之業、蓋出於其天資云。於此郷邑駭異、目爲神童。既而稍長、則請求多方、極力讀書、又自請受學於龍崎先生、頴悟強記、其業夙小成矣。到此親戚相勸、使君爲醫業、乃西遊京師、就堀玄孝氏、攻軒岐之書。居數年、悉得其秘薀、而經史文詩之業、亦復大成矣。於是還勢州、下帷桑名、學徒麇集。宝暦癸未、遊浪華。會韓使來聘、君與之唱和筆語、俄頃數百千言、詞翰之美、名播海外。而菰野公子、時方崇儒學、乃時時延請以資講學焉。明和中、君遂釈褐菰野。後又加秩、兼掌醫藥事。數奏神功、士庶受其業乞診治者、日夜輻輳其門。安永癸亥、祗役東都、勸學餘暇、與都下諸名士締交往來、名聲益煥發矣。君資質多病、辛丑之歳丁内艱、衰敗之餘、病大發焉。竟以九月十四日卒。享年五十。葬于大龜山金剛禪寺。前配加藤氏、生二男。長子守箕裘。次配矢田氏、生一女。君該博群書、最善詩詞。又好研究本朝典故、家家秘策、多方購求焉。又於醫書、尤多所發明云。銘曰、
釋褐桑梓 晝錦之榮 博學宏詞 人欽其名 龜山之側 茲保厥精
金剛不壊 箕裘生生
天明五年乙巳秋九月 北海江村綬撰
(君諱は維遷、字は士長、一の字は文璞、金渓と号す。南川氏、勢州菰野の人。家世農圃を業とす、故を以て君の幼時、家に一策子の読む可き無く、又た父兄親族の訓導勧学無し。而れども君は文学の業を好む、蓋し其の天資に出づと云ふ。此に於いて郷邑駭異し、目して神童と為す。既にして稍長ずれば、則ち多方に求めんことを請ひ、力を極めて読書し、又た自ら学を龍崎先生に受けんことを請ふ。頴悟強記、其の業夙に小成す矣。此に到って親戚相勧め、君をして医業を為めしむ。乃ち西のかた京師に遊び、堀玄孝氏に就き、軒岐の書を攻む。居ること数年、悉く其の秘薀を得、而して経史文詩の業、亦た復た大成す矣。是に於いて勢州に還り、帷を桑名に下す。学徒麇集す。宝暦癸未(13年[1763])、浪華に遊ぶ。会たま韓使来聘す、君之と唱和筆語し、俄頃にして数百千言、詞翰の美、名は海外に播す。而して菰野の公子、時に方に儒学を崇び、乃ち時時延請して、以て講学に資す焉。明和(1764~72)中、君遂に褐を菰野に釈く。後に又た秩を加へられ、兼ねて医薬の事を掌る。士庶の其の業を受け診治を乞ふ者、日夜其の門に輻輳す。安永己亥(8年[1779])、東都に祗役す。勧学の餘暇、都下の諸名士と締交往來し、名声益ます煥発す矣。君は資質多病、辛丑(天明元年[1781])の歳、内艱に丁り、衰敗の餘、病大いに発す焉。竟に九月十四日を以て卒す。享年五十。大亀山金剛禅寺に葬る。前配加藤氏、二男を生む。長子箕裘を守る。次配矢田氏、一女を生む。君は群書に該博たり、最も詩詞を善くす。又た好んで本朝の典故を研究す。家家の秘策、多方購求す焉。又た医書に於いて、尤も発明する所多しと云ふ。銘に曰く、褐を桑梓に釈く、昼錦の栄 博学宏詞 人其の名を欽む 亀山の側 茲に厥の精を保つ 金剛不壊 箕裘生生)
◯家世 家代々。◯策子 書冊。綴本。◯郷邑 むらざと。◯龍崎先生 前出の龍崎致斎。◯頴悟強記 聡明で記憶力が強い。◯小成 ひととおり成就する。『礼記』学記篇に見える。○堀玄孝 堀元厚(名は貞忠、号は北渚。宝暦4年[1754]没)のこと。伊勢松阪の本居宣長が在京中に医書を学んだ。◯軒岐書 医学書。〈軒〉は黄帝軒轅氏、〈岐〉は岐伯で、医術の祖。◯秘薀 秘伝。◯下帷 塾を開いて教授する。『漢書』董仲舒伝に「帷を下して講誦す」と。◯麇集 群がり集まる。◯韓使来聘 前掲、「立恭先生の碑」に見える「朝鮮聘使」。その語釈参照。◯菰野公子 土方義法(通称数馬。寛保3年[1743]~文化元年[1804])のこと。東陽に七絶「菰野公子数馬君に贈り奉る」詩(『詩鈔』巻七)がある。◯延請 招聘。◯釈褐 初めて仕官すること。◯輻輳 四方から集まる。◯締交 交わりをむすぶ。◯丁内艱 母の死にあう。◯衰敗(気力体力が)衰え萎える。◯長子 南川蒋山(名は志道、字は伯寧。通称文蔵。明和8年[1771]~天保4年[1833])のこと。伊勢長島で十時梅厓に従学した。◯箕裘 父祖の業を受け継ぐこと。『礼記』学記篇に「良冶の子は必ず裘を為るを学び、良弓の子は必ず箕を為るを学ぶ」と。◯桑梓 故郷。◯昼錦 故郷に錦を飾る。『漢書』項籍伝の「富貴にして故鄕に帰らざるは、錦を衣て夜行くが如し」から出た語。◯金剛不壊 『法苑珠林』巻七十三に「仏身は金剛不壊」と。◯生生 代々。いつまでも。
※南川金渓については、「文化十一・十二年の江戸」の平井澹所の条に参考文献を挙げておいた。そこに示した岩田隆氏の諸論考は、本文中に挙げた『宣長学論孜―本居宣長とその周辺』に収録されている。また土方数馬・南川蒋山については、前掲『菰野町史』参照。
なお、『日本詩選』に詩三首を載せ、作者姓名に「南維遷 字は士長、号は金渓。俗称南川文璞。伊勢菰野の人。今、本府の教授為り」という。また金渓の京都遊学中の詩友に大江玄圃(享保14年[1729]~寛政6年[1794])がおり、明和6年刊の『玄圃集』には、七古「伊勢海歌、南士長が郷に還るを送る」、五律「南士長が薦野公子の聘に応ずるを聞き、此の寄有り」詩がある。
【資料篇③】
「逸史糾謬序」(『文集』巻一)
猪飼文卿著逸史糾謬、求序於余、時罹恙伏枕、不能操觚。然其筆削之勤、不可不以贊一辭也。昔宋呉元美作呉縝新唐書糾謬序曰、唐人稱杜征南顔秘書為左邱明班孟堅忠臣。今觀其推廣發明二子、信有功矣。至班左語意乖戾處、往〃曲為說、以會附之。安在其為忠臣也。今呉君於歐宋大手筆、乃能糾謬纂誤、力裨前闕、殆晏子所謂獻可替否、和而不同者、此其忠何如哉。文卿之於逸史、亦誠善忠告救過、使同關子有知、則亦拜昌言於地下矣。
(猪飼文卿、逸史糾謬を著し、序を余に求む。時に恙に罹って枕に伏し、觚を操る能はず。然れども其の筆削の勤、以て一辞を賛せざる可からざるなり。昔宋の呉元美、呉縝が新唐書糾謬の序を作りて曰く、唐人、杜征南・顔秘書を称して左邱明・班孟堅の忠臣と為す。今、其の二子を推広発明するを観るに、信に功有り矣。班・左の語意乖戻する処に至っては、往々にして曲げて説を為し、以て之を会附す。安んぞ其れ忠臣為るに在らんや。今、呉君の欧宋の大手筆に於ける、乃ち能く纂誤を糾謬し、力めて前闕を裨し、殆んど晏子の所謂献可替否、和して同ぜざる者、此れ其の忠何如ぞや、と。文卿の逸史に於ける、亦た誠に善く忠告救過す。同関子をして知ること有らしめば、則ち亦た昌言を地下に拝せん矣)
◯罹恙 病にかかる。◯操觚 書写用の四角い木札を執る。転じて筆をとる。西晋・陸機「文の賦」(『文選』巻十七)に「或いは觚を操りて以て率爾、或いは毫を含んで邈然たり」とあり、李善注に「觚は木の方なる者。古人之を用いて以て書す。猶ほ今の簡のごとし」と。◯贊一辞 一言添える。『史記』孔子世家に「筆すべきは則ち筆し、削るべきは則ち削る。子夏の徒、一字も賛する能はず」と。◯呉元美 字は仲実。宣和六年の進士。◯呉縝 字は廷珍、成都の人。◯新唐書糾謬 二十巻。『知不足斎叢書』所収。◯新唐書糾謬序 ちなみに、清・顧炎武『日知録』巻二十七、漢人注経の条にも、この序を引き、「卓識の言と謂ふ可し」と評している。◯唐人云々 『新唐書』巻一九八、顔師古伝に「時人、杜征南・顔秘書を称して左丘明・班孟堅の忠臣と為す」と。〈杜征南〉は、西晋・杜預のこと。死後、征南大将軍を追贈されたので、杜征南と称する。『春秋左氏伝』の注、『左氏経伝集解』がある。伝は『晋書』巻三十四。〈顔秘書〉は、初唐の顔師古のこと。最終官位は秘書監。『漢書』の注で知られる。伝は『旧唐書』巻七三および先に挙げた『新唐書』巻一九八。〈左丘明〉は、『春秋左氏伝』の著者。〈班孟堅〉は、後漢・班固(字は孟堅)、『漢書』の著者。◯会附 原文は〈附会〉に作る。◯欧宋 北宋の欧陽脩と宋祁。◯大手筆 (詔勅など重要な)文章のすぐれた作り手。白居易「馮宿を兵部郎中知制誥に除する制」(『白氏文集』巻三十一)に「吾れ聞く武徳より開元中に曁びて、顔師古・陳叔達・蘇頲の輩有り、大手筆と称せらる」と。◯献可賛否 『左氏伝』昭公二十年に斉の晏子の言葉として「君の可と謂ふ所にして否有らば、臣其の否を献じて以て其の可を成し、君の否と謂ふ所にして可有らば、臣其の可を献じて、以て其の否を去る」と。◯和而不同 『論語』子路篇に「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」と。◯同関子 中井竹山の別号。三国蜀の関羽と誕生日を同じくするというので、つけられた。◯昌言 ためになる真っ当な言葉。『尚書』大禹謨に「禹、昌言を拝して曰く、兪り」と。
【資料篇④】
「富岡氏藏集書画冊の首に書す」(『淇園文集』巻六)
勢洞津閨秀富岡氏、余素聞其名久矣。乙丑春三月、來京謁予、出一冊子、乞予作畫、且請異日書其冊首時者、攜之還去。其冬十一月、以書寄冊子、請果前諾。富岡氏年可四十、能爲詩文、其書倣趙呉興、並皆可觀也。其來謁時、伏水米生在坐、舊與相識。問曰、君少時矢終身不嫁、今尚守寡否。答曰、妾雖女流、寧有不守宿志乎。米嘆嗟久之。又聞其父母歿後、身嘗又爲其家營之事。數往來京攝間、而今乃稍得間焉云。嗟、以一婦人、力能支其家、勞勩塵事、而其心未嘗失其文雅而娯玩書畫者、雖搢紳君子、或有愧焉。於乎亦偉矣。
(勢洞津の閨秀富岡氏、余素と其の名を聞くこと久し矣。乙丑の春三月、京に来たりて予に謁す。一冊子を出し、予に画を作るを乞ふ、且つ異日
其の冊首に書せんことを請ふ時は之を携ヘ還り去る。其の冬十一月、書を以て冊子を寄せ、前諾を果たさんことを請ふ。富岡氏年四十可り、能く詩文を為リ、其の書趙呉興に倣ひ、並に皆観る可きなり。其の来謁せし時、伏水の米生坐に在り、旧と与に相識る。問ひて曰く、君少時終身嫁せずと矢ふ、今尚ほ寡を守るや否やと。答へて曰く、妾、女流と雖も、寧ぞ宿志を守らざる有らんやと。米嘆嗟之を久しくす。又た聞く其の父母歿後、身嘗て又た其の家営生の事を為す。数しば京摂の間に往来し、而今乃ち稍間を得と云ふ。嗟、一婦人を以て、力能く其の家を支へ、塵事に労勩し、而して其の心未だ嘗て其の文雅を失はずして書画を娯玩する者、搢紳君子と雖も、或いは愧づる有らん焉。於乎亦た偉なり矣)。
◯洞津 安濃津。◯乙丑 文化2年(1805)。当時、淇園72歳、吟松44歳。◯趙呉興 元・趙孟頫(字は子昂。1254~1322)のこと。呉興すなわち湖州(浙江省)の人で、書画にすぐれ松雪道人・水晶宮道人と号した。『松雪斎集』がある。伝は『元史』巻一七二。◯伏水米生 伏見の商人で皆川淇園の弟子、米谷金城(名は寅、字は子虎。宝暦8年[1758]~文政7年[1824])のこと。松本愚山に「金城米谷先生墓誌銘」(『事実文編』巻五十二)がある。◯営生 生計を営む。◯労勩 骨折る。苦労する。◯搢紳君子 高貴なお方。〈搢紳〉は。笏を大帯(紳)にはさむ意で、大官をいう。◯於乎 感嘆の辞。嗚呼と同じ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
