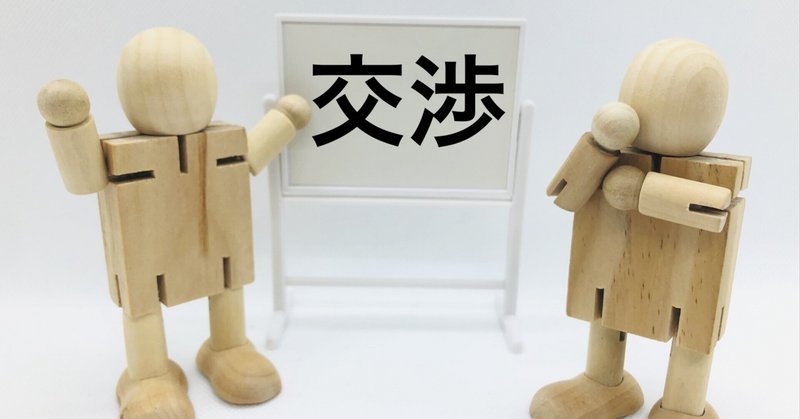
銀行員に交渉力はあるのか
結論
結論を先に言うなら、今の銀行員に交渉力は無いと考える。私は学生の頃SSでディスカッションを主にやっていた。ロジカル・シンキング(論理思考)そこで身につけた話法や交渉スキルが、行内で全く通用しないのを新入行員時に悟り、愕然としたのを覚えている。テーブルを挟んで相手側企業と交渉するイメージを抱き、行内でもその調整で上司達を相手に侃々諤々の議論をするというイメージが崩れ去ってしまった瞬間である。そこには稟議、ハンコ、文章主義(以降この3つを総称して「稟議制度」と呼ぶ)という言葉を交わさずに意思が決定されるシステムがあった。
稟議制度
稟議
稟議は例示するなら、一番下に起案者がいて、起案者のすぐ上(のポジション)の課長、課長はそのすぐ上の次長、次長にまで辿り着いてはじめて支店長がその案件の内容をみて判断を下すシステムである。要は「自分」のすぐ上にのみお伺いをたて、同意してもらえばいいシステムである。起案者以外、ここで言う課長、次長は中間的な立場であり、自分の意見を加味したければ自分のすぐ上と調整し、その調整結果を自分のすぐ下に伝達する。そして手直し後、またすぐ上と調整、同意といって、矢印で示すなら→向きの矢印を稟議の流れの向きとするなら、→→←←→→→というような動きをしてやっと決裁が下りるものである。
ハンコ
その稟議に欠かせないのがハンコである。ハンコが押されない限り「通過」しないのである。課長、次長は融資案件の決裁権限がないにも拘らず、である。全員一致・集団主義を良しとするシステムである。最初は歪な形であったものが整形され、最後にはありきたりの形となる、皆が「円」ですね、「四角」ですね、「三角」ですねとわかる、というものと言えばわかってもらえるであろうか。ありきたりの形に戻すから次の同意を得やすい、と。そんな保守的な考えを醸成するのがハンコの威力である。
文章主義
文章主義は文章に落とすことにより、その記録(文章)のみで判断することである。問題点は、文章では上手く表現できない感覚的な要素が除外されてしまうことである。起案者が相手とのやりとりで感じたことでも文章に落とし込むと、例えば「統率力がある」「技術には強い」「計数は弱い」「言葉には信用できない節がある」と書き込めるものの、ありきたりの表現でしか表現できない限界、微妙なニュアンス、程度まで文章にはできないもどかしさがある。
交渉による意思決定方式
私が思い描いたのは、起案者、課長、次長、支店長が一同に面して、起案者が予め配ってある要点資料に基づき、起案者が感覚的な要素を込めて説明し、4人で議論し意思決定する。これを「交渉による意思決定方式」とでも名付けようか、そこには下から上に上がる稟議はなく、途中のハンコもなく、全てを文章に落とし込むことも必要ないのである。
「稟議制度」と「交渉による意思決定方式」とどちらが交渉力が必要かと問われれば、答えは言わずもがなである。銀行員は交渉力を必要とされなかったのである。銀行・銀行の業界が交渉力を今まで軽視してきたからであり、従って行内の意思決定に用いれられないのである。
カードローン客の話
話は少し横道に逸れるが、私は以前こんなやりとりをしたことがある。金利が18%のカードローンの利用客から、こんなにも金利が高いという説明を受けていない、どうしてくれるのかというクレームであった。月々返済しているものの、ATMで残高を照会しても元金が余り減っていないのを不審に思い、訪ねて来られたのある。返済金の元利の内訳表をここ半年分ほど出力しお見せしたところ、確かに余り元金が減っていなかった。
客: 返済の半分以上が利息とは何だ!18%もの金利を取るなんて聞いていたら使わなかったぞ。どうしてくれる!
私: ご主人のお陰で銀行が儲かりました!ご利用していただきありがとうございました。半年間でこんなにたくさんの利益を当行にもたらしていただいたのですね。本当に感謝の気持ちで一杯です!
客(ご主人)は予想していた答えと違う答えが返ってきたのできょとんとしていた。普通の起こり得るやりとりを想定するなら……
客: 返済の半分以上が利息とは何だ!18%もの金利を取るなんて聞いていたら使わなかったぞ。どうしてくれる!
行員:お知らせしていないなんて、そんな筈はないと思うのですが…….。実際にご利用いただいていらっしゃいますし、当方としてはどうすることも出来ないのですが…….。
という受け答えをして客の怒りに油を注ぐことになっていたと思う。
私は違う方向から一発パンチを先に喰らわせたほうが、その後の展開に有利になるだろうと直感し、そういう受け答えをしたのである。
(その客の申込書を含む債権書類を保管庫からとってきてもらい)
私: ほら、申込書のお名前の横に金利がちゃんと書いてあるでしょ。(保証会社保証後の)利用手続き後、すぐにご利用されているということはその時急にお金が必要になっていたのですね。この速成型のカードローンはお申込からご利用手続きまで短時間でできるのが最大のメリットなのですが、その分金利を少しお高くしています。ところでどうでしょう、別のカードローン商品でございますが、違う保証会社の為、お手続きまで少しお日にちを頂戴します。その分金利を10%に抑えてありますので、こちらの商品をお申込みして借り直されるのはどうでしょうか?
その客は私の言う通りに違うカードローンを申込みし、借り直すどころか「お高い金利」のカードローンもそのままご利用されている。
(この私のやりとりの問題な点の批判は甘受します。)
交渉が不得手な理由
話を元に戻そう。交渉とは単に客と話すことを指すのではない。普段「交渉」をしていないと、先の話のようにありきたりの返答しかできないことになる。先程書いた、「交渉」を今まで軽視してきたというのは、今も銀行の力が強すぎるからである。銀行員は頭を下げて借換をお願いするような、顧客の銀行間の取り合いはある。取ったり取られたり、そんな話は枚挙に暇がない。重要なのは借りる相手(銀行)が替わっても、交わす銀行取引約定書を始めとする契約書は何等変わらないのである。そこには顧客の力を相対的に弱くしてしまう内容が記載されているのである。契約書の諸条項を顧客に合わせてカスタマイズできない。頭を下げ、お願いベースで顧客と契約を交わす、しかしながら契約を交わした途端、顧客は強大な銀行の力に支配されてしまうのである。断っておくが今回、銀行取引約定書の内容の問題点を挙げる気はさらさら無い。
融資回収の局面では、銀行の力をまざまざと見せつけられる。銀行はそれほどまで強い。ただ、契約書(法律)の範囲内でだけである。言い換えると、その額面どおりに力を発揮できないのである。お願いするだけで顧客は金を返さない。また、約定書を盾に脅すという不届者はいないと思うが、多分それは紙一重の差であろう、強い回収交渉を顧客とできる者が少ないのである。
交渉力は銀行員にも必須となる
金利(低レート)をエサに頭を下げて獲得する営業、お願いし情に訴える融資回収、そこには「交渉」は存在しない。
しかし今からは違う。銀行以外に資金を供給するライバルが増えた。広い意味で証券会社、ベンチャー・キャピタル、ファンドなどである。片や銀行は運転資金や設備資金という単一の先に資金を供給する以外に活路を見い出さねばならない。それはM&Aや再生ビジネスである。前者は銀行取引約定書という「葵の御紋の印籠」の効力はなくなる。カスタマイズできない悔しさは残るが、他のライバルの提示する各種契約書に対し、交渉力で勝負せねばならない。また後者も、単に頭を下げるだけでM&Aや再生ビジネスを託してくれない。綿密な計画を作成し、対象先(M&Aは被対象先とも)と交渉せねばならない。
では交渉力をいかにして高められるか。読者の方は物足りなさを感じるかも知れないが、方法論を訥訥と述べることはしない。交渉には相手が必要であり、学習して初めてできるものでもない。書店などには交渉力云々の本が並んでいるが、本を読むだけでは勿論、交渉力はつかない。一番の近道は普段から「交渉」することである。ただ先にも述べたように、稟議制度の中で果たしてできるのであろうか。疑問である。銀行の中でできないことを、銀行の外でやるとしても限界がある。今後この銀行組織の行き着く先を、交渉力を必要とする組織にしたい願いがある。即ち、交渉力=利益=強い組織(企業)にしたい。その関連性は今回は割愛させていただく。
5つの交渉要点
最後に、私が顧客と交渉するときに気を付けていることを5点述べる。
① 顧客(相手先)を充分に予習する。
② 殆どの質問はYes ,No 形式、或いは数値の答えにする。
③ 選択肢はこちらが用意する。
④ 相手側のテクニカル・タームや比喩を用いる。
⑤ 冷静で真摯であること。
① 敢えて書くことすらどうかと思ったが、それをやれていない銀行員が余
りにも多すぎる。行って話していくうちに何とかなる、と。相手の「弱い」ところを頭に叩き込んで交渉に臨まねば意味はない。
②「どうですか?」「どう思いますか?」など、相手のバリューに両足まで踏み込んでしまうような質問は愚問である。相手のペースに巻き込まれてしまう恐れがある。
③難しいと思うが、選択肢はこちらが用意・提示できるよう議論の流れの中で相手に自然と受け入れさせるのがポイントである。そうすることにより交渉をリードできる。
④交渉とは自分の言うことを相手に理解してもらわねばならないことである。テクニカル・タームとは、相手の使用する単語である。例えば「お客様」のことを相手側が「顧客」と呼ぶ場合、こちらが行内で「お得意様」と呼んでいても相手に合わせ、すぐさま自分の言語に変換する。自分らしかわからない専門用語はなおさらである。噛み砕き、わかりやすい比喩などを用い理解してもらう。
⑤感情的にはならずに強い交渉ができることである。
この文章は今から20年前に書いたものです。今の銀行組織は少なくともこうあって欲しいものですが、さて、どうでしょうか?
(終わり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
