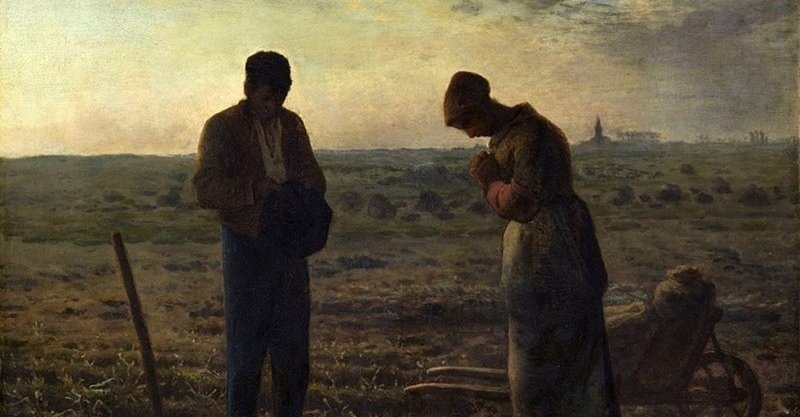
5.エホバの証人の教理の考察⑧「誕生日」
日本では現在、誕生日を祝うことは西洋と同じように広く行われています。この習慣について面白い記録があります。
「婦人と子ども」(1903年11月号。フレーベル會刊)
「我が国ではひょっとかすると、親の誕生日や自分の誕生日までも知らない者がある位だから、まして友人の誕生日など覚えている人はおそらく少なからうと、思はれる、所が、外国殊に独逸あたりでは、誕生日を祝するといふことは、中々大切なことになっていて、朋友同士互いによく誕生日を記憶して居つて、其日になるといろいろ趣向をこらして送物をする、(中略)此美風はどうか我が国にも移して…」 (漢字は新字に変更。以外原文ママ)
明治時代の雑誌(現お茶の水女子大学附属幼稚園の発行)ですが、このころ誕生日の祝いは日本では一般的ではなかったということがわかります。「我が国にも移して」とあるので、日本でもこの習慣を広めて行こうという論旨が読み取れます。近代以降、個人を重視するようになった結果であるとも言えます。(歴史上のお偉い方達の場合は例外でしょうけれども)。これより古い時代の日本の誕生祝いについては諸説あるようですが、とりあえず明治の時代の雰囲気がわかったかと思います。「誕生日」祝いは人類普遍のものではないということだけ冒頭でまず取り上げておきます。
エホバの証人の考え方
さて、エホバの証人が誕生日を祝わわないのは有名です。信者になると急に子供などの誕生祝いもしなくなるので、子供も信者でない家族も当惑することになります。(日本では親の誕生日というより、子供の誕生祝いを重要視する向きがあるでしょうか)。
この根拠とされるのは、聖書中の誕生日が全て良くない出来事と結びつけられているというものです。また、ユダヤにそのような習慣がなかったことなども根拠とします。ものみの塔紙上では次のように理由が説明されています。
塔03 11/15 27ページ 読者からの質問
「エホバの証人は誕生日を祝いません。その祝いは個人に過度に注意を向けるものですし,聖書には,まことの神に仕えていなかった支配者たちの誕生日のことしか記されていないからです。」
しかし、誕生日を禁止する(奨励する)明確な命令が聖書にあるかと言えば、「ない」というのが答えです。(下記のヨブ記の例などは解釈の問題です)。従って、禁止するかどうかは、各宗派の解釈次第ということになるでしょう。参考になるとすれば、ユダヤ人や初期クリスチャンたちがどのような習慣を持っていたかを調べて見ることでしょう。それも、時代と共に変化してゆくのであり、絶対的基準ではありませんが。
歴史的視点
古代ユダヤにおいて、誕生日を祝うという習慣がなかったことはおおよそ学問的に合意されていることです。現在でも、中東文化においては、誕生日は重要ではなく、年齢を知らない人さえいます。つまり、これは文化の問題でもあります。ムハンマドの誕生日の祝いも多くの土地で厳罰をもって禁止されています。(サウジなど例外もありますが)。
誕生日を祝うという概念は、個の認識が強い国民性に関係しているとおもわれます。中東の文化や歴史風土では、誕生日の重要性は顧慮されなかったということなわけです。論点としてはそれますが、中東やインドなどでは日記を書く習慣がなかったといわれますが、その理由としてやはり個を重視しない風土や時代背景を挙げる学者も多いです。このような背景が誕生日に対する見方にも影響しているのかもしれません。
キリスト教の歴史という観点から言えば、当初は誕生日を祝う習慣はなかったと考えられます。オリゲネスは3世紀初頭に、誕生日は異教の風習であるとして批難しています。今日のエホバの証人と同じく、ファラオとヘロデ(「異教徒や神を恐れぬ者」)の例を挙げて、批判しています。
つまり、聖書は誕生祝いを直接禁じてはいないものの、オリゲネスが指摘しているとおり、初期の記録の多くには誕生祝いに対する良からぬ感情が表れているというのも事実です。この問題が聖書に直接指摘されていないのは、当時誕生日を祝うこと自体当たり前ではない状況があったのではないかと思われます。ユダヤを起源とするキリスト教にも、もともと欠如した概念だったのでしょう。さらに言えば、オリゲネスの指摘通り、異教のイメージが強く、あえて良い悪いを評価する以前の問題だったのかもしれません。「そんな異教の習慣をわざわざ持ち込まなくても」というような感覚だったのでしょう。
これは、クリスマスの祝いについての歴史を見てもわかります。当初イエスの誕生日付すらあまり重要視されず(死が重要であった)、3世紀後半まではほとんどイエスの誕生の日付には関心は払われませんでした。(個人的にいつ誕生したか想定した人はたくさんいます)。やがて4世紀になると1月にイエスの顕現際を祝うようになります。
キリスト教は様々な「異教の習慣」を取り入れながら発展しました。ヨーロッパに伝播して行く際には、墓に花を手向けることや、ろうそくの使用などがなんども禁止されました。それでも結局は多くの習慣を取り込みながら現代に至っています。プロテスタントはその一部を批判し、否定しましたが、それでも多くの習慣を残しています。
今日エホバの証人は「異教的」な祝日や習慣を排除すべきだと主張します。その際の基準は、「現代でも異教的な意味があるかどうか」というものです。しかし、これはきわめて曖昧なものです。結婚指輪、乾杯、校歌、武道、祝日や学校行事など、多岐にわたる習慣があります。良いとするものもありますし、良心の問題から禁止まで判断も様々です。多くは聖書にはっきり書かれてはおらず、歴史的に言えば教会や教会会議が決めてきた問題です。それを今日「統治体」が決定しているのです。問題によっては「良心的な問題である」といいつつも、その幅を「統治体」が決定しているのが現状です。カトリック的な権威構造を批判するのであれば、このような体質自体も改善すべきでしょう。
このような流れを考慮するなら、誕生日を祝うかどうかは「禁止」するものではなく、良心に応じて決める自由なものであるべきでしょう。
上記のものみの塔が指摘している、個人を過度に重視するという傾向は確かにクリスチャンとしては、考えなければならない問題でしょう。これまでも繰り返しているように、キリスト教は結局人間中心主義ではなく、神中心主義だからです。(人間中心主義がキリスト教世界から顕著に始まるのも興味深いものですが)。中国の一人っ子政策の結果、「小皇帝」といわれる過保護な子供たちが増えているというようなニュースを聞くと、適切な愛情と過保護の違いは重要だとは思わされます。ならばというわけではないのですが、子供が「産んでくれたことを親に感謝する日」と考える方がよいのかなという気もするわけです。
ヨブ記の「誕生日」?
ちなみによく話題になるヨブ1章4節の「自分の日」とは、誕生日のことではないというのが「学問的」には優勢な説です。これは、毎日担当を変えて、祝宴を催していたということに過ぎないとされます。いくつかの翻訳を確認してみます。
字義「それぞれ自分の日に」
新世界訳(オリジナル):「自分の日に各々」
新世界訳(2019):「日を決めて順番に」
新共同訳:「それぞれ順番に」
聖書協会共同訳:「それぞれ自分の日に」
口語訳:「めいめい自分の日に」
やはりオリジナルの新世界訳は字義訳だけあって、分かり易い翻訳です。ただ、新世界訳の改訂版になると、かなり意訳になり、「誕生日ではない!」という解釈が含まれるようになってしまいました。基本的に日本で普及している聖書の多くは、あえて誕生日である(ない)という解釈はしていません。新共同訳略解では、「毎日ではない」意味であるとし、ヨブの息子達が人生を謳歌していたと説明しています。ただし、関根正雄訳「ヨブ記」では、疑問型にはなっているものの、「誕生日か」と推定しています。
文脈にあたる3:1のヨブが自分の誕生日に言及している(ただ、これも誕生日というニュアンスより、生まれたことそのものというニュアンス)のを関連づける人もいますので、やはり解釈次第ということにはなるでしょう。
まとめ
冒頭の資料でもわかるように、本来日本にさえ今日的意味での誕生祝いの習慣はなかったことを覚えておくと良いでしょう。「古来の習慣」だと思っていたものが、ここ百年ぐらいに始まったものだった、などということも以外に多いものです。
「子供のころの貴重な経験を失わせている」という意見もあり、現代的な価値観との兼ね合いも考慮されるべきかもしれません。子供が学校で誕生日の行事に参加できないことや、友人の誕生日を祝えないことから来るストレスなども考慮されるべき時代でしょう。
もっとも、家庭や世代によっては、誕生日など縁遠いという方も日本には大勢おられるのも事実です。聖書は直接は何も言っていないのですから、この件では目くじら立てすぎないことが重要かと思います。そして、この習慣を大事に思っている人たちの思いを尊重することも重要でしょう。
古代教父時代から数世紀、「誕生日のくだらなさ」は、何度か言及がある。(オリゲネスなど)。
初期教会は誕生祝い禁止にも務めた記録が残っている。
ただ、聖書自体が明確に禁止はしていない。ただし、記載される誕生日についての視点が、軽蔑的であることも確かである。
ユダヤ人にとって、誕生日をいわう習慣がなかったのだから当たり前か。(これは日本も同じ)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
