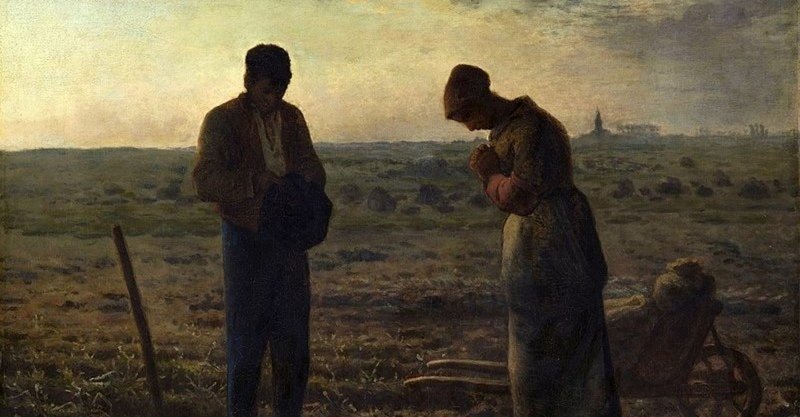
5.エホバの証人の教理の考察⑩「慈善事業について」
病にて入院などがあり、しばらく更新が滞りました。
さて、エホバの証人は、病院経営や学校経営はしない方針であり、あくまで伝道を本来の任務として行なってゆくという方針です。
最初に申し上げておきたいのは、彼らが他人の福祉に無関心であるというようなことは決してないということです。(自分を含めて)エホバの証人を批判する人たちが忘れてしまいがちなことですが、多くの場合彼らは一般社会でも「いい人たち」です。「円熟した」エホバの証人たちは、近所の世話をやき、「見知らぬ人」を助け、災害時には献身的に助け合います。私の友人は、田舎に「協会の任命で移動」しましたが、地元の町内会などにも積極的に参加し、「飲み会」の席にも積極的に参加して地元の信頼を得ていたことを思い出します。(私は人付き合いが苦手でしたが)。私が「移動」した田舎の会衆の場合は、日曜の清掃などのために集会の時間をずらすなど、地域でのできる限りのことはしたものです。もちろん、これも「布教のため」(「よい証言になる」という言い方をします)と言われればそうなのですが、地域の良い隣人であろうという努力がなされているのも事実です。
その一方で、熱心すぎて極端な人たちや、逆に怠慢な人たちはどの組織にも存在し、その人達のイメージが強烈に残り、良い評判を吹き消してしまうということもあります。(私を含めて、もともと社会からはみ出していた人たちが入信するということも原因かもしれません)。
本項目の慈善事業や地域での立ち位置に関する議論は、これらの要素を冷静に見つめた上で、行われてゆくべきでしょう。
エホバの証人の「慈善事業」への見方がわかる公式記事を紹介したいと思います。過去の機関誌では以下のように説明されています。長いので、一部省略しますが、基本的な趣旨を損なわないように配慮したいと思います。(記事はネットでも閲覧できます)。
目ざめよ!74 3/8 5–7ページ
慈善事業への寄付はいつの場合も賢明なことと言えますか
自分の寄付するお金のわずか1%から5%が困っている人びとの手に渡るだけで,あとはみな募金運動の費用に使われるとしたら,あなたは慈善事業に寄付することをどう感じますか。慈善団体の一番上に立つ人が,給料および経費として年間7万5,000㌦受け取っていることを知っているとしたら,あなたは慈善事業に対する寄付をどう感じますか。決して良い気持ちはしないのではないでしょうか。ところがそういうことが実際に,しかもたびたび生じているのです。
<略>
正しい動機から出た施しに祝福があることは事実です。しかし人が,自分はまちがいなく価値ある目的のために寄付をしているということをはっきり知りたい,と思うのも無理のない話です。慈善団体に寄付される何兆円というお金は,人びとを助けるためにどの程度使われているのでしょうか。そして博愛に基づく団体と考えられているこれらの団体は,営利を目的とする人びとによってどの程度運営され,あるいは利用されているのでしょうか。
宗教の名のもとに
カリフォルニア州のある新聞は,この寄付の問題と,募金の方法とにかんし,「かかりすぎる総経費,募金費が高いのは専門家の責任」という見出しの記事をかかげました。同記事は,地方都市の「慈善事業推進局」の局長が述べた,「慈善事業の中でも最もきたないのは」,「神の名のもとに」行なわれるものである,ということばを引用しました。そのようなスポンサーを持つ専門的な慈善運動にかんし,彼はさらに,「主の名のもとに寄付を集める宗教団体や人びとがいちばんよくない」と述べました。
<略>
高い募金運動費
赤十字のような,全国的に知られている有名な慈善団体は,10%から15%を募金運動費に当てるのが正当で無理のないところと考えています。したがって,寄付1㌦のうち85セントから90セントが慈善事業にまわされることになります。しかし多くの慈善団体はそれにほど遠い状態にあります。たとえばアメリカ腎臓基金は最初の年(1971年から72年)の間に77万9,000㌦を上回る寄付を集めました。ところが1973年6月8日のニューヨーク・ポストによると,患者の治療に当てられたのはわずか5%の3万9,000㌦にすぎず,残りは「経費」となってしまいました。
<略>
平衡の取れた見方
「貧しい人たちは常にいます」とイエスは言われましたが,そのことに疑問はありません。(マタイ 26:11)またイエスは,与えること,愛他的であること,人を助けることには喜びがあるとも言われました。しかしだまされやすいことは,貪欲な者や怠惰な者に報酬を与えることになります。施しを受けるに価する人また理由がある以上,人は分別を働かさねばなりません。「買い手は用心」という言いふるされたことわざを,「施し手は用心」と言いかえることができるでしょう。
そしてもちろんクリスチャン奉仕者である人たちは,金銀よりもはるかに良いものを与える立場にあります。それは何でしょうか。それは,慰め,希望,平安な思いをもたらし,永遠の生命さえもたらし得る神のことばの真理です。彼らはそれをただで受けたので,ただで与えます。(マタイ 10:8。使徒 3:1-8とくらべてください)そして使徒パウロは実際に,与えるさいわいのほうが大きいことについてのイエスのことばを,この種の施し,つまり霊の物を与えることにかんして引用しています。―使徒 20:35。
まず、この記事の主題には「いつの場合にも」と書かれていますから、確かに慈善事業が絶対だめだという趣旨ではないのは明らかです。しかし、全体のトーンは、慈善事業の不正などを強調し、使途の不透明さなどを強調しています。
このNOTEの前節でも強調したことですが、エホバの証人も、会計の不透明さは深刻であり、まったく他者を批判できないという点を忘れてはなりません。つまり、経費をまかなう寄付の使い道だけではなく、信者たちを救援する際などに使われるいわば「慈善事業費」についても、人の批判をしている場合ではないことにまず気づくべきです。
繰り返しになりますが、エホバの証人が互いに愛情をもって支え合い、助け合うことは良く知られていることです。私自身、貧しいときには本当に良くしていただきました。エホバの証人をやめてしまうと(そのやめ方も関係しますが)、このような点をすっかり忘れて、批判だけしたくなる場合が多いものです。実際には、病気の時や苦しいときも「嘘偽りのない」愛情を示していただきました。これらのことは、ここでもう一度きちんと申し上げておきたいと思いますし、今でも感謝しています。
さらに、公平を期して以下の記事も引用いたします。
目93年6月8日
慈善団体はどれも無駄が多くて詐欺的だと決めつけないようにしましょう。事実を確かめた上で,与えるかどうかを自分で決めてください。
確かにすべての慈善事業を否定しているわけではないのです。とはいえ、自らは決して「慈善事業」を行わないことや、そのような行為に多くの時間を取られることに否定的であるということだけは一貫しています。(事実赤い羽根募金などに募金することは我が家では「無駄なこと」と戒められていましたし、羽を付けて歩けるような雰囲気はありませんでした)。
では、キリスト教の成立時からの歴史は何を教えているでしょうか。
歴史的に見たキリスト教の慈善事業
初期教会において「使徒行伝」などを見ると、教団としての共有財産があったことがわかります。この寄付を巡っては歴史的事実かは別にして「強欲な人が神罰を受ける」(アナニヤとサッピラ[サフィラ]の例)ほど、共有の精神や進んで寄付する精神が強調されていました。
また1世紀にはパトロンとして巨額の寄付を行うような信者も現れ、寄付による資金集めは非常に重要な課題でもあったのです。使徒行伝の記録ではパウロが最後にエルサレムへ旅したのも、信者の献金を届けるためでした。(パウロが異邦人への伝道の権利を担保できたのは、このようなエルサレム側への献金を約束したからであることは聖書にはっきり示唆されている)。
また、「孤児ややもめ」を世話することは重要なテーマであり、そのための組織もなされていたことがわかります。このような慈善事業は、「終わりの遅延」とともにさらに必要になりました。史的イエスは、すぐにでも来る終末という意識を持っていたと考えられるので(異論はあると思いますが)、当初は財産など不要、または共有すればよいと考えられたのも当然でしょう。しかし、終わりが遅延して行くにつれて、信者の生活や教団の財産が問題になります。
その後4世紀ごろには、以前のNOTEでも言及した、ローマ皇帝ユリアヌスの言葉にもあったように、クリスチャンの相互扶助組織はきわめて発達しており、既に信者以外にも援助の手を差し伸べていたのです。
その象徴がクセノドケイオン(異人宿泊所)です。上記のユリアヌス帝の時代には各都市にもうけられていたようです。このクセノドケイオンには病院としての役割もあり、P.ブラウンによれば、このような施設は「古代世界において新奇な制度だった」といいます。このような施設は350年代から見られるようになり、以後近代までキリスト教の特徴となりました。もちろん、このような施設は悪い言い方をすればある種の「ばらまき」であり、人気取りだったとも言えるでしょう。しかしそれでも、慈善行為によって結果的に多くの人を救ったという事実は変わらないわけで、現実の人間社会では必要なものだったのです。
それでも、6世紀ごろまで教会自体が莫大な資産を持つことはまれでした。(P.ブラウン)。しかしその後教勢の拡大とともに、富の分配や貧者の救済は、ますます教会の重要な役割となりました。これは、地域社会が基本的にほぼクリスチャンで構成されるようになったため、教会の役割が変質しつつあったことを意味します。教会には、富の再分配の役割が期待され、今で言うような「慈善事業」の形態が整っていったと考えられます。
このあたりの詳しいことは、以前も紹介いたしました、ピーター・ブラウンの「貧者を愛する者 古代末期におけるキリスト教的慈善の誕生」に詳しいので、お勧めです。
何が問題なのか
慈善事業(いわゆる「霊的」以外の)を行うかどうかは、その教派が決めることでしょうし、経済的な負担を考えれば当然限界もあります。
では、エホバの証人の場合何が問題なのでしょうか。ここで、問題点を2つだけ挙げたいと思います。
1.終わりの遅延に関係する問題
終わりの遅延については、既にNOTE前半の各部分でも扱ってきました。この後の項目でも「終末論」の問題を考えますので、詳しい議論はここでは置くとして、関連する問題だけ指摘したいと思います。
エホバの証人の現在の「慈善事業に対する態度」の背景にあるのは、「間近に差し迫った終わり」ということが関係しています。つまり、もうすぐ神の裁きが近づいているのだから、何を置いてもそのことに警鐘を鳴らす必要があるということです。もしこれが真実であれば、確かに重要な活動は「伝道」であり、優先順位からいっても他の活動は後回しということになるでしょう。
しかし、実際はどうでしょうか。
まず聖書主義的な説明になってしまいますが、イエスは、おそらく間近に迫った終末を信じていたと言われます。(特に史的イエス)。しかし、それでも多くの人たちに「奇跡的な食事」をさせ「病人を癒やし」たとされます。これらが事実かは別にして、少なくともイエスは現実の問題にも目を向けている人物として描かれています。エホバの証人の解釈は、これらのイエスの「慈善行為」は、あくまで将来の「王国の支配」のデモンストレーションであるとします。確かに福音書内のイエスの色々な言動を総合して色々な解釈ができるでしょう。しかし、このような解釈は「逃げ」と言えないでしょうか。
現在「終末の遅延」は現実です。絶対に終末が来ないとは言いませんが、少なくとも1世紀以来、幾度もその期待は延期されてきました。そうであれば、「霊的な福祉」だけを中心にした宣教活動はやはり無理があるでしょう。現在のキリスト教諸宗派の多くが、慈善活動に力を入れるのは、ある意味で「終末」が来なかったからです。歴史的にみても、初期には終末を熱望した時代もありましたが、数百年数千年を経て、終わりが来ないという現実が、様々な(教理的な)変化を及ぼして行くのです。(そもそも王国って何?など)。
既に「終わりの日」に入って100年を超えました。前回1975年の「予言」が外れた(これは事実であることを認めなければならない)時から数えても、既に40年以上が経ちました。赤子が壮年になるほどの時間がたったのです。そうなると、「終わりが近いから、慈善事業をしない」という言い訳はもはやできないはずなのです。
2.寄付の還元の問題
二つ目の問題は、寄付が信者に十分還元されているのかという問題です。営利企業ではない以上、株主や社員への配当や給与のように「直接還元する」ということを問題にしているのではありません。また、「寄付」なのですから、何か「見返り」が期待されているわけでもありませんし、実際寄付する信者も見返りを期待せずに誠実な気持ちで寄付しているでしょう。
この「寄付の還元」という言葉を使うことで私が強調したいのは、寄付を受ける側(協会)の誠意の問題です。
宗教において、宗教施設や寺院を修繕したりするのはもちろん重要なことであり、相応の費用がかかるのは理解できます。壮麗な聖堂を建てるのも、その宗教の教義上必要なら批判はできません。
とはいえエホバの証人の場合、質素な暮らしを標榜し、信者にそれを推奨してきたことを考えると、そのような「はこもの」に過度なお金をかけることはすべきでないでしょうし、教義とも反することになります。王国会館や大会ホールは必要でしょうし、本部や支部の建物も必要でしょう。昨今王国会館や大会ホールも売却されるようになりましたが、これが信者の福祉のためであるなら、何も問題はありません。しかし実際は、信者が不便になったり、遠くまで出かけなくてはならなくなっています。なぜ売却がそれほど必要なのか、適正な情報の開示と会計の報告が必要となるでしょう。(この点はこれ以上はここではあつかいません)。
また、最近建てられた新しい本部は非常に立派なものですし、新しい映像教材を作成するための施設も新たに建設し始めています。(2021年現在)。視聴覚教材はたしかに非常に効果があるでしょう。しかし、肝心の「聖書冊子協会」の部分はどうなっているのでしょうか。ペーパーレス化やネットの利用などは時代の流れでしょうけれど、あまりにバランスを欠いている気がします。出版物の発行は激減し、内容も明らかに「浅薄」になっています。一般向けの雑誌の発行などは2020年から2021年にかけて、コロナの影響もあったとはいえ、停滞しています。これでは信者の福祉を真に省みているとは言えないでしょう。ビデオやドラマが悪いとは言いません。肝心の部分を忘れているのではと言いたいのです。
私の言いたい「寄付の還元」という言葉の意味は、信者の福祉にもっと関心を寄せるべきだということです。多くの誠実な信者は、昨今の電子化についても支持しているようですし、多くのビデオ教材や音楽などにも満足しているようです。しかし、問題をもっと冷静に考えてみるべきです。厳しい言葉を使えば、かつての「霊的食物」は、嗜好性の良い「ジャンクフード」に(いつの間にか)なっているのではないかという問いかけをしたいのです。
エホバの証人なりの「慈善事業」を考えて見るべき
他の宗教団体と同じようにすれば良いと言っているわけではありません。それぞれの組織体ごとにオリジナリティが発揮されるべきでしょうし、このNOTEで「こうあるべきだ」というような、特定の方法を主張したいわけでもありません。
それでも、特に災害時における対応や慈善行為について、もう一度見直すべきではないかと思います。確かに、エホバの証人は災害時にも迅速に信者を助けることで知られており、そのこと自体は素晴らしいことです。
しかし、災害時における一般社会への気遣いという側面について言えば、かなり反省点があるのではないかと思うのです。
たとえば、東日本大震災が発生した当初の公式ウェブサイトには、一般向けの気遣いや「お見舞い」「お悔やみ」のメッセージはまったくありませんでした。これはある意味で「衝撃的」です。大震災発生直後に、いろいろな宗教の公式ウェブサイトを調べてみましたが、ほとんどのサイトに一般の方達へのお見舞いやお悔やみの言葉がありました。しかし、エホバの証人のサイトにはそれが全くなかったのです。信者の(プライバシーの範囲内での)安否情報に関しても、結局支部からの手紙が来るまでわからない有様でした。公式サイト内での報告もかなり遅れて掲載されました。
もちろん、これも彼らが邪悪だからこうなるということが言いたいのではありません。その「一途な」信条故に「盲目」になったり「無感覚」になっている部分があるのではないかと指摘したいのです。どんなに伝道しても、このような点での配慮を欠くなら、社会の理解も得にくいのではと思います。
信者の福祉について
より重要なのは、せめて信者に対する福祉をもっと充足させる必要があるのではないかということです。もちろん、信者を「ライスクリスチャン」にする必要はありませんし、不純な動機でやってくる人にまで援助の手を差し伸べよと言っているわけではありません。
とはいえ、現在のエホバの証人の姿勢はあまりに消極的です。これは、私が冒頭で述べたような「愛ある親切が行われていること」と矛盾する評価でしょうか。私がここで言いたいのは、会衆内で行われている仲間同士の支え合いのことではなく、「統治体」をはじめとする指導部の姿勢の問題です。
エホバの証人の場合、「自助」や会衆単位の責任を強調します。しかし、初期クリスチャンたちの教会(会衆)の機能が、「富の再分配」であったことを考えると、「原始クリスチャンの復興である」ことを標榜している現代のエホバの証人の場合も、自助のみではなく組織(指導部)が率先して信者への支援を行う必要があるはずです。
エホバの証人の生き方はあくまで一般市民として生活しながら信仰を実践するというものであり、隠遁生活や修道生活をするものではありません。結果として所属する社会との軋轢も発生し、「そんなに出来ないことばかりなら、あなたたちで固まって暮らせばよい」というような議論も出てきます。このような考えは極端だとしても、例えば「輸血を拒否するなら、エホバの証人で病院を経営すればいい」「介護サービスで、誕生会や祝い事に参加できないのなら、エホバの証人の介護サービスを利用すべきだ」「学校で、柔剣道の問題が発生するのなら、エホバの証人の学校法人を造ればよい」というような意見も出てきます。
これらの意見は、現代社会が目指すべき寛容さや、異質さを受け入れることなどからすれば「狭量な」発言ではありますが、同時に一考に値する意見でもあります。つまり、社会との信仰上の軋轢は(信教の自由という観点からも)やむを得ないとしても、それを軽減するための教団指導層側の努力の欠如を浮き彫りにしているとも言えます。エホバの証人は、あまりに自己責任や自助を強調しすぎている気がするのです。
さらに言えば、これは古代からキリスト教批判の時に言われたことですが、「兵役を拒否する」「政治に中立」(これは公認以前の時代の問題でしょうけれど)などということは少数派の宗教であって初めて可能なことです。キリスト教がローマ帝国の国教とされる過程を見てもわかりますが、多数派になり、ほとんどの国民がキリスト教になると、もはや「兵役」「政治」などから離れてはいられなくなります。言い換えれば、国の全員がエホバの証人になった場合、その国の統治はどうするのでしょうか。国防はどうしますか。世俗の問題に「中立」であったり「拒否」できるのはあくまで少数派であるからです。この矛盾も、慈善事業への態度を考える上でも重要な要素だと思います。
エホバの証人が今後考慮できる分野として、学校や病院、介護施設の経営などが上げられるでしょう。おそらく実際には難しいでしょうし、「終わり」を強調する以上、これらの分野に手を伸ばすことはしないでしょう。しかし、「終わり」が来ない限り多くの信者は今後も病気にかかるでしょうし、老いて行きます。指導層はこのことをもう一度真剣に考えるべきでしょう。学校や病院を直接運営しないとしても、信者個人の経営を推奨ないしは後押しするなど路線の変更は必要でしょう。
エホバの証人は、内部にいると、救援活動に非常に熱心な団体であると感じます。私もそう思っていました。もちろん、現実にそのボランティア活動に献身的に参加してこられた方達の努力は大いに賞賛されるべきでしょう。信者一人一人も、自己犠牲的な愛を確かに持っています。とはいえ、そこには常に霊的なことを優先するという大原則から発生する「消極的な姿勢」も目立つのです。
そして重要なのは、エホバの証人「だけが」信者を真に気遣っているわけではなく、エホバの証人「も」信者を気遣っているということなのです。確かに問題がある宗教は多いでしょうけれども、同時に立派に活動している宗教もたくさんあるのです。
まとめ
繰り返しになりますが、結論は、組織はもっと信者の福祉を気に懸けるべきであるということになります。
もちろん、「一般社会での慈善事業などしない」というのも選択肢の一つです。しかし、「霊的なことだけ!」という信条を固守するのであれば、現実に必要とされる物質面での支援については、一般の団体への参加を促したり、慈善事業への自由な参加を促したりすればいいのです。しかし、現実には慈善事業そのものへの消極的な見解を公にすることによって、信者にそのような参加に対する否定的なムードを醸造することになっています。これは大きな矛盾です。
「もうすぐ楽園が来る」「ハルマゲドンですべて帳消しになる」などという言葉は、現実には既に空虚なものです。現実には時は流れて、信者たちの多くが高齢になり、終わりを信じて入信した若い頃からずいぶん時間が経ちました。これも繰り返しになりますが、現に「終わりの日」に入ってから100年以上が経過し、確実に一人の人生以上の時が過ぎたのです。既になくなった方も多く、病気や介護の問題に直面している人も多くいるのが現状です。彼らの福祉は本当に省みられているでしょうか。「霊的」なことだけしていればいいというような「逃げ」は(組織の指導層には)もはや許されないのです。
前述の通りエホバの証人の組織は、信者向けにも社会一般向けにも「慈善事業」を始めるというような展望はないと思われます。慈善事業は「ライスクリスチャン」を生み出すという主張もたしかに一理あります。しかし極論すれば、偽善でも慈善事業がなされるなら救われる命があるのです。アメリカなどでは、大金持ちが(ある意味偽善的であるとしても)寄付をするのは自然なことだとされています。動機が悪い!と憤慨する人もいるでしょうけれども、それでも何もしないよりいいのです。(もちろん、それが違法・脱法であってはなりませんが)。
私たちは、「明日この世が終わるとしても、リンゴの木を植える」という心構えが必要なのです。※1
この終末論に関係したことは、次の節でさらに詳しく考慮します。
長文失礼いたしました。
※1:この部分は過去記事「3.エホバの証人の組織の体質の問題③」でも論じていますが、以下にもう少し補足いたします」
この言葉は、ルターのものとよく言われますが、そうではないようです。C.V.ゲオルギウ「第二のチャンス」にルターの言葉として使われたものが広く知られるようになったという説が有力と思われます。
ゲオルギウ(ルーマニア人?)の「第二のチャンス」の日本語版は1953年に出版されていて、原書はフランス語です。以下のような文章。(小説では、ルターのドイツ語の言葉をフランス語に訳すというシーン)
"La fin du monde serait-elle pour demain,
je planterais quand même des pommiers aujourd'hui. . ."
日本語訳「世界の終末が明日であっても、自分は今日、りんごの木を植える」。
「第二のチャンス」の邦訳はちょっとニュアンスが違う(「世界の終末が明白であっても」)ので違和感を感じていましたが、ネット上を検索しておりましたら「ものがたり通信」というサイトがあり、そこに「邦訳には誤植がある」と説明されていて、なるほどと腑に落ちました。つまり、「明白」→「明日(demain)」の誤植ということのようです。
実際の初出は、1944年10月のドイツ・ヘッセン教会の回状のようで、そこにルターの言葉として引用されています。(領邦教会全国評議員会議長カール・ロッツによる)。なので、実際のルターの言葉ではないと結論できます。
この点は、下記の参考書でも詳しく論じられています。
「ルターのりんごの木―格言の起源と戦後ドイツ人のメンタリティ」(日本語あり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
