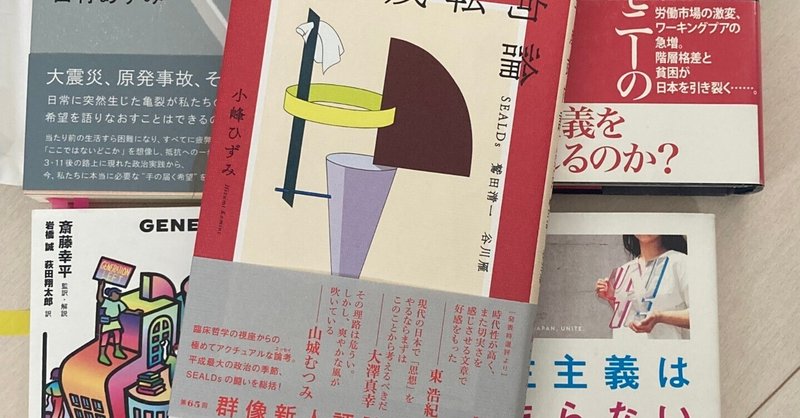
『平成転向論』についての覚え書き
7月中旬に札幌駅前の紀伊國屋書店で新刊本を漁っていたら「SEALDs」と題にある本を手に取ってみたら以前自分が書いた文章が元メンバーのものとして引用されていて驚いた。とりあえず買い、2~3日で読みきった。
同書への応答でもないけどもこの本についてnoteで文章をまとめたいなぁ、と思っていたが、考えがまとまらず、仕事が忙しくなり完全に忘れていた。8月くらいに毎日新聞の記事で著者が取り上げられると「プチ炎上」していた。
私の文章は「好意的」に何度か引用されている(ようだ)。
SEALDsには地域によってかなり差があった。私見では、言論のまじめさでは東北、マーケティング・メディア映えは東京、翻訳語と日常語の葛藤では関西、持続性では琉球。平成転向論は東京V東北・関西・琉球といったところがある(この構図そのものがダサいが)。実際、好意的な引用はすべて非東京勢。
— 小峰ひずみ@11月6日杉田俊介さんと対談!『ことばとvol.6』にRHYMESTER論! (@clinic_hizumi) June 3, 2022
多分、著者とは本質的な問題意識(=資本主義批判)を共有していると思う。会ったことはないけど、会ったらお互いに関わってきた運動の話とかをできそうな気がする。
ただ、同書での引用のされ方が恣意的だと感じる部分がある。引用された拙文は『民主主義は止まらない』(河出書房新社、2016年)という15年の国会前のデモの盛り上がりから野党共闘へ、そして16年の参議院選挙というSEALDsがイケイケどんどんの時期に出された本に納められている。『平成転向論』を読んでも、わざわざ引用元の賞味期限切れのマニアックな本にあたる殊勝な人はいないと思う。
なので本稿では私が書いた文章と当時の問題意識を整理した上で、『平成転向論』での引用箇所と比較し、その上で同書の議論の不十分な点を指摘したいと思う。
結論から述べると『平成転向論』はSEALDsという運動体が表明した解散の運動方針を「競争主義」的として批判しているが、反証不可能な批判である。SEALDsに代わるオルタナティブな運動として「哲学対話」を位置付けようとしているように見えるけど、そこから具体的にどのように政治性を作っていくかについては書いていない。批判のための批判のように読めてしまう。個人的には同伴知識人への批判をより明確化した方が良かったと感じる。
「日常」から見つめる民主主義 (『民主主義は止まらない』河出書房新社、2016年より)
・拙文について
文章はそもそもTOHOKUは私ではなく友人が立ち上げたという経緯の説明から始まる。その上で私はデモに対して「批判的」で最初、その友人と口論になった。
デモや大衆運動の高まりは、その社会において「いざという時」に結束して抵抗する、「力」が試されているのだと思っている。例えば2016年4月からフランスで労働法の改正に対して、大学生を含む若者から老人まで幅広い層で大規模なデモが起きているように。ただ、日本にはそんな「力」はないと思っていたし、今でも甚だ疑問だ。
おそらくその「力」は社会における「日常」の生きやすさと比例している。
当時、私は日本社会の問題点はどう考えても(私が生まれた年と同じ)1995年に出された日経連の「新時代の『日本的経営』」を出発点とした非正規雇用の増加や「ブラック企業」が跋扈するような労働運動の脆弱性にあると思っていた。
長時間労働と過重労働によって疲弊し、なんの平等の基準もなく企業の競争の論理にさらされ、個人がバラバラになると、人間は他者への想像力を働かせることが困難になる。 民主主義社会の基礎は、ある社会を構成しているすべての人々は平等であるという理念だ。 しかし競争の論理の前では、平等は絵に描いた餅になる。
個人的にデモへの参加は「非日常」的な興奮感があった。ただ、同時に長期的に考えると、このような人の結集は「日常」の閉塞感に覆い尽くされてしまうのではないか。その上で『平成転向論』で引用された箇所に繋がる。
「いざという時」に社会において結束して抵抗する「力」は、「日常」における他者への想像力が出発点になっている。そもそも日本は市民運動の層が、他の国に比べて薄い。 「日常」を競争の論理が覆っている。デモに行き、声を上げることができても、「日常」において職場で声を上げることができない社会が、「いざという時」に声を上げることができるだろうか。
この箇所をAとしよう。気になったのは『平成転向論』の中でAが引用されている部分で細字部分が省かれて引用されていることだ。通常の論文であれば省略する部分があれば「(中略)」とか「…」を使い、省いていることを示すと思うのだが、『平成転向論』ではそのような記載がない。このことについては次節で詳しく検討する。
その上で文章は以下のように結ばれる。
閉塞した「日常」の中で選挙に行くためにどうしたらいいのか?
アメリカの医療保険業界をテーマにしたマイケル・ムーア監督の映画『シッコ』においてイギリス労働党の国会議員だったトニー・ベンは次のように言っている。「借金苦の者は希望を失い投票もしない(略)国家の支配には2つの方法がある。恐怖を与えることと士気を挫(くじ)くこと」
希望のある社会へ。「日常」を変えていくことが選挙にもつながっていく。
・当時の問題意識
個人的には「国会前から選挙へ」のような「政治主義」的な考え方に批判的だった。日本社会のヘゲモニー状況は圧倒的に新自由主義的な競争論理に貫かれている。大学2年だった私は労働相談に関わるNPOで活動していたこともあり、その思いを強くしていた。長時間労働が蔓延していてストライキも暴動も滅多に起きない社会に対して、単に「選挙に行こう」と啓発したところで現在の日本社会のヘゲモニー状況が変わるとは到底思えなかった。
当時は熊沢誠の本や、渡辺治や後藤道夫などが編集していた『ポリティーク』関連の本を読んで現状分析の理論的下敷きにしていた。特にグラムシのヘゲモニー論を用いて、日本の戦後大衆社会を西欧の「福祉国家型社会統合」と区別した「企業主義型社会統合」と位置付ける後藤の『収縮する日本型<大衆社会>』(旬報社、2001年)はすり切れるくらい読んだ。
熊沢の本のタイトルの通り、日本において「民主主義は工場の門前で立ちすくむ」のだ。議会制民主主義があり、政治的にいくら民主的であっても、経済的には資本の専制に服従するしかなく、労働組合などで抵抗する「力」が圧倒的に弱い。
そんな矛盾したことも感じながらも一度関わった運動ということもあり、選挙応援だったり、イベントだったり活動をしていた。正直、自分で言うのも何だが、当時の自分は結構頑張っていたと思う。Twitterを更新したり、秋田や岩手に出張したり、仙台での街宣の準備をしたり。なので正直、「外野が好き勝手言いやがって」と思う気持ちもなくはない。
ただその活動に矛盾を感じていたので頼まれた文章は選挙についての本だったけれども逆張りで選挙について否定的に書いたつもりだった。
『平成転向論』の中での引用箇所
『平成転向論』の批判対象
同書は著者本人も認めている通り難解な本である。難解というよりは一つの概念の定義をなおざりにしたまま次の概念に進んでいくので論理を追うのが難しい。なので批判対象が「SEALDs」なのか「SEALDsの解散方針」なのか、それとも同伴知識人たちだったのかよく分からない。
私の力量不足のため異例の難解さのまま出版された(と囁かれている)『平成転向論 』ですが、ここに質問していただければ応えさせていただきます!なかった場合は、荒木さんからの追及を必死に避ける小峰の図しか見れません!(笑) https://t.co/kkLBRYVBQO
— 小峰ひずみ@11月6日杉田俊介さんと対談!『ことばとvol.6』にRHYMESTER論! (@clinic_hizumi) August 20, 2022
同書において重要なのは10章であり、主だったことは同章の議論を追えばなんとなく分かるような内容になっている。
小峰ひずみ『平成転向論』。序章と10章を先に読むと、著者の問題意識がわかりやすいのかもしれません(10章には杉田の名前も出てくるのですがそれとは関係なく)。回帰する1950年代~60年代の(新)左翼的な運動や文体の意味を考えてみます
— 杉田俊介 (@sssugita) May 27, 2022
ただ10章の文章はアジテーションが効きすぎていて、要旨が掴みにくい。『中央公論』に載った氏の文章の一部が『平成転向論』におけるSEALDs批判の要約になっている。
私が気になったのはSEALDsが自らの解散を正当化するために用いたレトリックだった。彼/彼女らは、大学を卒業した後、仕事に従事して「スキル」を磨き、次の運動に備えるべきだと宣言した。
この宣言はスキルを磨くことができる職業に就くことが前提とされている。つまり、SEALDsの面々が比較的恵まれた学生層だったから打ち出せた方針なのだ。フリーターなど仕事でスキルを磨くことができない人々も、運動の担い手となりうることが見過ごされている。この運動論は格差社会を運動のレベルで再生産しようとする。
実際「恵まれた学生層」じゃないメンバーもいた。個人的には解散する話は会議とかで聞いたのではなく、朝まで生テレビで奥田さんか誰かが話しているときに知った気がする。
例えば「離合集散のネットワーク型運動論」が運動自体の再生産性を担保できないというのは理解できる。実際に拠点や組織運営の資源がない中でその都度、一から立ち上げる必要があるからだ。
とはいえ、この「解散を正当化するために用いたレトリック」が「格差社会を運動のレベルで再生産」するとまでは言い切れないのではないか。このことは次項でも検討したい。
引用箇所について
同書では3箇所で拙文が引用または言及されている。
最初は5章の部分で、先ほどのAの細字部分を省いて引用し、次のように繋げる。
「いざという時」に社会において結束して抵抗する「力」は、「日常」における他者への想像力が出発点になっている。デモに行き、声を上げることができても、「日常」において職場で声を上げることができない社会が、「いざという時」に声を上げることができるだろうか。
「加害者の思想」から「他者の想像力」(ケア)へ。これが転向の論理である。むろん、彼を転向者だと非難したいわけではまったくない。斎藤の主張は正しい。SEALDsの限界とは私たちの限界である。私たちが外部に立つ「加害者」たりえない以上、「日常」(内部)から政治を立ち上げるしかない。
ここで「加害者の思想」とされているのは谷川雁が労働者をオルグするときに向けた言葉を指している。ちなみに直前の4章では転向の論理について「生活への回帰こそが、政治を豊かにする」(54頁)と定式化している。正直、ちょっとこの部分は論理が飛躍しているように感じてうまく理解できなかった。自分で書いた文章だけど「そうなの?」と不思議に思った。拙文は政治主義批判として書いたつもりだったので、好意的に受け止めれば、「他者への想像力」をとても広い意味で競争主義に対置する「ケア」の言葉として受け取り、文字通り「『日常』(内部)から政治を立ち上げる」必要があると著者は理解したのだろう。
ただ、拙文では「日常」の競争の論理を批判したかったのだが、引用のされ方として「そもそも日本は市民運動の層が、他の国に比べて薄い。 「日常」を競争の論理が覆っている」という部分が削られている。この部分を残すと(周辺的ではあったが)SEALDs内部にも競争主義批判があったという例証になってしまうから省いたのではないか、と邪推してしまう。
次に出てくるのは6章で著者が重視する「哲学対話」の文脈で出てくる。
(元)SEALDsの斎藤雅史は正しくも、日常での「他者への想像力」をもつところから、政治を立て直さなければならない、と述べていた。であれば、哲学対話は重要な政治的意味をもつ。哲学対話で見せる参加者のさまざまな側面は、「他者への想像力」を喚起する。ケアはまちがいなく政治性をもつ。哲学対話の教育現場への導入は、日本の政治的変革への第一歩だろう。
「他者への想像力」という言葉が一人歩きしている。個人的には直接的に労働組合や奨学金帳消しとか、そういう運動こそ抵抗の拠点になると思うのだけれども、著者としては哲学対話を重視する著者としては哲学対話こそが「政治変革の第一歩」となるようだ。
3箇所目は10章で、先に触れた同書の核心に迫る部分なので長めに引用したい。
もちろん、SEALDsの面々も、格差を無視しているのではない。むしろ、直面していた。(中略)が、SEALDsはこの怒りを凝視し理論的に捉えることはなかった。むしろ、格差の拡大再生産を前提とした「スキル」を己の光とした。諦めの形をとった怒りが、怒りの形をとった諦めに屈したのだ。
ここで(元)SEALDs TOHOKUの斎藤雅史がちらと言った「他者への想像 力」もその質が決まる。SEALDsの面々はたしかに、職場で差別を受けた被害者に連帯するだろう。それは手放しで賞賛できる。しかし、SEALDsの論理では、能力主義に抵抗できない。この論理に従って生きれば、彼/女らは「仕事」で蹴り落とした他人への「想像力」を持つことを拒否するだろう。「スキル」向上のために、自分は生き残らなければならない。「スキル」のある強者が民主主義を引っ張っていくのだ。再び国会前に力をつけて(パワーアップして)集まるために、他人を蹴落とすことを次の民主主義運動の前提とする。それが、彼/女らが闘い、考え、表明した方針である。
この方針によって、彼/女らは恐怖支配を肯定している。資本主義社会に根付く恐怖は、「スキル」の評価に基づく競争と深く関わっている。
この部分は全体的にそこまで言い切れるのだろうか、と思ってしまった。「恐怖支配の肯定」を「表明した方針」とするが、それを実証することはできない。そもそもメンバーにインタビューしたり、言説として分析する場合だとより幅広い参加者の声を拾ってマッピングした上で位置付けるなど仕方があったはずだが、そういうことは「あえて」せずにこのような書き方になったのだろう(幅広い参加者の語りは小林哲夫『平成・令和 学生たちの社会運動』(光文社新書、2021年)や尾崎孝史『SEALDs untitled stories 未来へつなぐ27の物語』(Canal+、2016年)などで見ることができる)。その結果、多くある言説のうち、自説に都合の良い発言を抜き出しているように見えてしまう。
牛田さんにいろいろ言われているのでもう一度言いますが、『平成転向論』はSEALDsが散布したイデオロギーに対する批判です。著書や記事などをできる限り読んでイデオロギー批判を行いました。外部に漏れていない組織の内情や方針については批判する必要がないと考え調査を行いませんでした。
— 小峰ひずみ@11月6日杉田俊介さんと対談!『ことばとvol.6』にRHYMESTER論! (@clinic_hizumi) August 22, 2022
正直、著者のこの批判は「アンフェア」と言われても仕方ないと思う。
加えて、そのような運動論があったとしてその後の日本の社会運動全体に対して具体的にどのような悪影響を与えているのかを(具体例を挙げることが難しかったとしても)より明確化すべきだったはずだ。
シールズ批判に対する批判をザっと見ていたが、問題は「シールズとそのイデオロギー」が権力として作用し、他のやり方で闘う運動に対して力を直接的・間接的にふるっていることに無自覚な点だ。だから、「批判するな」ということになる。それはおかしい。イデオロギーにはイデオロギーで対抗する。当然
— 小峰ひずみ@11月6日杉田俊介さんと対談!『ことばとvol.6』にRHYMESTER論! (@clinic_hizumi) August 5, 2022
著者が批判する「シールズとそのイデオロギー」がもたらしている権力性とは何か?著者が「オルグ」と呼ぶような組織化を否定する力なのだろうか、それとも「離合集散のネットワーク型運動論」を称揚する力についてなのか。
直接関わったわけではないが、その後のFridays For Futureとかでは組織論としてコミュニティ・オーガナイジングの手法を取り入れ、水平的なコミュニケーションを重視したり、運動内でメンタルヘルスのケアを行うなどSEALDs的な運動の問題点を乗り越えるような形式をとっていると言えると思う。
結局、著者から見てSEALDsはどうすればよかったのか。それまでの同書1~9章までの議論を踏まえて以下のように述べている。
日常生活(日常語)から政治運動(翻訳語)を批判する政治運動批判と、政治運動(翻訳語)から日常生活(日常語)を批判する日常生活批判を同時に敢行する孤立無援の〈中央〉たる「スキル」を磨くという方針を表明すべきだったのではないか。
これは具体的にはどのような活動を指すのか。解散後も形を変えて大学で根を張って活動すべきだったのか。同書で引用していたKANSAIで活動していた服部涼平さんは大学でサークルを作り学習会やシンポジウムを続けた。そのような形で活動を続けていけば良かったということなのか。その後、議論は<旗>、<声>、<党>という定義がよく分からない概念を使って締め括られる。
結局、同書を読んだ感想としては何となく言いたいことは理解できるけど、よく分からなかったというのが正直なところだ。書いてる本人もよく分からないで「′」(傍点)をつけたりしている部分もあるそうなので仕方ないのかもしれない。
知識人への批判
また、「左翼」の「活動家」として「シールズとそのイデオロギー」を批判するのであれば、そのイデオロギーを規定していた社会的存在そのものを批判すべきではないだろうか(資本主義批判は大前提として)。特に同伴知識人としてSEALDsを褒め称えた学者たちに対して強くその矛先が向けられるべきではなかっただろうか。特に大学であれば反安保の活動は支援するけど学生自治を蔑ろにする決定に手を貸すとか、そういう類のリベラル知識人こそなんやねんと思ってしまう。
「同伴知識人」がSEALDsやその後の運動を念頭に書かれた言説として、例えば木下ちがや『「社会を変えよう」といわれたら』(大月書店、2019年)では若者の社会運動の展望をとても楽観的に語っている。
上の世代が3・11後に培った「共有体験」と「闘争経験」が、若者たちの生活世界に内在した政治的想像力を発揮していくうえでの手助けになるかどうか。ここにわたしたちの 未来はかかっています。 (中略)若者たちがいまつくりあげつつある生活世界は、いずれ東アジア諸国の民主主義的社会運動とつながり、新しい世代の政治と社会運動の空間をつくりあげていく拠り所になり得ます。日本の若者と学生の「保守化」という現象は固定的なものではなく、また社会運動に若者や学生の参加が少ないという日本特異な現象も、過渡的なものにすぎません。
むしろ若者のいまのようなあり方は、決して「反動的」なものではなく、この日本社会ゆくえが見通せないということの集中的な表れであり、激動の東アジアの変化のなかで 「日本のかたち」が変わっていこうとしていることの「進歩のきざし」として捉えるのが適切なのではないでしょうか。
このように楽観的に考える要素が(特に地方の)大学内に残っていないことは小峰氏なら痛いほど分かるのではないだろうか。
中央公論の論考ではシェアハウスやイベントスペースなど「ワイワイガヤガヤ」とした拠点を社会運動の拠点としての「党」としていくことを提起しており、これについては個人的にとても共感するところがある。人が集うことなく運動は生まれない。現代日本社会は人が集うアジールを徹底的に潰している。
一方で「党」を「政治活動」に発展させるための契機については「芸術・遊びやビジネス」といった「自由の行為」を重視しているが、この部分についてはそれこそ、「芸術・遊びやビジネス」は「恵まれた層」にしか不可能だろうと感じた。「党」を社会運動における必要条件とするのであれば、十分条件として「政治活動」に発展させるための活動が必要になる。氏の言葉を借りるのであれば、それは「オルガナイザー(組織者)」の力量にかかっているだろう。
<余談>
大学と大学院で仙台に6年間いたが仙台メディアテークの館長である鷲田清一の著作にはほとんど触れることもなく、過ごしていたのでその辺は「そういうものなのかなぁ」とか思いながら読んでいた。学部3,4年は経済学部の「社会思想史ゼミ」という怪しいゼミで2年過ごしたが、鶴見俊輔や谷川雁の議論の部分についてもあまり詳しくなく、同じ戦後民主主義の思想家の中でも個人的には日高六郎や藤田省三の方にシンパシーを感じていたので鶴見については最近になってアナキズムの勉強で知った。ちなみに卒論は日高六郎論を書いた。
あと唐突に引用される『資本論』の価値形態論の部分が向坂逸郎訳だったので「上着とリンネル」が「上布と亜麻布」となっていて違和感あった。普段は(旧)新日本出版版か国民文庫版(岡崎次郎訳)を読んでいたから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
