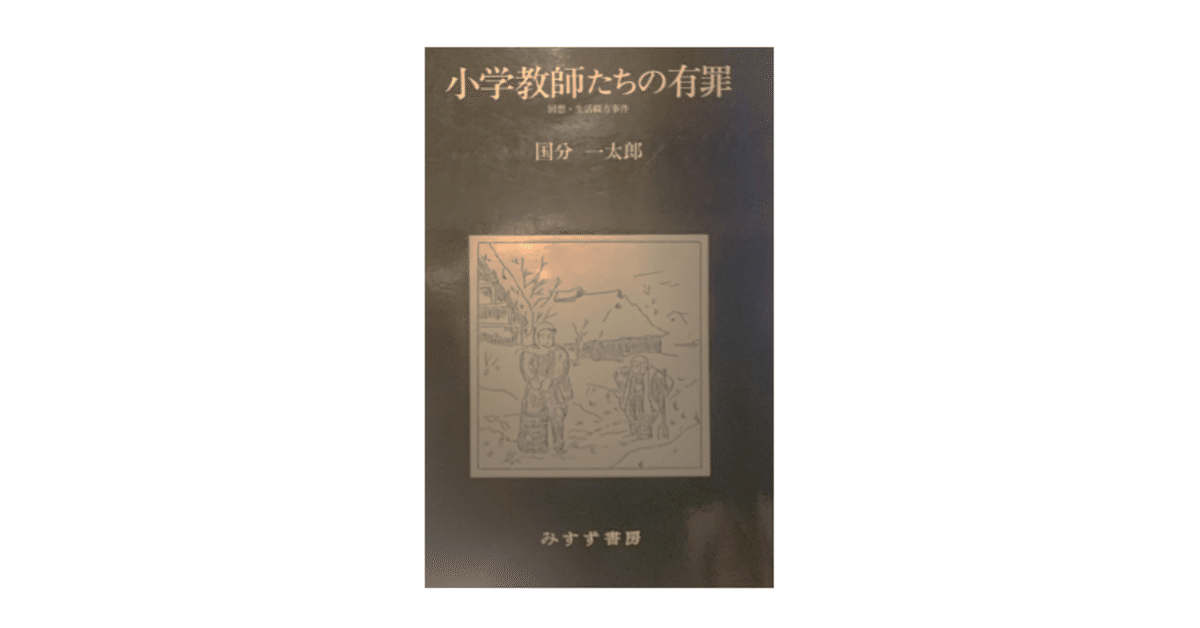
国分一太郎『小学教師たちの有罪』を読む17
前回の記事の続きです。この本はけっして読みやすい本ではありません。
28 空中楼閣
戦前の生活綴方教育運動に参加した教師たちが、東北地方を中心に検挙され、有罪判決を受けたり、不起訴になったとしても教育行政的に不利益な処分をさまざまにうけたりしています。この事件の期間中には、少なくない教師が警察の監房で亡くなったり、拘留中に病状が悪化して亡くなったりしています。村山俊太郎もこのときに得た病気のせいで、敗戦後の1948年に死去しています。
国分はこのような目にあった人々、いまは世をさった仲間の遺族の心をおしはかりながら、このような「空中楼閣」としての事件をつくりあげ、やがて出世していった砂田周蔵の執拗な取調べぶり、異常なまでの精勤ぶりをおもいます。
さらに、東京と東北といった地方との、検挙のちがいを指摘しています。地方では、当時手持ちぶさただったと思われる地方特高警察の実績づくりのために、東京のような中央では「網にかかりそうもないような、ちいさな『雑魚』が、ついに、おおきなものとしてとらえられ」たのではないかと国分は推測しています。(266p)
この章では気になる記述がありました。わたしは、ずっとこの本を読んできて、砂田との詳細なやりとりを国分はどのように記録し、また保存してきたのかということが気になっていたのですが、264pに「自分の記憶にたよりながら書きつづってきたのである」と記述されていました。あとがきには「断続的に書きとめていた」(281p)とあります。砂田周蔵はすでに亡くなっているので反論の余地はありません。文書の記録があるわけではありません。国分は日記でもつけていたのでしょうか。または国分の記憶力が相当なものだったのでしょうか。国分はどうしてこのような本が書けたのか、ということについては本書で語られておらず、これは大きな問いとして残りそうです。
29 無知と過剰転向と
最後の章では、国分らが検挙、送検・起訴され、有罪判決を受けるまでの「空中楼閣」が、たやすくつくられていくことについて、国分ら自分たち側の「主体の弱さ」にあったのではないかと論を進めていきます。
その弱さとは、第一に、当時の小学教師たちは「裁判」というものの本来の性質、裁判を受けることの権利をちっとも知らなかったということです。
第二に、具体的な治安維持法違反事件といったものについての「公判情報」に積極的に目を向ける習慣があまりなかったことが挙げられています。とくにマルクス主義あるいは自由な思想による研究活動・表現活動・編集出版・集会などの活動は、本来の治安維持法違反には該当しないと公判のなかで正当に主張することができる、という情報を耳にすることが皆目なかったと国分は回想しています。そういった情報を目にしたり、耳に入れたりしていれば、特高警察官や検事にも「そのような事実はありません」「マルクス主義や共産主義の本を読んだとしても、日本共産党の政治方針などを理論づけするものとして受け取ったり、引用などしたものではありません」と楯突くこともできた可能性を国分は指摘しています。
第三に、小学校教員などというものが、まったくもって「つぶし」のきかない人間としての存在であり、なるべくはやく教職へ復帰したいとのおもいが「過剰転向」への心を増幅させたと国分は指摘しています。
そして第四に、この「過剰転向」自身が、主体の弱さであると述べています。満州事変のおきた昭和6年(1931年)は、雑誌『綴方生活』の創刊二年目、『北方教育』創刊の翌年でした。このころ、教員の労働組合も弾圧されはじめていました。日本の右傾化と時期を同じくして、生活綴方教育運動や、雑誌『生活学校』を中心とする生活教育の運動も大きくなっていきました。そして「運動関係者たちは、良心の火をともしてそのしごとをつづけながら、その内心の深いところでは、『時局』がさそう国家主義的なものへの傾斜を、じわじわとした形で自分のものとしていく。」(277p)ということがあったと述べています。
国分が指摘している「過剰転向」とは、すこしばかりの左翼思想や自由主義思想をもったものは、それすらも「悪い思想」として考えなおす傾向があることを示しています。国分らのような、まじめで勉強熱心、社会科学の知識をもあれこれと吸収した教師たちの「過剰転向」が砂田の空中楼閣づくりを、おのずから助けることになったと国分は結論づけ、「反省」としています。(279p)
国分は本書の最後に、このように結んでいます。
全国各地の犠牲者たちのためにつくられた訊問調書・供述調書・予審調書・裁判官の判示の基調は、もと左翼的な文学運動に参加したり、いわゆる極左的なといわれた農民組合運動のわかいころの参加者、やがて「右へ」と転向したところの山形県警察部特高係主任警部補、のちには内務省警保局思想課左翼係主任に出世した砂田周蔵と、その背後の権力が、これをほしいままにつくりあげたのであって、けっしてあなたのご夫君や父上や祖父がつくったのではない!
わたくしのこの記録は、そのことをあきらかにするために、ただひたすらに、ながながとおおくの紙数をついやしてきたのである。しかし、ひとりのそのひとは、いまは死んでしまった。そして、そのひとを支えた権力は、いま死んでしまったのであろうか? わが愛する「小学教師たち」の未来のしあわせのために、じっくり考えてみなければならない。
国分はこの本が刊行された半年後の1985年の2月に、がんで亡くなっています。まさに国分の遺言ともいうべき手記です。「そのひとを支えた権力は、いま死んでしまったのであろうか?」という最後の国分の訴えが、今のわたしたちにも切実感をもってひびきます。権力はいともかんたんに、よわい教師たちを犯罪者としてしまう可能性はいまでも拭いきれません。権力に抗うための知識を持ち合わせていることが、いまの教師にとっても必要な教養であることを教えてくれた本でした。
また、志半ばにして亡くなった村山俊太郎、佐々木昂らが生きていたら戦後の生活綴方の再興の後、どのような実践を行なったのだろう。そして、彼らの生きていた当時の実践、思いをもう少し具体的につかみたいとおもいました。そのあたりは雑誌『北方教育』などを読むことで少し知ることができるかもしれませんし、多くの研究者が論じているところだと思うので論文にあたってみようと思います。また、小説ではありますが高井有一の『真実の学校』が当時の熱量も伝えてくれるでしょう。
本書のカバー(表紙)にこめられたメッセージ
本書『小学教師の有罪』の本のカバーは、実は2枚あります。一枚は、まるで遺影のようなものです。

その一枚の下には(こちらが表紙というのでしょうか)国分が児童の詩をあつめてまとめた詩集「もんぺの弟」に掲載した、国分の児童へのメッセージが印刷されています。
「もんぺの詩をよめ。もんぺはく子の詩を、こゑたててよめ。」

教師が子どもの作文や詩、つまり声を聞き、「生活と表現と」を知ることがなくなったら、それこそ生活綴方教育の遺産を遺影におさめて葬り去ることになるでしょう。そんな生活綴方のしごとを受け継ぐ者への国分のあつい願いもあったのではと、私は受け取りました。
