
全身小説家 ~作家・永沢光雄はいかに生き、死へ向かったか~
本作は、フリーライターで作家の故・永沢光雄氏(1959~2006年)について、プチ文壇バー月に吠える店主の肥沼和之が執筆したルポルタージュです。
プロローグ
「ライターをするのならさ」
30代後半の週刊誌記者は、酔いでややとろんとした目を僕に向けて言った。深夜2時、新宿ゴールデン街。2010年のことだった。フリーライターになったばかりで、当時30歳の僕に、この本は絶対に読んだ方がいいよ、と彼は著者名とタイトルを挙げていった。沢木耕太郎『深夜特急』、山際淳司『江夏の27球』、本田靖春『誘拐』など、知っていたり知らなかったりするノンフィクションが挙げられ、最後に紹介されたのが故・永沢光雄の『AV女優』だった。
1996年に刊行された『AV女優』は、その名の通りAV女優たちへのインタビュー集である。僕は未読だったが、読書好きの友人が絶賛しており、その存在は知っていた。
単なる読書好きに勧められたのならともなく、自分が生業にしようとしている業界の先輩に言われたのでは、無視できない。僕は早速、ほかに勧めてもらった数冊と一緒に、ネット書店で同作を購入した。次に先輩記者に会ったときに、ちゃんと買って読んだという既成事実をつくっておけば、仕事を回してもらえるなど良いことがあるのでは、という打算が7割。純粋に作品として読んでみたい、という好奇心が3割。『AV女優』は、そんな動機で購入した1冊だった。
数日後、届いた数冊のなかに、500ページ以上はゆうにあろうかという文庫本があった。それが『AV女優』だった。同作はもともとAV情報誌、つまりエロ本で連載されていた女優へのインタビューがもとになっており、書籍には42名分が収録されている。
薄紫色の表紙には、口を小さく開き、マフラーを両手で抱え、まっすぐにカメラを見つめる女性の姿がある。喜怒哀楽のどの感情にも当てはまらない、けれど何かを訴えかけているような表情が印象的だった。後で知ったが、その女優は日吉亜衣さんという人気女優で、本編にも登場している。
早速、本を開く。前書きはなく、いきなり冬木あずささんという女優へのインタビューが始まった。大げさでなく、度肝を抜かれた。冬木さんという人間が紙面から飛び出してすぐそこにおり、表情や仕草が目に浮かび、声が聞こえてくるような、圧倒的な臨場感があった。冬木さんへのインタビューは、彼女のこんなセリフから始まる。
広島の女は気が強いけ。あんた、奥さんを殴ったことある? ほう、あるんけ、その時、奥さんどないしとった? 泣いとったんか。広島の女はそうじゃないけ。相手がダンナであろうが恋人であろうが、やられたらやり返すけ。ウチが結婚してダンナに殴られたら、『おんどりゃあ、なにさらすんじゃ』言うて、そばにある灰皿でもなんでも、物を持って殴るけ。投げはせん。投げてはずれたらしまいじゃろ。持って殴るのが確実じゃけ。木刀があれば、ぶちいいんじゃがのう。木刀で突けば、相手が男でも一発でしまいじゃけ。そうじゃ、うちが結婚する時は嫁入り道具の中に木刀も入れることにするけ。木刀さえあったら、ハア、何があっても安心じゃけ。
続いて、冬木さんがいる広島に、永沢ら取材陣がたどり着く場面。待ち合わせ場所にやって来た冬木さんは、彼らにこう声をかける。
「遠いところを、ようきてくれたねえ。お腹へってるじゃろ。ウチが美味しいお好み焼き屋に連れて行ったるけ」
冬木さんの案内で街を歩いていると、パチンコ屋の店員が彼女に声をかけ、
「ようけ玉の出る台が、まだ空いとるよ」
「ホンマ? ほんなら後から来るけ、その台は空けといて」
というやり取りが交わされる。知り合いなのかと尋ねる永沢に、冬木さんは「知らん知らん」と首を振り、お好み焼き屋では「やっぱりお好み焼きは広島に限るけ。なんといっても、ソースが違うけ」と笑うのだった。
最初の2ページにあるこの描写だけで、冬木あずささんという人間のある一面であり、同時におそらく本質的な姿が、これでもかというほど表れている。読み進めると、冬木さんはさらにいろいろな一面を見せてくれた。
16歳まで生理が始まらず、自分は本当は男で、今にチンチンが生えてくるのではと悩んだこと。母親に相談すると、「ナプキン代が浮くしええじゃろ、このままこんかったらおもしろいけ、(生理が来ない)ギネスに挑戦してみい」と一蹴されたこと。青少年の悩み相談室に電話し、そのことを「びったれそうな(汚そうな)」女性に相談したこと。
AV女優になり、撮影で東京に行ったとき、サンシャイン水族館でマンボウを見た感想を「ビックリしたけ。なんであんなキッカイな魚が生きとるんじゃろ。東京にはなんでもあると思うとったけど、マンボウまでいるとは思わんかったき。ウーッ、マンボ! じゃ」と言い表したこと。
かと思えば子どものころ、おもちゃやゲームを買ってもらえなかったが、一度だけ親におねだりした思い出として、「空気銃を買うてください、言ったんよ。ハア、近所にぶり気に食わん年上の女がおって、そいつがウチのことを『みにくいアヒルの子』って言うとったじゃけ。そりゃま、色は黒いし決して可愛い子じゃなかったけど、ばり腹が立ったじゃけ。その子を空気銃で撃ったろうと思ったけ。結局、買うてもらえんかったから、夜にその子の家の前まで行って、石を投げて帰って来たけ」と物騒なエピソードを思い返したこと。
水泳をしていた冬木さんが、水に入るのが好きだと振り返る場面は、「泳ぐというより、水の中にもぐるのが好きじゃけ。水の中にいると、なんか違う世界に来たみたいな感じがするじゃろ。耳がツーンとなって。あれが好きじゃけ。ウチの本当の親はカッパじゃと思っとるけ」と書かれている。
読みながら、ふと思う。AV女優へのインタビューで、生理のことはともかく、なぜマンボウや空気銃や水泳のことを聞いたのか。雑談のなかでたまたま話題に出ただけだとしても、なぜ採用して文章にしたのか、にわかには理解できなかった。
こういった描写は、冬木さんという人間の像をより多面的に、詳細に浮かび上がらせているが、エロ本のインタビューなのである。もっと読者が求めているような、いわば「抜きたくなる」ような内容のほうが適切なのではないか。恋愛や性体験にも触れられているが、あくまで冬木さんの半生の一部としてであり、ことさら特別にフォーカスされているわけではなかった。
だが読み進めるうちに、この本の趣旨を理解し、納得できた。永沢が向き合って話を聞き、描いたのは、AV女優ではない。たまたま職業がAV女優というだけの、ひとりの女性だった。そのライフストーリーや素顔が、たまたまエロ本で連載されていただけだったのだ。性愛の話に重きを置かれていないのも当然だった。
また、『AV女優』はインタビュー集とされているが、女優が話した内容が中心に組み立てられているわけではない。インタビューの時間外に起きたエピソードや永沢が感じたこと、関係者たちとのやり取りなど、裏側の部分も物語を構成する重要な要素となっている。先のパチンコ屋の店員との会話がまさにそれだが、圧巻のものがもうひとつある。冬木さんへのインタビューを、永沢が宿泊しているホテルの部屋で行おうとしたところ、フロントの女性に見つかり、追加料金を払えと迫られる。それを見ていた冬木さんがブチ切れるのだ。
「そんな金、払わんでええがね! こがいなホテルは、もう一秒たりともおりとうないがね!」
確かにフロントの女性の態度には私もカチンと来たが、冬木がここまで怒るとは思わなかった。私が「マアマア」と彼女をなだめようとすると、
「もしあんたらが今日もここに泊まるんじゃったら、もう取材は断るけ。ウチにインタビューしたかったら、すぐにこのホテルをキャンセルせえ!」
ホテルの女性と冬木さんという、気の強い広島の女性たちの間に挟まれ、永沢たちはあたふたするのだった。冬木さんは元不良で気が強く、広島弁ということもあって、キャラクターとして非常に濃いのは間違いない。ただ、キャラの強さだけに頼って描かれ、これほどの読みごたえに仕上がっているのではなかった。
そう、ここには冬木さんがいるのだが、同時に永沢や取材陣もいる。パチンコ屋の店員やフロントの女性もいる。その人たちの有機的な営みや交わりが、何ともていねいに、巧みに、絶妙に表現されているのだ。だからこそ、非常に臨場感のある内容に仕上がっていたのだった。実際、冬木さんの紙面は12ページほどだが、読みごたえは中編ほどもあると感じた。
続いて登場する吉沢あかねさん、希志真理子さん……と読み進めていくと、そのことをさらに実感した。生い立ち、何気ないエピソードの数々、永沢たち取材陣とのやり取りなどが描かれ、彼女たちの実像や表情が浮かび上がっている。女優の個性が強いとか弱いとか、生い立ちが波乱万丈かそうでないとか、関係なく読みごたえがある。本当の意味で、誰もがオンリーワンであり、唯一無二のストーリーとして紹介されていた。
思わず呆気にとられてしまった描写もあった。永沢が取材相手である希志真理子さんに恋をし、交際を申し込んだことを書いているのだ(結局、振られてしまう)。そのエピソードが真実なのか、多少盛っているのか、まったくの嘘なのか知る由もないが、いずれにせよ「そんなことまで書いたの!? 何考えてるの、この人?」と驚いた。
さらに驚いたのは、川村弥代生さんの回だった。インタビューを受けるのが初めてという川村さんは、永沢が何を聞いても沈黙するばかり。口を開いたかと思えば、「いろいろね、ありましたから」というそっけないもの。結局、インタビューはうまくいかずに終わりを迎える。
ライターの立場からすると、面白くて読みごたえのある記事にするための「取れ高」が明らかに少ない状況だ。僕だったら、手を変え品を変え、いろいろな角度から質問をぶつけて、何とか取れ高を確保しようとするだろう。もしくは、地の文が中心の構成にして、川村さんのセリフの少なさをごまかし、あたかもうまく取材ができたようにまとめていたと思う。
だが永沢は違い、「インタビューは一切盛り上がることなく、淡々と進んだ」とあられもない事実を書いている。そのうえで、取材に同席した川村さんのマネージャーや、編集者やカメラマンの様子や言動、それに対する永沢の反応や心の動きなどを描写している。何とか取り繕って文字数を稼ぎ、紙面を埋めるためにではない。一期一会の、そのときに行ったその取材でしか書けない内容を、永沢はありのままに描いているのだ。
インタビューは、ジャズのジャム・セッション(即興演奏)に似ていると思う。基本的にアドリブで、ほかのプレイヤーが奏でる音やメロディ、くせや性格や考えていることなどを五感で捉え、一体感のある音楽をつくりあげていく。そのため、プレイヤー同士の相性や、その場に調和するための技術や感性や柔軟さが重要となる。もちろん、うまくいくときもあれば、そうでないときもあるが、少なくともその演奏に関してはやり直しがきかない。
永沢は女優たちとジャム・セッションをし、もしうまくいかなかったのであれば、失敗を肯定する。取材で思うように話を引き出せなかったら、正直に失敗譚として書く。そうすることで、失敗も成功になるのだ。書き手としてのそんな姿勢というか、小細工で見せかけの成功をつくろうとしない、彼の矜持を見た気がして打ちのめされた。
当時、僕は主にエンタメ分野でライター活動をしており、よく芸能人に取材をしていた。ただ、質問する内容といえば、出演予定のドラマや映画などのことがほとんど。つまりタイアップである。もちろん、それ以外の質問もしたが、予定調和の域を超えたことはあまり無い。返ってくるのは対外向けの無難な回答で、それ以上でも以下でもなかった。
『AV女優』はまったく違った。女優たちや出演作品のPRが目的であれば、作品のことや性的な話題に終始するのがセオリーなのだろう。しかし、そんな狭い範疇をゆうに飛び越え、女優たちのひとりの人間としての半生や個性や今という瞬間などが実に生き生きと、血の通った人間として描かれていた。彼女たちと向き合う永沢や周りの人々の存在と一緒に。
一話を読むごとに、ドキュメンタリー番組や映画を見終わって、登場人物たちの体温や表情や息遣いがしばらくそこに残っているような読後感を覚えた。僕は、女優たちと永沢たちのやり取りを、確かに間近で感じていた。
それから、永沢の著作をむさぼるように読んだ。スポーツ選手たちへのインタビュー集『強くて淋しい男たち』は、タイトルにあるように、スター選手ではあるが、どこか陰のある男たちが登場する。永沢は彼らの選手としての栄光だけでなく、弱さや寂しさをふくめて、ひとりの男としての素顔を描いている。ところどころに自分自身が登場する、永沢節も発揮されている。
『二丁目のフィールド・オブ・ドリームス』は、今は無き近鉄バファローズの大ファンだった永沢による、野球に関するエッセイ集。永沢が暮らしていた新宿二丁目や妻や酒のことなど、何気ない日常も盛り込まれ、彼にしか出せない味を出している。
『声を無くして』は、亡くなる4年前に下咽頭ガンの手術で声帯を除去し、しゃべることができなくなってからの日々を描いたエッセイ集だ。闘病記ではあるものの、悲劇というよりは面白おかしいトーンの文章が多く、一方で死んでいった仲間たちへの思いとともに永沢の死生観も綴られており、生への叫びで締めくくられている。
ほかにも『AV女優』の続編や、インタビュー集や短編小説集など、永沢の著書は多数ある。すべて読破したが、最も引き込まれたのは、『AV女優』をはじめとしたインタビューものだ。彼は『AV女優』のヒットにより、「インタビューの名手」と呼ばれるようになったというが、僕も小説などの創作よりも、他者に取材をして描いた文章こそが永沢の真骨頂なのではと感じた。小説がつまらないわけではまったくないし、太宰治賞の最終選考に残ったこともあるほど評価もされていた。だが、彼の小説が1であれば、インタビューものは永沢と取材対象者と登場人物たちが足し算プラス掛け算になり、5にも10にも20にもなっていると思う。それほどまでに圧巻で唯一無二だった。
取材対象者と向き合ったとき、永沢はどのようなことを考えて、どう立ち回っていたのだろうか? ライター目線で想像してみる。おそらくは、「面白いネタを引き出してやろう!」と意気込んで向かい合うのではない。合気道の有段者のようなひょうひょうとした立ち位置で、すべて成り行きに任せようという、無欲の姿勢でいたのではないか。そして対峙しながら、彼なりの取れ高、「すべらない話」も「すべる話」もこっそり集めていったのではないかと思う。
集め方も、第三者として外から情報を拾うのではなく、当事者としてしっかり巻き込まれ、等身大の視点でとらえようとしている。出演・冬木あずさ、監督&脚本・永沢光雄ではなく、監督&脚本&出演・永沢光雄として、これからつくられる作品のなかに、彼も初めから存在しているのだ。
ライターといえば、基本的には裏方の存在である。僕もよく先輩ライターや編集者から、「自分を出し過ぎるライターは使ってもらえない」と教えられていた。永沢は、ライターでありながら裏方に徹するわけでなく、かといって出過ぎるわけでもない。けれど、彼がいないと絶対に成立しない、まさに物語の一部になっている。
プロフィールを見ると、永沢はフリーライターという肩書であることが多かったが、そんな枠には収まらないインタビュアーであり書き手であったのだ。
永沢は2006年11月1日、肝機能障害のために47歳で亡くなっている。原因は酒の飲み過ぎである。自伝的小説やエッセイでもよく自虐的に書かれているが、永沢はアル中で、起きている間はひたすら飲み続ける、連続飲酒が習慣になっていた。
僕が永沢の著作を初めて読んだ2010年、彼はすでにこの世にいなかった。そのことに寂しさはなかった。太宰治の著作を読んだ後、彼が故人であることについて何も思わないように、歴史上の人物というとやや大げさだが、違う世界の住人として認識していたからだった。だが、パラレルワールドは、ある夜をきっかけにひとつになった。
2012年、僕はライター活動をするかたわら、新宿ゴールデン街にバーを開いた。ライター業が安定してきたこともあり、何か新しいことをしたいと、たまに飲みに行っていたこの街でバーを始めたのだ。これまで以上の頻度で飲み歩くうちに、永沢が行きつけだったという何軒かのお店に出会うことができた。それらの店で、マスターやママから、生前の彼の思い出話を聞きながら、感慨にふけるのは楽しい時間だった。彼の小説にもエッセイにも、飲み屋を舞台にした作品が多い。それらは僕が今いるこの空間だったのかもしれないと、生前の永沢が見ていたのと同じ風景を見ている気分になっていた。観光地で、永沢の等身大パネルに顔を突っ込んだお上りさんのように。
時が過ぎ、2015年のある晩、僕のバーに1人の女性がやってきた。初めて見る人で、おそらく50代。すでにべろべろに酔っぱらっており、席に着くなりハイテンションで下ネタを叫びまくる。ほかのお客さんたちはドン引きである。僕も普段なら不快に感じるところだが、なぜか嫌な感じはしなかった。拒否したい気持ちより、じっくり話をしたいと思った。
「おねえさん、楽しそうですね! もう飲んで来たんですか?」
「そうなのよ、お友達と一緒に教会に行ってきた帰りで、ここが3軒目なの!」
「どうしてうちに来てくれたんですか? ふらっと?」
「だって、ドアが開いてたから。私に『来て!』って言ってるみたいだったからよ!」
僕は笑った。危険人物ではないということがわかり、ほかのお客さんたちも彼女を受け入れ、店内は和やかな空気になった。ひとしきり飲み、騒ぎ、ひと段落ついた後、女性は店内に置いてある本棚に目をやった。静かに本を眺め、つぶやくように言った。
「私の旦那ね、ライターをやっていたの。本も何冊も出してたのよ」
「そうなんですね。本をたくさん出されているなんて、すごいです。実は僕もライターをやっているんですよ」
「そうなんだ。私の旦那は死んじゃったんだけどね。あなたは知ってるかしら……」
彼女が亡き夫の名前を口にしようとした瞬間、決して大げさではなく、啓示が降りてくるような感覚が僕の全身を包んだ。ある名前を、僕は確信を持って言った。
「永沢、光雄さんですか?」
「何でわかったの!?」
女性は目を丸くして大声を上げた。僕らは奇跡のような邂逅を喜び、興奮し、両手で固く握手をした。
永沢の作品に妻としてよく登場しているのは、恵さんという方だ。新宿二丁目の飲み屋で知り合い、その日のうちに恵さんの家に転がり込んだ。永沢は、風呂に何日入っていないのか聞きたくなるくらい汚れていたため、恵さんがシャンプーを5回して清潔にした。その1週間後にプロポーズされ、2人は夫婦になったのだと著書に書かれていた。結婚後も、永沢を献身的に支えてきた方である。
本人で間違いないか聞くと、その通りだった。ますます感動した僕は、永沢の作品がいかに好きか、書き手としてどれだけ影響を受けたか、延々と語った。恵さんは笑顔で、うんうんと頷きながら聞いてくれた。
「永沢と紀伊國屋(書店)に行くとね」
恵さんは言う。
「カートを押して、欲しい本をどんどん入れていくのよ。だから、いつも会計が2万円くらいになってたの。それが毎週だったけど、永沢は全部読んでいたんだから!」
永沢の著作『声を無くして』が、映画化される話があったことも、恵さんは明かしてくれた。誰が私の役をやる予定だったと思う? いたずらっぽい目で恵さんが僕を見る。再び、啓示が降りてきた。
「キョンキョンですか?」
「何でわかったのー!? あなた、本当にすごくない!?」
ちなみに、恵さんと小泉今日子さんは、誰がどう見ても似ていない。だが、お世辞で名前を出したわけでも何でもなく、本当にあの大女優の名前が降りてきたのだ。ハイタッチをし、ますます盛り上がり、それから何を話したのかあまり覚えていない。調子に乗って飲みまくってしまったために、途中から記憶がほぼ無いのだ(恵さんも負けないほど酔っぱらっていたことは何となく覚えている)。
翌日、ひどい二日酔いと引き換えに、僕は知った。歴史上の人物だとばかり思っていた永沢光雄が、我々の生きている世界と地続きの、薄い被膜のすぐ向こう側にいることを。同時に、永沢のことをもっと知りたい、この手で書き残したい、と強く思った。
第1章 時代を刻んだAV女優
永沢を語るにあたって絶対に外せないのが、冒頭でも紹介した『AV女優』だ。AV女優たちは今でこそ「セクシータレント」と呼ばれ、テレビの地上波でも活躍するのが当たり前だが、『AV女優』が刊行された1990年代はそうでなく、深夜のお色気番組やエロ本など、登場できる場所は限られていた。関係者によると、世間からの風当たりも厳しく、冷やかしの対象として見られる、親にバレて勘当される、なども珍しくなかったという。
『AV女優』は、白夜書房のアダルト情報誌『ビデオ・ザ・ワールド』『ビデオメイトDX』などで、1991年7月から1996年4月まで連載されていた記事がもとになっている。それが、10万部超のベストセラーになった。AV女優という、当時は市民権どころか、人権すら得られづらかった人たちを題材にした本が、一般社会に広く受け入れられたのはなぜか。
ひとつは、AV女優という偏見を一切取り払い、彼女たちを「ひとりの人間」として捉え、同じ目線で向き合い続けた永沢の目線だろう。繰り返しになるが、永沢は彼女たちのストーリーを、AV女優として描いていない。インタビューの時点から、「AV女優に話を聞く」という意識は持ちつつも、重視はしていない。たまたま職業がAV女優の、ひとりの女性に話を聞くというスタンスなのだ。だからこそ、紡がれた一人ひとりの物語が、普遍的な人間ドラマとして読者に届いたのではないか。
作家の鈴木涼美氏は、『AV女優』をこう評している。
インタビューに答えるAV女優の発言の中には、ドメスティック・バイオレンスや、貧困、差別、近親相姦などという「切実な社会問題」を映し出しているものがある。しかし、同書全体を通して描かれているのは、あるいはAV女優ではなかったかもしれない普通の女の子としてのAV女優の姿である。
それは何も、描かれる彼女たちがすべて平均的な家庭で特徴のない人生を送ってきたという意味ではない。つらい過去であれ興味深い経験や趣味であれ、詳細に記されながら、それがAV出演に直接に関係している論調でないということだ。(中略)AV専門誌という媒体上、対象をたまたまAV女優としているのであって、インタビューの興味がAV女優という「特異な存在」に迫ることでないことをにおわしている。現に同書のインタビューではAVについての具体的な話よりも、彼女たちの存在としての人生や日常に多くのページが割かれている。(中略)近親相姦の経験や、家庭内の問題といった比較的スキャンダラスな内容も、水泳部に所属していたことなどと同列に経験として語られ、そこにAV女優としての必然性を求めるような姿勢はない。
確かに女優たちの半生には、家庭問題、虐待や性暴力、いじめ、非行、貧困など、悲劇的なエピソードもたくさん登場する。それらをAV女優たちの半生のなかの「情報」として捉え、短絡的に物語を組み立てようとすると、「機能不全の家庭」「愛されなかった幼少時代」「満たされない心」などにことさら着目し、「AV出演」につなげたくなる気がする。いわゆる「AVに落ちる」として、わかりやすく、理解されやすいストーリーが構築しやすいからだ。
だが『AV女優』では、機能不全家族も貧困も虐待も非行も、裕福さも幸福も何気ない出来事も、どんな恋愛も性体験もAV出演も、彼女たちの物語を構成する一部であり、同列なピースのひとつとして扱われている。紡がれる物語には、美談も醜聞もふくめ、安直なバイアスは一切ない。永沢がその場で見聞きしたことや感じたことや体験したことを、創意工夫しながら、彼なりの「良い物語」にすべく、実直かつていねいに描いただけなのだ。
エッセイストの三善里沙子氏も、『AV女優』の書評で、非常にはしょって言えば、と前置きしたうえで、「彼女たちの多くが親との問題を抱え、その後出会う男ともトラブっている場合が多い」と記している。続けて、「ここでデータを語ることには意味がない。この本にあるのは、壮絶なまでの各々の生である」と、彼女たちの職業や家庭環境や恋愛体質を結びつけることはせず、やはりひとりの女性としてのライフストーリーを描いた本であるとしている。
永沢は女優たちのことを、AVマーケットで消費される「商品」ではなく、血の通った「人間」として捉え、尊重し、向き合い続けてきたのだ。そのことについて、彼はインタビューでこう話している。
上から見下ろす人間にはなれないですよ。僕はずっと仕送りをもらっていた人間なんだから。AV女優は19歳で体を張って生きているんです。浪人中だった僕が、「大阪芸大がいいか、桃山(大学)がいいか」とおかあちゃんに相談しているときに、彼女たちは実家に仕送りまでしている。(中略)僕は必然的に偉そうにはなれない人間なんですよ。
本音か照れ隠しかわからないが、自分はダメ人間なのでそもそも人を見下すことなんてできないですよ、と言っているのだ。後述するが、確かに永沢の経歴は立派とはいいがたく、高校を卒業してから、『AV女優』がベストセラーになっても、実家から毎月10万~20万円の仕送りをもらい続けていた。若くしてアル中になり、うつ病も抱え、小説家になると言いながら何も書かず、恋人に愛想を尽かされたこともあった。
生来の性格の良し悪し、思いやりのある無しとは別に、永沢の放蕩な生き方も、相手が誰であっても変わらない、フラットな視点や姿勢につながっているのは確かなのかもしれない。
ジャーナリストの故・立花隆氏は、『AV女優』について「まとめ方も巧み」だとしたうえで、それ以上にインタビュアーとしての永沢を絶賛している。
永沢はエロ本編集の世界に長かった人だというが、そういう世界にこれだけの人がいたのかと驚くほどいいインタビューである。まとめ方も巧みだが、それ以前に、相手の話をここまで引き出すことができたことそれ自体が大したものだと思う。これはテクニックではない。永沢のパーソナリティがいいのだと思う。
作家の高橋源一郎氏も同様に、『AV女優』のすごさは聞き手としての永沢の能力にあると分析し、彼以上のインビュアーはいないとまで言い切っている。高橋氏が特に絶賛するのは、刹奈紫之さんの回だ。
その回は、SMやスカトロなどが登場する、『AV女優』のなかでも屈指の過激な内容である。小6だった刹奈は、地元のエロ漫画のサークルに入り、女子高生たちとコミケ用の漫画を描く。終わると、打ち上げで彼女たちは服を脱ぎだし、バイブを用いてのオナニー大会が始まる。
官能の世界に足を踏み入れた刹奈は、好きだった女性エロ漫画家の仕事場で乱交パーティに参加するのだ。実に生々しいそれらの描写をいくつか抜粋する。
初めてオマンコをなめました。なんか液体がどくどく出てきて、なんかグミみたいな果物とバターをまぜたような味がしたな。舐めながら、『プリンをまぶしたらおいしそうですね』って言ったら、やってくれた。オマンコをプリンまみれにしてくれて『さあ、きれいに舐め取って』。
アナルもそこで仕込まれたの。『アナルはウンチがでるくらいだからチンポも入るのよ』って教えられて、みんなに指やバイブを入れてもらって広げてもらったの。ウンコも『さあ、してごらん』って言われてみんなの前でブリブリってしてた。それを見ながら、みんなオナニーをしたりペニスバンドでセックスしたりしてた。
このほかにも、彼氏が刹奈の排泄物や吐しゃ物を口にして病気になったことや、結構披露宴ではこれまで出演したビデオの上映会をしたいこと、両親の前で彼と浣腸をしあって互いの大便を食したいことなど、かなり、いやめちゃくちゃマニアックな性癖やプレイや願望が詳細に描かれている。
高橋氏が絶賛する理由のひとつは、大好きな遊びに興じる子どものように、純粋にプレイのことを話す刹奈やその言葉を、永沢がピュアな存在として受け止め、描いていることだという。
刹奈紫之さんが発する(そして、それを、永沢さんがていねいに書き留めて、文章にした)ことばは、どれも、わたしたちの常識を超えています。目をそむけたくなるような単語や、仰天するような行いが、わたしたちの前を通りすぎてゆく。
けれども、もっとびっくりするのは、刹奈紫之さんが、そのことばを、天真爛漫に使っていることです。一切の忖度なしで。なんの遠慮もなく。まるで赤ちゃんみたいですね。なんて最低で、しかも純粋無垢(一見、正反対ですが)なんでしょうか。(中略)それから、この文章では、ほとんど気づくことができないのですが、この、あっけらかんとした刹奈紫之さんのことばを、文章という形にして残した永沢さんの力もすごいのだと思います。
排泄物を食べて喜ぶのも、駄菓子屋でサイダーを飲んで喜ぶのも、永沢は同列の純粋な喜びとして受け止め、描いているのだ。高橋氏はさらに、刹奈のここまでピュアな言葉の数々を引き出したのは、永沢のインタビュアーとしての姿勢があったからだと続ける。
刹奈紫之さんのことばは、ものすごくわかりやすい。それは、永沢さんが、彼女のことばをきちんと聴くことができる耳を持っていたからだと思います。
「なんか変なやつだな、気持ち悪い」とか「生意気な女だ」とか「しょせんAV女優のくせに」と思った瞬間、ことばという脆いものはたちまち崩れ、永沢さんには、彼女のことばを理解することができなかったでしょう。おそらくは、ばらばらに話されたことばの断片をつなぎ合わせ、それがきちんとした世界を作るまで、たんねんに再構成して、この「文章」はできています(中略)グロテスクな内容であるにもかかわらず、ある種の爽やかささえ感じることができるのは、永沢さんが刹奈紫之さんという、きわめて個性的な人間とその生き方を、自分にはできない自由なものとして、リスペクトしているからでしょう。
永沢はかつて、「レイプや殺人など他人に一方的な危害を加える者以外、性的に変態と形容される人間はいないと思っている」と書いている。一般的に、自分や世間の理解の範疇を明らかに超える趣味嗜好や思想を持つ人を、尊重して受け入れ、理解しようと努力することは、言うは易く行うは難しで、簡単にできることではないだろう。だが永沢は、やってのけている稀有なひとりなのだ。
元AV女優で、漫画家の卯月妙子さんという方がいる。僕は2022年に、卯月さんに取材をさせていただいた。女優時代の卯月さんは、排泄物や吐しゃ物にまみれたスカトロ作品に多く出演し、作中でミミズを食したこともあった。そのため、メディアでは色物として紹介されることが多かったが、卯月さんがマニアックな作品に出演し続けたのには理由がある。
高校生のころ、卯月さんは地元・岩手県で、ゲイやレズビアンやバイセクシャルなど、さまざまな性癖を持った人たちと交流してきた。彼ら彼女らのなかには、「カミングアウトできない」「パートナーが見つからない」など悩み、ひとりで苦しんだ末に、死を選ぶ人が少なくなかった。鼻フックのマニアの友人が、クレーン車で鼻を釣られた後、思い残すことなく自殺したこともあったという。
当時、SMプレイで使った赤いロウソクが髪についたまま授業を受けていた卯月さんに、担任の教師は「AV女優だけにはなるなよ」と諭したが、「いえ、なることを念頭に置いています」と返した。それも、できるだけマニア向けの作品に出ることで、マイノリティゆえに行き場をなくした人たちを勇気づけ、「生きてほしい!」というメッセージを届けたいからだった。
自分のことで恐縮だが、僕がこのような話を聞くことができたのは、永沢のような向き合い方で、卯月さんに取材をしたからだと思う。性産業従事者だと侮蔑し、マニアックなプレイを「こんなことする人がいるんだw」と面白おかしく捉えていたら、卯月さんの本当の思いにたどり着けなかっただろう。
昨今のコンテンツを大量消費しがちなメディアでは、本当の思いを知ることなどそもそも求められないのかもしれない。変な人がいるよ、理解できないね、面白いね、で十分なのかもしれない。
けれど、僕は書き手として、そんな風潮に抗いたい。真摯に取材対象に向き合い、本質的な姿や思いを描きたい。そう強く考えるようになった背景に、永沢の存在があまりにも大きいことは言うまでもない。
こういった書き手としてのスタンスを永沢が貫き通し、形にできたのは、時代性と、編集者たちの度量の大きさもあったのだろう。1970年代ころからアダルト雑誌は、単なるエロ情報だけでなく、カルチャー誌の側面も多分にあった。評論家の平岡正明氏、僧侶の上杉清文氏、写真家の荒木経惟氏などが紙面を飾り、エロ本でありながら「抜けないけれど面白い読み物」がたくさん生まれていたという。
永沢が『AV女優』のもととなるインタビュー記事を連載していた『ビデオ・ザ・ワールド』『ビデオメイトDX』などでも、文筆家の高杉弾氏、ライターの藤木TDC氏や本橋信宏氏など、そうそうたる書き手が活躍し、サブカルやアングラ文化をつくりあげていた。『AV女優』の解説には、『ビデオメイトDX』編集長だった中沢慎一氏(現コアマガジン社長)の、エロ要素の無い読み物も肯定する粋な言葉が紹介されている。
いいんだよ、おめえ。俺たちグラビアの方でエロやってんだからよ。これはなんかプライドのある文章だからこれでいいんだよ。文章までエロになっちゃうと、なんかヤなんだよな。
そんな時代のエロ本から生まれた類まれな書籍は、どのような経緯で世に出たのだろうか。『AV女優』の編集担当・向井徹氏と、発行元のビレッジセンターの元社長・中村満氏に話を聞いた。
『AV女優』の書籍化に最初に動いたのは、フリー編集者の向井氏だった。アダルト雑誌を習慣的に読んでいた向井氏は、『AV女優』のもととなる永沢の連載にひときわ注目していた。一般的なAV女優へのインタビューのように、どんなセックスをしてきたか、どんな体位が好きか、などの質問は重要視していない。ひとりの女性としての本音を引き出し、結果的にその時代が見えてくるノンフィクションに昇華させている。斬新さや画期性のあるニューウェーブな書き手とは違い、新しさはなくとも非常にていねいな仕事をし、心に染みる文章を書く職人だと感じていた。
あるとき向井氏は、藤岡美玖さんへのインタビューに衝撃を受ける。藤岡さんは、1998年に発生したコンクリート詰め殺人事件(※)に触れ、こう語ったのだ。
※女子高生が不良少年グループに拉致・監禁され、1ヶ月以上にわたって暴行や強姦されて死亡。死体はコンクリート詰めにされ、東京湾に捨てられた事件
わかるね。やった方の気持ちもやられた方の気持ちも。徹底的に淋しくてお互いにあんなことをしているうちに、あんな結果になっちゃったんだよ。親がさ、ちゃんと子供に愛情を注いでいれば子どもはあんなことしないって。わたしは東京の江戸川区で育ったけど、あそこじゃあんなことはたくさん起こってるもん。あれはたまたま女の子が死んじゃっただけでさ。親とか教師とか、大人が変にびくびくしてるから子どもは自分がどんなにいけないことをしているのかも知らずに、ああいうことをやっちゃうのよ。子どもをそこまで淋しくさせているのは大人なんですよ。
被害者と年が変わらない女性の視点で、生まれ育った土地の風土を交え、なぜこのような悲劇が起こったのかを、多くの人に事件の記憶が刻まれているこの時代に、藤岡さんにしか話せない言葉として表れている。「これは時代を捉えた、すごい聞き書きだなと思ったんですね」と向井氏。
「それで当時、兄貴分のような存在だった民俗学者の大月隆寛に読ませたんです。そうしたら、『これはもう民俗資料だぞ、本にしよう! 本になったらぜひ解説を書きたい!』と言われました」
向井氏は白夜書房に連絡し、中沢慎一氏の許可を得て、その時点での永沢のインタビュー記事をすべてコピーさせてもらった。書籍化の企画を最初に提案したのは、かつて向井氏が所属していた新聞社の出版部。懇意にしていた編集者に話したところ、最初は「大月さんが出てくれるのなら」と前向きだったが、企画会議では散々な結果になった。
「その編集者から罵倒に近い感じで、『おめぇ、版元の品格を考えろ』って言われたんです。メインストリームから外れたものに対する感受性はある人だったのですが、『AV』と聞くとアダルトビデオのイメージしか浮かばなかったのでしょうね。企画会議に参加したほかの人からも、『ちょっとうちでやる本ではないと思います』と言われて、結局ボツになりました」
そこで向井氏は、付き合いがあった出版社・ビレッジセンターの中村満社長に相談する。同社は主に技術書を出版しており、企画として適切ではないかも、という懸念はあったが、向井氏が見本の原稿を届けたその夜に、「俺、泣いちゃったよ。これ本にしよう」と中村氏から電話がかかってきたという。翌日、ビレッジセンターで2人は顔を合わせ、『AV女優』を書籍化することが正式に決まった。
永沢の原稿を読んだ印象を、中村氏はこう振り返る。
「誰のインタビューを読んだのか覚えてないけど、ぶつけているような力強い訴求があったんですよ。ひとつのカルチャーとして、すげえ力が入ってるなと感じて。この連載をまとめたいよね、と思いましたね」
一方で、『AV女優』の書籍化を許可した中沢氏は、形になったとしても、売れるかどうか懐疑的に見ていたという。
「あの連載の評価に関して、僕らはわからなかったですね。面白いと思っていたけど、僕らは業界人だから。どのくらい一般の人たちが面白いと思ってくれるかどうか、目利きができなかったんです。有名女優ならともかく、(永沢の連載は)そうでない女優のインタビューが多かったし、どこまでみんなが喜ぶか。だから、本にしても売れないだろうと思っていましたね」
そんな冷静な見方をしていた中沢氏から、永沢の連絡先を聞き、向井氏が電話した。連載を本にしたいと伝えたところ、「そんなことってあるんですか?」というのが永沢の第一声だった。彼も中沢氏と近い思いだったのか、周囲に「単行本にしようって酔狂なところがあるんだ。売れると思う?」と聞いていたそうである。
その後、向井氏と中村氏、永沢の3人で会った。場所は永沢のホームの新宿二丁目。彼の行きつけのバーで、AV女優の書籍化プロジェクトは動き出した。
プロジェクトの責任者である中村氏は、向井氏に「好きなように本をつくれ」と指示し、女優のインタビューは可能な限り収録することにした。分量が増えれば制作費は高くなるが、『AV女優』は時代を動かすような本になる予感があったからだった。ビレッジセンターは、コンピューター系以外の本も出版していたものの、無名の新人作家の本、しかもAVというテーマでここまで力を入れるのは異例だった。
永沢は原稿を読み返しはしたものの、ほぼ手を入れず、「間違ってるところがあったら君が直して」と向井氏に命じた。向井氏も、それまで500冊近くを手掛けてきたベテラン編集者である。プロとして遠慮なく手を入れ、本文を完成させた。
同時に、女優たちへ掲載許可を取るために奔走した。引退しているため断られたり、行方不明になっている人もいたりしたが、探し当てることができた女優たちの多くは永沢のことを覚えており、「あのクマさんみたいなおじさんね。何か知らないけどいっぱいしゃべっちゃったよね」と振り返っていたという。こうして、単行本には42名分が収録できることになった。
最後に後書きである。だが、永沢から送られてきた原稿が、まったく面白くなかったのだと向井氏。
「AV女優など、何かしらの手掛かりをもとに取材して文章にするのであれば、永沢さんは書き手としてとても優れているんです。けれど何もないところから、あるいは記憶を頼りに書くことは、照れや不慣れのせいもあってか、苦手なのかなと感じました」
そこで、解説を務める予定だった大月氏が永沢にインタビューをし、その内容をもとに、大月氏によって後書きが書かれることになった。新宿二丁目の飲み屋に、永沢、大月氏、向井氏が集まった。飲みながら、永沢がライターとしてのスタンスや他者との向き合い方を語り、大月氏は涙を流しながら聞いていたという。向井氏は当時の様子を振り返る。
「あるノンフィクション作家が、(元AV女優)の黒木香さんに取材をしたんです。その翌日に、黒木さんがホテルから飛び降りてしまったことがあって。その作家の黒木さんへの接近の仕方が、『不幸を探す』『何かを暴く』というような功名心が出ていて、僕の感覚にはなじまないと。そんな話をしているときに、大月氏は泣いていましたね」
そのときの永沢の言葉を、大月氏は後書きでこのように紹介している。
あれ読んで、なんか、いじめ以外の何物でもないなあ、なんでこの状態の彼女にこれだけしゃべらせなきゃならないのかな(中略)ほら、なんていうか、うれしくなる話ってあるじゃないですか。僕はそういうのが聴きたいんですよ。
こうして後書きは、『AV女優』本編にまったく引けを取らない、1万字はあろうかという力作に仕上がった。表紙には、本編にも登場する女優の日吉亜衣さんの写真を使った。永沢の盟友であり、編集者で写真家でもある松沢雅彦氏による撮影だった。
最終的に、570ページを越えた。ハードカバーにしたり、本文に写真を入れたりとこだわったため、価格も2800円と高額になった。初版は8000部と強気な数字だが、これだけの部数を刷らないと採算が取れないからだ。
「作りを結構ぜいたくにしたので、1冊売れて利益は300円。出版社社長としてはもう大失格ですよ」(中村氏)
朝日新聞に広告も出した。最初はタイトルがふさわしくないと断られたが、「3本出稿してくれるならば」という条件で許可された。広告費は100万円と提示されたが、中村氏は「勝負したろうじゃないか!」と迷わずOKした。
発売直前、付き合いのあったいくつかの書店に『AV女優』の見本を並べて、テスト販売をすることに。向井氏は、本の出来栄えには大満足だったが、題材や内容や価格からして、どれだけ売れるのかと危惧していた。すると翌日、中村氏から「かなり動いてるよ」と、数十冊単位で売れていると連絡が入ったという。
新聞広告の効果もあったが、大きかったのは30をゆうに超える、さまざまな著名人の書評だった。特に反響が大きかったのは、ドリームズ・カム・トゥルーの吉田美和氏による、雑誌での書評だったと中村氏は回想する(ちなみに、その雑誌のバックナンバーをすべて調べたが、該当の書評は見つからなかった。ドリカムの公式サイトから、そのような書評を書いたか問い合わせたが、返事はなかった)。
永沢への取材依頼も100以上相次いだ。女優の菅野美穂が主演で、数名の女優をオムニバスにする形で映画化の話も持ちかけられたが、脚本を見て永沢と向井氏は「これは違う」と、散々ダメ出ししたうえで断ったという。
「俺はね、やっとくべきだったと思うよ。でも結局、光雄と向井が脚本にNG出してね。冬の屋台でおでんを食いながらね」(中村氏)
「東映のくさい文法みたいな。昔の昭和的なね。それをそのまま引きずってやろうとしていましたよね。旧態依然の人情ものとして仕立てちゃってて、ちょっと悲しいものがありましたよ」(向井氏)
永沢や向井氏が、いかに原作に思い入れを持っていたかが伺え、同時に映画化の話が出るほど『AV女優』が話題になっていたことも伺えるエピソードだ。
なぜ『AV女優』はここまでヒットしたのか。雑誌「創」の篠田博之編集長は、援助交際やブルセラが社会問題になっていた1990年代という時代も、読者が同書を身近にとらえ、受け入れる要因だったのではと書評で分析している。性産業と一般的な日常の垣根が低くなり、特殊だと思われていたAV女優という職業やその人生模様が、ひとつの生き方の記録として多くの読者に読まれたのではないか、と。
そして、その題材を描いた永沢の、効率や生産性を度外視した、職人のような文章の紡ぎ方も、ヒットの一因ではと向井氏。
「大月の言葉ですが、今川焼き屋のおやじが今川焼きを焼いてるような、『AV女優』はそういう仕事だと。作品として何かを書くことを、本来ならそれほど求められないAV雑誌で、手作業で、手を抜かずに誠意を持って、女性と自分との出会いが記念になるような良い形で、彼女たちの一生を本気で文字に刻むと。そういう仕事は、書き手が出版業界で何かやるのとは違う次元の、書くことの原初的、初心みたいなものだと思うんですね」
発行部数はたちまち10万部を超え、記念に向井氏、松沢氏、永沢、彼の妻の恵さんで集まり、中村氏はトロフィーとチャンピオンベルトを贈った。永沢は大喜びしたそうだ。奇遇にもそのとき、テレビではアントニオ猪木の引退試合が放映されていたという。
向井氏や大月氏と同様に、『AV女優』という本を、中村氏も「時代を刻んだ本」だと振り返った。実際、同書には、コンクリート詰め殺人事件などのほか、開通したばかりの東北新幹線、ビデオというメディアなど、1990年代だからこそ聞けた話のかけらが散りばめられ、時代を反映している。
「いろんな時代があるじゃない? ビニ本の時代もあって、AVの時代もあったんです。今は(アダルト動画が)インターネットで無料で流れてるけど、当時はビデオの時代だったんだよね。『AV女優』のどこかに書いてあるけど、(1982年に)東北新幹線が通ってから、東北から素人の女の子が出てきて、AVの撮影を1日やって帰るようになったと。『AV女優』は、そういう時代も刻んでいるんだなぁと」
おそらく永沢には、「今の時代を描いてやろう!」という意識はなかっただろう。目の前の女の子に向き合い、その話にひたすら耳を傾け続けた。すると結果的に、「時代」が投影された文章になった。数十人分の原稿としてまとめられたときに、点が線になり、面になって、その「時代」が表れていた、というわけだ。刊行を決断した中村氏の予感通り、『AV女優』は社会を動かし、歴史に残る1冊になったのだった。
ちなみに永沢は、『AV女優』が増刷になるたびに、印税の一部を向井氏と松沢氏にも支払われるよう、中村氏に頼んでいたという。彼らがいなければこの本はできず、ここまで売れることもなかった、という意識が強くあったようだ。「(印税の計算や手続きが)細かくなるし、俺からすると迷惑な話だよ」と、中村氏は豪快に笑いながら明かした。
書籍『AV女優』ができるまでを振り返ってきた。では、この本のもととなる、雑誌『ビデオ・ザ・ワールド』『ビデオメイトDX』『AVいだてん情報』での連載は、どのように始まったのだろうか。
永沢は大阪芸術大学を中退後、上京して白夜書房へ入社。アダルト雑誌の編集などに従事し、29歳で退社する。小説家になるため、というのが退社理由だったが、実際は1日中何もせず、同居していた女性のヒモ同然だったという。そのときに、白夜書房の同僚で、『ビデオメイトDX』の当時の編集長であり、カメラマンでもあった松沢雅彦氏が、永沢にライターの仕事を依頼したのが始まりだった。
「久々に会って飲んだときに、『文章書いてんの?』って話をしたんです。そうしたら、書いてないっていうから、『それほど原稿料払えないけどうちで書く?』って。『ビデオメイトDX』で、面白そうなビデオを見て、コラムを書いてもらったんです。それが、今でも名文だと思うんですけど、こんなすごい文章を書けるのかって」
そのときのビデオは、深作欣二監督による、実在したヤクザの生き様を描いた『仁義の墓場』。主演の渡哲也が演じるのは、仁侠や仁義を無視し、組織や盃にも牙をむく凶暴なヤクザで、その破滅的な生き様ゆえに壮絶なラストが待ち受けている、という内容だ。永沢はそのヤクザの半生を「転がる石には苔が生えぬ、だがすり減る」と表現し、まったく別の人生を送っている彼に自分自身を投影しながら、破滅へ向かうのは自分でもあるのかもしれない、と読み取れるような描写で締めくくっていたという。
その後も何本かビデオ評を依頼していったあるとき、『ビデオメイトDX』の巻頭で、AV女優へのロングインタビューの連載企画が持ち上がった。松沢氏がライターとして抜擢したのが、永沢だった。
アダルトビデオ情報誌で、女優へのインタビューは珍しくないものの、質問内容は「性感帯は?」「初体験は?」「好きな体位は?」といった紋切り型ばかり。永沢はそもそもAVを見る習慣がなく、既存のライターの枠組みにもとらわれないだろうから、面白い記事ができるのでは、と見込んで打診したのだった。15ページで、原稿料は10万円。月1回の連載だ。当初は乗り気ではなかった永沢だが、結局引き受けることに。1991年のことだった。
だが最初のころは、期待していたような原稿は上がってこなかったという。女優にインタビューをして、400字詰め原稿用紙に30枚もの手書き原稿が送られてきたが、書かれていたのは「女に捨てられた」「アル中で酒ばかり飲んでいる」など、永沢自身のことばかり。女優のことはほぼ描かれていなかった。
指針があったほうが進めやすいだろうからと、「大正ロマン風に描いてほしい」と事前注文していた表現も、「薄日が差した部屋で目が覚めて」などというよくわからないもの。
そこでゲラ(校正刷り)を見ながら、取材にも同行していた松沢氏が、「ここは削ろう」「削ったところにあの話を入れよう」「そうすれば話がつながる」などと助言すると、「そこは松に頼むよ」とポツリ。時間も無いため、松沢氏が必死に編集して原稿を完成させると、永沢は「よくなったねー」と他人事のようによろこんでいたという。
そのように、連載当初は先が思いやられたが、5~6回目から見違えて原稿の質が変わってきたと松沢氏。
「誰か忘れたけど、話を聞いているときに、(永沢が)泣き出したんですよ。そのくらいから文章も変わったような気がするんだよね。最初はAV女優のインタビューなんかしたくない、AVを普段から見ていて業界のことも知ってる人がするべきだ、みたいな思いがあったのかもしれないけど、続けているうちに、本人のなかで楽しくなってきたんだろうね」
面白いのは、と松沢氏は続ける。原稿は、まず松沢氏がリード(導入文)を書き、続いて永沢が本文に取り掛かる、という流れで進めていた。回を重ねるごとに、松沢氏のリードに、永沢の文章が妙にマッチするようになったという。編集者とライターのコンビとしては日が浅かったふたりの感覚が、徐々に調和してきたのだ。
後に永沢は、『AV女優』に関するインタビューで、「取材にも原稿にも、絶対に自分を出さないことを心がけました。こんなことを言うとおこがましいですが、日本のノンフィクションには書き手が出過ぎているものが多すぎる。僕はそれがイヤなんです」としれっと語っているが、松沢氏がどんな編集方針で、どんな原稿を求めているか、つかめてきたということなのだろう。
AV女優へのインタビューは、『ビデオメイトDX』での連載が終了し、1993年に同じく白夜書房が発行する『ビデオ・ザ・ワールド』に場所を移して、当時編集長だった中沢慎一氏に引き継がれた。松沢氏はカメラマンとして、引き続き取材に同行した。
「名インタビュアー」と評されていた永沢は、女優たちから本音や深い話をどのように引き出していたのか。インタビューの技術や工夫、あるいは一瞬で心を開かせる何かがあったのか。尋ねると、松沢氏は首を振った。
「あいつのやり方は、鞄から缶チューハイを出して、『僕はこれを飲まないと』って飲み始めるんです。飲み終わって、そろそろインタビューが始まるのかな、と思ったら2本目を開ける。その辺から(同席している女優の)マネージャーが、中沢さんのほうを『この人大丈夫なんですか?』みたいな感じでチラチラ見るんです」
確かに永沢は、『AV女優』のなかでも、飲酒をしながら女優たちへインタビューをしていることを綴っている。ライターが飲食店を会場に、飲みながら取材をすることは決して珍しくない。だが、女優へのインタビューの多くは、白夜書房の会議室で行われていた。そういった場で、相手の断りなく飲み出すのは、ふざけているのか、と一瞬思ってしまう。
だが永沢としては大まじめで、「初対面の人間へあれこれと話を訊くのは苦行に等しい。相手に対して失礼だな、と思う。こんなことを尋ねるのは余計なお世話だな、と思う。よってやはりアルコールで自分を力ずくで昂揚させてインタビューをさせて頂くことに相成る」と著書で理由を語っている。
なるほど、飲酒によって自らの緊張を解きほぐすのはわかった。では、いざインタビューはどのように進めていくのか。質問内容は、初体験や性感帯など、エロに関することは基本的に無し。彼女たちは、そういったことをすでに何度も聞かれているため、ウンザリされてしまうだろう、という永沢の考えだった。
そこで、小さいころからの生い立ちを聞いていったのだそう。女優からすると、普段されているような質問が一向に出ないため、「性感帯とか言わなくてもいいんですか」と逆質問されることもあったという。
どんなことを聞くか、事前に女優サイドに伝えることもしなかった。ケースバイケースだが、ライターは取材前に、質問内容を相手に共有することが多い。そうすることで、取材相手はあらかじめ回答を考えることができ、取材がスムーズに進んで、取れ高も確保しやすいからだ。
永沢のスタイルはまったくの正反対で、出たところ勝負。だからこそ、その取材でしか聞けなかったこと、感じたこと、現場にいた人たちの様子などを、毎回臨場感いっぱいに描けていたのだと思う。
もうひとつ、永沢の取材の大きな特徴は、時間がかかることだ。インタビューにかかるのは最低3時間で、長いと5~6時間にも及んだという。その理由として、生い立ちから細かく半生を聞いていくからでもあるが、永沢は女優の言葉を「待つ」ことができるからだと、松沢氏は説明する。
「聞くのがうまいとかじゃないんですよ。永沢は女優が沈黙しても、辛抱強く待つことができるんです。すると女優は、しゃべらなきゃ、って思ってくるわけです」
インタビューを成功させるには、技術も必要であることは間違いないが、「待つ」とは何とも意外だった。だが確かに、永沢はインタビューの方法論で、細かなテクニックではなく、「ボタンを押す」「あいづちを打つ」のが自分の役割だと話している。
ずっとこの仕事やってて、ほんとにみんなどの子もしゃべりたいこと持ってんだな、と思いますよ。みんな忙しい中ちょっと時間とってもらって、そのしゃべりたいボタンをポッと押すのが僕の仕事なんですよね。で、いざ押してしまうと、あとはもうやることない。じゃあ何してるかっていうと、相手の表情見てるのね。あいづちうってる。うん、うん、って。それで相手の話をフォローすんのね。はあー、とか感心して。あと、ここだな、と思うところで眼を見てあげるのね。
永沢に取材を受けたことのある女優の沙羅樹さんに、彼のインタビューを振り返ってもらうと、まさにその通りだと話した。
「決して多くを語らない方でした。こちらが言葉に詰まったときも、ずっと黙っている状況があるんですよね。急かしたり、違う話題に変えたりしようとせずに待っている。すると永沢さんと目が合って、彼が『うふ』って笑いながら、雑談か何かをひょこっと入れてくるんです。そうすると、『実は……』みたいについ話してしまうんですよね。相手が何を話そうとしているのか、言い出しづらくてためらっているのかなど、汲み取るのが上手だったと思います」
沈黙している間も、永沢は下を向いていることが多かったため、重圧を感じることもない。求められるような答えをきちんと話せなくても、少しずつ引き出してもらえる、という安心感もあったという。初めて会う女優たちから信頼を得て、話を引き出せるのは、「気持ちを汲み取り、時間をかけて話を聞く」ことが大きかったのでは、と沙羅さんは分析した。
ただ、あまりにも沈黙が続くと、同席している中沢氏や松沢氏はさすがに心配になってくる。間を持たせるために、撮影用の照明の位置を変えるなどと、きっかけをつくってみるが、それでも女優が何も話さないときは、中沢氏が口をはさむこともあった。そんなとき、永沢はしめしめという顔をすることもあったのだと中沢氏。
「話があまりにも進まないと、俺が口を出そう、というときが結構あったんですよ。そうしないとインタビューが終わらないから。永沢も、待ってましたと思ったときもあったんじゃないですか。誰かに入ってもらったほうが、また話すきっかけをつくりやすかったのかもしれないし」
確かに『AV女優』には、中沢氏がインタビューに割り込んでくる描写がよく見受けられる。現場に居合わせた人たちが心理戦を繰り広げ、誰かがアクションを起こす様子が、ちゃっかりと誌面に反映されていたのだ。永沢自身も、ひとりではインタビューができないと告白している。容疑者を自白させるとき、厳しい刑事と優しい刑事がいるように、タイプの違う中沢氏や松沢氏の存在を、永沢は心強く感じていたのだろう。
それにしても、編集長だった中沢氏の立場や気持ちを考えると、インタビューを少しでも早く終わらせたくなる気持ちはとてもわかる。何せ時間がかかり過ぎると、女優のマネージャーから無言の重圧をかけられていたというのだから。
「インタビューの開始時刻は伝えても、終わり時間は言ったことが無かったんです。何時に終わるかわからないですから。すると途中から、マネージャーが『早く終われ!』って言わんばかりに、机をバンバン叩くんです。永沢は全然気にしていなかったけど。インタビューがあまりに長いから、(女優への謝礼を)2万円から3万円にしたんですよ」(中沢氏)
何事もそうだが、時間をかければ成功するとは限らない。ところが永沢のインタビューは、時間をかけたからこそうまくいくことが多かった。最初は不機嫌で、口を開けばグチしか出てこなかった女優も、時間が経てば不思議と態度を軟化させていったという。永沢も、「話を始めて3時間から4時間あたりになってくると、女性たちの顔が柔らかくなって、そこから出てくる話がいいんですよ」と振り返っている。
その大きな理由は、前述した通り、永沢がAV女優ではなくひとりの女性として彼女たちに向き合い、どんな話も受け止める姿勢や人柄が、時間の経過と共に伝わるからなのだろう。実際、最初は「チョー」などと当時のギャル言葉を使っていた女優も、普通の話し言葉になることがあったという。それは、彼女たちのバリヤ―が無くなった瞬間なのだと永沢は捉えている。
結局、「うざい」など今風のしゃべり方は、援助交際に対する大人へのバリヤーなんだろうなと思います。まず、自分たちを守る。ちょっとやそっとでは心を許さないぞ、という防御としての言葉なんでしょう。でも、そんなことを気づかずに、30分くらい彼女たちと話しただけで結論付けたがる編集者たちもいるんですよ。「この荒廃した女子高生たち!」という具合にね(笑)。
女優たちが安心し、心を開き、誰にも話したことのない内容も気づけば打ち明けている。そういった関係性や状況をつくるために、「待つ」ことは欠かせなかったのだ。
インタビューが終わった後も、永沢は女優たちを飲みに誘い、OKしてついてきた人とはさらに何時間も語り合うこともあった。プライベートの場ということで、さすがに録音はしていなかったそうだが、そのときに出た印象的な言葉や女優の様子も、記事に盛り込んでしまうことがあったという。改めて、膨大な情報が凝縮された、密度の高い記事だったということが理解できる。
ちなみに永沢の外見は、一般的にはイケメンとはいえない部類に入る(と思う)。生え際はやや後退し、眼鏡をかけ、無精ひげを生やした男性。しかも、実年齢よりかなり老けて見える。だがその風貌も、女優たちの安心感につながっていたのでは、と永沢本人も中沢氏も推察している。異性として意識しないので、女優たちは変に飾る必要がなかったのではという、男性としては少々悲しい状況も、インタビュアーとしては立派な武器になったのかもしれない。
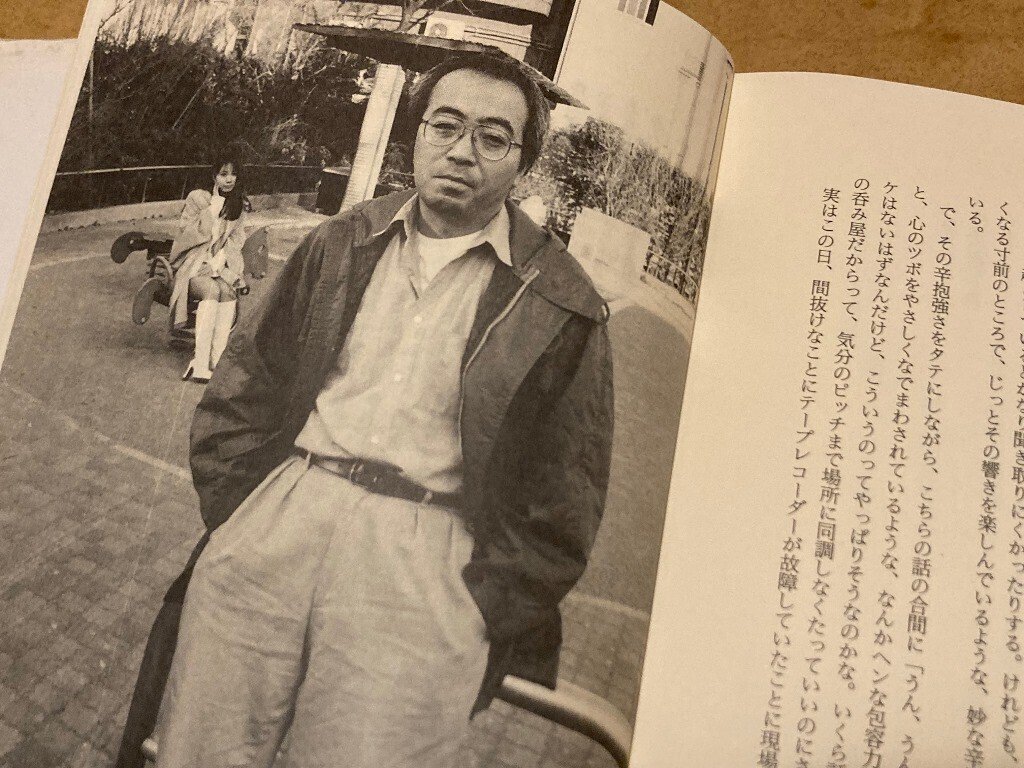
そしてインタビューが終わると、多くの場合、女優たちはすっきりした顔で帰っていったという。半生を打ち明けることで、自分自身を解放させるからでは、と永沢は書いている。
人間の一生で、自分の生い立ちからなにから聞かれる機会って、なかなかありそうでないじゃないですか。自分を説明することによって、はじめて客観的に自分が分かってくるというんですかね。あるいはしゃべることで自分を癒しているというか、言葉ってすごいな、最近そう思うようになりました。
だがもちろん、すべての女優が永沢を受け入れたわけではない。先に紹介した川村弥代生さんへのインタビューは、一切盛り上がることなく終わった。それどころか、川村さんがあからさまに不機嫌になる場面も描かれている。ハワイで知り合った男友達のことを話した彼女に対し、永沢が「じゃあ、そいつとやっちゃったんだ」と、デリカシーのかけらもない発言をしてしまったのが発端だった。
その後、インタビューが成立しているかのような文章が続くが、永沢は「こうやって書き記していると、一応会話をしているようだが、彼女の口調はまさにケンもホロロ」と注釈を入れ、自らのせいで陥った状況を自虐的に描いている。
書籍には未収録の広末奈緒さんもそう。ペニシリンというバンドが好きだという彼女に対し、薬の名前だと勘違いした永沢が、「ということは性病になったんですか?」と尋ねると、広末さんは大きなため息。その後も、女優の深田恭子を永沢が知らなかったことで呆れられ、ますます空気は悪くなり、「今日のインタビューは3・4時間はかかるって言われたんですが、こんなちぐはぐした感じでしたら、1時間も持つかどうか心配ですね」と吐き捨てられてしまうのだ。結局最後まで、可愛そうになるほど永沢は否定され続けたのだった。
同じく未収録の朝岡実嶺さんは、なんと最後まで一言もしゃべらなかったという。仕方なく、彼女のセリフはすべて「……」にし、中沢編集長や松沢氏との心理描写でページを埋めたのだった。
このように、たまにかみ合わない相手もいたが、これまで嫌いだと思った女優はひとりもいないと永沢は断言している。そういえば、後に紹介する高校や大学の友人たちは、彼のことを「優しいやつ」「人のことを決して悪く言わない」と口を揃えた。どんな相手でも否定せず、受け入れる心の広さがあったのだろうか。それとも、嫌なことを受け流す鈍感力が強かったのか。いずれにせよ、『AV女優』のインタビューには、このような舞台裏があったのだ。
ちなみにインタビューした音声は、約3~4倍の時間をかけて文字に起こしていたという。しかも、原稿用紙に手書きである。かかる時間も労力も半端ではないが、この作業によってやり取りの内容や状況を改めて確認し、文章にしていったのだ。
先に紹介した冬木あずささんの、広島弁の特徴だという「ハア」という口癖や、「思わんかったき」「ぶり気に食わん」「一秒たりともおりとうないがね!」などあまりにもリアルな言葉づかいも、もとの言葉を忠実に再現した結果なのだろう。
そして、次の過程で発揮される永沢の構成力が、間違いなく『AV女優』の読み物としてのすごさの核になっている。とにかく、文章構成のバリエーションが豊かなのだ。永沢の視点での三人称、女優の独白で進む一人称、永沢と女優の一問一答、神の視点で描いた小説形式など、さまざまな文章の形式が用いられ、ときに組み合わされて物語は進む。
さらに、永沢はインタビュー以外のことも平気で記事に盛り込んでしまう。ある女優にカラオケボックスでインタビューをしたとき、同席していた中沢氏に警察から電話がかかってきたことがあり、あたふたしていた様子もしっかり書かれていたという。
二日酔いで目覚めた。今日は女優のインタビューがあるのに、資料としてもらっている出演作のAVを見ていない。これから見よう……と、永沢の日常から書き出しが始まることもある。
かと思えば、冒頭に「クイズ」として、読者への問題から始まったこともある。「中学一年生の女の子が、次に挙げるものをつかってあるものを作りました。何でしょう?」とし、「ヘアースプレーの缶」「アロンアルファ」「ラジコンのモーター」など小道具を並べ、答えを「バイブレーター」と明かしてから、本編に入っていくのだ。
『全裸監督』の原作者で知られるライターの本橋信宏氏は、倉沢まりやさんの原稿を読んで打ちのめされたと回想している。その回は、倉沢さん本人ではなく、彼女がAVに出ていることに気づいた弟、高校時代に愛し合った先生、愛人関係にあったヤクザ、浮気をされて別れた会社員、今の恋人であるホストたちが、倉沢とのエピソードを語っていくというもの。ほぼ間違いなく、取材をしたのは倉沢さんだけのはずだが、そこで聞いた話を永沢は何とも大胆に構成し、本人が語る自分史とは一味も二味も違った物語に昇華させたのだ。
とんでもないオチが仕掛けられていることもある。『AV女優』ではないが、スポーツ選手へのインタビュー集『強くて淋しい男たち』の、輪島功一さんの回だ。冒頭、永沢は後楽園ホールにおり、ボクシングの新人王決定戦を観戦している。輪島さんのジムからも3人の選手が出場し、いずれも勝利を収める。KO勝ちしたボクサーは飛び上がって喜んだが、急におとなしくなる。「負けた人間もいるのだから、そんなに喜ぶな」と、かつて輪島さんに怒られたことを思い出したのだ。輪島さんは「しょうがねえ奴だ」と彼をしかりつつも、その顔には満面の笑みを浮かべていた……そんな臨場感のある描写から、輪島さんへのインタビュー本編に入っていく。
だが記事の最後、永沢は冒頭の場面で、後楽園にいなかったことを告白する。酔っぱらって寝ていたため、取材をすっぽかしてしまったのだという。あの描写はスポーツ新聞や、撮影で現場にいた松沢氏の証言をもとに書いた、と明かされて記事は終わる。大失敗もネタにしてしまうのは、永沢が図太い、反省していないということではなく、根っからの物書きだという証なのだろう。
永沢自身も構成には非常にこだわっていたようで、インタビューのなかで創作過程をこう明かしている。
まず、つかみ。1行目に何をもってくるか。わけのわからないセリフをもってくるか、風景をもってくるか、自分の思いをもってくるか。出だしをかいているうちに、ケツがおぼろげながら浮かんでくる。400字詰め原稿用紙の1枚目を書いた時点で、その裏側にケツを書いておく。それを目指して、書き進めていくようにしています。
あとは最小限、説明の文章を入れなければならないですよね。それをできるだけ説明じゃないような書き方で、各所にふりわけていく。そういう志の高さだけはあるんですがね(笑)。
自由かつ豊かな発想の構成力は、永沢が大変な読書家であり、小説家志望であったことと、恐らく密接に関係している(小説家にどれほどの憧憬があったかについては、後に詳しく記す)。
白夜書房時代、彼が同僚の編集者たちに勧めていた一冊が、アントニオ・タブッキの小説『供述によるとペレイラは…』だった。物語の舞台はファシストが支配するポルトガル。体制派の新聞社で働くペレイラが、ある男女との出会いをきっかけに、ペンを武器に国家へ牙をむく、という内容だ。
文章構成における同作の特徴は、各章のすべての書き出しが、「ペレイラの供述によると……」「……とペレイラは供述した」のように始まっていること。捕らえられたペレイラの供述によって、物語が語られているという設定になっている。
永沢が、同作の内容をいかに評価していたのかは不明だが、このユニークな構成に刺激を受けていたのは間違いないと思われる。書き手として新しい表現の可能性を常に模索し、チャレンジしていたという意味でも、構成力はまさに『AV女優』の物語の核だったのである。
永沢は決して筆が早くない。エッセイのなかでも、「締め切りをすっぽかした」ということをよく書いているが、実際は直前で送られてくることがほとんどだったと、松沢氏も中沢氏も口を揃える。彼がもともと編集者だったこともあり、締め切りを守らないことがどれだけ迷惑になるか、重々承知していたからだろう、ともふたりは続ける。
ただ、締め切りが近づいても原稿が送られてこないときは、さすがに心配になる。松沢氏が電話を入れると、焦っているのかいないのかよくわからない永沢が出てこう言ったのだそう。
「いやー、ちょっと出だしがさぁ……とか言ってるんだけど、カランカランって音がするの。焼酎か何か飲んでるんだよね。それで、明日の朝までに送るって言って、結局その日の夜中になって、朝一で写植に入れて。でも、原稿を落とした(締め切りまでに送られてこなかった)ことはなかったんじゃないかな」(松沢氏)
余談だが、編集者は原稿を依頼している作家やライターに、締め切りを2~3日早めに伝えることが多い。原稿が来ない、書き直しが多い、など想定外のことがあっても、余裕を持ってリカバリーできるからだ。だが編集者時代の永沢は、「嘘があったら信頼関係が成り立たない」という理由で、必ず本当の締め切りを伝えていたという。何とも実直な、彼らしいエピソードだ。
そうして世に出たインタビュー記事は、AV業界に根強いファンがたくさんいた。新人の女優に対し、監督が「永沢さんに取材受けてみな」と勧めることも多かったそう。記事が出た後、女優が所属するプロダクション側とトラブルになることがほぼ皆無だったのも、永沢の連載の特徴だったと中沢氏が明かす。
「ほかのライターが書いた女優へのインタビュー記事では、ちょっとうるさい事務所のとき、(記事に出たことで)親や知り合いにバレた、どうしてくれるんだ、引退したらどうする、落とし前をつけろ、みたいな話がたまにあったんです。でも、永沢はトラブルが一切無かった。原稿の事前チェックは(プロダクションに)させなくて、書いた原稿をそのまま載せていたのですが、クレームが来ることは無かったですね」
その理由はいくつかある。大前提として、『AV女優』に登場する女優は、新人~中堅が中心だったため、プロダクションも記事の内容にそこまで過敏になっていなかったことが挙げられると中沢氏。ただそれ以外にも、女優に向き合う永沢の姿勢や目線はもちろん、相手を傷つけてしまうようなことを決して書かず、記事が世に出たときにも悪影響が出ないよう、細かな配慮にも注意を払っている。
取材で聞いた内容のどこを書いてどこを書かないか、取捨選択について永沢はこう語っている。
下品な文章は書かないように気をつけています。例えば、取材対象者が誰かの悪口を言っても書かない。話をしていて、相手がふっと気を許して言う瞬間ってあるじゃないですが。それはいわずもがなオフレコ。その人に責任がかかることは書かない。
こういった永沢の姿勢は、『AV女優』以外でも見受けられる。例えば、スポーツ選手たちへのインタビュー集『強くて淋しい男たち』に収録されている、キックボクサーの上田勝次の記事。過去に上田がヤクザとケンカをし、死なせてしまったことが文中で紹介されている。その後書きに、永沢と編集者の松沢氏のこんなやり取りが収められている。
私は編集者・松沢雅彦に言った。
「上田さんが人を殺してしまったことは、タイトルはもちろん、見出しにもしないでくれよね」
松沢は意外そうな顔をして私を見た。
「当たり前じゃん。そんなことして読者の気をひくゲスな真似はしないよ」
私はあの朝のことを忘れない。他の編集者なら、いや、私が編集者だったら、そのことをタイトルにし、表紙にまで載せただろう。
ちゃっかりオチをつけているが、ここから見えるのは、永沢や松沢氏たちの優しさであり、取材対象への敬意であり、同時にプロの書き手・編集者としての矜持でもある。単に過激な内容を見出しに持ってくるという、安直であり、松沢氏のいうようにゲスな手法は、彼らの美学に反していたのだ。
取材する側には、いわゆる「取れ高」がある。永沢は、ライターであればついガッツポーズをしてしまいそうな取れ高であっても、その内容次第では断固として拒否すると、創作論で明かしている。
負けていくボクサーを描いたノンフィクションがよくありますよね。物語としてはいいと思うんです。ただ、たまに負ける姿が最初から見えていて、ライターが「もらい」と思って書いているものがあると思います。最初から「負け」を売りにしようとしたドラマです。そうなると、負けるしかない物語が読者に組み込まれていく。これは怖いことですよ(中略)だから、「負け」が見えて「もらい」と思って書いた物語を読むと、このライターは冷たい人じゃないかな、と思うんです。
取れ高とは、記事に山場をもたらすことのできる情報であるほか、テレビだったら視聴率、雑誌は販売部数、ネット記事はPVなど、数字の伸びにもつなげられるような資源でもある。だが取材対象者を貶め、消費するだけの情報など、永沢は最初から取れ高だと見ていないのだ。
スパルタ教育でかつて社会の注目を集めた、戸塚ヨットスクールのドキュメンタリー番組を見たことがある。取材班がスクールに密着していたところ、生徒が飛び降り自殺を図った。僕はその場面を見ながら、もし自分が取材班だったら、「もらい」と思うのだろうか、自問自答したことがあった。取れ高ができたと内心では興奮しつつ、現場では神妙な顔をして取材を続ける自分がもしかしたらいるのでは、とも想像した。そうでありたくないと思ったが、実際に直面したらどう思うか、どのように振舞うか、わからなかった。
どうするのが正解で不正解か、答えはライターや編集者の性格や価値観、メディアの方針や評価基準によっても異なるが、おそらく永沢だったら、ひとりの人間としても書き手としても、尊厳を何より大切にした態度を貫いていたことは間違いないだろう。
余談だがネット全盛の現代、編集者たちはいかにクリックされる見出しをつけるかに精力を注ぎ、「釣り」「あおり」といったそれも氾濫しているのを見たら、永沢はどう思うのだろうか。
『AV女優』の記事ができるまでの過程を書いてきた。永沢の女優への向き合い方から、彼を優しく温かく、謙虚で誠実な人柄だと思うかもしれない。
もちろん、その通りなのだろうが、一方で彼がひどく冷静に女優たちのことを見ていたのも事実だ。作家・村上龍氏との対談のなかで、永沢は風俗嬢とAV女優の違いを挙げ、女優たちからたくさんの言葉を引き出すことができた理由を分析している。
AVだけは芸名であっても、他の芸能人たちと同じように、公の存在になるわけです。その中でセックスをしている。それが商品として店頭に並べられる(中略)AV女優にはやはりどこかに「私は匿名ではない」というプライドというか、喜びみたいなものがあることです。だからあそこまで語ってくれるのだと思う。
そのうえで、全員とは言わないが、彼女たちは何かが欠落していると思う、と続け、AV女優という職業を選んだこととの因果関係にも言及している。
「何をやっても、お母さんだけはあなたの味方なんだからね」というような、幼い時にギュッと抱きしめられ、無償の愛を受けたことがない子がほとんどだな、という気がします(中略)だからセックス体験も早くなると思うんです。抱きしめられたい、でも何かが満たされない。そこにブラックホールのようなAVという世界が表れる。スカウトの人や事務所の人が親切にしてくれ、現場に行ったら女王様です。プラス、「私がいなければ、この現場はダメなんだわ」という責任感まで持たされた喜び。それが一瞬だけのものだということは、彼女自身も自覚している。しかし、そこを通過するだけでも、少しは癒される。その喜びのために、皆が吸い込まれてしまうのだと思います。
コアマガジンが発行していたカルチャー誌『BURST(バースト)』の元編集長の曽根賢氏(ピスケン氏)は、AV業界に身を置いていたことがある。永沢は女優たちと同じ目線で向き合いつつも、好きにはなれなかったのでは、と推察する。
「俺はね、(永沢が)AV女優を心底愛したとは思えない。そこらへんはクールに書いていたと思う。最後まで好きになれなくて、苦しんでいると思ってたのね。(AV業界にいたときは)俺もがんばって、女優たちと向こうを張ろうとしてたけど、『夢はお嫁さん』とか聞くと、バカじゃねえの、お前らみたいな感じで。どうしてもこいつらの次元には立てないなって。永沢さんもそんなの嫌いだったと思うけどな」
続けて曽根氏は、『AV女優』がインタビュー集やノンフィクションと呼ばれていることに対し、永沢が女優たちを題材にした私小説集であると断言。あくまで自分の作品として描いていたと語った。
確かに永沢も、『AV女優』がノンフィクションとカテゴライズされることに否定的だった。インタビューした内容をもとに、つまり事実をもとに書かれた内容なので、ノンフィクションであることは事実なのだが、永沢は「自分が書いていることは全部ウソ。そもそもノンフィクションなんてない!」というスタンスだった。
インタビューしているのが僕であるということ自体で、その人の言うことが変わるわけじゃないですか。(中略)また、それをテープ起こしする段階で、発言をチョイスする。その時点で完全に嘘ですよね。(中略)完全に僕の解釈であり、作りものになっているわけで、書けば書くほどノンフィクションなんてないよな、と思えてきたんです。
曽根氏が指摘するように、永沢にとって『AV女優』はインタビュー集ではなく、「その人を材料に好き勝手に書いた」ことによって生まれた、作品集なのだった。
永沢亡き今、彼がどのような思いで女優たちに向き合い、執筆していたのかは知ることができない。ただし、後述するが、物心がついたころから強烈に抱き続けてきた、純文学作家として認められたいという切望が、永沢にとって何よりも強かったことは間違いない。名インタビュアーという評価も、ベストセラー作家という肩書も、家族からの深い愛情も、決して彼を満たせなかったのだ。
ただいずれにせよ、『AV女優』が傑作であり、時代を刻んだ1冊になったことは、ゆるぎない事実なのである。
第2章 神童から落ちこぼれになった10代
永沢は1959年7月14日、宮城県仙台市で生まれた。光雄という名を付けたのは父親で、「男らしく、強くて、光り輝く子になってほしい」という願いが込められている。父親は郵政局に勤務し、母親は編み物教室を経営。3つ年下の弟がいる。この親にしてこの子ありというが、父親はとにかく大酒飲みで、毎日のように泥酔して帰宅していた。酔っぱらって自転車でトラックに突っ込み、血まみれで帰ってきたこともあったという。
さすがに幼少期の永沢は、父親にならって飲酒をすることは無かった。むしろ、神童として大人たちを驚かせていた。まず、生まれついての読書好きだった。生後数ヶ月でありながら、ぐずっていても母親が絵本を読み聞かせると泣き止み、母が眠そうにすると、「おたあちゃん、ねんねだめ!」と続きをねだったそうだ。
小学生5年生のときには、児童図書館にある本をすべて読んだほどの、圧倒的な読書量だった。中学生になって、一般の図書館でも本を借りられるようになり、ゲーテやトルストイの本を受け付けに持っていくと、「君が読むの?」と何度も聞かれたという。中学1年生のときに書いた作文には、旧ソ連のノーベル賞作家ソルジャニーツインの名が、さも当たり前のように登場しているほどだった。
文章力も並外れていた。読書感想文では、いつも学年代表に選ばれていた。先生たちから、親に手伝ってもらって書いているのでは、と疑われたこともあった。中学に入り、「中学生になって」というテーマで作文を執筆したときは、45分の制限時間で、ほかの生徒は400字詰め原稿用紙1~2枚書くのが精いっぱいだったが、永沢は38枚も書いた。
音楽にも造詣が深い。ロックやジャズやクラシックやアイドルなど幅広いジャンルを聴き、特にクラシックの演奏会には中学生ながらよく足を運んでいた。部屋にはカラヤンのポスターを貼っていたほどファンで、アルベルト・シュバイツァーなど同級生がほとんど知らない音楽家にも詳しかった。学校の音楽コンクールでは指揮者を務め、全クラスの24人の指揮者のなかで1位に選ばれたこともあった。
永沢は弁も立った。中学の学年代表のあいさつでは「校長先生よりも上手」と言われ、高校生に混じって出場した討論会では「中学生と思えない」と称賛された。当然のように生徒会長や学級委員長も務め、成績も学年トップ。教室に高校生がいるようだ、と先生たちの間で話題になるほどだった。女子からも人気があり、休み時間には下級生の女の子たちが、ぞろぞろと永沢を見に来ていたほどだったという。
中学から大学にかけて、永沢は演劇活動に力を入れるのだが、その片鱗も幼少期から表れていた。自らの誕生日会ではくす玉をつくり、演出を務めて、司会もこなしたという。小学6年生のときには、初めて自作の劇を上演。以来、中学や高校の文化祭で、永沢は監督・脚本・役者を務めて、毎年のように彼の劇が上演された。
永沢が神童と呼ばれていた幼少期~中学時代を駆け足で紹介したが、このエピソードの多くは、母親の故・昌子さんが彼との思い出をつづった文章が収録されている書籍『神様のプレゼント 永沢光雄・生きた 書いた 飲んだ』からの抜粋だ。後に詳しく書くが、昌子さんは生きがいとも言えるほど、永沢を溺愛していた。我が子が可愛いあまり、何割か盛られている可能性がなくもないが、同級生や教師に取材したところ、永沢がいかに秀でていたか、全員が口を揃えたことからも、ほぼ事実だと思われる。
中学卒業後、永沢は仙台の私立高校・東北学院榴ケ岡高等学校に進んだ。同校は、自主性を重んじる自由な校風の男子校で、個性的な生徒が多かった。当時は3クラスで、生徒数は135人。そのなかでも、永沢は入学早々、一目置かれるようになったのだと、当時27歳の国語教師だった渡辺光昭氏が振り返る。
「授業で3分間スピーチをやったんです。どんな内容でもいいから、頭にあるものを3分間で話してみなさい、というものです。光雄君は確か、授業をさぼって映画を見に行った話をしたと思います。その映画がどんな話か、イメージが浮かんで、自分も観たくなるような説得力と面白さがありましたね」
永沢少年は結局30分近くもしゃべり続け、さすがに渡辺氏が止めたほどだった。勉強もできて、部活は軟式テニス部に入り、夏は上半身裸で練習をするなど、文武両道を地でいくような高校生だった。
渡辺氏は読書好きで、小説も執筆していた。永沢はそのことを知ると、休日によく渡辺氏の自宅を訪ね、文学論や作家論を交わした。高校1年生と国語教師では、さすがに永沢も分が悪いかと思いきや、先生も圧倒されるほどの知識や批評眼を持ち合わせていたという。
あるとき、『旅芸人の記録』という、難解で知られる映画を一緒に観に行った。渡辺氏はあまり理解できなかったが、永沢は興奮して感想を語り、その鑑賞眼に驚かされたこともあった。
永沢の性格がよく表れているエピソードも、渡辺氏は教えてくれた。まず、自分が間違っていないと思ったことに対しては、絶対に折れない頑固さが表われている事件。
高校2年生のとき、文化祭で上演する劇の脚本を、永沢が執筆した。そのなかで、キリストが十字架に貼り付けにされ、リヤカーで運ばれるシーンがあった。榴ケ岡高校はミッションスクールであり、渡辺氏は「まずいのでは?」と忠告したが、永沢は本番でそのシーンを決行。案の定、校長は激怒し、永沢と渡辺氏は校長室に呼ばれた。そこで厳重注意を受け、行動を改めないとこの学校には置けない、と通告されたが、永沢は最後まで謝らなかったのだ。
3年生のときも、似たようなことが起きた。思うことがあったのだろう、日本史の試験で答案用紙を白紙で提出すると、先生が「お前には絶対単位をやらない!」と激怒した。渡辺氏が間に入り、ことを収めようとしたのだが、永沢はやはり謝罪しなかったという。
形だけでも頭を下げる、お詫びの言葉を口にする、ということをするつもりは毛頭ない。単位がもらえなくても、卒業できなくても自分の信念を貫きたい、という芯の強さがうかがえるエピソードだ。ちなみに結局、最後の最後で単位はもらえたのだそう。
永沢は優しい性格で、人の悪口を言うことも一切なかった。そんな人柄が表れているのは、高校時代の合コンのときだったという。永沢と友人ら3人と、ほかの高校の女性3人で、大きな池のある公園に遊びに行った。ボートに乗ることになり、3組のペアになって漕ぎ始めた。すると、永沢の乗ったボートは、一緒になった女子の体系がふくよかだったため、深く水面に沈んでいた。女子たちと別れた後、そのことを友人たちがはやし立てたところ、「女性を笑いものにするのは許せない」と永沢は怒ったという。「女性への接し方や女性観は、後の『AV女優』のインビューに通じているのかな」と渡辺氏は振り返った。
だが高校1年生の途中から、永沢は少しずつ不真面目になってしまう。授業中は本を読んだり、寝たりしていることが増え、成績も見る見るうちに下降。1年生の終わりには学年最下位にまで落ちた。
付き合う友人も、不良ではないものの、いわゆる優等生とは反対の人たちを選ぶようになった。カツアゲやケンカなどはしないが、学校をさぼったり、夜遊びをしたりするように。つるんでいた仲間たちとは、文学や芸術の話題はあまりできなかったが、それでも永沢はそのコミュニティを選び続けた。「自分にないものを持っていた人たちだからじゃないでしょうか」と渡辺氏は推察する。
永沢が中学1年生のときに執筆した「老人」という短編小説がある。おそらくは永沢の分身である、厳しい家庭で育った中学生もしくは高校生が、公園でひとりの老人に出会う。老人は彼に、いわゆるエリートの道を進むことの空しさを諭すのだ。
おれは今まで六十年生きてきたがその中で一体どんなことをしたろう。そうだ学生時代は一生けんめい勉強して志望していた大学に入れた。いや、大学にはいってもなにも得はしなかった。ただ勉強ばかりして結局得たものは何もなかった。だが一流会社に入ったじゃないか。しかしそこもたいくつしてすぐやめた。
永沢のなかで、勉強をして良い大学や良い会社に入って良い人生を送るべき、という世間の風潮に、疑問を感じるような何かがあったのかもしれない。
高校2年生のころからよく遊んでいたという、同級生の原田康博氏は、永沢とどのような時間を過ごしたかを話してくれた。
「土曜日の夜中とか、俺んちに来るんだよね。あいつは4~5キロ離れたところに住んでたんだけど、23時か24時に自転車こいで現れて、仲間たちと酒飲んで、深夜3時くらいまでいて帰っていくってことをしてた。真冬でも、半纏みたいなのを着こんで来るんだぜ」
会話の内容は高校生らしく、授業がつまらないということ、将来のこと、女の子のことなど。永沢は同級生たちとの時間を楽しみ続けていた。
余談だが、高校時代の同級生には、『ジョジョの奇妙な冒険』の作者・荒木飛呂彦氏がいる。後年、永沢は飲み屋で、「荒木がいじめられているのを俺が助けてあげたから、あいつはスタンドを思いついた。だから、俺がいなかったらジョジョはない」と、本気か冗談か言いふらしていたのだそう。
優等生だった永沢が変わったのは、勉強をして真面目に高校生活を続けていく先に、自分の望む将来がないと気づいたんじゃないかな、と原田氏は続ける。永沢が志していたのは、小説家だった。
「物書きになりたいとずっと言っていた。高校のとき、あいつが書いた小説を読ませてもらったこともあって。それは、デパートのエレベーターガールを後ろから見たら、ストッキングに黒い線が入っていて、足の線のことをずっと書いてある文章で。僕にはそれがいいとか悪いとかわからなかったけど、渡辺先生はすごく評価してくれたと光雄は喜んでいて、こいつ本気なんだと思った記憶がある」
実は幼稚園のころから、永沢は「お話を作る人になりたい」と言い続けてきた。王貞治選手が800号ホームランを打ったとき、永沢は母親と一緒にテレビ中継を見ていた。画面に王選手の両親が映り、「王選手は親孝行したね」といった母に対し、永沢は「僕、芥川賞取ってお母さんに親孝行するね」と言ったという。
小説家になるためには、早稲田大学の第一文学部に行かないといけない、と永沢は考えていた。神童であっても、もちろん入試のために努力は必要である。だが、勉強をすればするほど、永沢のなかで違和感が生まれるようになった。そして、「小説家になるために早稲田の一文に行きたい」「勉強などしたくない」という、相反する行動を取っていった。
永沢は宣言通り、早稲田大学を受験するが失敗。文学や芸術への知識・批評眼は高校生離れしていたが、何せ勉強をしなかったのだから、当然の結果なのだろう。東京で浪人生活を送ることになった。早稲田にある予備校と寮の費用は、母親が支払った。
だが2ヶ月後、永沢が予備校に行かず、毎日図書館で本を読んでいるようだと、寮母から実家に連絡が来る。父親は激怒し、寮に迷惑だからすぐ追い出せとまくしたてたが、母親はすぐ東京に行き、寮にお詫びをして、永沢のためのアパートを都内に借りた。無理に大学に行く必要もないから好きなことをしなさい、とも伝え、仕送りも続けた。息子への期待も願望も叱咤も嘆きも超越し、慈愛だけでただ彼を包んでいたことが伺える。
母親が金銭的なサポートを行えたのは、永沢が中学1年生のとき、治療院を開業したからだった。姑といざこざが起きたのをきっかけに、自立できる生き方を目指したのだ。それまで営んでいた編み物教室では、子ども2人の教育費にはならないため、指圧マッサージの国家資格を取って、永沢治療院を開業した。1回につき約3500円の施術を、毎日10人以上に行っていたという。客は当時の仙台市長をはじめ、比較的余裕のある人が多く、常に繁盛していたそうだ。永沢は「自分の目に触れるところには看板を出してほしくない」と言ったそうだが、この治療院で母が稼いだお金が、長きにわたって彼を支えることとなる。
受験から解放された永沢は、読書やアングラ演劇のサークルでの脚本制作にのめり込んだが、やはり進学への思いも捨てられなかった。しかし、受験勉強はまるでしていない。そこで、入試が小論文だけしかない大阪芸術大学を受験し、2浪で入学が決まったのだった。
この話には裏側がある。永沢は受験前日、大阪・天王寺のホテルに宿泊した。その近くにあった鳥仙という焼き鳥屋に入り、客たちに大阪芸大の受験が明日であることを話すと、「あそこは朝まで飲んでいかないと受からないよ」と助言された。気づけば、朝4時までどんちゃん騒ぎをし、二日酔いで試験に行ったところ合格。焼き鳥屋の人たちの言うことは正しかったんだな、と永沢はしみじみ思ったという。
第3章 酒浸りの大学生活と母の寵愛
永沢は大阪芸術大学の文芸学科に入学した。文学好きの彼だけに、「現代詩研究会」というサークルに所属する。そこで出会ったのが、後に一緒に劇団を立ち上げることになる、舞台芸術学科の三枝希望氏だ。
サークルに入ったのは良いものの、どうも面白くない。詩の公募で佳作を取っただけで、鬼の首を取ったかのように周囲に自慢をしている先輩を、永沢は憐れむような眼差しで見ており、三枝氏が同調したことですぐに意気投合した。永沢の最初の印象を、「読書量と知識量に圧倒された」と三枝氏は話す。
「ロラン・バルトがどうとかロダンがどうとか、バカにもわかるように話してくれたので、こっちも興味を持つことができましたね。(演劇の)『熱海殺人事件』では、(俳優の)平田満がこういう風に演技していた、っていう話も聞きました」
当時、永沢が住んでいた下宿は、大阪府羽曳野市にある安アパート。絵に描いたような汚部屋で、腐りかけの畳には万年布団が敷かれ、ゴミが散乱していた。部屋にはそもそもゴミ箱が無かったので、まずゴミ箱を用意してそこに捨てる習慣をつけたほうがいいと三枝氏がアドバイスし、最初はその通りにしていたが、すぐ元通りになってしまったという。
「泊まりに行ったとき、布団で寝ろって言われたんです。横になったらウジ虫がうにゃうにゃ這っていて、ぎゃーって叫びましたね。ほかにも、電子ジャーを開けたら黄色と青と緑の煙が出たとか、冷蔵庫にあったレタスをつついたら一瞬で水になったとか、そんな部屋でした」
部屋には永沢らしく、小説や漫画など大量の本が積み上げられていた。机には原稿用紙があり、永沢が小説を書いていた痕跡もあった。
服装はいつも、洗濯していないであろう茶色系のもので、冬でもサンダル履き。ひげを生やして眼鏡をかけ、風来坊かホームレスかといういで立ちだったが、無頼派のような雰囲気が魅力に映ったのか、芸大の女子たちにはモテていたという。

同級生にはよしこちゃんという長身で肉感的な美人がおり、男たちに思わせぶりに近づいてもてあそぶタイプだったが、その子も永沢には引かれ、付き合い始めていたという。
永沢と三枝氏は、とにかくよく飲んだ。行きつけの焼き鳥屋・鳥仙で飲み、永沢の家に場所を移して飲み、酒もつまみもなくなると、朝まで営業している近所の中華料理屋に移動して飲んだ。買い出しをして再び永沢の家で飲み、午前11時になると餃子の王将へ。夕方まで居座り、鳥仙の開店時間になったら移動してまた飲む。三枝氏もかなり飲める口だが、まるでお茶のように延々と酒をすすり続ける永沢の酒量はけた外れだった。
「当時からアル中で、肝臓が肥大しているんだ、フォアグラなんだってよく言ってましたね。そうなってもおかしいくらいの酒量でした」
永沢の執念深さがうかがえるエピソードも、三枝氏は披露してくれた。いつものように酔っぱらった後、三枝氏が犬の糞を永沢にぶつけたことがあった。すると永沢は、犬の糞を棒に刺し、延々と三枝氏を追いかけ回し、復讐に成功したという。トランプのセブンブリッジをすると、永沢は自分が勝つまで決して止めようとしなかった。三枝氏は、こいつとは絶対にケンカしたくない、と思ったのだそう。
時系列が前後するが、この話を聞きながら、なるほどと僕は納得した。永沢がフリーライターとして活動していたとき、ある編集者が仕事を依頼した。内容は、都内の屋台の飲み屋を取材するというもの。だが、目をつけていた渋谷の屋台で取材交渉したところ、頑固そうな大将に断られてしまった。そこで永沢がとった行動は、OKをもらえるまで居座って飲み続けることだったというのだ。結局12時間ほどいて、折れた大将に取材許可をもらったのだそう。
AV女優たちへの取材で、永沢は何時間でも待つことができると紹介したが、望む結果のためなら我慢比べをいとわず、しかもその過程すら楽しめるメンタルがあったのだろう。
劇団を結成したのは、三枝氏といつものように飲んでいるとき。永沢からの「芝居しようか」という誘いで、ふたりは劇団を立ち上げた。劇団名は「愛の冷やしパンツ」という、前衛的なのかふざけているのかよくわからないもので、命名したのは永沢だった。名前に特別な意味はなかったという。
当時は劇団新幹線や、南河内万歳一座など、大阪芸大出身者による劇団が注目され始めていた時代。映像では、庵野秀明が評判になりつつあった。そんななかで、自分たちも一旗揚げたいという野望と、若さゆえのノリで劇団を立ち上げたのだった。メンバーには、永沢の恋人であったよしこちゃんと、同じく芸大生の安藤基博氏も加わって、4人で劇団活動は始まった。
永沢は主宰でありながら脚本、演出、出演もこなした。「蜻蛉日記」「私が月を捨てた晩」という男女のシリアスな人間ドラマと、三枝氏も安藤氏も覚えていないというもう1本の合計3本を上演した。観客の入りや評価はいずれも悪くなかったが、アングラ演劇を意識した作風だったこともあってか、客先からヤジが飛ぶこともあったと三枝氏は苦笑する。
「(初の南極点到達を競った)アムンゼンとスコットはどうしたこうした、っていうシーンがあるんです。私が歌舞伎の隈取をして、『先にスコットが着いちゃったからアムンゼンが遭難した』としゃべっているときに、客から『ナンセンス!』ってやじられました。あれは辛かったな」
永沢自身も役者として、夏休みにラジオ体操の出欠を管理するおじさん役を演じた。ヌレゾーというそのおじさんは、出席した人に押すためのハンコを持っているため、絶対的な権力者として君臨している。太陽がまぶしかったという理由で、彼は出席した人を殺してしまう、というシュールな設定だったという。ちなみにヌレゾーとは、カミュ『異邦人』の主人公であり、太陽がまぶしかったという理由で殺人を犯すムルソーのもじりである。
演劇はお金がかかる。困ったときに永沢が頼るのは、やはり母親だった。彼はそのときの様子をこう綴っている。
芝居の制作でお金が足りなくなったとき、ぼくは10円玉で大阪から仙台のおふくろに電話して「100万円よこせ」ガチャン、ですからね。そのうち、60万円は飲み代に消えましたけど(笑)。
母親の昌子さんはお金を出すだけでなく、公演があるたびに仙台から駆け付け、観劇した。そして、高校時代の恩師である渡辺先生に電話し、感想を楽しそうに話していたという。大学の学費を支払い続けたのも、もちろん母親である。
「愛の冷やしパンツ」の活動期間は3年間、3本の公演をもって演劇活動は休止となるのだが、三枝氏や安藤氏との交流は変わらず続いた。もちろん、そこには常に酒があった。彼らの拠点となったのは鳥仙だ。
同店があったのは、大阪・天王寺にかつてあった「あべの銀座商店街」。西成や飛田新地にほど近い、いわゆるディープな飲み屋街である。競馬で勝った帰りの客が来ると、ほかの飲み屋にもすぐ連絡が行き、「あの客は金持ってるで!」と伝達される。たちまち客引きがたかり、飲み屋から遊郭まで連れていかれ、肌身をはがされてしまうという都市伝説のあった一角だ。学生運動の活動家たちのたまり場もあり、公安がよくウロウロしていたという。新宿でいうとかつてのゴールデン街のような、魔窟のごとき怪しさのある飲み屋街だったのだろう。
実際、鳥仙の客も変わった人が多かったという。文芸誌の編集長や写真家や医者、大学生たち、そして何をしているのかわからない怪しい人たち。かつて常連だった人は、こう回想する。
「これ知っているか? と店のなかでパンツを脱ぎよって、真珠入りのチンチンや、って見せられたんです。少年院に入ってるときに、歯ブラシの柄をコンクリートで削って丸くして、そのまま入れたらばい菌がついて危ないから、口のなかで消毒して入れるんや、って言うてましたね」
かと思えば店の人は、入り口の前で寝ている酔っ払いに水をぶっかけて追い払う。そのように店側も客もたくましく、自由奔放な空間だったのだ。
永沢が初めてやって来たのは、前述したように大学受験の前日だ。当時を、鳥仙の店主である通称おばちゃんはこう振り返る。
「ふらっと入ってきて、『黒岩重吾の小説であべの銀座のことを書いてあった。面白そうなところですね』と言ったわ。それで周りのお客さんに、あのアホ芸大は飲まな入られへんぞ、みたいに飲まされてましたね」
大阪芸大に入学後、永沢はほぼ毎日のように鳥仙に通うようになった。当時、焼き鳥が4本で200円、ビールが400円。庶民的だが、学生が毎日通うとかなりの金額になる。お金の出どころはもちろん、母親からの仕送りである。当時、お金のなかった三枝氏や安藤氏にも、永沢はいつもおごっていたという。
鳥仙での永沢は、居合わせた人と仲良くなるのが抜群にうまく、たちまち人気者になった。人生経験豊富な大人たちが、単なる大学生の彼に、なぜか話を聞いてもらいたくなるような雰囲気を醸し出していた、とおばちゃんは言う。
「聞き上手やったな。人見知りしているようで、していない。飲んで、みんなの話を聞いているという感じやった。自分から面白い話をするとか、ふっかける話はせえへんかったからな」
後に『AV女優』で、名インタビュアーと称されるようになった永沢は、話を引き出す秘訣として、まさにこの時代の経験があったからだと話している。
まあ、だてに飲み屋には行ってないから(笑)。学生の頃、飲み屋でおっさんの話を訊くのが好きでしたね。おっさんが話し始めると、「やった!」という気になりました。嘘か本当かわからないけど、わくわくしながら延々と物語を聞く。全然知らない世界じゃないですか。聞いていて楽しくなって、もうおっさんの世界に入りますよね。
おばちゃんや三枝氏や安藤氏など、大阪で親しかった人々と永沢の付き合いは、この後30年近く、永沢が亡くなるまで続くこととなるのだった。
永沢の母・昌子さんと、大阪の母・おばちゃんの交流が始まったのも、永沢が大学生のころ。「愛の冷やしパンツ」の公演を、母親が観に来たときに初めて会った。「派手なおかんでな。紫色や黄色の洋服を着たりしてたわ」と、おばちゃんは印象を振り返る。
公演の準備で忙しい永沢の代わりに、おばちゃんが阿倍野のバス停まで迎えに行き、一緒に観劇した。おばちゃんは「わけわからん芝居」という感想だったが、昌子さんは大絶賛していた。そして、「光雄の夢は私の夢です」と目を輝かせていたという。
久々に息子のもとを訪れた母親は、会えなかった時間を取り戻すかのように数日間滞在し、彼の世話をした。たまりにたまった洗濯物を、レンタカーで何往復もして、クリーニング屋に運んだ。汚れ切った布団を新しく買ってあげてくださいと、おばちゃんにお金も託した(本人に渡すと飲み代に使ってしまう、と予見したからだそうだ)。もちろん、仕送りの使い道や酒浸りの日々について、息子を叱ることや注意することは一切しなかった。だがそんな愛情をよそに、永沢は母がくれた佃煮などの食料を、押し入れに放置して腐らせてしまうこともしばしばだった。
大阪芸大に入学して4年。本来であれば卒業間際の時期に、大学の総務課から母親に電話があった。永沢は大学に行かなくなっていており、卒業できないという。結局、大学は中退した。それでも母親は、落胆するどころか、「両親が4年間授業料を収めたことに誇りを持ちましょう」と受け入れた。
それだけでない。その後、永沢はある会社に就職が決まったが、思うことがあったらしく、入社を辞退した。その報告を受けると、母も「辞めていい」と伝えたという。父親は激怒したが、母親はここでも永沢の味方であり続けたのだった。
その後も昌子さんは、永沢が亡くなるまで、月10万~20万円を仕送りし続けた。昌子さんは、永沢が死去した数年後に亡くなっている。おばちゃんは、亡くなった方のことを悪くは言えないけど、と前置きしたうえで、「ゴッドマザーだった」と語る。
「おかんは過保護を超えてたな。ちょっとおかしいと思った。自分ができへんかったことを、光雄に半分乗っかってやらせているなと思ったわ。下の息子(弟)も、放ってはおけなかったかもしれないけど、光雄ほど溺愛してへん。ちょっとハミ子やったん違うかなと。やっぱり光雄本位やったん違う?」
永沢と8年間交際し、婚約までした女性も、昌子さんの強すぎる愛情が、彼を縛り付けていたと言及した。そして、「永沢を殺したのはお母さんだと思っています」と打ち明けた。
永沢の小説やエッセイに、Rさんとして登場する女性がいる。大学時代、よしこちゃんと別れた後に知り合って恋人になり、一緒に上京して暮らしていた相手だ。年齢は永沢より2歳下。彼女は会社勤めをしていたが、永沢は小説を書くといって働かず、1日中原稿用紙の前にいた。そんな彼に、Rさんは飼っていた犬の散歩をすることで、1回500円をあげていた。1日3回、1500円を貯めて、永沢は焼き鳥とチューハイ代にしていたという。だが結局、働かない永沢に愛想を尽かし、彼女は去って行ってしまう。Rさんとのエピソードはそんな風に描かれている。
犬の散歩の話は、本当だという説と、あまりにもでき過ぎているため嘘だという説の、両方があった。Rさん本人に会うことができ、確認すると、「完全に事実ですね」と笑いながら答えてくれた。この方こそが、永沢の婚約者だった方だ。
Rさんは、永沢と同じ年に大阪芸大に入学し、共通の友人を通じて知り合った。「愛の冷やしパンツ」の活動が終わりかけのころだった。会って少し話した瞬間、2人は引かれあい、すぐに付き合うようになったという。
「多分、波長が合ったんじゃないかな。心の中が透けて見えたというか、こんなときに傷つくとか、こんなときに寂しいとか、ふっと目を上げたときに彼の見ているものが私にも見えた、みたいな感じでした」
2人はRさんの部屋で同棲に近い生活を始める。彼女が卒業した後、東京に行きたいという永沢について、2人は上京。世田谷区のアパートで暮らし始めた。永沢との日常は楽しいことがいっぱいあったとRさん。散歩へ行ったり、海や温泉へ行ったり、交換日記や手紙のやり取りをしたりと、何気ないけれど幸せな時間をたくさん共有した。甘えたがりな性格のRさんを、永沢はしっかりと受け止める役割だったという。
Rさんは下戸だが、永沢について飲み屋に行くこともあった。人前でも必要以上に彼を立てることはせず、「気に入らないことを言ったら水や酒をかけたりしていました」と笑う。一緒に動物園に行ったときは、後の『AV女優』にも通じるような、永沢の優しさを表すエピソードがあった。
「たくさんウサギがいたんですけど、ほかのウサギにかじられたのか、耳がギザギザになっている子が永沢の足元に寄って来たんです。こういう子に慕われるんだね、という話をしたことがありますね。本来は力強くても、弱い立場に置かれてしまったものに対する優しさは、人一倍あったと思います」
だが一方で、永沢が抱えている危うさも、常に見え隠れしていたという。酒を手放せず、酔っぱらって人々と交流したりはじけたりする永沢の姿は、どこかつくられたようにRさんには映った。Rさんの前だけで見せる、むき出しになった本来の永沢は、常に死に向かっていたのだと彼女は話す。
「あまりにもセンシティブだから、自分のままではいられなかったと思います。だから、酔っ払ったり、おちゃらけたりすることに全力を傾けていた。そうすることで人とコミュニケーションを取り、同時に自分のバランスも保っていたと思います。とにかく感覚を麻痺させないと、彼はもっと早く死に向かっていただろうし」
おそらく本人も、自らのなかにある死への衝動には気づいていた、とRさんは続ける。
一緒に演劇活動をしていた安藤氏も、永沢の繊細さを目撃したことを回想する。
「永沢のアパートで飲んでいるときに、彼が過呼吸の発作を起こしましてね。ビニール袋をかぶって、二酸化炭素を吸って過呼吸を治めることをしていました。発作を見たのはそれ1回だけだったのですが、もしかしたらデリケートな部分があって、彼の家に僕たちがいて話していること自体が、精神的な負担になっていたのかなと」
永沢自身も、著書のなかで、幼いころから鬱や希死念慮にさいなまれていたと書いている。死への衝動と、それを防ぐために薬や酒に頼らねばならなかった心情が実に生々しい。
子供の頃から私は自分の鬱病気質に苦しんできた。いつも、わけのわからない絶望感が体を占領し、死とか自殺とかいう言葉が隣でほくそ笑んでいた。高校生の頃に精神病院に足を向けたが、子供だましのような精神安定剤はセイロガンほどの役にも立たなかった。20代になり、私はアルコールにより自分の正体をなくし自分と対峙しない術を覚え、なんとか或る会社に勤めることができた。だがアルコールと鬱病気質は絶妙な相関関係にある。自分に絶望している自分をどうすることもできずに酒を飲む。何杯か飲むうちに本来の陽気な自分と思っている自分がやってくる。だがその時点で飲酒をやめるのはほぼ不可能だ。したたかに酔う。そして翌日はお決まりの自己否定だからまた酒へ手が伸び……
大抵は日がな一日、襲ってくる自分の将来への不安をアルコールで吹き飛ばすことに懸命だった(中略)一種の、緩慢な自殺であったかもしれない。とにかく、睡眠薬とアルコールで、一秒たりとも素面の自分と面と向かうのを私は拒んでいた。それこそ、一瞬たりともてめえ自身と顔を見つめあったら、本当に喉をナイフでかき切りそうだった。
Rさんは、彼を死へ向かわせていたのは、母親の昌子さんの存在だったと断言する。前述したが、昌子さんは同居していた姑との関係が良くない時期があった。夫に相談しても、まったく耳を傾けてくれない。苦しみ、悲しみ、怒り、憎しみ、やるせなさ……味方もおらず、降りかかるさまざまな感情をひとりで受け止め、押しつぶされそうになっていたとき、自分の前にいたのが永沢だった。私はこれから、この子と生きていく。そう決意してから、昌子さんの思いが永沢に取りついたのではという。
「お母さんは相当に苦しまれていたと思います。永沢の幼いころの思い出のなかで、『一緒に死のう』と母に首を絞められたことがあると言っていました。彼がうつ病になり、死へ向かっていったのは、そういう影響があまりにも大きかったのではないでしょうか」
もちろん、あくまでRさんの感じ方や想像であって、真実はわからない。だが手がかりのひとつとして、昌子さんが「思い出したくもないことだが」と当時の出来事を振り返っている文章を引用しながら、照らし合わせてみたい。永沢が小学校4年生のときである。
姑が私に対して異常な行動をとることが増えてきていた。夫に相談しても暖簾に腕押しで、全く頼りにならなかった。息子の職場での失敗も嫁のせいにしてなじられるような状況だった。私はどんなになっても姑に反発はしたことがなかった。ある時、姑の恐ろしい形相に、私は足ががくがくするほどの恐ろしさを覚えた。
永沢も、このときの出来事が印象に残っているのか、私小説でその場面を描いている。
母親が祖母の部屋に夕食の準備ができたことを知らせに行った。すると、今まで耳にしたことのない母親の「キャー!」という悲鳴が聞こえた。「キャー!助けてえ!」
台所でテレビを見ていた弟と私が走った。母は祖母の部屋の前で腰を抜かして座り込み、顔をひきつらせていた。そしてその前にはいまだに思い出すと全身に震えが走るのだが、体中から酒の臭いを発散させた全裸の祖母。その両手には包丁が握られている。目を血走らせて白髪を振り乱した祖母が母に低い声で言った。
「お前を殺してやる」
母親は永沢と弟の手を引いて、近所にある母親の弟の家に逃げ込んだ。だがそこで夕食を食べた後、永沢は「家に帰る」と、父や祖母のもとへ戻ってしまった。永沢が何を考えているのかわからず、親子の絆が突然立たれたように思え、母親は大変落ち込んだという。実は永沢は、弟だけでなく自分も母親と一緒にいたら、両親が離婚し、家庭崩壊してしまうと考えたため家に戻ったのだった。
永沢には会いたいが、祖母のいる家に戻るのは怖い。逡巡していた母親が、占い師に相談したところ、「姑もあなたを待っているから帰った方がいい」と助言され、ようやく家に戻った。永沢と再会して、昌子さんは彼の気持ちをこう理解した。
光雄は「お母さん帰って来た!」と私に飛びついてきた。その時、光雄が突然自分ひとりだけで家に帰った真意を悟った。「自分がいるところにお母さんはきっと戻ってくる」と確信していたのだ。
お母さんは自分から離れない。自分を捨てるはずなどない。必ず戻ってくる。永沢がそう思っているのだと気づいたことで、「この子と生きていく」という決意や覚悟を決めたと読み取れる。離婚や家庭崩壊を防ぐため、という永沢の真意とは若干ズレがあるように思える。昌子さんが夫や姑の力を借りなくても自立できるよう、指圧マッサージの資格を取ろうと決めたのは、この出来事の直後である。
Rさんの話に戻る。彼女は、昌子さんの寵愛から永沢を引き離そうとした。自立させ、本来の永沢として生きて欲しかった。けれど、自分にはできなかったと、Rさんは吐露する。
「お母様に取り込まれて苦しんでいるんだったら、自分を解放するために一緒に闘おうよ永沢、って私は思っていました。2人で乗り越えたかった。けれど、自分の人生なんだから、自分で解決すべきだとも思っていたし。若かったこともあって、応援の仕方がわからなかったんですよね」
お互いの結婚観や家族観の違いもあった。結婚したら永沢姓になるのが当たり前だと思っていた永沢や彼の家族に対し、Rさんは夫婦別姓を望み、さらには夫というだけで彼が世帯主になることを許せなかった。そして付き合い始めてから8年、永沢が30歳のときに、Rさんは別れを切り出した。彼は著書のなかで、当時のことをこう書いている。
毎日、図書館に行って分厚い本を借りてました。それを机の上に置いて、いかにも勉強をするふりをして酒を飲んでいましたね。そしたら、ずっと同棲していた女性の堪忍袋の緒が切れたようで、「出ていって」と言われたんです。
その通りだったのかRさんに確認すると、「私が言ったことを、世間に向けた共通語で表して、そう書いたのだと思う」という返事だった。実際にRさんが伝えたのは、「あなたのなかの悪魔を私が追い払えないから別れる」という言葉だったという。
永沢のことが好きという気持ちは、最初から変わっていない。けれどこのまま2人で進むと、彼か自分が死ぬしかないところまで追いつめられることが、明らかに見えていたからこそ、別れを決意したのだった。
「それ(死)を私が引き受けるか、引き受けないかという選択を迫られるような精神状態になっていました。そういったものに連れていかれて死んでしまうのは、彼の美学ではあったかもしれない。でも私の美学ではないなと思ったので、別れたんです」
「あなたのなかの悪魔を追い払えない」という言葉を、永沢はどのような思いで受け止めたのか。言葉の意味は伝わったのか。咀嚼して飲み込めたのか、それとも口に入れただけで吐き出してしまったのか。文章にするとき、どんな思いで世間に向けた共通語に変換したのだろうか。
今や知る由もないが、永沢がこのエピソードを文章にした際はいずれも、「恋人に愛想を尽かされて去られたダメな自分」という、ユーモラスなトーンで描かれている。
昌子さんと永沢が共依存のような関係から抜け出せなかったことを、Rさんが確信したのは、彼の死後だった。永沢の訃報を報じるニュース番組に昌子さんが出演し、コメントをしていた。その内容は、永沢との思い出ではなく、「妻の恵さんはいかに永沢に尽くしてくれたか」だった。その様子に違和感を覚えたという。
「テレビ局は、お母さんと息子のエピソードが聞きたかっただろうに、『なぜ恵さんがこんなに尽くしたか?』をしゃべっていたんです。妻がこれほどに尽くした、意味のある男だったというのを母が語るのは、すごくおかしい。そのときに、やっぱり永沢はお母さんに取り付かれていたんだ、と思いました」
思い出話をするのではなく、永沢の価値が高まるような話に終始する。健全な関係性だったら、純粋に自分が楽しかったことや印象的なことを話していたのでは。Rさんにはそう映ったのだった。
本当の意味で、100%健全で幸せな家族など、ほぼいないと思う。親子や兄弟もそう、夫婦もそう、友達や恋人もそう、職場の上司や同僚もそう。一見うまくいっているように見えても、裏側を覗けば、どこかで我慢したり、あるいはガス抜きをしたりと、関係を成立させるための何かしらのことを、意識的あるいは無意識的に行っている。結果的に、不満らしきものが完全に解消されずとも、日常生活や関係性や心身に支障をきたさない範囲で収まっている状態が、本当の意味での健全といえるのだろう。
ただ、そのためのはけ口が外部ではなく、すべて相手に向いてしまったとしたら。すがりつくことでしか「愛」らしき関係性を成立させることはできないのではないか。そしてその関係性は、無償の愛を贈与しあっている風に見えても、実は共依存に陥っていたのかもしれない。
昌子さんの永沢への愛情の原動力は、どこから来ていたのか? 鳥仙のおばちゃんから「ハミ子」と見られていた弟はどう思っていたのか? 愛情が永沢を縛り付けてしまっていた面はあったのか? こればかりは他人にはわからないこともあるだろう。
僕は永沢の弟のYさんの勤務先を調べ、手紙を出して取材を申し込んだ。「メールでよければ」ということでOKをもらい、以下のようなやり取りをさせていただいた。
――昌子さんの光雄さんへの愛情の原動力は、どこから来ていたと思いますか? 兄が寵愛されているのを、弟としてどう思いましたか?
「原動力は不明。愛情としては、均等に向けてくれたように感じます。私も、長い大学院生活を金銭的に支えてもらいました」
――光雄さんはお母さんに愛され、支援を受け続けることで、縛られてしまっていた部分もあると思いますか?
「依存症に関して、その人間の周辺に依存を可能にする『イネーブラー』の存在が指摘されます。母は、まさにイネーブラーです」
イネーブラー。初めて聞いた言葉だった。辞書で引いてみると、以下のように解説されていた。
1,他の人の行動に力を貸す人。後援者。「―型企業」
2,依存症者などに必要以上の手助けをすることで、結果的に状況を悪化させる人。
3,コンピューターで、特定の機能や機器などを利用するためのソフトウエア。
おばちゃんやRさんの話を聞いた限りでは、昌子さんの存在はまさに2がそのものではないか。当人からすると愛情だが、過剰あるいは歪んだそれは「呪縛」となり、相手を負に引き込んでしまうのかもしれない。
僕は心理学者でも何でもないし、簡単に答えを出すつもりも、いや、出せるとも思っていない。だが、永沢と母親の関係性を紐解く、あくまでひとつの回答や意味付けとして、「過剰あるいはゆがんだ愛情」というキーワードが見えてきた気がした。
余談として、永沢とRさんのエピソードを書く。大阪で同棲しているとき、ふたりの間に子どもができた。Rさんは生みたかったが、学生ということもあり、堕胎を選択した。その少し後、永沢が手にケガを負ったとき、傷跡が人間の形をしていたという。永沢は、「これは、自分が産んであげられなかった子どもだ」と言ったのだそう。
その傷はずっと消えず、永沢が亡くなったときに、「もしかしたら彼が一緒に連れて行ってくれたのかもしれない」と思ったことを、Rさんは明かしてくれた。これによく似た話は、永沢の短編小説『共犯者』でも書かれている。
第4章 永沢光雄のお酒列伝
永沢がアルコール中毒だったことは紹介してきた。いつから飲み始めたのかは定かではないが、高校生のころから友人宅にウイスキーの瓶を持参し、大学生で立派なアル中になり、47歳で死ぬ前日まで飲み続けていたというのだから、まさに酒とともに歩んだ人生だった。そんな永沢の、酒にまつわるエピソードをいくつか書く。
まず、酒を飲むことに対する執念のすごさ。大学時代、三枝氏といつものように飲みに行こうとした永沢だったが、お金がなかった。そこで、当時の恋人のRさんに頼み込み、彼女が小銭を貯金していたボトルからお金を取り出し、両替して酒代に充てた。あまりにも申し訳なくて、三枝氏はRさんの顔を見られなかったが、永沢は酒が飲める喜びからか、満面の笑顔だったという。
調子に乗り過ぎて逆襲されたこともあった。飲みに行って金が足りなくなり、Rさんを電話で呼び出したところ、支払いを立て替えてもらう代わりに、思い切りビンタをされたことがあったそうだ。
似たようなことは社会人になってもあった。白夜書房に勤めていたころ、同僚の松沢氏と飲みに行こうとしたが、やはり手持ちがない。そこで永沢は、松沢氏の3ヶ月分の定期を解約させ、意気揚々と飲み屋へ向かったのだった。
飲みだすと全裸になることもしばしばだったという。あるカラオケスナックでは、全裸になって歌を歌い、おかまのママに性器を割りばしでつままれ「くさい!」と笑われた。
仲間たちと飲んだ帰りに、路上で急に全裸になった。さすがに逮捕されるかもしれないと、仲間たちがたまたま持っていたビニールテープで、性器をぐるぐる巻きにして隠し、事なき(?)を得た。
新宿で朝まで飲んだときは、全裸でリュックを背負って街を闊歩。途中、道端でシンナーを吸っていた若者を、その格好で注意したという。さらにタクシーに乗って、参拝客がいる明治神宮に行くと、外国人の女の子に指を指された。母親が慌てて「ドント・タッチ・イット!」とたしなめたという。
全裸で大騒ぎをすることもあれば、静かなままのときもある。行きつけのバーで、こっそり裸になり、何事もなかったように飲み続けていたことも。永沢は笑わせようとしたらしいのだが、いつものことなのでママや常連は特に反応しなかった。この脱ぎ癖のためか、そのほかの理由か、永沢がかつて務めていた白夜書房の近くのスナックには、「白夜書房お断り」という貼り紙があったのだと、まことしやかに言い伝えられている。
飲みをただの飲みで終わらせず、イベントごとにしたがるのも永沢なのかもしれない。あるとき、秩父の山奥に男10人ほどでキャンプにいった。当然、酒盛りになり、酔っぱらって相撲を取り始め、みんな泥だらけに。酒は飲みきれないほど用意してあったが、永沢は「これじゃ足りねー! 買いに行こう」と言い始めた。同じくキャンプに来ていた、見ず知らずの人に車を借り、泥酔した永沢たちは猛スピードで山を下って酒屋へ。あまりにも酔っぱらっていたため、店番の女性に怒られながら酒を買い、何とかもとの場所まで戻ったという。キャンプからの帰りの電車で、泥酔した永沢が床で寝ていると、おばあさんに「最近の若い者は!」と痰を引っかけられたのだそう。
死にかけたエピソードもある。バーで泥酔し、白夜書房時代の後輩に担がれて帰ろうとした。だが、同じく酔っぱらっていた後輩が手を放してしまい、永沢は後頭部から地面に落ち、動かなくなった。すぐに救急車が呼ばれ、搬送されたのだが、翌日彼は、その後輩に押されて車椅子ですいすいと病院内を走り、楽しそうに探索をしていたという。
かと思えば、飲み屋の人々から信頼されていることが伺えるエピソードもある。新宿二丁目にはレズバーがあり、基本的に男性は入店できないのだが、永沢は入れるのだ。二丁目でいつも飲み歩き、素性を知られているため、お店側は安心感があるのだろう。ただそれ以上に、永沢の人柄や振る舞い方、他者への向き合い方が大きいのかもしれない。AV女優たちへのインタビューではないが、人がつい心を開きたくなる、永沢の持って生まれた何かは、飲み屋でも自然に表れ、歓迎されていたのだ。
このほかにも酒のエピソードは山ほど、それほど富士山級ほどあるのだが、とても書き切れないので割愛する。
第5章 純文学作家への憧れ
母親の愛情は、生涯にわたって永沢を縛り続けた。もうひとつ、彼が生涯縛られ続けたことがある。純文学作家として認められたい、という切望だ。永沢は幼少のころから、将来は作家になりたいと強く願っていた。29歳で白夜書房を辞めたのも、小説家になるためという理由だった。
だが無職になって時間ができ、机のうえの原稿用紙に向き合っても、筆はまったく進まない。そんなときに、編集者の松沢雅彦氏からライターの依頼を受け、後に『AV女優』がベストセラーになったのは、先に紹介した通りだ。
一躍売れっ子になった永沢は、「先生」と呼ばれるようになり、さまざまな媒体からインタビューやエッセイや書評などたくさんの執筆依頼が来る。スポーツ紙や文芸誌やアダルト誌や一般誌のほか、中学生向けの新聞や少女向け漫画誌など、永沢が寄稿していた媒体は実に幅広い。彼が通っていた新宿二丁目の焼き鳥屋は、値段が3000円、5000円、1万円の3種類で、客の懐具合を店主が見定めて、いずれかを請求していた。かつての永沢は3000円でいつも飲んでいたが、『AV女優』がヒットしてからは1万円を請求されるようになったという。
永沢の作家人生で、最も大きな事件のひとつとして、太宰治賞の受賞を逃したことは外せないだろう。太宰治賞は、出版社の筑摩書房が運営する純文学作品の賞である。永沢は2001年、この章の最終候補に残り、受賞の最有力候補と見られていたが落選した。
永沢に太宰治賞への応募を勧めたのは、筑摩書房の編集者(現顧問)・松田哲夫氏。ふたりが出会うきっかけは、松田氏がテレビ番組「王様のブランチ」で、本を紹介するコーナーに出演しており、ある回で『AV女優』を紹介したときにさかのぼる。ベストセラーとなっていた同作を松田氏も読んでおり、ぜひ番組で紹介したいとプロデューサーや司会者に提案したが、午前中に放送される若い女性向け番組ということもあって、最初は難色を示された。
だが松田氏は意地になって、「読んでもらえれば、何で僕が取り上げたいと思ったかわかるはず」「AV女優たちは番組の視聴者や出演者のタレントたちも年齢が近いし、訴えかけるものが必ずある」と説得した。すると、『AV女優』を読んだプロデューサーたちが納得し、紹介することを許されたのだった。
その後、松田氏は、永沢と仕事ができたらと思い、ビレッジセンターの中村社長に連絡して3人で会うことに。昼過ぎの新宿二丁目で中村氏と落ちあい、飲み屋が密集するビルに行くと、そこにいたのが永沢だった。
「あるお店の前に、浮浪者みたいな人が、新聞紙を引いて寝っ転がっていたんです。もぞもぞ起き上がってきて、それが永沢さんでしたね。恐縮した感じで、目をきょとんとさせていました」
それから焼き鳥屋に移動した。どんな話をしたか、松田氏はあまり記憶に残っていないそうだが、中村氏から「こいつに小説を書かせてやってくれ」と頼まれたことはよく覚えているという。永沢が小説を書くことを望んでいたように、中村氏も彼の文章のファンとして、小説を読んでみたいと切望していたのだった。
永沢と松田氏は、すぐにライター・編集者として仕事をするようになった。まずは永沢が過去に連載していた、いろいろな業態の風俗店を取材した記事を、書籍にすることにした。その本は『風俗の人たち』というタイトルで、1997年に上梓された。1999年には、やはり永沢が連載していた、さまざまなスポーツ選手へのインタビュー記事が、『強くて淋しい男たち』として書籍になった。
松田氏は、中村氏の頼み通り、永沢に小説の執筆も依頼した。筑摩書房が毎月発行しているPR誌「ちくま」での、短編小説の連載だった。念願だった小説の執筆を仕事にできて、永沢がとても喜んでいたのが印象的だったという。
「『AV女優』にも『強くて淋しい男たち』にも私小説的な部分が見えますし、やはり小説を書きたいっていう思いがあったみたいですね。実際に小説の原稿をもらったときも、なかなかいい味を出すなあと。連作をまとめたらいい本になるんじゃないか、と思っていました」(松田氏)
その言葉通り、ちくまへの連載は、永沢にとって初の小説集『すべて世は事もなし』として、2001年10月に出版されることになるのだが、「太宰治賞受賞ならず」の事件は、さかのぼること同年4月に起こった。永沢に太宰治賞への応募を勧めたのは、ほかならぬ松田氏。実は、そこに至るまでには伏線があった。
前年、選考委員の作家の故・吉村昭氏のもとへ、松田氏が社内選考を終えた太宰治賞の最終候補作を届けると、「この程度のものしかないのか」と厳しく批判された。一方で吉村氏は、ちくまを読んで、「永沢光雄って人はなかなかいいものを書くね」と評価していたという。その永沢が応募すれば、受賞する可能性が高いのでは、と松田氏は考えたのだった。
永沢は小説のなかで、松田氏との当時のやり取りを次のように書いている。小説ではあるが、事実をベースにしていると思われる。
或る出版社の編集者から飲み屋で、その社が主催する文学賞に応募してみないかと言われました(中略)選考委員でもある〇〇先生が今までのあなたの作品をかなり気に入ってるらしいんです、だからどうか安心して書いて下さい。どういう意味なのか瞬間には理解できませんでした。えーと、えっ、それっと出来レースということですか?
まだ一字も書いていないのに? いえいえ、さすがに編集者は苦笑してかぶりを振りました。けど、かなり優位であるのは確かだと思います(中略)いくら〇〇先生があなたに好意を持っていても、僕が応援していても、それに見合う作品を書いてくれなければ受賞は無理なんですよ。要は結局、実力勝負なんです。
その編集者こと松田氏は、個人として応援していることを表明し、さらに「僕はあなたに賞を取ってもらい、これからのあなたの作家としてのジャンピングボードにして欲しいんです」と永沢を鼓舞した、と続いている。
すっかりその気になった永沢は、3ヶ月ほどで約100枚の中編を書き上げた。それが、エロ本のライターをしている男が主人公の自伝的小説『グッドモーニング・トーキョー』だった。彼と、恵さんがモデルの妻と、余命3ヶ月の義母との交流ややり取りが、切なくも温かい筆で描かれている。「永沢さんの作品のなかでとてもよかった」と松田氏が太鼓判を押すほどの力作で、社内選考に当たった編集者たちの同意も得て、同作は最終候補作に残った。
松田氏からその連絡を受けたときの言葉を、永沢は小説内でこのように書いている。
「おめでとうございます。まあ予想通りですが、社内での最終選考に残りました。ここまでくれば、少なくとも僕としては受賞確実だと思います」
最終選考では、選考委員の文芸評論家の故・加藤典洋氏が絶賛し、「受賞作はこれしかない」と強く推薦。同じく選考委員の作家・柴田翔氏は、厳しい感想を交えつつも、基本的には評価するとした。
だが、ただひとり大反対したのが、永沢の小説をほめていたはずの吉村昭氏だった。理由は、作品の冒頭に、SMの風俗店での食糞のシーンがあったこと。当時を思い返したのか、松田氏は無念の表情で話す。
「小説は何を書いてもいいとは思うけれど、生理的嫌悪感を覚えるような描写は読みたくない。そういう作品を受賞作にするわけにはいかない。吉村さんは非常にはっきりとした意見で、そう言われました。ちくまに連載していた永沢さんの作品も、同じようなものじゃないですか? と思いましたが、口に出すわけにもいかず、非常に辛かったですね」
そして、吉村昭氏の鶴の一声で、『グッドモーニング・トーキョー』は受賞を逃すこととなった。永沢は、受賞は確実という思いで、結果の連絡を待っている。松田氏が重い気持ちで電話をし、「残念ながら……」と伝えると、しばしの沈黙の後、小さく「わかりました」とだけ返ってきたという。
確かに松田氏も、食糞のシーンがそこまで重要だとも、文学的なインパクトがあるとも思えなかった。その箇所を削っても、十分にいい作品だという評価は変わらない。吉村氏に頼み込むなりして、何とか永沢に賞を取らせたほうがよかったのでは、と今でも思うのだそう。
「この(食糞の)部分を外させますから、受賞作にしてもらえませんか? と吉村さんに根回しや土下座をして、無理やりでも通しちゃった方が良かったかもしれない、という気持ちはあります。けど永沢さんにとっては、作品そのものを否定された、それを捻じ曲げて押し通したという、二重の傷になってしまう。そう考えたら、落ちたのも名誉のうちだと考えるしかないのかなあと」
もちろん、永沢に食糞のシーンを削ってほしいとお願いしても、応じなかっただろうと松田氏。高校時代、自分が 正しいと思ったことであれば、誰であれ頭を下げなかったというエピソードからうかがえるように、実際にその通りだっただろう。
けれど、文学への憧れが非常に強い書き手である。太宰治賞という勲章を持って、仙台に錦を飾りたかったんじゃなかったかな、とも松田氏は回想する。いずれにせよ、永沢の太宰治賞へのチャレンジは、たった1シーンの描写が原因で敗れ去ったのだった。
太宰治は、芥川賞の選考委員だった川端康成に、「自分に賞をください」と手紙を送ったことがあった。「愛の冷やしパンツ」のメンバーだった三枝氏は大学時代、その手紙が掲載された雑誌を永沢とふたりで読み、「情けねぇよな」と笑っていたという。その十数年後、その太宰の名を冠した賞を永沢が取り損ねたと、本人から連絡を受けたときの心境を振り返る。
「電話がかかってきて、『大人の世界は厳しいんだよ』って言ってました。作品が認められないことに対する恨み言が太宰とほぼシンクロしてたし、それくらい応募作にも自信があったんじゃないかな。永沢は、賞は欲しかったと思う。評価されることで、ステップアップできるチャンスだったと考えていたと思うよ」
ちなみに、出来レースはなかったと永沢、松田氏ともに語っているが、永沢が周囲に「賞をもらえるから応募する」「受賞できるんだって」と話していたという証言が複数ある。永沢を応援したい、受賞してほしい、という松田氏の強い思いを言葉で受け止めたときに、もしかしたら永沢は「賞をもらえる」と脳内変換してしまったのだろうか。それとも実際、松田氏がそのような言葉をかけていたのだろうか。今となってはわからないが、永沢にとっては、かけたハシゴを外された心境になってしまったことは事実のようだ。
落選が決まった夜、行きつけだった新宿二丁目のバー「サイドビー」に現れた永沢は、これまでにないほど泥酔したのだと、ママの恵子さんは思い返す。
「僕は賞なんて欲しくありません、って言ってたけど、見事に落っこちたわけよ。そのときは大変だった、もう。一言も口きかないで、がぶがぶ飲むもんだから、『そんな飲み方ダメ、何か食べないとお酒つくらないからね』って。(妻の)メグちゃんも、手に負えなくて先に帰っちゃって、えー、って感じで」
読書家でもある恵子さんは、『AV女優』はもちろん読んでおり、高く評価していた。永沢も恵子さんの批評眼を信頼しており、「感想を聞かせてほしい」と、小説を連載していたちくまを持ってきたことが何度もあった。だが、小説が面白いと思ったことは一度もなかったと恵子さんは切り捨てる。
「インタビュアーとしては優秀だと思うけど、小説ははっきり言ってつまらん。私小説しか書けないから、物語を作るのがへたくそで、面白いと思ったものはないって言った。永沢さんはたくさん本を読んでるし、頭が良過ぎるから、これまで読んだものがごっちゃになって、ゼロから生み出すのは難しかったと思うね」
太宰治賞の応募作『グッドモーニング・トーキョー』も事前に読んでいたが、「これじゃ無理でしょう。絶対取れないな」とひそかに思っていたことを恵子さんは明かした。
僕も、同作を読んだ正直な感想を書いておきたい。同作はいかにも永沢らしい私小説だった。だが、彼が発表しているほかの短編が中編の分量になっただけで、さして目新しさのない内容だと感じた。そして、最大の欠点として、ラストにあるどんでん返しが起こるのだが、それがここまで紡いできた物語を台無しにしてしまっているように思えた。ストーリーテラーとしての工夫なのかもしれないが、人情ドラマが突如、別の物語に変貌することで、温かさや切なさも消えてしまっていた。本作に関しては、食糞の描写がどうこうよりも、ひとつの作品として受賞できなかったのではと、小説に関しては素人ながら僕は感じた。
永沢は生涯で短編小説集を3冊出している。『すべて世は事もなし』のほか、『BURST』などで連載されていた小説をまとめた『恋って苦しいんだよね』『愛は死ぬ』だ。もちろん、非常に面白い作品もあるが、『AV女優』や『強くて淋しい男たち』の域へ到達しているかというと、そうではないと僕は思う。けなしているわけではまったくない。この評価は、インタビューをもとにした永沢の記事のレベルがいかに高いか、ということの裏返しにほかならない。
『AV女優』の編集者の向井氏も、永沢の小説を「面白く読める」としつつも、それ以上でも以下でもないと評価 している。
「彼の小説に関心はなかったです。そんなに深い感動を感じたことはないし、もともと永沢さんは小説には向かないと思っていました。なのにあるとき、『僕は芥川賞タイプだ』みたいなことを言い出したことがあって、自分の本当の良いところがわからなくなっているな、という気はしました」
だがそれでも、永沢に原稿依頼をする出版社はたくさんあった。『AV女優』の著者であり、太宰治賞の最終候補に残った彼への期待は大きかったのだろう。編集者たちは、永沢がサイドビーを根城にしていることを知っており、「永沢さんいますか?」と店によく電話が来た。そして、「先生、期限は設けませんので、長編小説を書いてください」と依頼が相次いだという。そのことも永沢のプレッシャーになっていたのでは、と恵子さん。
「みんな永沢に期待しすぎてたよね。本人に書きたい気持ちはあっても、書けないよって私は思ってたから。ものすごいプレッシャーだったと思う。もともと鬱だし、文章も思うように書けないし。飲みに来たら明るくしてたけど、生きてるのが辛かったかもしれない」
『BURST』の編集長だったピスケンこと曽根賢氏は、同誌や系列誌で永沢の連載小説の担当をしていた。曽根氏は2000年に自伝的短編小説集『バーストデイズ』が野間文芸賞候補になった作家でもあり、アルコール中毒でもあった。
永沢と共通点が多い曽根氏は、インタビュアーではなく、作家でありたいという彼の強い意志を常に感じていたという。さらに、永沢が理想とする創作に向き合う様を、「苦しんでいた」と断言する。
「本当に苦しんでたな。新しいスタイルを探すというか、より高度なものを書こうとしたら、禁酒するしかない。『酒止めて書いたら?』って、何度もここ(喉元)まで出たことあるんだよ。俺もすげえ飲んでて、40代をまるまる潰したからわかるんだけど。誰も言わないから、俺しかいねえのかと思ってたけど、言わなかった。言っちゃいけないことだなと思ったし、永沢さんも『そんなのお前に言われなくたってわかってる』って思っただろうし」
曽根氏はあるとき、永沢からアルゼンチンの作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編集を勧められたことがあった。ボルヘスは、現実と非現実が交錯するような、幻想的な作風で知られている。おそらく永沢も、私小説ではなく、あのような小説を書きたいと思っていたはず、と曽根氏は続ける。
私小説は、小説の手法としてある意味では安易であるため、できれば避けたい。だが、自分の経験をもとにしないと、書くことにリアリティを感じられない書き手のため、私小説を選ばざるを得なかったのでは、と分析する。
「永沢さんって、文学に関しては、すごく高いところを目指していたはずなんだよ。私小説っていう形は、ダサいっていうかさ、本当は取りたくなかったと思う。俺もそうで、すごく苦しんだからよくわかる。一人称から三人称に飛ぶのは、俺たちみたいな書き手は難しいんだよな」
曽根氏は『バーストデイズ』が野間文芸賞候補になり、純文学の世界で一躍注目を浴びるようになった。次の芥川賞は彼が取るのでは、という論評もあった。だがそれを機に、新しい文体やスタイルを追求するようになり、重圧もあって、一気に書けなくなったという。長編を書いてほしい、という編集者からの要望も、筆が進まない要因になった。永沢も、まったく同じ状況で悩んでいたと、曽根氏は自身に重ねる。
「永沢さんは、短編作家だよね。長編を書くには、ストーリーをつくらないといけないからさ。でも、それが嫌いな人だったと思う。リアリティがなくなっちゃうから。だから、最後は私小説に落ち着いたってことかな」
永沢の初の小説集『すべて世は事もなし』では、私小説風の作品もありつつ、新しい創作への意欲や工夫が見える作品も多かった、と曽根氏。逆に、その思惑が表れすぎているため、あざとさとして映ることもあったという。普通の物語になることを嫌って取り入れた仕掛けやひねりが、必要以上に目立ってしまっていたのだ。
だが、永沢が2002年7月に咽頭がんの手術をしてからは、『BURST』で連載していた小説の作風が良い意味で変わったと続ける。
「ぶっちゃけて言えば、永沢さんの小説を『お!』と思ったのが、手術後なんだよね。あ、これは違うって、すぐわかったの。一気に地味な私小説にいったんだけど、すっごいよくなったんだよ。俺も体が悪いからわかるんだけど、体力がなくなったとき、だんだん開き直って、何かが変わるんだよな。それでもうあんまりひねらずに、私小説にしちゃったんじゃないかな。私小説であってもいろいろあるからさ。どう変わったのか聞かれると困っちゃうんだけど、永沢さんらしいスタイルができたねって感じ」
曽根氏だけでなく、担当編集も作風の変化に気づき、「永沢さんの原稿すごかったね!」と話していたほどだった。後日、曽根氏がそのことを本人に伝えると、「あ、そう」とそっけない返事だったが、永沢は喜んでいた様子だったという。私小説というスタイルだけに、本人が納得していたかどうかはわからないが、皮肉なことに病気で体力を失ったことで、作品はシンプルな味わいを醸し出すようになったのだった。
純文学の最先端や最高峰を常に見据え、悩み、病み、苦しみ続けた永沢は、本物の小説家だったと曽根氏は言う。
「やっぱ芸術至上主義っていうか。政治とか公共ボランティアとかは下々がやることで、作家はそういう野暮なことはなし。僕らはのんべんだらりと酒ばっか飲んで、ときたま書いて。そういう点では、人としてものすごいヤバいんだよ。自分が一番うえのステージにいるんだもん。全身全霊、作家っていうことに命かけて、それ以外は一切を削ぎ取って。それしか考えてなかった人だね」
まあハードコアな人だったよ、と曽根氏は目を細めた。
最終章 47歳での死
小説はともかく、ライターとしての永沢の評価は高かった。記事の執筆依頼は絶えず、AERAなど書き手からすると憧れの媒体からも熱烈な誘いがあった。長編小説の打診も変わらず続いた。そんな2002年7月、43歳のとき、永沢は咽頭癌にかかった。その数日後に手術で声帯を摘出し、声を失ってしまったのだ。
永沢は、ものすごく声がいい。『AV女優』の解説で、大月隆寛氏が冒頭に「声のいい男である。低くて太い。心地良い」と書いているほどである。サイドビーの恵子ママは、「本当にアナウンサーになれるくらいの声」とほめ、声フェチだという曽根氏も初対面で永沢の声を聞いて、その場で一緒に仕事をすることを決めたそうだ。ある歌手は、永沢とよくカラオケスナックに行っていたそうで、「俺たちが歌うと、ふたりとも声がいいものだから、よくモテたよ」と笑いながら回想した。
僕は、NHKのテレビ番組に出演した永沢の映像を見て、その声を初めて聞いた。確かに、低くて太く、心地よい声だった。言葉数は多くなく、ゆっくりボソボソとした喋り方がまた声に合っている。彼の声もまた、インタビュアーの名手と呼ばれていた永沢の、話を引き出す強力な武器になっていたのではと感じた。その声を、永沢は失ったのだ。
がんが発覚する直前、のどや体調に起きていた異変を、彼はエッセイのなかで綴っている。
私は頻繁に近所の耳鼻科医院に通った。なにせ呼吸がままならないのだ。深夜何度ものどをかきむしって目を覚ましたことか。冬だというのにパジャマがびっしょりと濡れており、暗闇の中で妻が同情をとっくに超えて迷惑な色を目に当てて私を見ていた。ゼーゼーとした声でごめん。私は妻にいい隣の部屋に布団を敷いて横たわった。(中略)初めて連載していた小説を落とした。落とした。書けなかったのである。とてもとても机に向かえる私ではなかった。ベッドの上であらゆる体の穴から液体を出ししかし、息だけはできず、王先生(※行きつけの診療所)のところへ行った。
すると診療所で紹介状を渡され、大学病院でガンと診察されたのだ。レントゲンを撮ったところ、喉には白いキノコのような影がびっしりと張り付いていたという。ステージ3だった。抗がん剤が効かなかったため、12時間に及ぶ手術で声帯を除去し、呼吸を確保するために喉に穴が開けられた。そして両の鎖骨の中間ほどに、永沢いわく「グロテスクな肉穴がブラックホールのように」存在するようになったのだった。
声が出ないため、以降はおもちゃのホワイトボードを首にかけて、水性ペンで書いて筆談をするのが、彼のコミュニケーション方法となった。専用の機器を喉に当てることで、振動で声を出す方法も医師に勧められたが、自分のものとはかけ離れた人工的な声だったため断念した。
声を失ったこととの因果関係は不明だが、その直前に永沢は、NHKのロケで岡山県津山に行っている。僕が彼の声を初めて聞くことになったテレビ番組だ。
なぜ津山だったのか。それは永沢の強い希望で、1938年に都井睦雄という22歳の青年が、村人たち30人を殺した末に山中で自害した、日本の犯罪史に残る「津山30人殺し」の取材のためであった。
同番組は、作家が好きな場所に取材旅行に行き、その土地で題材を見つけ、原稿用紙10枚以内にまとめるというもの。その旅の様子を追ったドキュメンタリーだった。僕はDVDを入手して見たのだが、このロケは永沢の半生で、間違いなく大きなひとつの転機になっていると感じた。
番組ディレクターの坂本康子氏は、永沢と一緒に津山まで行き、彼の行動の一部始終を追った方だ。彼女への直接の取材はかなわなかったが、収録を振り返った手記を送っていただいたので、それをもとに当時の詳細を紹介していく。
どの場所へロケに行くか、打ち合わせをした新宿二丁目の酒場で、永沢は坂本氏に「津山30人殺しって知ってる?」と聞いた。もしやそこに行きたいと言い出すのではないだろうか、と坂本氏が控えめにうなずくと、永沢は目を輝かせて「そうそこそこ!」と即答したという。
「本当に行きたくなかった」と坂本氏は振り返っている。そのような凄惨な事件が起きた場所に、カメラを持ったクルーが押しかけたら、地元の人たちはどのような感情を抱くだろうか。事件が起きたのは1938年で、まだ遺族や関係者は存命の可能性が大いにある。町自体があのことに触れてほしくない可能性も十分にあるのに、カメラの存在が傷口を広げてしまう可能性があるからだ。
坂本氏が、永沢の出身地である仙台などを提案すると、彼も「テレビだしなぁ」と諦めてくれた様子だった。だが翌日、坂本氏のもとへ、永沢からFAXが届く。そこにはただ一言、こう書かれていた。
「やはり津山へ行きませんか。これから生きるために」
番組は、津山へ向かう列車内の映像で始まる。缶ビールを片手に、永沢がなぜあの場所へ行きたいのかを独白する。だが、明確な理由は自分でもわからないのだという。永沢は10代の初めのころから、殺人事件に関する本をたくさん読んでいた。小説よりも、実際に起きた事件の本をむさぼるように読んでおり、津山事件とその実行者である都井睦雄を知った。
その日から、彼は永沢の頭に棲みつくようになったのだという。永沢は番組内でこう話している。
何でこれほどまでひとつの事件を忘れることができずに、いつか行きたいと思っていたのかな、というのを自分なりに、40過ぎだし、けじめをつけて前を向いていこうと。何を大げさなことを言ってるかと思うかもしれないが、それほどまでに僕にとってその場所に立つことは僕のなかで、多分、何らかの句点であり読点になる。事件についての資料とか本を読めば読むほど、何かが分からなくなってくるんです。土地に立って初めて自分のなかで、決着がつくんじゃないかなと。
津山へ行きたい理由は自分でもわからない、としているが、偶然手に取った幸田文の『崩れ』という本が、同地へ駆り立てられたヒントになっていると続く。同書は、山の崩落に引かれた著者が、全国の崩落跡を巡る。そのうちに、崩れは「拒みようもなく屈服を強いる強大な暴力」、すなわち強さだと受け取っていたのが、「地質的な弱さ」だと学ぶのだった。永沢はここに殺人を重ねる。人殺しも強さではなく、弱さが原因で起こるのでは。その規模が大きければ大きいほど、それに比した弱さがあるのでは、と。
永沢は幼少期の自分を思い返す。そして、自分がいつか崩れる人間、すなわち事件を起こしてしまうような人間だと自覚し、抑止のために殺人事件の本を読み漁っていたと気づき、津山の地へ足を踏み入れたのだ。
事件が起こった村の雰囲気は、未だにそれを超える経験がないほど異様だったと、坂本氏は振り返る。
「うまく伝わるかどうかは分からないが『現場がうねっている』感じ。何か大きなものに引き寄せられている、という感じだった。それは『そのこと』をいつも感じ取ろうとする私だけでなく、あそこにいるみんながそう感じていた。なんだろう、何を見ろ、何を知れと言っているのか。それは誰だ……? 全ての現場が何か一本の見えない何かに引っ張られていく、そんな感じだった」
地元の郷土史家や住職に事件のことを聞くが、反応は芳しくない。住職に至っては、「60年も経って、なぜこういうものを起こすか不思議」「寝た子はええ子なので寝かしときなさいというのが今の意見」と、厳しい口調で永沢に詰め寄る。それでも永沢は、自分がなぜここに来ているのかわからないが、土地に立って風景を見れば、僕のなかに残っていた都井睦雄と別れられるのではないか、と胸の内を正直に打ち明けるのだった。
その後、居酒屋の酔客や、畑仕事をしている老婆などに話を聞くうちに、少しずつ事件の背景がわかってくる。都井睦雄は非常に利口でハンサムだったが、結核だったため村人たちから忌み嫌われていた。当時、結核は伝染病として恐れられ、罹患した人や家族は家の周りに縄を張られ、外出を禁止されていたほどだった。事件後、都井睦雄の母は、「むっちゃんは悪くない、悪口を言った人間だけを殺していった」と息子をかばい続けていたという。
永沢も、小学校3年~中学校3年まで学級委員を務め、勉強もできた。見た目も都井睦雄の少年時代にどこか似ていた。だからこそこの事件に関心を持ち、自分が彼になっていた可能性もあったかもしれない、と想像を巡らせる。
僕がここにいて、結核になっていたら、僕が都井睦雄になってたのかもしれない。なるほどね。だからか。それですごく、10歳のときからやべーぞって。そういうことやっちゃいかんぞって、この事件は僕に教えてくれて。おかげ様で43歳まで人を殺さずに生きてこられた。
そして永沢は、都井睦雄が村人たちを殺害した後に自害した場所を探して山に登る。明らかに運動不足で小太りの中年が、生い茂る灌木をかき分けて走る。ひたすら、走る。やがて、木洩れ日が差す先に、大きな丸い石があった。永沢は、ここが都井睦雄の自害した場所だと確信して、石の隣に座り込むのだった。
下山後、永沢は涙を流しながら、坂本氏に送ったFAXは間違いではなかった、と振り返る。津山で見た風景が自分の原点になるんじゃないかな、とほほ笑み、「30数年間、私の中に棲み続けていた彼が、姿を消した」というセリフで番組は終わる。これが放映されたシーンだ。
だがその裏で、恐ろしい事態が起こっていたと坂本氏。永沢を先に下山させて彼女たちは山で撮影を続け、下りたときには彼の姿が見えなかった。二手で探してもいない。嫌な予感がしたとき、遠くから永沢がよぼよぼと歩いてきて、「蟻んこを見てた」と一言。心配してた分、坂本氏は激怒したが、永沢の尋常ではない様子を見て固まったという。
「見ると、ガタガタと全身の震えが止まらないのだ。ひぇ~! まじでやばい!!! 勘弁してくれ~神様仏様むっちゃん!! 『むっちゃんの墓を暴いたからバチが当たった』彼はそう言って笑った」
そして津山から帰った直後、前述した異変が永沢の体に起こり、病院に行ったところ、咽頭がんであることがわかったのだ。
がんだと診断された後、永沢と恵さんは、大騒ぎしながらサイドビーにやって来た。恵子ママや常連たちは、「津山で何か持って帰ってきちゃったんじゃないの!」とざわついていたという。何かとは、心霊的な呪いやたたりのことである。
だが編集者の曽根賢氏は、違う意味での危うさを感じながら、番組を視聴していたことを明かす。
「山のうえのほうで、(都井睦雄が)自殺したところに石があって。あれ見て、あ、永沢さん、やばいところに足を踏み入れちゃったなと思って。幽霊がとりつくとかさ、そういうことじゃないんだよ。作家は行っちゃダメなんだよ。作家って、死に近い場所まで行かないといけないって気持ちがあるからさ、感じたことが増幅して、いろんなものをもらっちゃうから」
曽根氏にも似たような経験があるという。編集長を務めていた『BURST』は、ドラッグ、人体改造、死体写真、性愛、アウトローなど、刺激的な誌面でアングラカルチャー界にムーヴメントを起こした雑誌だ。その中心にいた曽根氏は、取材する人や場所に対し、「これ以上踏み込んだら危険だ」という感覚が自然と研ぎ澄まされていたという。実際、一線を踏み越えてしまったときは、致命傷を負うほどの暴力に見舞われるなど、命の危険にさらされた。そういった経験や、作家の過敏すぎる感性が何を捉えてしまうのか、熟知している曽根氏の言葉には説得力がある。
永沢の恋人だったRさんも、番組を見ながら、曽根氏と同じように感じていた。まさに山中で例の石を見つけて座り込む場面が、かねてから死へ向かい続けていた彼のベクトルが、必ず通るであろう通過点として、違和感なく映ったという。
「彼が向かっていた方向(死)が、こんなにも修正がきかないものなんだ、という証拠が並んでいただけだなと。表面上の意識ではない何か、魂の根底に持っていたものが、まっすぐ彼を引っ張っていたのでしょうね。それじゃあ、私の手には負えなかったなと思いました」
永沢は「生きていくため」に、津山を訪れた。だが彼の繊細な感性が、あの地に立ち込めている――いや、もしかしたら何もないのかもしれないが、彼の感性によって増幅した何かをとらえ、自分のなかに取り込んだ。その「何か」は心や神経にまとわりつき、結果的に身体に悪影響が及んだ。ばかばかしい妄想にすぎないかもしれないが、決してありえないことではないようにも思える。
永沢が事件のあった山で何を見たか、何を感じたのか知りたくて、僕は2020年に津山へ行った。津山駅でレンタカーを借り、1時間弱で事件現場の周辺へたどり着いた。 民家が立ち並び、人が住んでいるのだろうが、不思議と気配をまったく感じなかった。郵便配達のバイクが通った以外、誰も見かけなかった。どの家もカーテンや雨戸が閉まっており、なかを見ることはできなかった。確かに、村全体に、普通でない雰囲気を感じた。
やがて、NHKにも登場した、例の山が見えてきた。僕は車を止め、山へ入っていった。灌木をかき分け、道なき道をひたすら登る。小雨が降り始め、スニーカーやズボンがたちまち泥だらけになった。20分ほど登っただろうか、やがて大きな石が見えてきた。戸井睦夫が自害した現場として、永沢の旅のゴールとして映像に映っていたあの石によく似ていた。これが、永沢が泣きながら愛でた石だろうか。もしかしたら、少し形や色が違っていたかもしれないが、僕はこの石がそれだと思うことにした。だが、石に触れても、何の感情も浮かばなかった。

山を下り、近くにある戸井睦夫の墓へ移動する。あのような事件を起こしたことから、きちんとした墓石は立てられず、丸い石を置いただけの墓だった。誰かが備えた缶ビールやお茶が置かれていた。やはり、僕は何の感情もなかった。後で何かに使うかもしれないと、撮影をして終わりだった。僕にとってここに来たことは、ちょっとしたドライブとハイキングに過ぎず、心身ともに何の変化もなかった(もちろん、都井睦雄やこの事件に思い入れが無いので、当然といえば当然だが)。だが、永沢は違ったのだ。
声を失った永沢の日々は、どう変わったのか。2005年に上梓した『声をなくして』というエッセイに詳しく書かれている。
喉に開いた穴を湿らせるため、ネブライザーという器具で1日3回、1回につき5分間ほど蒸気を当てるのが日課になった。腸の一部を喉へ移植したため、腸液が常に鼻から垂れてくるので、丸めた綿を鼻に詰めている。
その移植が原因で腸閉塞が起こった。喉の穴は気管と直結しており、湯が入ると大変な苦しさになるため、風呂嫌いになった。あとは1日に20種類近くの薬を焼酎で流し込み、ダラダラと酒を飲みながらテレビを眺める。そんな日常を送っていたそうだ。
同書のもととなるエッセイや書評の執筆は行っていたが、声が出なくなってしまったため、筆談で行った1件を除いてインタビューの仕事はしていなかった。長編小説を書いてほしいと依頼されていた編集者たちからも、徐々に連絡は少なくなっていった。代わって、病院通いでは非常に多忙になっていたことを、永沢はこう書いている。
今、自分の前のカレンダーはただただ、私を落ち込ませるものであった。「〇日、東京医大、精神科」「〇日、東京医大、耳鼻科」「〇日、東京医大、外科」「〇日、東京医大、肝臓内科」「〇日、東京医大、精神科」……っきり。連日のようにがんの手術をしてもらった大学病院に通え、と、カレンダーは私に銘じているのである。
闘病中で弱っている永沢のもとへ、友人や知人たちの訃報が届く。白夜書房の後輩、新宿二丁目のゲイバーの経営者、かつて取材をしたAV女優……さらに、先に死んでいった仲間や友人たちのことを回想し、永沢は鬱に襲われる。マンションの11階のベランダに、ふらりと歩みを進めると、恵さんが窓の前に飛んできた。以下は永沢の文章だ。
「駄目だよ! 死んじゃ! ミッちゃんが自殺なんかしちゃったら、せっかくガンから助けてくれた渡嘉敷先生が、悲しむよ。くやしく思うよ! 手術に、12時間もかかったんだからね。先生は必死にミッちゃんを生かしてくれたんだからね!」
妻は、妻自身の気持ちも、私の両親、弟、私の友人のことも言わなかった、ただ、渡嘉敷医師のことのみを必死な形相で訴えた。
その声を聞き、その顔を見、私に突然襲い掛かった鬱が、ほんの少し、輪郭を薄ぼんやりとさせていった。
『声をなくして』の最後では、「少し長いあとがき」として、約30ページの文章が綴られている。永沢が初めて死の概念を知った幼少期の回想や、「雫である。人の一生なんて、南天の葉の上の朝露のように、きらきらと輝きながらも、あっという間に消え去るものだ。それで、良しなのである」という死生観、自殺したAV女優の友人だった女性の言葉。
最後は、永沢の涙声が聞こえてくるような、心からの叫びによって締めくくられている。
私は、言う。ちゃんと言う!
みんな、死ぬな!
友へ、仲間へ、家族へ。そして、自分自身へも向けられているのだろうか。
同書は『AV女優』以来、永沢の著書で話題になった1冊で、映画化の話も持ち上がったほどだった。闘病記でありつつ、明るくユーモラスな文章もそうだが、何よりも他者への愛情が随所に表れている。仕事仲間、飲み仲間、友人、取材をした人など、彼ら彼女らへの永沢からの手紙とも取れるメッセージの数々は、個人的なそれであるはずなのに、なぜか第三者の読者も物語に巻き込まれ、胸に響く。 永沢の筆力はもちろん、人間性も存分に発揮されている1冊である。
だが、同書を「あんな最低な本はない」と言い切る人もいる。『AV女優』を刊行したビレッジセンターの社長・中村氏だ。
「やっぱり良くないよ、そういうのは。ハンディキャップを売り物にするなという気持ちと、お前さ、小説書くんじゃなかったの? と思ったわけ。インタビュー集まだやんの? って。その気持ちは本当にあったよね。俺、それが一番悔しいわ。本気で小説を書けよって。光雄の一番嫌な本だと思う」
永沢の文章を愛し、小説を書いてほしい、と応援し続けていた中村氏だけに、彼がエッセイやインタビュー集を出すことに、誰よりも落胆や悔しさを感じていたことが伺える。そして、永沢が小説を書かなかった原因として、やはり酒を挙げる。
「一番残念なのは、やっぱり酒ですよ。小説書きたいんだったら我慢しなきゃ。朝スポーツ新聞買って、毎日家でナイター観て酒飲んでるんだぜ。止めさせろって(妻の)メグに言ったんだけど、『それができたらとっくに止めさせてますよ』って。それも酷い話だよなと。メグはさ、つまみをつくってるわけ。何でこんなことしてるんだ? それって生産的か? ひとつ好きなことを我慢すれば見方も変わるじゃん。でも、光雄はそういうのおかしかったよな。堕落するのがカッコいいみたいな」
永沢はがんの手術をした後も、変わらず連続飲酒を続けていた。その周囲には、中村氏や曽根氏のように、酒を止めて小説を書いてほしい、と切望する人たちが常にいた。ふたりのように明言しなくても、同じ思いでいた人はたくさんいたはずである。友人として体調を気遣っていたのではまったくない。永沢自身が文学に憧れ、小説家として大成したいと望んでいることを、よく知っていたからだ。
『声をなくして』では、永沢が見た夢の話や、南天の葉の上に雫が乗っている場面など、明らかに小説的・文学的な描写が散見する。そういったところも、永沢が小説を書くことを待ち望んでいる人々には、苦々しく映ったのかもしれない。同書は、名著とされつつも、関係者の間で賛否を読んだ1冊となった。
一方で、『声をなくして』から新たな縁も生まれた。同書を読み、永沢にインタビューをしたことをきっかけに、彼の最後の連載を担当したのが、産経新聞社の桑原聡氏だ。
インタビューで彼のマンションを訪ねた桑原氏は、昼にもかかわらずいきなり焼酎を振舞われるという、永沢にとっては当たり前の、ただし大多数の人にとっては驚愕の歓待を受けた。お酒好きの桑原氏は、驚きつつも相伴に預かり、4時間ほどインタビューをした。会話(永沢は筆談だが)を始めてすぐに、桑原氏はすぐに好感を持ったという。永沢が持っている強烈な美学を感じたからだった。
「本音があっても、照れによってどことなくゆがめてしまうというか。かっこいい事は絶対に言えない。そういった人柄で、美学がありましたね。人間の弱さをしっかり受け止めて、ものすごく正直に生きていた人だから、他人の弱さを認められる優しさが、彼の心の底にあったのではないでしょうか」
その後、紙面で新しい連載コラムが始まることになったとき、桑原氏は永沢に依頼した。タイトルは「生老病死」。仏教用語で、生まれること、老いること、病むこと、死ぬことの4つが、人間が逃れられない苦悩という意味の言葉である。まさに闘病中の永沢を表し、その末に死が待っているかのような、非常に不吉な言葉に思えるが、桑原氏はこのタイトルで打診をした真意を口にする。
「まさに不吉な予感を持って、です。初めてご自宅に行ったとき、恵さんとも話をして、あまり(残りの生命が)長くはないなという予感があったんですよ。だって永沢さんは起きている間、ずっと焼酎を飲んでいるわけですよね。腸閉塞を起こしやすいとか、そんな話も聞いて。本人もその時点では、そんなに長く生きる気は無いのかなと思ったんです」
この連載が永沢の遺作になる可能性もあるかもしれない、という予感もあったという。永沢も、桑原氏の意図を知ってか知らずか、何の異論もなく引き受けた。
コラムの内容は、テーマや題材は一切問わず、身辺雑記で構わないと伝えた。永沢であれば、一般人からすると当たり前の日常であっても物語を見つけ、独特の文章にできる感性があるため、十分に作品になりえるという判断だった。
余談だが、NHKで津山ロケに同行した坂本氏も、まったく同じことを話している。彼女が次のドキュメンタリー企画の題材として考えていたのも永沢で、彼であれば日常を撮影しただけでも、必ず面白いものになると確信していたのだ。
「タイトルは『作家と過ごした10日間の夏』と決めた。内容は、まさにそのまま永沢光雄と10日間を過ごすだけだ。数日間、家の中にいるかもしれない。特に何ということのないただの10日間かもしれないが、それでよかった。『きっと彼は自ら事件を起こす』そういう確信があったからだ。シーン替えとか、撮るための材料とか、仕掛けとか、そんなものを一切削ぎ落とし、ただ作家と向き合った1日間を記録する。この企画はいくら考えても永沢さんとしかできないと思う」(坂本氏)
「生老病死」の話に戻る。桑原氏の狙い通り、上がってきた原稿は期待通りのもので、手を入れることは一切無かった。同時に、どの原稿にも人を傷つけるようなことは一切書かれておらず、永沢の優しさを感じたと続ける。
特に印象的な原稿として、「母からの“贈り物”」というコラムを挙げる。食に興味が無いが、母のつくったお雑煮だけは欠かせない、という書き出しから始まる。それを食べないと、正月が訪れた気にならないほどだが、癌の手術をしたこともあって帰省できないので、冷凍のお雑煮を母に送ってもらった。元旦、妻に雑煮を解凍してもらっていると、母から電話がくる。永沢は声が出ないが、それでも受話器越しに話したいと母は言う。
「光雄。長生きするんだよ! 絶対に母さんよりも長生きするんだよ!」
聞こえてきた母の言葉に、受話器を爪で叩いて応える。電話を切り、雑煮を食べる。そして「餅が喉につかえた」と締めくくられるのだ。「ほろっとして涙が出ました」と桑原氏は振り返った。
それから月に1回ほど、桑原氏は永沢の家を訪問した。情報交換会という名目だったが、実際は昼から夜まで酒を飲みながらの雑談。筆談であっても、永沢はとにかく会話がうまく、知識も豊富なので、話は尽きなかったという。声を失って悲しいことは、という質問に、本音か冗談なのか、「落語ができなくなった」というユーモアな回答が返ってきたこともあった。音楽の話は、2人とも好きということもあり、特に盛り上がった。不思議でならないのは、と桑原氏。
「永沢さんの声を聞いたことがないけど、私の記憶のなかでは筆談じゃないのね。永沢さんがしゃべっているんですよね。何なんだろうなぁ」
ただ会話は、楽しいものだけではなかった。病に侵されている苦しさも、永沢は時折吐露した。病状が悪いとき、睡眠薬を大量に飲んで無理やり眠っていたが、飲み過ぎたせいか最近は効きが悪くなってしまった、とよくこぼしていたという。
そして、そのときは訪れた。2005年7月3日から始まった「生老病死」は、2006年11月3日に絶筆となった。2006年11月1日に永沢が死去したためだった。最後のコラムは、タイトルからして異様だった。それまで永沢は、ごく一般的なタイトルをつけていたが、最終回は「産経新聞文化部 桑原聡様」と、桑原氏へ宛てたものであることを示している。少々長いが、コラムを引用する。
(前略)ところで今日の昼過ぎ、私は猛烈な吐き気に目を覚まされました。少しでもその気持ち悪さを楽にできる格好はないかとベッドの上を転げまわったのですが、吐き気は増すばかりです。ああ、また腸閉塞かという思いが頭をよぎりましたが、今までの経験からしてそこまでは至っていないようです。胃薬を飲みましたが状況は変わりません。これはもう力ずくで眠るに限る。私は今日の夜の分の睡眠薬を口に放り込みました。
けれども、昼間であった為か、もう長年愛飲している薬の効果がなくなったのか、二時間で目を覚ましてしまいました。私は後者だと思います。
けれども、わずか二時間でも眠ったおかげか、吐き気はなくなっていました。私は安堵し、秋の夕暮れの光が入ってき始めた寝室の天井を眺めました。そして、ふと気づいたのです。
隣室に、『死』というものが潜んでいることに。しかし、私はその輪郭のはっきりとしない、ぼんやりとした『死』というものにおびえることはありませんでした。むしろ、慰められました。これで、やっと楽になれると。
私に自死をするつもりはありませんし、多分しないでしょう。けれども『死』が向こうからやってきたら甘んじて受けるつもりです。これからやりたい仕事はいろいろありますが、仕方ありません。ただ残した妻にいろいろな厄介をかけることだけに罪悪感を覚えてます。
今週末、心臓の検査で大学病院へ行きます。死の影に慰められた人間が、生きる為にだるくて重い体をひきずって病院へ行くのです。なんと滑稽なことでしょう。
だから、人間は面白いのかもしれません。
桑原さん。これからも私に限りがくるまで、なにとぞよろしくお願いいたします。
あきらかにいつもと違う原稿だったと桑原氏。しかも、締切より5日も早く送られてきており、「土曜日(10月28日)に自分の身に何かが起こりそうな気がするから、早めに送ります」と添えられていた。桑原氏はただならぬ予感を感じたという。すぐに電話をしようと思ったが、永沢は声が出せない。妻の恵さんに様子を聞くのもためらわれ、我慢した。
そして11月1日、永沢は亡くなるのだった。恵さんが朝起きたとき、永沢はすでに冷たくなっていた。トイレにでも行こうとしたのか、寝室の床に倒れた状態だったという。死因は肝機能不全だった。
最後のコラムは、あまりにも静謐である。死がすぐ隣室にまでやって来ているのに、永沢は達観したようにそれを受け止めていた。むしろ、慰められたと書いている。妻も母も残して、小説で認められたいという夢も叶えられぬまま、自分が消えてしまうというのに。
そして実際、この原稿を送った数日後に、永沢は息を引き取ってしまう。死は、永沢が感じ取ったように、すぐ隣にいて、少しずつ近づき、手を伸ばしていたのだった。
桑原氏は、「こんな状況で、よくぞここまで落ち着いて、自分の心を過不足なく表現できるなと。やっぱり、物書きとしてのすごみを感じましたよね」と語った。
永沢の通夜は2006年11月4日に、新宿二丁目の寺で行われた。仕事仲間や同級生や飲み屋つながりの人たちはもちろん、それ以外のたくさんの方も訪れ、300人以上の人たちが集まった。永沢の思い出話に花を咲かせながら、さながら大宴会のような様相で、159本ものビールが空いたという。「この記録は破られないでしょう」と、葬儀社の人がつぶやいていたという。
同年12月19日、四十九日には、仙台のホテルで「偲ぶ会」が開かれ、恩師や同級生のほか、東京からもたくさんの人が訪れた。こちらも終始、温かな雰囲気だったという。
ここからは、取材に協力くださった方たちの、永沢が亡くなったことへの思いを紹介していく。あえて、誰がどの発言をしたのかは伏せる。
「本人も死ぬとは思ってなかったと思うよ。急死ですよ。ただみんな、がんであることもアル中であることも知ってたので、急だけど『ああ死んじゃったのね』って感じだよね。悲しいっていうか、しばらく経ってからだよね。さみしいって感じ。永沢いないんだなって。だけど、いなくなっても話題に普通に出てくるし、死んでからもまだ存在しているみたい」
「光雄はやっぱり短編向きだと思うし。もっとはっきり言うと、あの10倍書いたら絶対に売れたと思う。誰かが書かせなかったのが悪いんだよ、俺に言わせると。あんな量じゃ評価できないんだよ。光雄はあの10倍書くべきだったんだよ、死ぬまでに。そしたら絶対に売れた。あいつは書けば書くほど自分が出るから。それが残念」
「あれだけ酒を飲めば、仕方ない。そもそも、彼といた部屋の白かった壁は、出るときタバコのヤニで茶色だった。それが、彼の亡くなった物理的理由だと素直に思う。あの延長線上にしか彼の人生はなかったのだと思うと残念。ここの時点で、私は離れると決めたけど、ほら、まっすぐ直線距離で(死へ)向かってたでしょう?」
「いや、あれだけの酒の飲み方してれば、死ぬよなぁ……という。こうなるとは分かっていただろうし、まぁでも、声を無くして、病院のいろんな課を巡り歩いて、薬をじゃらじゃらもらって帰ってくるという。それを嬉しそうに語り書く、自虐的な永沢さんというのは困ったもんだけど」
「悲しいっちゃ悲しいんだけど、複雑だよね。悲しくないことは無いけど、あんなに食事もしないで、酒ばっかり飲んで、長生きしようと思っていない生き方をしていたのは事実だから。急に亡くなったけど、こんなに元気だったのに、という印象はなくて。印象としては、長生きしないだろうなというのがあったから。しょうがなかったのかなと。元気な人が急に亡くなったら、いろいろな思いがあるんだろうけど、そこに関しては、本人がそういう風な生き方で来ていたから。そんなに長く生きられないだろうと、自分も絶対思っていたからね」
「俺が最後に永沢さんに生きているときに会ったのは、死ぬどのくらい前かな。1ヶ月くらい前なのかな。いつもの感じで行って、俺が『2人で漫才コンビ組まない?』って。日本初の、ボードで声の出ないやつがボケで、俺がツッコミやるからって。『それで全国を回らない?』『いいよ』って言うから。じゃあやってみようよ、って即興で。メグちゃんを客にして、2人で『はーい、どうも!』って。コンビ名も付けたんだよな」
「恵さんが起きたら亡くなっていたというのもダサい。恵さんの周りの人は、『そっと逝ったことは彼の優しさだ』と言っていましたが、私はちゃんとお別れすべきだったと思うし。というか、周りに迷惑をかけたくないという考え方なら、まあ、確かに、そっと逝ったのは正解かも? でも、『生きている自分』『思いのある自分』を軸にしていたなら、もっと違った死に方をしただろう」
「その夜、永沢光雄の嫁・メグちゃんから留守電が入った。『永沢が亡くなりました。時間あったら今晩、家でお通夜やります』。47歳、肝機能障害。死因は癌ではない、酒だ! とんでもなく打ちのめされた。しばらくしてメグちゃんが『49日に坂本さんが以前作ってくれた番組の長い方を来た人に配りたい』と言ってくれた。嬉しかった。〇〇さんにお願いし、再編集させてもらった。やっぱりずっとずっと触っていたい素材だった。徹夜した明け方、編集を見直していると『あ、僕、死んじゃいました』と言ってるように見えた。『ぼさっとするな』と。明け方の編集室でひとり、ぽろぽろ涙が止まらなかった。それからしばらくして、メグちゃんとふたり、二丁目で飲んだ。そして2人で抱き合って大声でわーわーと泣いた」
「ちょうど亡くなる3日前に、私が訪ねたときに会いました。ずいぶんやせ細っていましたが、亡くなるとはまったく思っておりませんでした。ちょうど9月から10月にかけて、会いに行かなくてはならない、という思いが私の心に沸き上がり、所用で東京に行った帰り、2時間ほど会いました。別れ際、彼の方から手を差し出してきて、握手をしました。2人で握手をした記憶が薄いので、握手をしながら、珍しいなと思っておりました。家族も覚悟はしていたと思います」
「通夜では、永沢のお母さんが本当にね。気丈にもさ、一人ひとりあいさつに来るの。誰それさんがあのとき来てこうだったよね、って言うんだよ。やっぱ永沢の親だね、抜群の記憶力。圧倒されたけど、それよりも、お母さんが『永沢の友達が遠くから来てくれたよ』って。泣くしかねぇじゃん。お母さんの気丈さも心中も余りある。うちのお袋に、俺バカだから、『永沢君のお母さん、こんなにも気丈に息子とお別れしていたよ。おっかさんも俺が死んだら……』って、バカか俺って。そんくらいトチ狂っちゃうくらい感動したんだよね」
「私は外から永沢を拝むだけではアレやから、永沢を見たいと。動いたね、口が。ほんで、私びっくりして。口がふっと動いたから、わーっと。錯覚かなと思ったら、死後硬直でそういうこともあると。そやけど、何が言いたかったのか、何か知らんけど、誰にも言わんかったわけ」
「悲しい。業界の方が、AV女優さんの不幸を聞いたりとか、そういうのはやっぱり嫌ですよね。そういうのがクローズアップされるじゃないですか、この業界って。だから元気で頑張っているとか、元気で活躍しているという情報を聞くほうがやっぱうれしいですよね。素朴に思ったことは、どうしてかなって、何があったんだろうとか、そういう感じに受けましたね」
「まさかっていう思いと、やっぱりな、っていう両方でしたね。それまでも(病状が)悪いっていうのは、ある程度伝わってきていたので、両方の気持ちが同時に出たようなアレかな。でも面倒を見てもらっていた、恵さんっていう女性に巡り合えたのも、光雄の人間性なのかなと。光雄とその女性が一緒になったときに、お金がなくて、結婚指輪も買ってやれなかったらしいんです。仙台に2人で来たときに、友達が金を出し合って、結婚指輪を買って光雄に贈ったらしいんです。いい話だなって覚えてましたね」
「いつかは、と思っていてもね。こういうのはふいに来るからね。ちょうどその夜も酒を飲んでいい調子で家に帰って、しばらくたったら電話が鳴って、めぐみさんから、永沢が今朝亡くなりましたと。そのときは、もう夜10時を回っていたので、翌朝にすぐに死に顔見に行ったんですけど。きれいな死に顔でしたね」
「正直いうと、とうとう来たか、なんだけど。でも、考えてはいなかったよ。考えたくはなかったので。とうとう来たかと思ったけど、ちょっと悲し過ぎるよねって。46~47でしょ? せめて50までとか。どうせ死ぬんだったら、1回飲もうよ、と。どうせ肝臓悪いなら、ひとりでも飲むなら、一緒に飲んでもいいじゃんって思う」
「赤塚不二夫って漫画家いましたよね。彼は二酸化炭素のボンベ置いて、チューハイを自分でつくって、家でずっと飲み続けてみたいな。本人いわく、アルコールを点滴で入れてほしいくらいや、っていうことを言ってたのをテレビで見たのですが、(永沢も)ほとんど同じじゃなかったんですかね。ご飯も食べていなかったんじゃないですかね。アルコール自体にはカロリーはありますのでね、多少は。亡くなるときは、自分が死んじゃうなと考えてなかったんじゃないですかね」
「永沢っていうのは、私の価値観とか生き方に対して、大きな影響を与えているとは言えないですが、ある部分は、芸大の時代のひとつの大きな、永沢光雄と親しく付き合いができたというのは、私にとっての大きな思い出といいますかね」
「でも、ちょうどよかったんじゃない。出版業界が終焉を迎えるなって俺たちは思っていたから。それに抗ったときもあったけど、結局負けて、雑誌潰して、いま考えれば、雑誌文化が終わるのに、こう無理やり流れに竿刺して、ばーんと吹っ飛ばされたみたいな感じで。『売れるものを作ろう』なんていうことじゃなくて、雑誌文化の終焉を何とか堰き止めようとやってたんだなって。そんなものと戦っていたら、それは死にかけるよ。俺も永沢さんが死ぬ辺りが一番危なくてさ。体も精神もおかしくて。酒の量もむちゃくちゃだったから。30分でボトル1本半くらい飲んでたもんね。永沢さんが先に死んだなみたいな感じで、俺も追っかけるよ、みたいな」
最後に、永沢の死後、妻の恵さんがインタビューで、彼への思いを語った言葉を紹介する。
いつもありがとう、それとごめんねって。1日何回も書いてました。でもそれは病気になる前から。愛してるよって1日何回も言ってくれてたし、飲みに行くときも必ず手をつないでたし。だから永沢=ダメなんだけど、
私はぜ~んぶ大好きでした。
「ありがとう」「本当に幸せだった」。今の私には、亡き夫に捧げるべき、別の言葉が見当たりません(中略)お義母様が仙台からみえた時、私「これからも永沢の姓を名乗らせてください」って、お願いしました。ずっと、あなたの妻でいるつもりだから。
エピローグ
2015年、永沢恵さんに出会ったことをきっかけに、僕は永沢光雄の半生を描くことを決めた。そして2023年2月、何とか原稿を書き終えたのだが、実は2015年のあの夜以降、恵さんには会っていない。電話番号を交換したし、住所も知っている。だが、電話をしても出ず、メールを送っても返事がない状況なのだ。永沢さんの関係者の誰も、恵さんと連絡が取れないのだという。
そこにはある事情や理由がある。僕も知っているのだが、ここには書かないことにする。決してポジティブな事情ではないからだ。
それでも、最後にもう一度、話を聞きたいと強く思い、手紙を書いてマンションの郵便受けに入れた。あなたに会ったことで僕は永沢の話を書いています、よければ連絡をください、永沢も行きつけだった鉄板焼き屋で飲みましょう、と。
やはり連絡はなかった。自宅前で待ち伏せをすることも考えたが、今の恵さんに無理やり会い、永沢の話を聞くことが正しいとはどうしても思えなかった。恵さんを傷つけこそすれど、誰も幸せにはしないのでは。僕は恵さんに会うことを断念した。
残念ではあるが、仕方ない。これこそノンフィクションではないか。この何とも締まらないラストを、永沢だったらどのように描くのだろう。僕はやっぱり、つい取り繕おうとしてしまう。無理やり美談にしたくなってしまう。それってダメかな? どうすればいいと思う? と永沢に聞きたくなる。
2019年、僕は汗だくになって、勾配を登っていた。場所は仙台市営の葛岡墓地。ここに永沢は眠っているのだった。
仙台駅からバスに乗って10分強、墓地の近くのバス停に到着する。花屋があったので立ち寄った。紫と白の花を購入する。『AV女優』の表紙と同じカラーにしたのだ。墓地の敷地内は想像していたよりはるかに広く、永沢の墓がどこにあるかもわからない。受付で職員に聞いたが、「親族以外には教えられない」と断られた。東京からわざわざ来たのだと泣きつき、こっそり教えてもらう。永沢の墓は、入口から最も遠い、最深部にあるとのことだった。
僕は歩き続けた。11月の仙台の気温は、東京育ち・暮らしの僕には極寒に感じられたが、汗ばむほど体が火照っていった。途中、1台の車が僕の横で止まった。
「さっき受付で聞こえたのですが、お目当てのお墓の場所はわかりますか? ずいぶん遠いと思うので、乗っていきますか?」
仙台市民の優しさに心から感動したが、ていねいにお断りした。やっぱり、自分の足でたどり着くべきだと思ったからだ。戸井睦夫の墓を探して、汗と泥にまみれながら、運動不足の体で疾走した永沢のように。
30分近く歩いただろうか。ようやく目的の場所に到着した。「永澤家」と書かれた立派な墓石で、名家なのだなと改めて実感した。線香をあげ、手を合わせる。それからバケツに水を汲み、お墓を磨いていった。

たどり着くまでは、墓の前に立ったとき、さぞかし感慨深く感じるのだろうと思っていた。でも、特別な感情は沸いてこなかった。これまでの取材で、永沢と散々時間をともにしてきたが、結局僕らは一度も会ったことがないからかもしれない。いや、僕の乏しい感受性のためだろうか。ここで涙でも出れば、そのことを感動的に描写して、クライマックスにふさわしい場面として使えるのでは、と思ったが叶わなかった。現実はやっぱり面白いなと、心のなかで苦笑した。
墓参りの後、仙台の街に繰り出した。図書館やブックカフェに行き、「永沢光雄って作家を知っていますか?」と尋ねたが、知らない人がほとんどだった。夜は壱弐参(いろは)横丁という飲み屋街に行き、6~7軒を飲み歩きながら永沢のことを聞いたが、同様だった。「光雄さんはね、仙台市民の誇りですよ……」みたいな話が聞けたら、ものすごい取れ高になるだろう、という期待はあっさり打ち砕かれた。
何だよ、あなたは仙台のヒーローじゃなかったのか! と毒づきたくなったが、この状況もありのまま書けばいいじゃんと、とあっさり気持ちが切り替わった。なぜなら、あなたもきっと、そうしていただろうから。同時に改めて気づく。書き手としての僕が、永沢に受けた影響の大きさは計り知れないことを。
最後に。あなたは、ノンフィクションを虚構と言い切った。その通りだと、今の僕も思っている。だから、僕も虚構としてあなたの物語を書く。どんな風に書いても文句を言わないでほしい。ただし、永沢イズムは、勝手にだけどきっちり受け継いでいるつもりだから、どうか安心してください。
うつ病でアル中でヒモでマザコンで小説家としては鳴かず飛ばずだったみっともない男、みたいな物語にすればインパクトがあるのだろうけど、そんな表層的な要素なんかじゃなく、永沢光雄っていうひとりの人間としての、あなたの半生に向き合わせていただく。
だから、つまらない話になるかもしれないけど、味わいっていうのは出るんじゃないかな。あなたがこの原稿を読んだときに、「お、いいね」と言ってもらえるように意識して書きました。お母様があなたのことを殺した、って書くときは、かなり心が痛んだし迷ったけれど、あれを書かなければライター失格ですよね。あなたも、きっと書いていたのでは? そんなことないって? でも、あなたもお母様も故人ということもあるし、どうか許してほしい。
一度、あなたに会いたかったけど、会わなくてよかったような気もする。会っても、今さら話すことなんてなさそうだもんね。でも、あなたの飲みっぷりと、聞き上手だというあいづちは一度見てみたかった。
あなたが行きつけだったサイドビーで、あなたのボトルは僕が受け継いでるよ。焼酎を継ぎ足し、継ぎ足し。でも、あのお店も最近ずっと閉まったままで。ほかにあなたが行きつけだったお店も、どんどん無くなっていってるんです。寂しいけれど、時の流れってこういうものだし、仕方ないですよね。そう、僕はあなたもよく来ていたゴールデン街でバーをやってるんです。常連になってくれていたら、さぞかし上客だったんだろうな、なんて。
あなたの関係者の皆様に取材をして、印象深いことがあるんです。それは、ほとんどの方が、「永沢の話だったら」と喜んで引き受けてくれたこと。見ず知らずの、どこの馬の骨かもわからない僕なんかに、何時間も割いて、話を聞かせてくれたり、資料となるようなものをかき集めてくれたり、この人にも話を聞きなって紹介してくれたり。あなたの思い出の場所を案内してくれた方もいた。月並みな言い方だけど、あなたは愛されていたんだな、って感じた。もちろん、取材を断られてしまった方も何人もいるけれど、それもその人たちなりの愛情なのかもしれないね。
じゃあ、永沢さん。「はじめまして」も「さようなら」もないまま、僕たちの関係は始まって終わるわけだけど、最後にお礼だけはぜひ言わせてほしい。本当に、ありがとうございました。〈了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
