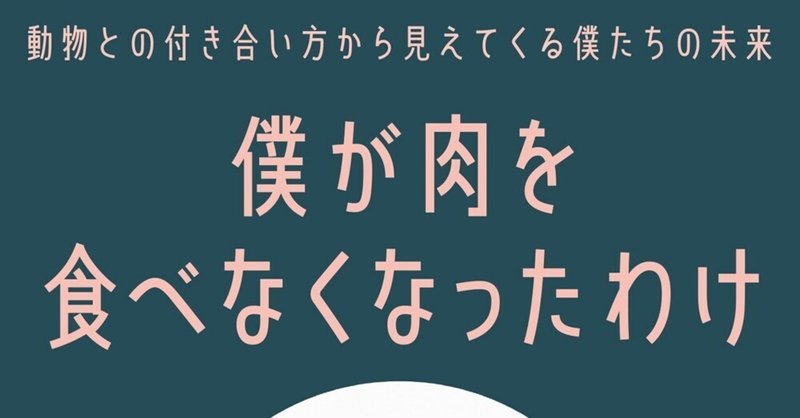
僕が肉を食べなくなったわけ―イントロダクション
愛とは、自分以外の存在がそこにある、という、とてつもなく難しい気づきのことである。
愛とは、真実を発見するということなのだ。
――アイリス・マードック
この世でうわべだけでも意味のある振る舞いを続けたければ、
物事には正しいことと正しくないことがあると信じないわけにはいきません。
――ジョーン・ディディオン
僕と同世代のなかでも一番の優秀な頭脳が、猫の動画に破壊されるのを僕はこの目で見ている。ペットの猫がピカピカの床の上を滑る。箱に飛び込む。隣の家の屋根に飛び移るためのジャンプの軌道を計算し損なう。それはインターネットの黄金時代のことだ──ワクチン陰謀論者や、反・反右翼派が台頭して物事をめちゃくちゃにする前の話である。
そういう動画は、僕たちのある側面を物語っている。僕たちは自分たちのことを、動物愛好家(アニマル・ラバー)だと思っているということ。野生動物のドキュメンタリーや、動物のお手柄についての心温まる物語を片っ端から観る。動物を可愛がる政治家に共感する──彼らのペットが選挙に出たら、再選される可能性は彼らよりも彼らのペットの方が高いかもしれない。
だが、僕たちが動物に感じる愛情には自己不信がついてくる。人間社会が動物とかけ離れた方向に進んでいることを僕たちは知っている。敢えて問われれば、僕たちは、ほとんどの家畜は幸せに暮らしてはいないこと、野生動物の多くは棲みかをなくしていることを認めるだろう。そうじゃなかったらいいのに、とは思うが、これは僕たちが豊かであることの代償なのだ。
だから僕たちは動物のことはあまり考えない。僕たちの食べ物や衣服の多くは動物由来だし、人間社会の盛衰には動物が大きく関わってきたし、人間が地球上からいなくなってもおそらく彼らは残るのだろうが、でも僕たちは彼らの存在について深く考えたりはしない。
ここは人間の住む惑星なのだ。現在の世界人口のほとんどがそうであるように都会暮らしの僕は、一日のうちにお目にかかる動物と言えば数えるほどだ。ハトの群れの横を通り、ミバエを追い払い、広げた雑誌の、ちょうど読んでいるページの上に陣取っている飼い猫クランブルをそおっとどかしてからまた読み続ける。動物は、陳腐な喩えに使われたり奇抜なロゴに使われていたりもするが、意識を持つ生物の大多数を占める存在として描かれることはない。人間は、500種ほどの霊長類、6400種の哺乳類、推定で700万から800万種類いる生物の、たったの一種にすぎない。だが、その事実を僕たちが認識することはめったにない。
僕たちは、動物を生物種やグループに分けて考える──ウシ、犬、キツネ、ゾウ、といった具合に。そしてそれぞれに、人間社会における居場所を与える──ウシは皿の上、犬はソファの上、キツネはゴミ箱の中、ゾウは動物園。それ以外の無数の野生動物たちは、どこか他所(よそ)にいて、願わくば、デイビッド・アッテンボローのドキュメンタリーシリーズの次回に登場してほしい。この、分類する、という能力は素晴らしく人間の役に立った。そうすることによって僕たちは、食べ物を手に入れ、友人や娯楽を見つけ、危険な動物から身を護ることができたのだ。サンドイッチを買うたびに哲学的な議論をする必要もない。自分の存在そのものに罪悪感を感じずに済むのもそのおかげだ。
だがその分類は脆く、壊れやすい。事実、今やこうした分類はバラバラに崩れようとしているのだ。身近な動物たちについての新しい知見が毎日のように報告される。人間が食べ物として扱ってきた動物──なかでもブタとウシ──は、複雑な知性と社会性の持ち主だということが今ではわかっている。昔から、必要のないものとして扱ってきた動物──たとえばオオカミやビーバー──は、実はこの世界になくてはならないものだった。非常に貴重だとされる動物──ジャガーやオランウータンなど──は、人間の進出によって棲むところを失っている。
こうした分類は、動物たちについてよりも、僕たち自身についてより多くのことを語っている。動物たちの、その存在そのものを愛するようになればなるほど、分類はあやふやなものになる。西欧では、日本人がクジラを、韓国人が犬を、カンボジア人がネズミを食べるのは間違っていると考える人が圧倒的に多い。でも、ブタやウシを食べるのは良くてクジラや犬を食べてはいけないのがなぜなのかを説明しようと試みれば、哲学の迷路に迷い込んで出られなくなる。クエンティン・タランティーノの映画『パルプ・フィクション』の中で、犬には「性格がある」から汚い動物じゃない、と主張する殺し屋みたいなものだ。ブタにも性格はある。だったらどうして、年間に15億頭のブタを殺すのは良くて、犬を1匹殺したと言って激怒するのだろう? ブタを味気ない囲いの中に閉じ込めるのは良くて、犬にそれをしてはなぜいけない? 十数頭のクジラを捕獲するのが倫理的に間違っているのに、何百頭ものイルカが絡まってしまう魚網を使うのは間違っていないとされるのはなぜなのか?
平たく言えば、動物愛護は西欧社会の核をなす概念の一つだし、合理的思考もそうだ。ところが、僕たちの動物の扱い方はそのどちらにも沿っていない──昔からの慣習と惰性に従っているだけだ。迫りくる野生動物の集団絶滅を良しとする人はいないだろうし、動物自身だってもちろんだろう。いったいぜんたい僕たちはどうやって、次の世代に集団絶滅を釈明するのか。でもそれは、僕たちの目の前で起こっているのだ。チャールズ・ダーウィンは、顔を赤らめるというのが最も人間らしい表情である、という結論に至った。よかったと思う──だって僕たちには、顔を赤らめる理由が山ほどあるのだから。
新型コロナウイルスが蔓延する以前、楽観論者たちはよくこう言ったものだ──今ほど人間でよかった時代はない、歴史上、好きな時代を選んで生きることができるなら、今がそのときだ、と。でも、他の動物はどの時代を選ぶだろう? 仮にあなたが今、人間以外の哺乳動物に生まれるとすると、畜産場の、狭苦しくて不自然な環境に生まれる可能性が、かつてないほど高い。大規模な酪農場では、1頭の雌牛から搾れる牛乳はおそらく100年前の4倍になっているが、雌牛の寿命は実は短くなっている。野生動物に生まれるとしたら自分の生息地が破壊される、あるいは気候変動に適応できない危険性が先祖たちに比べて高いだろう。「生きている地球指数(Living Planet Index)」によれば、1970年代以降、野生動物の数は平均して3分の1になっている。野生動物の売買が、特にアジアで盛んになっているので、捕獲されて過酷な環境に置かれる可能性も高い。現代のアメリカで飼われている犬の生活──ソファの上でのんびり寝そべり、オーガニックのビスケットを齧り、気の利いたインスタグラムのアカウントだってある──を思い浮かべる人もいるかもしれない。でも、もしも僕たちが無作為に何かの動物に生まれ変わるとしたら、アメリカの畜産場でニワトリとして生まれることになる可能性の方が、少なくとも20倍は高い。いつの時代に生まれるかを選べるとしたら、動物たちは今を選ぶだろうか? 選ばないと僕は思う。
人間が動物のことを──すべての動物のことを考えたらどうなるだろう? 僕たちは、食べ物を手に入れる方法を、自然界の扱い方を、動物園の動物に対する態度を変えるだろうか?
(中略)
ダーウィンの進化論は人々の心の中で、生存を懸けた残忍で非道徳的な競争と結びついた。進化論の起案者であるダーウィンは、人間と動物の関係についてこの科学的発見が何を意味するのか、その答えを出すことを後世に委ねたのである。
嬉しいことに人間は、動物についてじっくり考える時間さえあれば、動物に対する態度を変えることが多い。イギリスで最も有名な自然保護主義者の一人に、南極探検家スコット大佐の息子であるピーター・スコットがいる。1909年生まれのスコットは、WWFの共同創設者の一人である(あの有名なパンダのロゴをデザインしたのも彼だ。パンダが選ばれた理由の一つは、白黒の方がコピーするのに向いていたからだった)。彼は大の愛鳥家で、多くの自然保護活動家に影響を与えた。だが彼は人生の大半を、鳥を撃つのを趣味として過ごした。「狩りをするのは人間の本能の一部であり、狩られるのは鳥の本能の一部である」と彼は書いている。前装式の鉄砲に撃たれるのが鳥の本能であるという理屈はどうしても真実とは思えず、40代になって、狩猟があまりにも容易で残酷であるという現実を突きつけられたスコットは、考えを見事180度転換させた。
同様に、ホールフーズ[アメリカの食料品店チェーン。健康や環境に対する意識の高い店として知られる]の創業者、ジョン・マッキーは、長年ベジタリアンとして店を経営していたが、あるとき、養鶏場や酪農場の環境が劣悪であるのに、自分は卵や牛乳を食べることに抵抗はないのか、と内省した。のちに彼は、ヴィーガンになる前は「見て見ぬふりをしていた」のだと回想し、「そのことをはっきりと認識したくなかったのだ」と言っている。
僕の経験から言うと、動物に対する見方を変えるのは(言葉遊びをするつもりはないが)一つの進化過程である。その過程はまず、漠然とした不快感から始まる。思い出すのは、ある日、飼い犬を去勢したばかりの同僚にたまたま出くわしたときのことだ。「何が問題なのかなんとなくわかったよ」と彼は言った。「まるで『侍女の物語』[カナダの作家マーガレット・アトウッドによるディストピア小説。出生率が低下した架空の国で、数少ない健康な女性はただ子どもを産むための道具として支配者層に仕える「侍女」とされる]みたいでヤバイよな」。それは、他の動物の行く末を人間がコントロールしている、という不愉快な認識だ。
この本のための取材を始める前の僕は、漠然と自然を愛するベジタリアンだった。今はヴィーガンとなり、特定の状況での狩猟や漁獲を支持し、地球上に、他の動物たちのための場所をたっぷり確保する必要があると考えている。あなたが達する結論はそれとは違うかもしれない。この本では、「僕たちは」こう思う、という言い方をすることがある。すべての人間が同じ考え方をするからではない。実際、動物に対する態度が全員一致する家族にさえ、僕はほとんど会ったことがない。だが、僕たちはみな、今よりももっと動物のことを考えるべきだし、動物のことを考えれば、意見が一致する点はたくさんあるということに気づくはずだ。
第一章では、動物に対する人間の態度が、近年のヴィーガン・ブームに至るまでの過去数百年間にいかに変化したかを要約する。その後、人間が現在、畜産・漁猟・医学研究・狩猟などによって動物を殺すことをいかに正当化しているかを検証する。80億人いる雑食性の人間の食料を得るためには何が必要なのか? 後半では、人間がいかにして動物を愛そうとしてきたかについて考える。そのために僕は、サンフランシスコ、モンゴル、コロンビア、インドネシア、そしてイギリスの田舎を訪れ、動物園の所有者、保全生物学者、ペットを飼っている人たちに取材した。本書の最後に、人間だけでなく生きとし生けるものすべてにとってより良い世界をつくるために、僕たちが個人として、また社会としてできる、いくつかの実践的な提案を示す。僕たちはすでに、一部の動物を大事にしている。次はそれを徹底させる番だ。
僕にとってそれは、発見と希望の物語だ──今はまだ脇役だが、これから社会の主流になり得る物語である。「精神(マインド)とは混沌とした喜びであり、そこから未来の世界とより静かな喜びが生まれる」と、ビーグル号での航海中にダーウィンは書いた。人間と他の動物の一番の違いは、人間の精神にある。そして、動物たちとの均衡点を見出すために最も役に立つのも人間の精神だ。
以前の僕は、今現在人間が動物に対して行っているひどい仕打ちは、意図した選択の結果であり、人間は単に、人間以外の動物が大切だと考えていないのだと思っていた。だが今では、それは僕たちが、自分の行動が引き起こす結果についてきちんと考えていなかったせいだと確信している。僕たちには、動物に対して持っている根本的な愛情と矛盾しない生き方をすることが可能だ。動物が僕たちに何を与え、僕たちは彼らに対してどんな責任があるのか、きちんと答えを見つけることができる。動物について、もっと頻繁に、もっと深く考えることで、僕たちは心の平安を見出すことができるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
