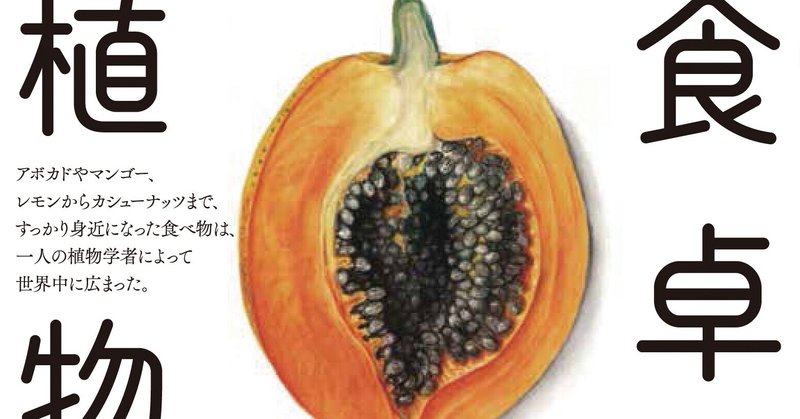
食卓を変えた植物学者―訳者あとがき
自分が今、当たり前のようにスーパーマーケットで目にし、購入し、食卓に並べている食べ物が、実はあるときにはっきりした意図をもった誰かの手で我が国に持ち込まれ、栽培されるようになった、あるいは輸入されるようになったものであるという可能性を、多くの人は考えたこともないかもしれない。本書はアメリカの物語だが、今や手に入れられない食材はないと言ってもいいアメリカは、今からほんの百数十年前には、ヨーロッパからの移民が植民地に持ち込んだわずかな食材しかない、食の貧しい国だった。そこに、いわば「国策」として海外から多種多様な「食べられる植物」が導入されることになる。そしてその中心的な役割を果たしたのが、本書の主役、デヴィッド・フェアチャイルドである。
19世紀の終わりから20世紀前半にかけてアメリカに初めて持ち込まれた食物について、その植物学的・園芸学的特徴やアメリカでの本格的な栽培に至る歴史的な経緯を正確かつ詳細に記した学術書をお探しの方には、本書は少々物足りないかもしれない。
むしろ本書は、アメリカがその歴史上最も華々しい発展を遂げた魔法のような時代に生きた、異様なまでに幸運な一人の男の生涯を綴った伝記であり、冒険談であり、紀行文であると言う方が正しい。建国100年、シカゴ万博、蒸気船による遠洋航路の発達、電話、飛行機の発明……。「金ぴか時代」と呼ばれる、まさに絢爛とした時代背景に、個性の強い登場人物たちが歴史に残る冒険を繰り広げる本書は、映画化したらさぞや面白いものになるに違いないと思う。
主役のデヴィッド・フェアチャイルドは、題名の通り植物学者であり、1890年代から1920年代にかけて、それまでアメリカになかった数百種類の植物を海外から持ち込むという功績を残した「プラントハンター」の草分け的存在である。持ち帰った珍しい植物で植物園をつくりました、という話ではない。組織的に海外から植物を導入し、農家に提供して農業という産業を支援する、というアイデアを実現させ、米農務省内に「種子と植物導入事業部」を創設し、彼が海外から送った種子が、挿し穂が、アメリカの土で芽を出し、根を下ろし、大々的に栽培されて他国と競合できる産業を生み出し、アメリカの農業を根幹から創造し、まさにアメリカ人の食卓に大きな変革をもたらしたのはフェアチャイルドだと言っても過言ではないのである。
もう一人の主役バーバー・ラスロップは、莫大な父親の遺産を受け継ぎ、贅沢三昧の海外旅行に日々を費やす有閑階級で、デヴィッド・フェアチャイルドより22歳年上の伊達男である。怖いものを知らない傍若無人の典型のような、大きく膨らんだ自我ではちきれんばかりの、だが時折意外な優しさと無防備さを見せる洗練されたラスロップと、カンザスの田舎出身で、知的好奇心に溢れてはいるが世間知らずで自信もなければ金もない不器用なフェアチャイルド。何の接点も共通点もないように見える2人は、船上で偶然に出会い、やがて世界を股にかける旅をともにするようになる。新しい植物・食物をアメリカに紹介するというフェアチャイルドの野望にはラスロップの金が必要だったし、贅沢ではあるが目的のない旅に満足できなくなっていたラスロップには、フェアチャイルドの計画を助けることで自らの旅を意味のあるものにすることが必要だった。
初めのうちは感情的にすれ違い、衝突もする2人だが、旅を続け、苦楽を共にする中で、互いが互いの持つものを必要としていたというだけではない、生涯続く真の友愛が育まれていく。世界五大陸のすべてを豪華客船で巡りながら二人が採集してアメリカに送った農作物は、アボカド、マンゴー、デーツ、タバコ、綿花、米、レモンをはじめ数百種に及び、現在のアメリカの農業と人々の食生活に多大な影響を与えている。またフェアチャイルドは、有名なワシントンDCの桜を日本から輸入するのにも大きな役割を果たしている。
この2人の旅と植物探しの背景に彩りを添える脇役もまことに豪華である。フェアチャイルドが少年の頃に、生涯消えることのない熱帯の島への憧憬を彼の心に植え付けた、進化論の実証をダーウィンと競い合ったアルフレッド・ラッセル・ウォレス。電話を発明したアレクサンダー・グラハム・ベルとその娘マリアン。動力飛行機を発明したライト兄弟、その他、フェアチャイルドの脇を、金ぴか時代のアメリカの富裕層・知的エリートたちが見事に固めている。
さらに、後半になって登場する重要人物が、フェアチャイルドの幼なじみであったチャールズ・マーラットという昆虫学者だ。彼は新しい植物とともにアメリカに植物の病原菌や害虫が入ってくる危険性を訴え、フェアチャイルドと激しい闘いを繰り広げる。昆虫学者としての懸念に、フェアチャイルドの幸運さに対する私怨が重なって、フェアチャイルドへの彼の攻撃は熾烈を極める。アメリカの生活をより豊かなものにするために新しいものを貪欲に迎え入れようとするフェアチャイルドの楽観性と、未知のもの、知らないものを恐れ、嫌悪し、遠ざけようとするマーラットの悲観的な考え方の対立。結局、2人の争いは、マーラットが検疫法を制定させることに成功して決着するのだが、ハリウッド映画ならば当然、観客が応援し、軍配を上げるのはフェアチャイルドのはずだ。
だが、私が本書を翻訳した2020年は、ご存知の通りCOVID-19が世界的に大流行し、人も物流も否応なく足止めを食らった1年だった。中国のどこかで新しいコロナウイルスが見つかったらしい、という情報が流れてきた、と思ったらあれよあれよという間にウイルスは世界中に広がり、蔓延し、気がついたら世界を膠着状態に陥れていた。ウイルスの侵入を防ぐために国境は閉鎖され、海外旅行どころか国内の移動すらままならなくなった。
フェアチャイルドとラスロップが乗っていた船の上でペストを発症した乗客が「事故で」死亡し、ぞんざいに水葬されて、船は検疫のための隔離を免れた、というエピソードが登場する。それが遠い昔の、自分とはまるで関係のない他人事とは思えないシュールな状況がリアルタイムに進行する中で、このフェアチャイルドとマーラットの検疫法の制定をめぐる熾烈な闘いを訳していた私が、ともすればマーラットの肩を持ちたくなったということは否めない。本書の著者がフェアチャイルドの味方であり、ほぼ手放しで彼の功績を称えているのは明らかだが、本書が書かれたのが2020年であっても著者の心情は同じだっただろうか。
外来種の侵攻によって在来の動物や植物が絶滅に追いやられる、というのは事実としてこれまで繰り返されてきたことだし、フェアチャイルドの事業がいかに計画的かつプロフェッショナルに行われたことであろうとも、望まれざる客を招いてしまう危険があったことは事実だろう。また今回のコロナ騒動で、「病原菌の侵入を水際で食い止める」ことの重要性と困難さは、世界中の人々が否応なく思い知らされたことでもある。だから、マーラットをゼノフォビアの権化であるかのように言う気には、私にはなれなかったのだ。
私がついマーラットを応援したくなった理由はそれだけではない。
子どもの頃からの夢であったマレー諸島を初め、世界中の国々に人の金で贅沢三昧しながら訪れ、大好きな仕事をして社会的にも認められ、愛する人(それもかのアレクサンダー・グラハム・ベルの娘である)に出会い、結ばれ、生涯裕福な暮らしを満喫して、自分が愛した熱帯の木の下で息を引き取る、という、およそこれ以上に恵まれた人生はなかろうと思われるフェアチャイルドの、一種呆れるほどの純粋さとまっすぐさには、どこかまた一抹の物足りなさを感じるのだ。
たとえば、フェアチャイルドが結婚して植物探しの旅に出ることができなくなった後、フェアチャイルドの後を継いでその任務を背負ったフランク・マイヤーは、フェアチャイルドのように大金持ちのパトロンが付いているわけでもなく、過酷かつ危険な条件下での孤独な旅を続け、やがて精神を蝕まれていく。彼がフェアチャイルドに救いを求め、振り絞るようにして書き送った言葉に対してフェアチャイルドは為すすべを知らず、マイヤーに精神的に一番近いところにいたはずの彼は、結局マイヤーを救うことができなかった。マイヤーの死が自死であったことを最後まで理解しなかった、あるいは信じようとしなかった、ということを知れば、彼にはマイヤーの苦しみを理解するのに必要な共感力も想像力もなかったのではないのかと思わざるを得ないのである。
フェアチャイルドが優れた植物学者であり、猛烈な働き者であったことは確かだ。飛行機も冷蔵輸送技術もなかった時代に、西欧人がほとんど訪れたこともない、しばしば豊かな暮らしがあった地から、アメリカで育つであろう植物を見分けて送り届ける、というのがどれほど大変なことかは想像がつく。そして、高齢になってからも好奇心を失うことなく常に新しい知識を求め、純真な探究心を生涯失わなかったというのは素晴らしいことだ。けれども同時に彼が、英国から独立し、意気揚々と国力を増していく得意満面のアメリカの、とりわけ東海岸のエリート層の手本のような存在であるのもまた事実である。もちろん、自分のしていることが、後年アメリカを中心に進むグローバル化(とその弊害)の一助となっていくことを、当時の彼に自覚できようはずはない。とは言え、アメリカの植民地政策を「悲しいこと」と言う彼の言葉は真摯なものであったかもしれないが、海外の植物を導入してアメリカで産業として育て、競争力をつけて世界市場を制覇する、というのは、植民地政策と同様の帝国主義ではないか。
ちなみに、彼が20代になったばかりの1890年、アメリカの西部開拓は、米第七騎兵隊によるウンデッド・ニーでのネイティブアメリカンの人々の虐殺をもって終焉したと言われている。彼は、そのことをどう受け止めたのだろう、とふと考える。
仮にフェアチャイルドがこうやって植物導入をしなかったとしても、交通手段の発達とともに地球が小さくなり、食物のグローバル化が進むことは歴史の必定だったことだろう。人間は旅先で美味しいものを食べればそれを持ち帰りたくなるのが自然というものだ。そして、私を含め、そうやって豊かになった食生活の恩恵を受けていない人など、少なくとも先進諸国にはいないだろう。今、青果売り場には、もともとは外国産だけれども日本で栽培されるようになったもの、あるいは海外から空輸されるものを含め、世界中から届いた食物が並んでいる。フェアチャイルドやマイヤーが世界各地からアメリカに運んだものの遺伝子を引き継ぐ青果や観葉植物は、おそらく私たちの身の回りにいくらでもある。
地球が気候温暖化の脅威に晒される今、フェアチャイルドの時代には誰一人考えたこともなかったであろう「カーボン・フットプリント」という言葉が生まれ、食の地産地消の見直しを訴える声がある。一方、見直すべきは食物の輸送によるカーボン・フットプリントとあわせて、食物をどのように育てるかであるとする主張もあり、この議論には未だ結論が出ていないようだ。食のグローバル化はもはや止めようがないだろうが、本書が「ウィズ・コロナ」の時代の始まりとなる2021年に刊行されるという一つの偶然も、この問題について考えるきっかけを与えてくれたような気がしている。
そんな問題提起はさておき、蒸気船で巡る世界の国々の描写は、旅心をくすぐるノスタルジックかつロマンチックな魅力が満載で楽しめる。途中からは、ラスロップ役には今よりもう少し若い頃のダニエル・デイ=ルイスあたりが適役だなどと考えながら、頭の中に映像を思い描きつつ訳した。一方、優れた植物学者として大きな功績を残しながら純粋さを失わず、永遠の少年を心に宿すフェアチャイルド役の俳優は、残念ながらまだ候補が見つかっていない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
