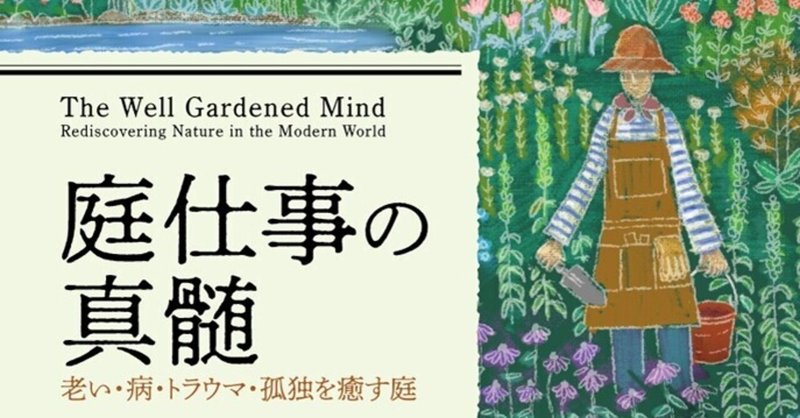
庭仕事の真髄―本文より抜粋
庭を耕す──人生とコミュニティと環境をつむぎ出す
ちょうど地球が持続可能でなくなっているように、私たちのライフスタイルも心理的に持続可能ではなくなっている。最近では、全世界で、うつ病が呼吸器系の疾患を抜いて、健康障害や身体障害の原因第1位になった。この上昇がクライメート・グリーフから直結しているというわけではないが、関係がないというわけでもない。問題は深くからみ合っているからだ。生きる力を取り戻すために人々が何を必要としているかを無視するのは、自然が繁栄するのに何をすべきか考えないのと同じ心の在り方の兆候だ。この問題は大地を耕す(cultivate)という意味の核心に直結している。
ヴォルテールの時代を超えた箴言(しんげん)「私たちは自分の庭を耕さなければなりません」というのは、彼の小説『カンディード』の結末だ。250年以上も前に出版された物語は直接現代に語りかけている。『カンディード』は最初の近代的災害と呼ばれたリスボン大地震の直後に書かれた。この地震は、当時広くいきわたっていた文化的な前提を粉々にした。
リスボンの町はそのころ裕福さも人口の多さも世界屈指の都市の一つだったが、歴史上でも最悪といえる地震で1755年に完全に破壊された。地震の揺れが津波を引き起こし、続いて火災旋風が発生し、田園地帯を荒廃させた。災害の傷痕は非常に深く、ニュートン力学が生んだ時計仕掛けの宇宙〔宇宙は神によってつくられた機械式時計のようなものであり、ニュートン力学に従い進行し続けるという考え方〕は順調に進んでいくという、18世紀の考え方を支えていた信念に疑問を呈することとなる。時計仕掛けの宇宙というモデルは、今の私たちにはバカげて見えるかもしれないが、西洋世界の考え方で、機械の普及を比喩として、取り上げているのだ。現代に同じものを求めるとすると、脳をコンピューターに例えるという話だ。そこには機械と自然の間に同様のミスマッチが見られる。比喩というものは強力だ。思考を深めることができるが、それと同様に思考に制限をかけたり、捻じ曲げたりもする。生物圏が危険な状態になったのは、人類が自然に対し生きたシステムとして敬意を表さなかったからだ。そしてその意味で、私たちは時計仕掛けの宇宙という比喩が及ぼした広範囲にわたる結果を見ているのだ。
ヴォルテールは情熱をこめて、完璧な機械のように順調に進んでいく宇宙という考え方と結びついた哲学的で宗教的な信念に異を唱え、カンディードの物語を通じて風刺したのだ。秘密裏に出版されると、本はすぐさま禁書となり、そして大ベストセラーとなった。物語の中でヴォルテールが主たる標的としたのは、やみくもな楽観主義(ライプニッツ〔1646─1716年。ドイツの哲学者、数学者で予定調和の説を展開〕の哲学の一解釈)で、頑固に最善を信じ、最悪を無視するというもので、それによって結果的に喜ばしくない現実が否定される。次々に明らかになる事件、ある場面で斬殺されたり怪我をしたりした人物が、別の場所で急に現れたりするというありえないプロットの展開はこの楽観主義を映し出す。その結果、マジックリアリズム〔日常にあるものが日常にないものと融合した作品に対して使われる芸術表現技法〕のさきがけと解釈されている。
カンディードの冒険を読み進むにつれて、どれほどこの種の楽観主義が世界で起きているどんな恐ろしいことにも人々を動揺させないようにしているのか、無視できなくなってくる。サトウキビ農園でひどく身体が不自由にされた奴隷の苦境に遭遇した時、カンディードはやっとこのことを理解する。砂糖生産のために人間が払う代償は驚くべき新事実で、楽観主義とは「すべてがまったくうまくいっていないのに、すべて良いと信じて疑わないという熱狂」なのだと、初めて彼は認める。カンディードの問題は、自分を守る無条件の楽観主義がなくなると、今度は悪に負けてしまって、自分は一人ではどうすることもできないという憂鬱状態に陥るということだ。このようにすべてを否定する異常な熱狂に代わる唯一の選択肢は悲観主義のように見える。対処するには問題が大きすぎるか、難しすぎるという理由から、世界や自分自身の中の何かを変えようという努力は、意味がないと思ってしまう憂鬱な心の傾向のことだ。
物語結末で、カンディードはマルマラ海の浜辺で船から上陸する。そこはちょうど私の祖父が戦争捕虜となった場所だ。この偶然から私はテッドの第一次世界大戦での経験を連想し、本書の初めに戻ることになるのだが、ヴォルテールの物語を読んでいる人には、まったく別の連想となるだろう。あの時代、最も普通に想像されるのは、トルコといえばエキゾチックな場所であることと、スルタンの壮麗な庭だろう。それから伝統的な「ボスタン」ガーデンだ。これは各地にあった生産性の高い野菜畑のことだ。
コンスタンチノープルの近くの田舎で、カンディードは小さな農園に息子たちや娘たちと一緒に住んでいる一人の「立派な老人」と出会う。老人はカンディードと連れの者たちを自宅に招き入れ、庭の果物を勧めた。続けて、オレンジやパイナップル、ピスタチオと、自家製のシャーベット、スパイスの効いたクリームをごちそうしてくれた。カンディードはこの飾り気のない農園がとても実り豊かであると知って驚いた。彼は友人たちとともに長々とした哲学的議論に時間を費やしたが、みんな退屈し、落ち着かなくなり、不安になった。彼らは庭を耕さなければならないのだとカンディードは気がついた。
ヴォルテールの楽観主義と悲観主義は、別の装いで今日の私たちの生活を支配している。悲観主義は私たちのまわりのいたるところにある。特に、うつ病や不安障害の流行、世界の状況や気候危機、戦争と暴力、また自然や人々からの容赦のない搾取に対する消極的な気分と無力感が広まっていることなどだ。カンディードの世界のように、私たちはまるで極が二つある世界に住んでいるかのようだ。私たちが進んでいる未来について圧倒的な憂鬱に苦しむか、否認の状態にとどまって別の世界へと連れていってくれるスクリーンに見入ったまま、「すべてはうまくいく」と希望的観測をしているかだ。
庭は人生を表す、おそらく最もよくできた比喩だ。だが、それはまた比喩をはるかに超える存在だ。ヴォルテールにとってそうだった。『カンディード』の出版後、晩年の20年間、彼は自分の伝えたかったメッセージを実践し、時間とエネルギーをたくさんつぎこんで土地を耕した。フランス東部のフェルネーで放棄されていた地所を手に入れ、そこで、正式なデザインのフランス式庭園を否定し、生産性のある果物と野菜の庭をつくり出した。ミツバチを飼い、何千本という木を、その多くを手ずから植えた。彼はかつてこのように書いている。「私は一生の間にただ一つ賢明なことをした。土を耕すという仕事だ。畑を耕す者は、ヨーロッパ中の文士気どりたちよりも人類により良い奉仕をする者である」。
ヴォルテールは庭を休養の場とは考えなかった。それは公共の利益になるいたって実用的な手法なのだ。「私たちは自分の庭を耕さなければならない」という言葉の意味は、生きるということは栄養豊かに育てられなければならない、また、私たちが生きている自分の人生とコミュニティと環境のきちんとした方向づけを通して最善がつくせるのだと受け入れることだ。ヴォルテールの物語からの教訓は、理想化された世界の姿を追いかけて、目の前にある問題に目をつぶってはならないというものだ。自分のまわりにあるものを最大限に活用し、何か現実にあるものに真剣に取りかからなければならない。
仮想世界と偽りの事実が溢れるこの時代に、庭は私たちを現実に引き戻してくれる。周知のもの、予想可能なものという類いの現実ではない。庭は常に私たちを驚かす。そこでは別の種類の「知る」という体験をする。感覚的で、身体的、そして自分という存在の、感情的な、精神的な、認知的な側面を刺激するものだ。この意味で、ガーデニングは古代的であると同時に現代的でもある。古代的だという理由は、脳と自然との間の進化学的適合にある。また、採集して食べることと農業の間の生き方として古代的だ。深く刻まれた場所への愛着の必要性を表現している。現代的なところは、庭が本質的に未来に目を向けるもので、庭師は常により良い未来をめざしていることだ。
「耕す」という行為は両方向に働く。内側へも外側へも向かっている。庭を耕すことは人生に対する姿勢になりうる。テクノロジーと消費がますます支配的になってきている世界では、ガーデニングはどのように生命が生み出され、維持されているのか、また、生命とはいかに壊れやすく、束の間のものかという現実を人間に直接教えてくれる。今やこれまで以上に、人間は地球の生き物だと、何よりまず思い出さなければならない時なのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
