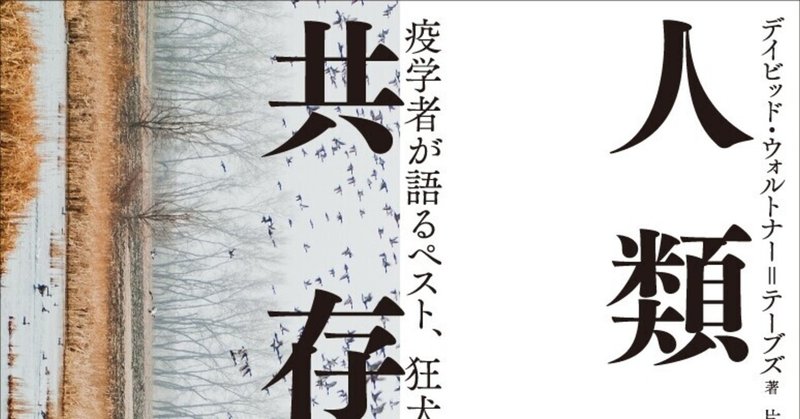
人類と感染症、共存の世紀―はじめに
感染症の世界へようこそ
1990年代後半に鳥インフルエンザが派手に登場し、さらに今世紀初頭、それ以上に衝撃的なSARS(重症急性呼吸器症候群)の騒動も冷めやらぬ中、私は本書の旧版 The Chickens Fight Back: Pandemic Panics and Deadly Diseases That Jump from Animals to Humans(ニワトリの反撃--パンデミックパニックと動物からヒトにうつる死の病)を執筆した。まったく違った形で、どちらの病気も1918年に起きたインフルエンザの世界的流行[パンデミック]の恐怖と記憶を呼び覚まし、世界中で家畜は殺処分され、空港は閉鎖され、政府はパニックを起こし、自治体の長はわめき散らし、大騒動が巻き起こった。一方、2009年と2010年に世界を席巻したインフルエンザ(初めブタインフルエンザと呼ばれ、のちにH1N1という専門的なあだ名が付けられた)のパンデミックは、半信半疑の控えめな反応を引き起こした。
2020年、私はこの新版を、新型コロナウイルスSARS-COV[サーズコブ]-2(ウイルス名)とCOVID[コービッド]-19(それが引き起こす病名)の爆発的な拡散に対処するための世界的ロックダウン(都市封鎖)の中で書いている。COVID-19は今や、長きにわたって人類史につきまとってきたパンデミック、近パンデミック、パンデミックの可能性のリストに名を連ねている。SARS、鳥インフル、ブタインフル、エボラ、腺ペストといった通称を持つこうした疾患には、いずれも共通点がある。これらは人獣共通感染症、つまり他の動物という本来の居場所から、人間に棲みつこうと飛び移ってきた病気なのだ。あるものは--ほとんどはインフルエンザウイルスだ--ニワトリやブタから人間へと直接伝わった。またあるもの、エボラ、COVID-19、SARSなどは、コウモリを起点に回り道をして、他の1、2種類の動物--たぶんハクビシン、サル、あるいはセンザンコウ--で休憩を取ってからヒトにたどり着いた。21世紀にようこそ。
SARS-COV-2の突然の発生と全世界への感染拡大は予測できた、そう言い張る者もいるかもしれないが、それは、世界のどこかで地震や火山の噴火があることが予測できるという意味で予測できる、ということにすぎない。たとえば世界の火山の4分の3以上が存在し、太平洋を取り巻く馬蹄形をした環太平洋火山帯の縁に沿って火山の噴火や地震があるだろうと予測することはできるが、正確にいつ、どこで起きるかははっきりしない。
もちろん、新興感染症に関する報告、政府関係者の説明、警告、動物を起源とする形跡のあるキメラウイルスの噂はあった。今思えば、報告に耳を傾けておけばよかったのだ。それは単なる悲憤慷慨ではなかったのだから。それは科学的研究とシミュレーションに基づいていた。だが、私たちを悩ませ続けているのは、中国の市場の凶悪なウイルスだけではない。そして集団的な混乱と否認の中で、私たちは驚いた。驚くほどのことはなかった、と言いたいところだが、「だから言ったじゃないか」式の後知恵が、慰めになったり役に立ったりしたためしを、私は知らない。
われわれのあいだでもっとも科学リテラシーの高い者ですら、王冠を戴いているとはいえ不安定なウイルス〔「コロナ」の語源はラテン語の「冠」〕にもたらされたアウトブレイクが、新しい時代の、あるいはまったく異質な時代の前ぶれですらあるのではないかと、疑いたくなるのもしかたあるまい。中には、十分な証拠に基づいて、王冠を戴く頭はいつも、いくぶん不安定であったと主張する向きもあるかもしれない。一方で、小さな出来事の影響─たとえばブラジルの蝶の羽ばたきがテキサスの嵐に及ぼす影響─を過小評価していたのはわれわれが最初ではない。私たちが信じたいと思っているよりも、世界は混沌として予測しがたいのだ。
失われた生息地と消えゆく野生動物からの顕微鏡サイズの難民の物語
2020年以前に映画や小説の中で想像されたパンデミックの多くは、ゴミが散らばる街をよろよろと歩き回る人々、全身の穴から噴き出す血、ゾンビ、数十億の死、街頭の死体などが描かれた終末論的なシナリオを含んでいた。もしかすると一部の宗教やイデオロギーの狂信者は、たいていは密かにではあるが、歴史家のウォルター・シャイデルが述べた、ありがちな神の救いとしてのパンデミックが、「旧秩序をたたき壊」して「収入と富の格差をなくす」だけの激しい衝撃を与えることを望んですらいるかもしれない。
大半の文芸作品のシナリオで想像されていなかったのは、急速に広がり、数十万の人々が感染し、ほとんど行き当たりばったりに殺すような感染症だった。もちろん、過去のパンデミックのように、COVID-19では高齢者や、がん、糖尿病、心臓病などのため免疫系がすでに圧迫されている人のほうが死に至りやすい傾向がある。だが私自身を含め多くの者が見ていて衝撃を受けるのは、働き盛りの健康な人が2人、SARS-COV-2に感染して、これといった医学的説明なしに一人は死亡し、もう一人は生き延びることだ。これはまるで、私のコロンビア人の同業者が1990年代に語った、車からの無差別銃撃だ。
だからそう、SARS-COV-2のパンデミックは予測可能だったが、本書執筆時点でロックダウン下にあるイタリア人の同業者はこう言った。「地震のときでさえ、地面が揺れている真っ最中、最初の反応(せいぜい数秒以内)は否認だ。こんなことはありえない、そんなはずはない、ここで起きるわけがない! あとで廃墟を見てさえも、まだ信じられないのだ」
私たちの大部分は20世紀の特徴である荒れ果てた風景、失われた生息地、消えゆく大型動物に気づいている。私たちは鳥やサイの絶滅を心配している。ある節足動物、ミツバチやチョウのようなものを守ろうとしながら、同時に別のものを殺そうとしている。それでも、消えゆく動物たちをすみかとする何兆というウイルス、酵母、菌類、細菌について、また、私たちがその生息地を壊して鉱山や牧場や都市にしてしまったら、こうした微生物相がどこを新しいすみかとすればいいか、もっとも環境保護意識が高い者でさえ考えることはめったにない。本書で述べる病気は、ある意味で、そうした失われた生息地と消えゆく種からの顕微鏡サイズの難民が関わっているのだ。
地球上のすべての生き物は、機能不全を起こしている一つの大家族だといえる。その中ではほとんどの細菌、ウイルス、寄生生物が有益で不可欠であり、病気には本質的に有益な役割があり、私たち自身が微生物から進化し、微生物で構成されている。私たち─厄介ですばらしい、矛盾した人類を含めたこの大家族─は、ある種の真剣な物語療法の力を借りて、問題を解決することができる。戦争は、動員、技術兵器、国家の威信、市民的自由の停止、外国人嫌悪、副次的被害を伴うため、いかに感染症と闘うかの比喩としてよく使われる。だがそれはあまりに貧困で偏狭なイメージだ。たぶん政治、いわゆる可能性の技術のほうが比喩としてふさわしい。戦争は最後の手段だ。
数千年にわたって病原体と闘い、最悪のもののいくつかを撲滅したわれわれは、病原体と交渉し、互いに必要とするものを融通しあい、形式的なちょっとした小競り合いをし、双方にそこそこ許容範囲の犠牲者を出して終わるという道さえも見いだせるかもしれない。21世紀には、われわれには共通の未来があることが、あるいはそもそも未来なんかないことがわかりつつある。だが、そうした未来のためには、今までと違う生態学をより意識した形で、私たちはみずから学ぶ必要がある。数多い課題の一つが、その学びを新しい常識、われわれが共有するこの驚くべき惑星への思いやりに満ちた、他の人々や他の生物種との連帯のようなものに変換することだ。
お互いの周辺視野に敬意を払おう
臨床神経学者のオリバー・サックスは、われわれが「周辺視野に対して、本来払うべき敬意を払っていない」と述べている。サックスは、自身の個人的経験について言っているのだが、私たちの中には、生物医学がきわめて狭い範囲に集中しながら、混乱してふらふらと落ち着かないのは、周辺視野への敬意が総体的に欠けている─どころか周辺視野を病的に喪失している─ことを反映しているのだと主張する者もいる。
もしもヒトの疾患を扱う疫学者がもっと動物の疾患について知っていれば、もしも獣医疫学者が公衆衛生当局者との対話にもっと時間を割いていれば、もしも経済学者と政治家が複雑な社会・生態学的な網の目をより意識していれば、もしも新興ビジネスの指導者がみんな破壊的な起業イノベーションの予期せぬ結果を知っていれば、もしもわれわれが、今目の前にあるものにするのと同じように、自分を取り巻く世界に関心を払えたとしたら……たぶんわれわれはCOVID-19の出現にこれほどの衝撃を受けなかったのではないか。「もしも」ばかりだが、そのいずれもただ一人の専門家、科学者、政治家によって対処できるものではない。グローバルな意味での周辺視野は、互いに気をつけ合うことを私たちに要求する。過密な21世紀において、私たちは互いの周辺視野なのだ。
私たちはみんな死ぬ。それは自然な人生の一部だ。それでも、私たちの死をもっと愉快に、あまり悲惨でないように、より人間らしいものにする方法はある。詩人のW・H・オーデンはこう言っている。地獄の標語は食うか、食われるか。天国の標語は食い、そして食われる。
私たちがこの地球を共有している動物たちとそれが運ぶ微生物を、つまり私たちが食うものと私たちを食うものを、もうほんの少し理解するなら、自分自身のこともわかり始めるかもしれない。
本書で使う病名について
最後に、アウトブレイク、エピデミック(流行)、パンデミックに関わる蝶が引き起こした専門用語の竜巻に踏み込む前に、名前について触れておかなければならない。ハリケーンの名前は批判を受け入れたが〔ハリケーンにはかつて女性の名前がつけられていたが、性差別的であるとして1979年から男女両方の名がつくようになった〕、病名はさらに問題が大きい。ものに名前をつける仕事は、17世紀の上流階級のラテン語にせよ、大衆文化にせよ、人が背負った重荷だ。この仕事は深い思慮なしに引き受けるべきではない。場合によっては、軽率な命名の結果、コウモリが棲む洞窟が見境なく爆破されたり、ハクビシンやイヌが殺処分されたりすることもあるのだ。病名にそれが最初に発見された地名(西ナイル、ラゴス、香港、アジア、ロシア、武漢など)をつけるのは、現地調査員が間に合わせにするには便利だろうが、煽動や外国人嫌悪や人種差別を助長する言葉にもなりうる。
名前は優れた公衆衛生プログラムを実行する妨げにもなりかねない。H1N1はブタインフルエンザと呼ばれていたが、一部の中東の指導者が、無理もないことだが不快感を覚え、メキシコウイルスと呼ぶことを提唱した。ウイルス学者は、どこかの平行世界の住所を示す郵便番号のような名前をつけて、ことを鎮めた。かと思えば、誰かが、無思慮にか悪意でか病気に民族、性的指向(たとえばHIVを「ゲイの病気」とするなど)、国籍、経済状況に基づくレッテルを貼った結果、多くの人々が汚名を着せられ、追放され、街頭で襲撃され、殺されてきた。本書で私は、できる限り専門的な学術用語を用い、それが使えなかったりあまりにピンとこないときにはSARS(Severe Acute Respiratory Syndrome、重症急性呼吸器症候群)のような説明的な一般名を使うことにする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
