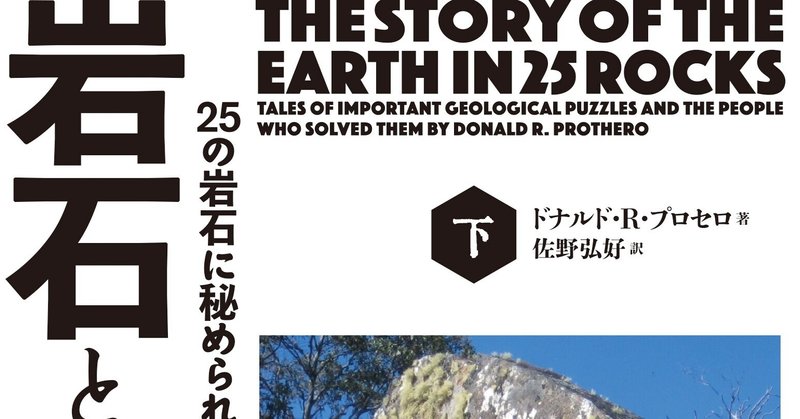
岩石と文明 下―訳者あとがき
本書『岩石と文明』は、ドナルド・R・プロセロ著"The Story of the Earth in 25 rocks" を上・下巻に分冊したものである(上巻:第1~16章、下巻:第17~25章)。地球生命の進化や多様性を記録する25種類の化石を題材にした" The Story of Life in 25 Fossils"(「化石が語る生命の歴史」シリーズ全3巻、築地書館)の姉妹書といえる。
著者のプロセロ博士は地質学と古生物学の研究と教育に長い経験をもち、専門分野で多数の論文を公表している。またこれらの分野に関する多くの教科書、普及書を出版している。例えば、地質学分野ではフレッド・シュワブ博士との共著による" Sedimentary Geology"(1996, W.H.Freeman and Company)、"California's Amazing Geology"(2016, CRC Press)など、また古生物学分野では、"Evolution"(2007, Columbia University Press)、"Bringing Fossils to Life"(1997, McGraw-Hill Science)などがある。
本書は、地球科学の一分野としての地質学の歴史を記述した一冊である。しかし、類書によく見られるような、通史的に地質学研究の発展を綴っていくという構成ではない。本書では個別の岩石、地層、露頭、自然災害、地下資源などの具体的なことがらを題材として幅広く取り上げ、その題材をめぐって、研究者がどのようにして真実に迫り、結論を得たのか、研究の発端から、進展そして結果に到達するまでの道のりが述べられている。また隕石や月の石についてのトピックスを紹介して月や太陽系の起源にも言及しており、地質学のみならず、広く地球科学研究の歴史にも踏みこんでいる。
著者は研究過程を、ジグソーパズルのピースを発見してひとつずつはめていく作業にたとえている。質のよいデータを集め、合理的な解釈を行って、地球の営みについての真理を追究するというごくオーソドックスな研究過程の結果、多数の新しい発見がもたらされてきたことは事実である。そのような地道な研究の一方で、研究者の柔軟な頭脳が発想の転換を生んで、予想もしなかった結論が劇的に訪れることもあったようだ。柔軟な発想の転換には研究者自身の資質に加えて、自由な研究環境や人的交流も大切だったに違いない。ともかく、それぞれの研究者がどのような過程を経て、大きな発見や輝かしい成果に到達したのか、読者にはこの点にも興味をもって読み進めてほしいと思う。
地質学に限らず、研究とは人間が行う行為であることは言うまでもない。したがって、研究者がおかれていた社会を抜きにして研究の歴史を語ることはできない。本書では、証拠となる事実を発見し、研究を進めた主人公としての研究者の思想や生きざま、研究成果の意義と同時に、その当時の社会や文化についても述べられている。地球科学の研究にその当時の社会のあり方や文化の潮流が影響を及ぼしていたことがわかる。地球科学の研究を切り離して考えるのではなく、社会や文化、歴史との関係を重要な要素、背景とみなしている点は、本書のたいへんユニークな視点ではないだろうか。物理学や化学などと同じく、地球科学の研究も歴史、社会、文化と無縁ではありえなかったのだ。
多くの場合、研究の道のりは決して平坦なものではなく、挫折、貧困、軍隊への召集などによる研究の中断、研究者仲間からの疎外や中傷、妨害などに加えて、政治からの弾圧や圧迫すらあった。しかし研究者たちはそれらを乗り越えて、苦労を重ねた結果、誰も想像すらしなかった輝かしい成果、すなわち地球にかかわる真理を導き出して、科学史に名を残したことが各章の記述からわかる。あとから思えばほんの些細な発見、あるいは思いもしなかった偶然の発見であっても、それを記憶の底に葬り去ることなく、すくい上げて研究し、科学史に残るような大きな業績へと発展させた事例も紹介されている。
もっとも、「観察の領域では、チャンスは準備万端の心のみを好む」という細菌学の大家ルイ・パスツールの言葉(第20章)通り、研究者は「予期せぬ偶然(セレンディピティ)」を待っていただけではないことは言うまでもない。
本書が取り上げている題材は、紀元79年のベスビオス火山の大噴火で起きた古代都市ポンペイの大惨事(第1章)に始まって、氷河期の原因や到来の周期を計算したジェームズ・クロールとミルティン・ミランコビッチ(第25章)まで、きわめて多岐に及んでいる。各章の書き出しは、トピックスに関連する岩石や重要な露頭などの紹介から始まる。最終章で解説されている有名なミランコビッチ・サイクルの場合でも、北半球各地に点在する「迷子石」――氷河が運搬してきた巨礫をまず紹介するという具合である。
本書に取り上げられている25のトピックスは幅広く、たいへん多彩である。本書を読んでとくに印象に残ったトピックスをいくつか紹介しよう。
第1章の古代ローマ帝国の都市、ポンペイを襲ったベスビオス火山のプリニー式噴火による噴煙柱の形状とその変化、ポンペイ市内に侵入した火砕流の状況、噴火中に起きた海水面の上昇、噴煙と有毒ガスに襲われ、命を落としたポンペイ市民の悲惨な最期などを、命を賭けて冷徹な目で観察し、その結果を正確な記録として残した大プリニウスとその甥、小プリニウスの行動をそれ以後の自然科学研究につながる姿勢として著者は高く評価している。
第6章で取り上げられている石炭は、18世紀半ばに始まった産業革命を推進する原動力になったエネルギー源を提供した化石燃料だ。折しも世界に先駆けて産業革命が始まった当時のイギリスには、伝統的な地質学の手法を確立したウィリアム・スミスが登場した(第7章)。スミスによる地質図と地質断面図の作成は、現在の地質学でも基本的とされる重要な研究手法である。その手法を確立するにあたっては、産業革命の進展を背景に当時のイギリスで高まった石炭の需要が、少なからず彼の研究を後押ししたことだろう。負債を抱えて収監されるという辛酸をなめながらも、野外調査を続けたスミスが「世界を変えた地質図」を完成させると同時に名誉を回復し、化石層序学の基礎を確立したのだった。
第8章では、放射性同位体による年代測定の基礎を確立したアーサー・ホームズについて述べられている。放射性同位体法を用いて岩石の数値年代測定が始まった初期に、決して恵まれていたとは言えない研究環境の中で気が遠くなるほど厳密な実験手順を繰り返して鉛同位体比の定量分析を行って、岩石の数値年代を測るという壮大なテーマに挑み、ホームズは輝かしい結果を得た。同時に彼は、地球内部には熱源となる放射性同位体が存在すると主張している。ホームズのこの考えによって、斉一説を提唱し、近代地質学の父と言われた18世紀の思弁的科学者ジェームズ・ハットン(第4、5章)が唱えた「地球は巨大な熱機関だ」という卓見が百数十年の時間を経て、ようやく実を結んだのである。
存外知られていないが、アーサー・ホームズは、アルフレッド・ウェゲナーの大陸移動説(第18章)からハリー・ヘスらが提唱した海洋底拡大説(第21、22章)、そしてプレートテクトニクス(第22、23章)へと進展する地球観の大変革に大きな役割を果たしていたのだ。ウェゲナーの大陸移動説が学界からほとんど葬り去られていた20世紀前半、ウェゲナーが説明に窮した大陸移動の原動力をホームズはマントル対流に求め、海洋底拡大説登場のきっかけをつくったことを本書から読み取ることができる。
また優れた研究には、その基礎になる多数の先行研究や同時代の共同研究が大きな助けになる場合があることも述べられている。ジョー・カーシュビンクが提唱したスノーボール・アース仮説(第16章)は、にわかには信じられないほどセンセーショナルで、たいへん魅惑的な優れた研究のひとつである。スノーボール・アース仮説としてまとめたカーシュビンクの素晴らしい才能は、本書に述べられているとおり、万人が認めるところであろう。
しかしその着想が現れる前には、ダグラス・モーソンによる決死の南極探検とオーストラリア南部での先カンブリア紀氷成堆積物の発見、W・ブライアン・ハーランドやポール・ホフマンらによる氷成堆積物を覆う石灰岩層の発見と古地磁気データなどの重要な地質学的発見があった。さらにミハイル・ブディコのアルべド・フィードバックシステムにもとづく全球気候モデリングなど地球物理学からの重要な貢献もあった。そしてカーシュビンク自身が火山活動による全球凍結状態からの脱出を提案して、画期的なスノーボール・アース仮説として実を結んだ一連の過程が本書を読むとよくわかる。研究とは決して一人の力で成し遂げられるものではないことがこの事例からも見てとれるのではないだろうか。
さて本書、とくに前半を読むと、物理学や天文学などと同様、地球科学の萌芽期でも、キリスト教会からの圧力、聖書の教義が人びとの自由な発想に対する大きな制約になっていたことがよくわかる。例えば地球の年齢についての「ノアの大洪水」説による強力な制約もその一例であろう(第4、5章)。
この説にもとづいて、地球の年齢や生命の進化などについて諸説が提案され、広い賛同を得たものもあった。これも自然科学萌芽期の一頁であった。しかし多くの研究者は宗教的な制約、呪縛から自らを解き放ち、合理性を欠いた学説に敢然と立ち向かい、自由で伸びやかな発想に立って地質学、広くは自然科学の発展に大きく寄与してきたのだ。宗教と自然科学の関係性についてあらためて考える機会を本書は提供している。現代風に言えば、「宗教」の二文字を「既存の学説、定説」に置き換えることができるだろう。
本書を読むと、社会情勢の重要な一局面である戦争と地球科学には深いかかわりがあることもわかる。銅鉱石をめぐる古代キプロス島の争奪戦(第2章)、錫箔(すずはく)で内張りされた缶の発明が軍隊の大規模な動員作戦を可能にしたこと(第3章)、第一次世界大戦中に測候所での観測要員に転属させられたアルフレッド・ウェゲナー(第18章)、またオーストリア=ハンガリー帝国によって捕らえられたミルティン・ミランコビッチ(第25章)などがその例としてあげられよう。研究者といえども戦争という大きな波に翻弄されていたことを本書から読みとることができる。
その一方で、地球科学研究者の軍事協力が実在していたこともわかる。例えば、さまざまな政治的圧力に屈せず、鉛の健康被害に警鐘を鳴らし、環境保護に全力をつくした鉛同位体比測定の大家、クレア・パターソン(第10章)が、原爆を開発したマンハッタン計画に参画していたことは驚きであった。
本書を読んで、20世紀のアメリカの地球科学研究が軍事研究と無縁ではなかったことを実感する読者もいることだろう。ただし、本書で紹介されている地球科学研究者の軍事協力がその業績、地球科学への貢献、名誉をいささかなりとも損なうものではないことを強調しておきたい。
本書は各章が独立しており、どの章からでも読み進めることができると思う。しかし、いくつかの章を読むうちに、章どうしに深いつながりがあることに読者は気づくのではないだろうか。つながりとは、地球の真理をひたすらに追究する地球科学者の情熱、飽くなき探究心だ。はるかな過去から続くわれらが地球の営みに思いをめぐらせながら、本書を楽しんでほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
