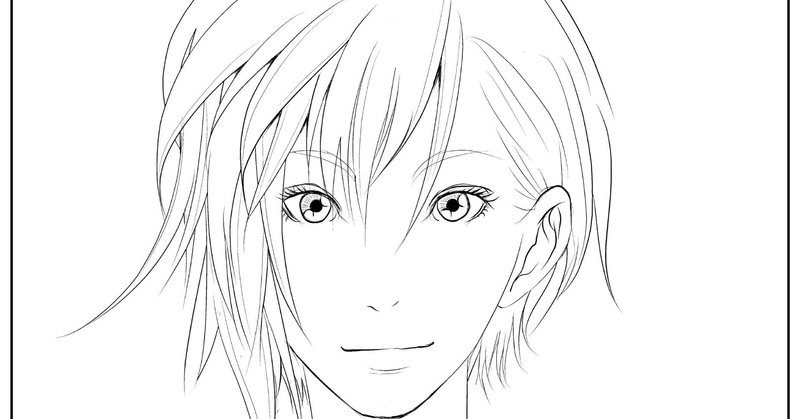
やさしい法律講座ⅴ37 副題 他人の占有物等に係る自己の財物(刑242条)の保護法益
今回は、財産罪の保護法益を本権説(所有権)と所持説(占有権)について、陥りやすいことに的を絞って解説する。
2021.2.17
さいたま市桜区
田村 司
はじめに
今回は 「他人の占有物等に係る自己の財物(刑242条)」が何を保護法益にしているかについて、本権説(所有権)と所持説(占有権)の対立がある。
民法上の物権の概要は次の通り。
本権(占有を法律上正当づける実質的な権利)
所有権(民法206条)
制限物権
用益物権
地上権(第265条)
永小作権(第270条)
地役権(民法第280条)
入会権(民法262条、民法294条)
担保物権
法定担保物権
留置権(民法第295条)
先取特権(民法第303条)
約定担保物権
質権(民法第342条)
抵当権(民法第369条)
占有権(180条) ・・・物に対する事実上支配状態(占有権)の保護を目的とする権利。
1,本権説(所有権)は
占有を裏打ちする「所有権その他正当な権利・利益」が保護法益であるとする。
2,他方の所持説(占有権)は
他人の占有等に係る自己の財物 第242条 「自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。」という規定も設けている。所有権に基づかない占有(所持している)状態その物も保護される。ここでは「所有権その他正当な権利・利益」が謳われていない。
ここに、窃盗罪の保護法益は、本権とは関わりのない占有権そのものだとする所持説(占有権)を支持する一つの根拠がある。
さらに、所持説(占有権)については、財産秩序をどのように構成するかという見地から理論づけがなされている。
すなわち、社会生活が複雑となり、権利関係が錯綜している今日では、社会生活上の財産秩序は、占有という外観上の基準をもとに構成しなければならない。
そこで、所持説は、私法上適法な占有と言えない場合でも、刑法上保護されるべき占有が認めれれると解する。
社会生活上の財産秩序が権利者らしい外観を示す占有を基礎に成り立っていることからすれば、所持説は正しい面を有している。そして、民法の占有権の規定から窺い知る事ができる。
解説・・・占有訴権制度の目的は、通説はこれを「自力救済の禁止」に求める。
現にある支配状態が仮に法的に許されないものであっても、これを裁判の手を借りずに私力で除去しようとするのは法治国家の建前上許されないから、一時的にであれ現にある事実状態を維持するという点にこの制度の存在意義があるとする。
3,民法の条文から垣間見えるもの
所有権の取得の規定は「無主物の帰属」の規定のみであり、ほとんどは占有権の規定が主であるところからも法の目指す方向が垣間見える。以下占有権に関する規定を列挙する。
(占有権の取得) 第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
解説:自分で利用したいなどで所持するだけで占有権を取得する。適正な取引によるものなどの条件は付与されていない。所持するだけで適法な権利と推定される。
(現実の引渡し及び簡易の引渡し) 第182条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
解説:占有権の譲り渡しは「物」の引渡しにより所持人が代わる。つまり占有者が代わる。これで権利の移転(権利譲渡)は完了する。
(占有の態様等に関する推定) 第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
解説:占有しているだけで正当な権利者らしきものと推定される。反証があれば、裁判で覆せる。例、盗品であることを知っていた事実(悪意)を立証。
(占有物について行使する権利の適法の推定) 第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
解説:権利者らしきもの権利行使であるから適法であろうと推定される。反証があれば裁判で覆せる。
(即時取得) 第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
解説:取引行為(売買・贈与など)
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件) 第178条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
(占有の訴え) 第197条 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
(占有保持の訴え) 第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
(占有保全の訴え) 第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
(占有回収の訴え)
第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
(本権の訴えとの関係)
第202条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
解説・・・占有の訴は、占有の事実自体につき決定されるべきもので、本権(所有権、地上権、永小作権、賃借権等)に関する理由に基づいてこれを裁判することができない。つまり、占有の訴えについては、本権に関する理由で裁判をすることが許させず、占有の侵奪や妨害や妨害の危険性のあるなしだけで裁判される。占有であれば、たとえ、本権によらない占有であってもこれを占有権として保護するという占有権制度の趣旨から当然の規定である。本権の理由で裁判したのでは、占有自体が権利として保護されないことになるからである。
占有の訴で被告として敗訴するも、本権の訴で勝訴することが出来よう。
所有権の取得の規定は(無主物の帰属) 第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
(占有権の消滅事由) 第203条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
しかし、「被害者による自己の物の奪い返し」のように正当な権利者が不法占有者から財物を取り戻す場合については、検討の余地あり。これは窃盗の被害から数日経過して被害者が取り戻すような場合である。というのは窃盗の現場で、被害者が奪い返すのは当然の権利(正当防衛)として認められるからである。
さて、窃盗の被害者が自己の物を奪い返す場合に不法占有者の占有を保護して、被害者を窃盗罪に問うのは不合理である。刑法がこのような場合も含めてあらゆる事実上の占有を保護するとすれば私法関係に対する過度の刑罰権の介入になるとともに一般国民の健全な正義観念に反することになる。そこで窃盗罪やその他の財産犯罪において保護される占有は、いわば単なる占有ではなく、仮に本権に基づかないとしても、一応の理由のある、外観上平穏な占有ということになる。(船山氏p287~288)
吾輩の考えとしては、我が国の刑法は自力救済を認めず、「外観上平穏な占有」に保護法益があると規定する。正当防衛や緊急避難に通わせてこの機会を逃したら困るという限定的な範囲で違法性阻却を認めるべきである。
4,刑法242条の「他人の占有等に係る自己の財物」について「他人の財物とみなす」の解釈
本権説:242条は自己所有物の特例を定めた例外規定であって、そこにいう他人の「占有」とは、権限による占有、すなわち適法な原因に基づいてその物を占有する権利(本権)のある者の占有だけを意味している。
占有説:242条は他人の占有それ自体の保護を示す注意規定であり、ここにいう「占有」は占有一般を意味し、占有が適法か否かは客体の要保護性と関係が無い。
○修正本権説
小野清一郎先生(元東京大学名誉教授、故人)
→刑法242条の「占有」は、一応理由のある占有、その意味で適法な占有であることを必要とするが、必ずしも実体的な権利 (本権)に基づく占有であることを要しない
団藤重光先生(元東京大学名誉教授、元最高裁判事、行為無価値論の巨頭)
→窃盗罪の保護法益を「所有権のほかに、占有の基礎となっている本権及び占有の裏付けとなっている法律的―経済的見地における財産的利益」
平野龍一先生(元東京大学名誉教授、元総長、結果無価値論の巨頭)
→一応平穏と思われる占有のみを保護(平穏占有説)
*近時の判例の事案は、本権説の側からも理解が全く不可能とは言えないこと、また、すべての占有を刑法的保護の対象とするのは妥当ではないから、平穏占有説が有力である。
5,行為者が窃盗犯人から盗品を取り戻す行為
(修正)本権説:被害者の占有は最初から行為者の意思に反した無権原・不適法な占有であって、およそ正当な権利者である行為者の所有権に対抗することはできず、仮に窃盗罪の構成要件該当性を認めるとしても、その行為は自救行為を援用するまでも無く適法と解せられる。
→なお、平穏占有説では、窃盗犯人の占有が行為者との関係では平穏でないとして窃盗罪の成立を否定する。
占有説:それが自救行為(権利を侵害された者がその回復について国家機関による法的救済に待つときは回復が不可能又は困難となる場合に、自力でその権利の救済を図ること)の要件を満たさない限り、窃盗罪を構成する。
刑法学においては、法益の帰属主体(誰がその法益の持ち主か)に着目して、個人的法益、社会的法益及び国家的法益に三分するのが通例である。この分類も、その法令の解釈や適用の指針とすることを目的とする。
(窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪) 第235条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
(強盗) 第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項とする。
(横領) 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
(業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領) 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
解説:これがネコババというものです。占有離脱物横領とも言います。
参考文献
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
