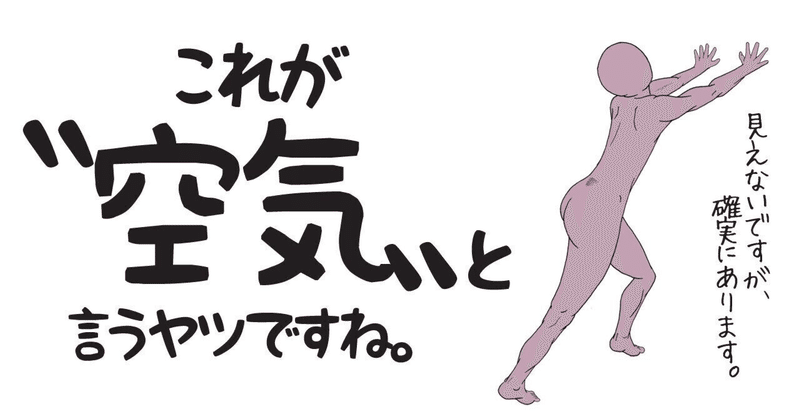
通級がハマる子ハマらない子
正直、通級とは微妙な制度だとつくづく思う。
なんといっても自治体で運用が相当異なる。
人手も予算もばらばらだから、しょうがない。
東京はたぶん、予算もつぎ込んでいるし、制度をつくったえらい人もチェックしやすいみたいで、現場が「ルール通り」かどうかかなり厳しく見られる。
しかし発達期の子どもたちがルール通りであるはずがない。
基本的に〇年で退級、とかいうけど来年その子がどうなってるかなんて誰がわかるというのさ。
というわけで前提としてはいろいろアレなところばかりなのだが、
それを言っても始まらないので片目をつぶる。
というか両目つぶって片方だけ薄目をあけてる、みたいな感じ?
本当に学校という場所は、それくらいじゃないと気を確かに保てないと思う。
それでも通級という制度が合っていて、
あるいはタイミングや人材がフィットして、
結果としてとてもうまくいく子もいるのだ。
単純に、通常級よりはだいぶコンパクトで一度にいる人数が少ない。
わたしが見た中では小学校の小集団活動でも子ども5人、大人4人が最大だった。
個別指導だと1対1だから、まず思ったことを言うハードルが低い。
だいたい通級指導の先生は優しくて、どんなことを言ってもちゃんと受けとめようとしてくれる人が多い。
いやもちろん強めのしゃべりの先生もいるけど、基本はコミュニケーションはかなり取りやすい。
「個別指導」で特性にも配慮することが決まっており、特に高学年や中学生ともなると意思決定を自分でするサポートも含まれるので、とにかく考えを聞こうとはしてくれる。
もちろん、それでも自分の考えを言いづらいっていう子もいる。
そもそも、なんで思ってることを「言わされ」なきゃいけないのか、と感じている子もいるだろう。
通級に通っている目的を、本人が納得しきれていないこともあるということでもある。
通級をネガティブに思っている子もいる。
それは、学校の雰囲気の問題でもあるし、保護者の感覚かもしれない。
まあほとんどの場合、大人の説明がダメなことが多いのだが、
子どもたちの間の同町圧力もけっこう強いこともあるからなあ。
ただ、そういう「感覚」、「困り感」と「人からどう見られるかの不安」の葛藤、みたいなものは、成長の過程で変化するものなので、やはりタイミングがとても重要ということは言える。
どんな子でも、タイミングが合えばハマる。
周りの大人は、あきらめず細く長くその子のタイミングを待ってあげたいものだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
