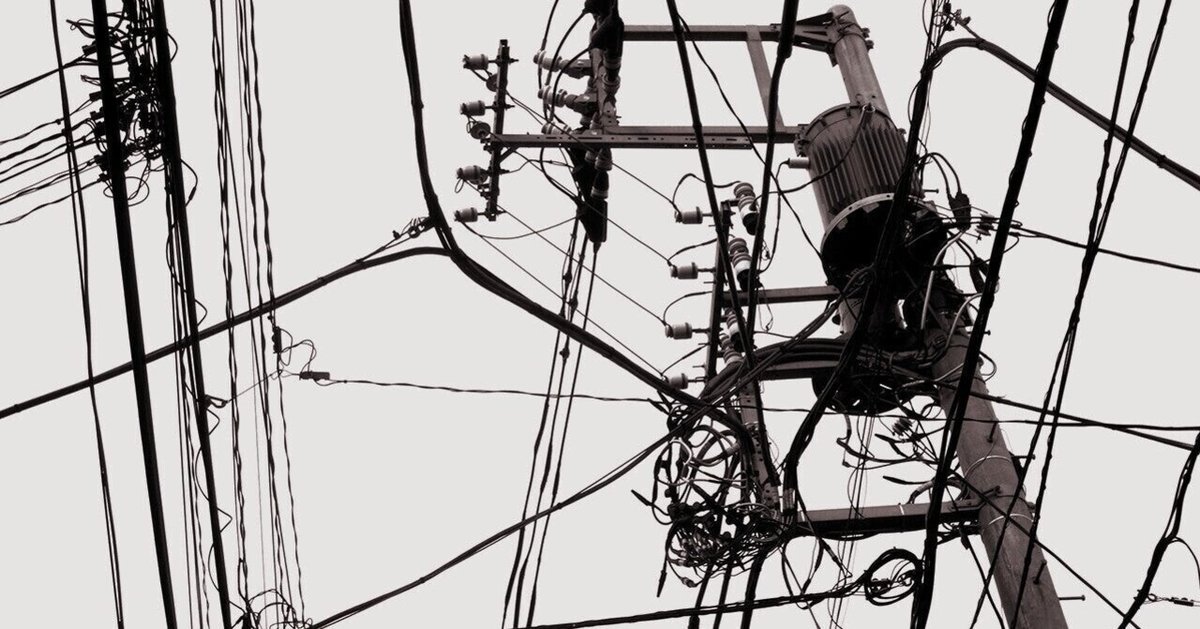
聾学校の「養訓」は何を勉強する時間なのか分からなかった。道徳や学活と同じような位置づけで私にはそれらの区別はなかった。
聾学校には「養訓(ようくん)」という教科があった。養護訓練の略で、週に3コマくらい入っていたように思う。小学部にあがったとき、時間割は平仮名「ようくん」であり、「こくご」や「さんすう」と同じようにそういう科目があるのだと思っていた。学年があがり、時間割は漢字の「養訓」になっていった。それと前後して、近隣の小学校との交流授業があり、時間割には「養訓」がないことに気付いた。養訓は聾学校だけなんだなと思った。そして、養訓は養護訓練の略だということもどこかで分かっていた。だから一般学校では「養護訓練」がないのも道理かと思っていた。私たちは、耳が聞こえないから「養護」的な「訓練」を受ける必要があるんだと思っていた。
養護訓練とは、聾学校でいえば、発音指導、日本語読み書き指導などがあたるだろう。
小1,2の頃は確かに、時間割通りに、養訓の時間で、発音の練習をした記憶がある。しかし毎回発音の練習でもなかった気もする。発音練習では、「h」「s」「k」といった子音ごとに舌の位置はどうか開く口の形はどうかという口腔内の断面イラストの画像を使っていた。それはカレンダーのようにめくるものであり、教室の黒板左横の壁に紐でかけられていた。先生はその絵を黒板にマグネットで貼り、それを指さしながら、舌の位置、歯の閉じ方、息の吐き方を私たちに説明するのであった。先生は、50代の男性であった。その時にはまだ発音の練習が嫌だという感覚はなかった。まだ自身の発音のことを自覚できていなかったからだ。
そのような発音練習は、小3になったあたりからなくなっていったように思う。口腔内の断面イラストのカレンダーみたいなのも次第に見かけなくなったような気がする。しかし、私は次第に自分の発音の悪さに気づき始めていった。発音練習はなくなったが、発音の指摘をされることは時々あった。それは養訓の時間ではなく、予期せぬところで出てきた。
指摘をする先生は、ほとんどの場合、穏やかにそれを指摘した。それは平穏な日常のなかで、時折顔を出すトゲであった。トゲが刺さるたび、それはしばらくの間抜けないのであった。トゲだと思っているのは、私だけであった。
学活も道徳も養訓も、同じような時間だった。その区別は私たちにはなかった。何をするのかわからない時間。
それらの時間では、年度初めや学期始めでは、学級目標や個人目標を話し合って立てた。運動会や学芸会、卒業式などの行事が近づけば、練習時間に最優先であてられる時間だった。修学旅行前では行先下調べをする時間になり、卒業前には文集作成の時間になった。それらの時期を除いては、自分たちが自分でやりたいことを提案し、それを行うことができた。小学高学年のときは、みんなでトランプをすることもあった。トランプをみんなでやるのはとても楽しかった。しかしその時間は、学活か道徳か養訓だったかは、しかと思い出せない。
小学校高学年から、私は養訓の存在を疎ましく感じるようになった。養訓がなければもっと勉強ができるのではないか、ただでさえ遅い勉強が養訓のせいで授業時間が削られてしまう、と思っていた。トランプなどをするのは大好きだったが、道徳と学活で十分ではないかとも思っていた。
おそらく先生たちも、養訓では何をすればいいのかわからなかったのかもしれない。道徳と同じように。先生による裁量が大きすぎた。
聾学校卒業後進学した高校では、予想通り養訓はなかった。クラス時間割をみて、私はなんだか嬉しかった。道徳もなかった。学活は「HR」という名前だったかもしれないが、何をしたかはさっぱり覚えていない。
養護訓練は無くなり「自立活動」に変わっている、と知ったのは、私が聾学校を卒業しておよそ10年後のことであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
