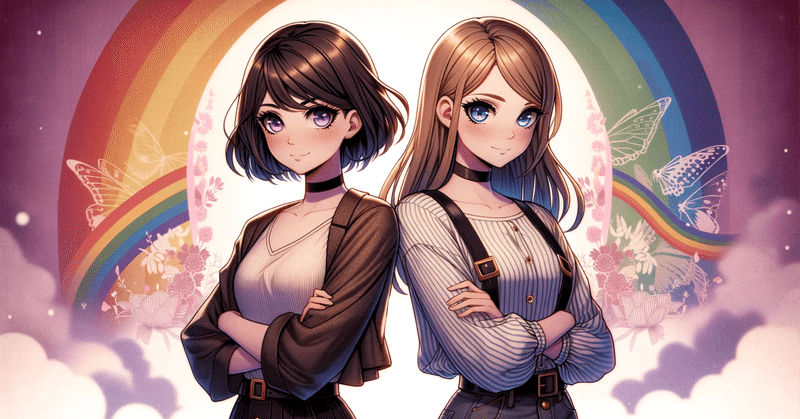
性別変更事件
こんにちは。
今日は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づく性別の変更が問題となった3つの事件(最決平成31年1月23日と、最決令和3年11月30日、最大決令和5年10月25日)を紹介したいと思います。
1 性別の変更をめぐる事件
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項には、以下のように、性別の変更の審判に関する規定が置かれています。
【性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項】
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 18歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
平成31年と令和5年の事件では、生物学的な性別は男性であるが、心理的には女性である申立人が、特例法3条1項に基づいて、性別の取扱いの変更の審判を申立てました。ところが、性別の変更には、生殖腺除去手術を受ける必要があったため、その申立が却下されました。そのため、申立人は、特例法3条1項4号は、身体への侵襲を受けない権利を規定する憲法13条と平等権を定めた憲法14条に違反し、無効であると主張しました。
また、令和3年の別の事件では、身体は男性でありながら、自認する性は女性であった申立人が女性と結婚し、長女をもうけました。その後に、申立人は離婚し、性別適合手術を受けた後に性別変更の申立をしようとしたところ、長女が未成年の子であったことから、申立が却下されました。そのため、特例法3条1項3号の要件が憲法13条に違反していると主張しました。
2 平成31年最高裁判所の決定
性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の規定の下では、性同一性障害者が当該審判を受けることを望む場合には一般的には生殖腺除去手術を受けていなければならないこととなる。本件規定は、性同一性障害者一般に対して上記手術を受けること自体を強制するものではないが、性同一性障害者によっては、上記手術まで望まないのに当該審判を受けるためやむなく上記手術を受けることもあり得るところであって、その意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約する面もあることは否定できない。もっとも、本件規定は、当該審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば、親子関係等に関わる問題が生じ、社会に混乱を生じさせかねないことや、長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける等の配慮に基づくものと解される。これらの配慮の必要性、方法の相当性等は、性自認に従った性別の取扱いや家族制度の理解に関する社会的状況の変化等に応じて変わり得るものであり、このような規定の憲法適合性については不断の検討を要するものというべきであるが、本件規定の目的、上記の制約の態様、現在の社会的状況等を総合的に較量(きょうりょう)すると、本件規定は、現時点では、憲法13条、14条1項に違反するものとはいえない。このように解すべきことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかというべきである。論旨は採用することができない。
よって、申立人の抗告を棄却する。
3 令和3年最高裁判所の決定
性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に未成年の子がいないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号の規定が憲法13条、14条1項に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである。論旨は理由がない。
よって、申立人の抗告を棄却する。
4 令和5年の最高裁判所大法廷決定
性同一性障害とは、生物学的な性別と心理的な性別が不一致である状態をいい、医学的な観点からの治療を要するものである。今日では、心理的な性別は自己の意思によって左右することができないとの理解の下に、心理的な 性別を生物学的な性別に合わせることを目的とする治療は行われておらず、性同一性障害を有する者の社会適応度を高めて生活の質を向上させることを目的として精神科領域の治療や身体的治療が行われている。
性同一性障害を有する者については、治療を受けるなどして、性自認に従って社会生活を送るようになっても、法令の規定の適用の前提となる戸籍上の性別が生物学的な性別によっているために、就職等の場面で性同一性障害を有することを明らかにせざるを得ない状況が生じたり、性自認に従った社会生活上の取扱いを受けられなかったりするなどの社会的な不利益を受けているとされている。
性同一性障害については、上記のとおり、性同一性障害を有する者の生活の質の向上を目的とした治療が行われているところ、特例法が制定された平成15年7月当時は、日本精神神経学会の定めた「性同一性障害に関する診断と治療のガイ ドライン」第2版に沿って、いわゆる段 階的治療という考え方に基づく治療が行われていた。段階的治療とは、原則として、第1段階では精神的サポート等の精神科領域の治療を行い、次に身体的治療として、第2段階ではホルモン療法ないし乳房切除術を、第3段階では性別適合手術 を行うという3段階の手順を踏んで治療を進める考え方であり、性別適合手術は、第2段階を経てもなお自己の生物学的な性別による身体的特徴に対する強い不快感又は嫌悪感が持続し、社会生活上の不都合を感じている者に対する最終段階の治療とされていた。なお、第1段階及び第2段階の各治療は必ずしも次の段階に移行することにより終了する ものではなく、精神科領域の治療やホルモン療法は第3段階を経た後も継続するものとして予定されていた。 また、ガイドライン第2版においては、第3段階を経た性同一性障害を有する者について、法的性別の変更がされなければ、社会生活上大きな障害になるものとされていた。
国会での審議における法案の提出理由等からすると、特例法は、性同一性障害が世界保健機関の策定に係るICD(国際疾病分類)第10回改訂版等にも掲載された医学的疾患であるとの理解を前提として、性同一性障害を有する者が、段階的治療の第3段階を経ることにより医学的に必要な治療を受けた上で、自己の性自認に従って社会生活を営んでいるにもかかわらず、法的性別が生物学的な性別のままであることにより社会生活上の様々な問題を抱えている状況にあることに鑑み、一定の要件を満たすことで性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることを可能にし、治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するために制定されたものと解される。
特例法には、その立案段階における議論を踏まえ、附則において、性別変更審判を受けることができる性同一性障害者の範囲等については、特例法の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする旨の規定が置かれた。そして、特例法3条1項3号は、特例法の制定時には「現に子がいないこと。」 と規定されていたが、平成20年法律第70号による改正によって、「現に未成年の子がいないこと。」に改められた。
性同一性障害の治療は、特例法の制定当時は段階的治療という考え方に基づいていたところ、その後、臨床経験を踏まえた専門的な検討等を経てガイドラインの見直しがされ、平成18年1月に提示された第3版では、性同一性障害を有する者の示す症状は多様であり、どのような身体的治療が必要であるかは患者によって異なるとして、段階的治療という考え方は採られなくなった。具体的には、性同一性障害を有する者について、まず精神科領域の治療を行うことは異ならないものの、身体的治療を要する場合には、ホルモン療法、乳房切除術、生殖腺除去手術、外性器の除去術又は外性器の形成術等のいずれか、あるいは、その全てをどのような順序でも選択できるものと改められた。
ICD第10回改訂版において、性同一性障害は「精神および行動の障害」の一つに分類されていた。その後、「障害」との位置付けは不適切であるとの指摘がされたため、2019年(令和元年)5月に承認された第11回改訂版において、性同一性障害は「性の健康に関する状態」に分類されるようになり、それに伴い名称が「性同一性障害」から「性別不合」に変更された。性同一性障害を有する者を取り巻く社会状況等平成16年7月の特例法の施行から現在までに、1万人を超える者が性別変更審判を受けるに至っている。 この間、国においては、法務省が、平成16年以降、性同一性障害を理由とする偏見等の解消を掲げて人権啓発活動を行い、文部科学省は、平成22年以降、学校教育の現場において性同一性障害を有する児童生徒の心情等に十分配慮した対応がされるよう、各教育委員会等にその旨を要請する通知を発出したり、教職員向けのマニュアルの作成、配布を行ったりしており、厚生労働省も、平成28年、労働者を募集する際の採用選考の基準において性的マイノリティを排除しないよう事業主に求めるなどの取組をしてきた。令和5年6月には、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的として、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が制定された。また、地方公共団体においては、平成25年に、東京都文京区で性自認等を理由とする差別的な取扱いその他の性別に起因する人権侵害を行ってはならない旨の条項を含む条例が制定されて以降、相当数の地方公共団体の条例において同趣旨の条項が設けられている。さらに、一般社団法人日本経済団体連合会は、平成29年、企業において、性同一性障害を有する者を含むいわゆるLGBTへの適切な理解を促し、その存在を受容することに向けた取組を行っていくことが急務である旨の提言をしたほか、令和2年以降、一部の女子大学において法的性別は男性であるが心理的な性別は女性である学生が受け入れられるなどしている。また、特例法の制定当時、法令上の性別の取扱いを変更するための手続を設けている国の大多数は、生殖能力の喪失を上記の変更のための要件としていたが、その後、生殖能力の喪失を要件とすることについて、2014年(平成26年)に世界保健機関等が反対する旨の共同声明を発し、また、2017年(平成29年)に欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反する旨の判決をしたことなどから、現在では、 欧米諸国を中心に、生殖能力の喪失を要件としない国が増加し、相当数に及んでいる。
以上を踏まえ、本件規定の憲法13条適合性について検討する。 憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているところ、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利として、同条によって保障されていることは明らかである。 生殖腺除去手術は、精巣又は卵巣を摘出する手術であり、生命又は身体に対する危険を伴い不可逆的な結果をもたらす身体への強度な侵襲であるから、このような生殖腺除去手術を受けることが強制される場合には、身体への侵襲を受けない自由に対する重大な制約に当たるというべきである。ところで、本件規定は、性同一性障害を有する者のうち自らの選択により性別変更審判を求める者について、原則として生殖腺除去手術を受けることを前提とする要件を課すにとどまるものであり、性同一性障害を有する者一般に対して同手術を受けることを直接的に強制するものではない。しかしながら、本件規定は、性同一 性障害の治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対しても、性別変更審判を受けるためには、原則として同手術を受けることを要求するものということができる。 他方で、性同一性障害者がその性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることは、法的性別が社会生活上の多様な場面において個人の基本的な属性の一つとして取り扱われており、性同一性障害を有する者の置かれた状況が既にみたとおりのものであることに鑑みると、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益というべきである。このことは、性同一性障害者が治療として生殖腺除去手術を受けることを要するか否かにより異なるものではない。 そうすると、本件規定は、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対して、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を実現するために、同手術を受けることを余儀なくさせるという点において、身体への侵襲を受けない自由を制約するものということができ、このような制約は、性同一性障害を有する者一般に対して生殖腺除去手術を受けることを直接的に強制するものではないことを考慮しても、身体への侵襲を受けない自由の重要性に照らし、必要かつ合理的なものということができない限り、許されないというべきである。 そして、本件規定が必要かつ合理的な制約を課すものとして憲法13条に適合するか否かについては、本件規定の目的のために制約が必要とされる程度と、制約される自由の内容及び性質、具体的な制約の態様及び程度等を較量(きょうりょう)して判断されるべ きものと解するのが相当である。そこで、本件規定の目的についてみると、本件規定は、性別変更審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば、親子関係等に関わる問題が生じ、社会に混乱を生じさせかねないこと、長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける必要があること等の配慮に基づくものと解される。 しかしながら、性同一性障害を有する者は社会全体からみれば少数である上、性別変更審判を求める者の中には、自己の生物学的な性別による身体的特徴に対する不快感等を解消するために治療として生殖腺除去手術を受ける者も相当数存在することに加え、生来の生殖機能により子をもうけること自体に抵抗感を有する者も少なくないと思われることからすると、本件規定がなかったとしても、生殖腺除去手術を受けずに性別変更審判を受けた者が子をもうけることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれなことであると考えられる。また、上記の親子関係等に関わる問題のうち、法律上の親子関係の成否や戸籍への記載方法等の問題は、法令の解釈、立法措置等により解決を図ることが可能なものである。性別変更審判を受けた者が変更前の性別の生殖機能により子をもうけると、「女である父」 や「男である母」が存在するという事態が生じ得るところ、そもそも平成20年改正により、成年の子がいる性同一性障害者が性別変更審判を受けた場合には、「女である父」や「男である母」の存在が肯認されることとなったが、現在までの間に、このことにより親子関係等に関わる混乱が社会に生じたとはうかがわれない。これに加えて、特例法の施行から約19年が経過し、これまでに1万人を超える者が性別変更審判を受けるに至っている中で、性同一性障害を有する者に関する理解が広まりつつあり、その社会生活上の問題を解消するための環境整備に向けた取組等も社会の様々な領域において行われていることからすると、上記の事態が生じ得ることが社会全体にとって予期せぬ急激な変化に当たるとまではいい難い。以上検討したところによれば、特例法の制定当時に考慮されていた本件規定による制約の必要性は、その前提となる諸事情の変化により低減しているというべきである。 次に、特例法の制定以降の医学的知見の進展を踏まえつつ、本件規定による具体的な制約の態様及び程度等をみることとする。 特例法の制定趣旨は、性同一性障害に対する必要な治療を受けていたとしてもなお法的性別が生物学的な性別のままであることにより社会生活上の問題を抱えている者について、性別変更審判をすることにより治療の効果を高め、社会的な不利益を解消することにあると解されるところ、その制定当時、生殖腺除去手術を含む性 別適合手術は段階的治療における最終段階の治療として位置付けられていたことからすれば、性別変更審判を求める者について生殖腺除去手術を受けたことを前提とする要件を課すことは、性同一性障害についての必要な治療を受けた者を対象とする点で医学的にも合理的関連性を有するものであったということができる。しかしながら、特例法の制定後、性同一性障害に対する医学的知見が進展し、性同一性障害を有する者の示す症状及びこれに対する治療の在り方の多様性に関する認識が一般化して段階的治療という考え方が採られなくなり、性同一性障害に対する治療として、どのような身体的治療を必要とするかは患者によって異なるものとされたこ とにより、必要な治療を受けたか否かは性別適合手術を受けたか否かによって決まるものではなくなり、上記要件を課すことは、医学的にみて合理的関連性を欠くに至っているといわざるを得ない。 そして、本件規定による身体への侵襲を受けない自由に対する制約は、上記のような医学的知見の進展に伴い、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖 腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになったということができる。また、前記の本件規定の目的を達成するために、このような医学的にみて合理的関連性を欠く制約を課すことは、生殖能力の喪失を法令上の性別の取扱いを変更するための要件としない国が増加していることをも考慮すると、制約として過剰になっているというべきである。 そうすると、本件規定は、上記のような二者択一を迫るという態様により過剰な制約を課すものであるから、本件規定による制約の程度は重大なものというべきである。 以上を踏まえると、本件規定による身体への侵襲を受けない自由の制約については、現時点において、その必要性が低減しており、その程度が重大なものとなっていることなどを総合的に較量(きょうりょう)すれば、必要かつ合理的なものということはできない。 よって、本件規定は憲法13条に違反するものというべきである。これと異なる結論を採る最高裁平成31年1月23日 第二小法廷決は変更することとする。
以上によれば、本件規定は憲法13条に違反し無効であるところ、これと異なる見解の下に本件申立てを却下した原審の判断は、同条の解釈を誤ったものである。 論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、その余の抗告理由について判断するまでもなく、原決定は破棄を免れない。そして、原審の判断していない5号規定に関する抗告人の主張について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
6 今後の性別変更の取扱い
今回のケースを通じて裁判所は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号にいう性別適合手術が、生命又は身体に対する危険を伴い不可逆的な結果をもたらす身体への強度な侵襲であることから、憲法13条に違反するとしました。
最決平成31年1月23日は、最大決令和5年10月25日によって変更され、戦後12件目の違憲判断となりました。引き続き、特例法3条1項3号の「未成年の子がいないこと」の要件をめぐる問題も含めて、今後の国会の動きについて注目していきたいと思います。
では、今日はこの辺で、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
