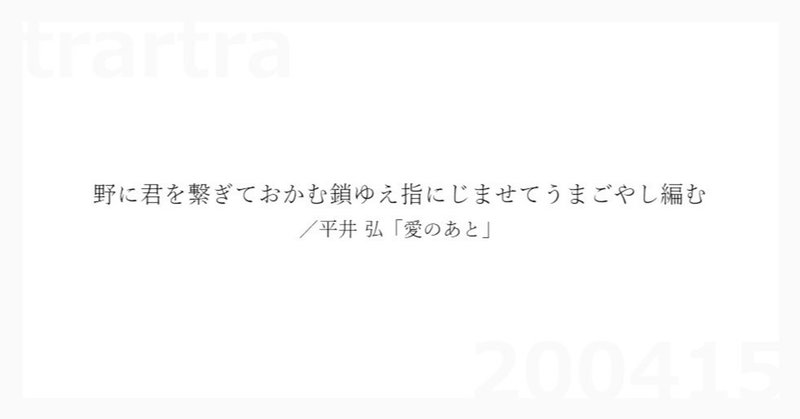
指にじませて/5分で読める現代短歌07
野に君を繋ぎておかむ鎖ゆえ指にじませてうまごやし編む
/平井 弘
ここでの〈うまごやし〉とは、おそらくはシロツメクサ, クローバーのこと。全体をそのまま牧草・肥料とするため、その名がつけられた。
下句〈うまごやし編む〉のとおり、主体はシロツメクサで〈鎖〉を編んでいる。その鎖はいずれ花冠になるのかもしれない。くさはらに座り込んで、周囲のちいさなシロツメクサのひとすじずつを丁寧にちぎり、編んでつなげてゆく。細くとも確かに植物であるシロツメクサの茎をちぎれば、汁が出るだろう。嗅げば青臭いのかもしれない。何本も何本も摘むうちに、主体の指にはうまごやしの汁がにじんでゆく。
否、ここでにじんでゆくのは〈君を繋ぎておかむ〉とする主体の心寄せもだろう。繋いでおくために、何本ものシロツメクサを摘んで鎖を編む、その意志。ある束縛心。うまごやしに〈繋ぎておかむ〉とする意志を託し、なおも収まらず指先がにじんでゆく。
ただし、ここでの記述があくまでも〈指にじませてうまごやし編む〉の語順であることには注意したい。実際の事象として“にじんだ指”は〈うまごやし編む〉ことによる副次的な結果なのだが、主体の意識はむしろ〈指にじませて〉の能動性を確立している。編んでいると指がにじんだ……という受け身ではない。自身が、指をにじませて、鎖を編むのだという意志である。もちろん短歌定型の要求への応答でもあるのだが、そこに操作≒作者の手つきを感じさせないことこそ、秀作が秀作足りうる要素だろう。
野に君を繋ぎておかむ鎖ゆえ指にじませてうまごやし編む
主体にとって〈指にじませて〉まで編む理由は、その鎖が〈野に君を繋ぎておかむ〉ための鎖だからだ。その機能こそが、その鎖の価値なのだ。君を繋いでおくそのために、主体は指をにじませる。決して、繋いでおけると約束されるわけではないのに。〈指にじませて〉からは、主体が本気でこの鎖によって〈君を繋ぎて〉おけるとは考えていないであろうことが、わたしには感じられる。しかし、言い捨ててしまえば無意味であるこの自己暗示、そのような鎖としてのシロツメクサたちへ捧げる自己犠牲、機能への献身が確かにある。ややもすると自己憐憫的にすらなりうる、この四句が唯一の身体に即したディティールだ。
この歌において、〈君〉は〈野〉すなわちこの世, 俗世的なるものから離れてゆく存在として認知される。病や戦争などで死が身近にあるのかもしれないし、いわゆる浮世離れしている性格のひとなのかもしれない。あるいは、主体自身が引き留めておくことの難しい恋人なのかもしれない。
一首単体では詳細まで読み取ることはできないが、いずれにせよ〈君〉は主体の認識において身体性の伴わない存在として扱われる。シロツメクサで編んだ鎖によって繋ぐことを望むような存在である。おそらくは、鋼鉄の鎖や牢を用意しても留めることはできないだろう。それらは身体的《君》への束縛であり、野に足のつかない〈君〉には無意味だ。身体を離れた、清浄な精神としての〈君〉をこそ繋ぎ留めたい。そのように考える主体が、まさに〈野〉からうまごやしを摘んで鎖を編む。主体に触れられない、その指をにじませて鎖を編む。
むしろ主体は、〈指にじませて〉編むことによってこそ〈野に君を繋ぎておかむ鎖〉たりうる、と考えている節すらある。まったく身勝手な思い込みである。しかし往々にして一方的な宣言、誓約がちからを持つことはあるだろう。相手の気持ちを強力に推し量るべくひとが花びらで占うように、野のシロツメクサをひとつずつちぎるたび主体は鎖の機能を強化する。その代わりに指をにじませる、というちぎりである。
君の身体ではない、こころやいのちを私の地平につなぎとめるため、主体は身体をつかって草花の鎖を編む。その逆転のなかで、〈繋ぎておかむ〉とする意志だけは、指先からにじみだしている。
野に君を繋ぎておかむ鎖ゆえ指にじませてうまごやし編む
/平井 弘「愛のあと」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
