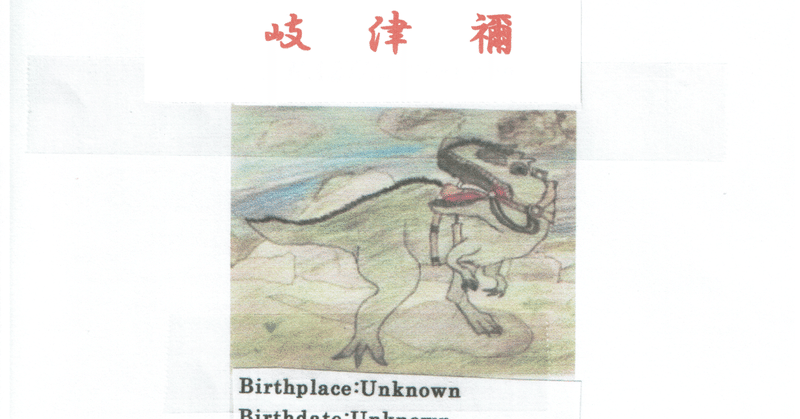
「岐津禰」No.4
4,
度部は、近くに可愛い女の子が引っ越してきて、それが嬉しくてならない子供のように心が弾んだ。一日の始まりが待ち遠しく、一日が楽しくて仕方なかった。
勤務を終え、特にその方面に用事もないのに、わざわざ島の全周の半分の距離を、自転車で遠回りして、吉津祥子の家を遠目に見ながら官舎に帰るのが習慣になっていた。
通り掛かりに、庭に出て洗濯物を取り込む姿が見えたりすると、なにか覗き見がバレたように気恥かしくなり、何かの陰に隠れたりした。
また時に、庭に出て吉津祥子は、近所の母子と立ち話している姿も見掛けた。母親はザルに載せた干物を女に渡し、娘の方を見て話す声が風に乗って聞こえてきた、
「ほんとうに、ありがとうございます、こんな島の中、この子、裁縫の一つ、お茶の一つも習いたくても、そんなこと誰も教えてくれるひとがいない、と文句ばっかり云っていたのに、吉津さんが来てから、もう毎日、今日こんなこと教えて貰った、と喜んでばかりで。
今度、もうすぐ祭りの時にでも、うちに来て貰って、うんとご馳走してお礼しようと話しているんです」
こんな、南方の、大海原にぽつんと浮かぶ小さな島、雨が降れば、風が吹けば、それはまるで嵐の襲来を受けたように、激しく降り、そして激しく吹き荒れる。
度部は、官舎の部屋に居て、吉津祥子の無事が気に成って仕方なく、雨合羽を着込み、自転車に跨いで、女の家の近くまで走って安全を確認し、暫し、雨戸から漏れる電灯の灯りを見守っていたりした。
度部は、正しく思春期の真っ只中の少年のように、四六時中、吉津祥子のことを想って過ごした。
そんな折、島に海上自衛隊の一小隊が、訓練の為、島に駐留することになった。
警察署員は、駐留する自衛隊員の安全と、住民との諍いを防止することに専念するため、全警官がその任務につくことになった。
だがそんな心配はすぐに必要なくなった。島民は元から穏やかで、自衛隊員はよく規律を守って行動していた。
島には、一軒だけ小料理屋が在った。だが店には、直角に曲った親指の先を、注いだ盃に無神経に漬けて出す婆さんと、丸い鼻、鼻の穴の空向いた、それもかなりの高齢の女が切り盛りしていた。が、これでは、若い自衛隊員の慰労には何の役にも立つまいと、そして村長は、自衛隊駐留を村の繁栄のために今後もこの島で継続して貰う為には、と、どこであの女のことを聞きつけたか、吉津祥子に頼んで店に出て貰うようになった。
それまで店に寄りつこうともしなかった隊員たちはその日を境に、客が入り切れなくて入口で喧嘩沙汰になる程に、我先にと店に雪崩れ込む程に繁盛した。そして余りの繁盛ぶりに、元の経営者は疲れ果てて入院した。以後、店は吉津祥子が切り盛りすることになった。吉津祥子は、店の名前を「キツネ」に換えた。
度部は、若い隊員らが押し寄せる前に、「キツネ」に先に入り、入口で、席の空くのを待つ隊員らの列を無視して、ちびりちびりと盃を口に傾け、註文した焼き魚も、箸の先で小さく一口分抓んで口に入れ、ゆるりと噛み砕き、俺は常連客、吉津祥子には特別の客だと云わんばかりに長居を決め込む。
酔った若い隊員らは吉津祥子に何かと絡み、しかし適当にあしらわれ、いなされて大喜びし、互いのドジっぷりを貶し合って大笑いする。
しかし、度部にはそんな店の賑わいに馴染めなかった。まず第一に吉津祥子を大笑いさせるような洒落た話の持ち合わせは無く、軽妙な話しぶりなど出来るはずもなく、一人、カウンターの端に居座って、話に付いて行けない己を呪い、その苛立ちで次第に不機嫌を募らせながらそこに座り続けた。何であれ、とにかく「キツネ」が繁盛することが度部には面白くなかった。
毎夜のように通う数人の若い隊員の一団があった、狭い店内に店じまいになるまで居残って、最後には酔い潰れて、へべれけになって帰るのだが、その中の、30歳そこそこの隊員で、名は佐川と云い、度部が一番気に入らない客だった。
吉津祥子はこの隊員を、
「サガちゃん」
と呼び、この佐川と話す時は、度部には見せない笑顔で応じた。
だが、その佐川は、通う内、吉津祥子の色香にのめり込んだか、歳の差も忘れて、露骨な物言いをするようになり、次第と不機嫌を顔に表す吉津祥子に尚もしつこく言い寄り、同僚に制止されると怒って暴れだす始末だった。
吉津祥子は、そんな時、カウンター隅の度部に、困ったような顔を見せる。
遂には同僚に引き摺り出されるまで吉津祥子に絡むその悪態を見る度、腸が煮えくり返る程に度部の苛立ちは募るが、カウンターの隅で、度部は怒りの暴発を抑えていた。
