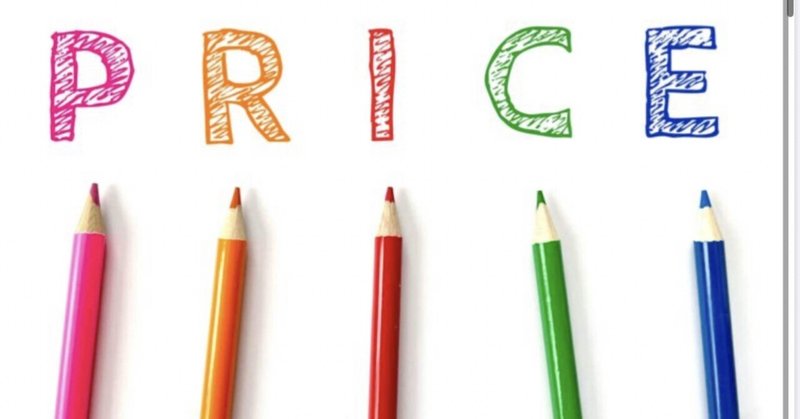
商品も人の労働も値上げすべき?
おはようございます。シンです。本日は「商品も人の労働も値上げすべき?」について。
目次
①給与をもらうこと
②給与を払うこと
③需要と供給
①給与をもらうこと
お勤めされている方は基本的に毎月「給与」をもらいます。
振込日は10日なのか、20日なのか、企業によって違う。
給与は生活するため、趣味を充実させるため、家族と旅行にいくためなど、人生を豊かにするために必要な存在です。
自分の労働の対価として、毎月(必ず)一定の給与をもらえる。
なんて素晴らしい制度なんだろうか。
②給与を払うこと
一方で、給与をもらう側がいるとすれば、払う側もいます。
毎月10日なのか、20日なのか、企業によって違いますが必ず従業員に給与を支払う。
契約や労働基準法を守るため、感謝を伝えるためなど、事業を存続させるために必要な存在です。
従業員の労働の対価として、毎月(必ず)一定の給与を払う。
改めて、素晴らしい制度ですね。
③需要と供給
ツラツラと何を言っているんだ?と思われる方もいるかもしれません。
当たり前のことを話してまとめようと思います。
仕事には「需要」と「供給」がありますね。
需要とは、給与を払う側が「こういう仕事できる人いますか?いたらこれだけのお金を払うのでお願いします」と仲間を探すこと。
供給とは、給与をもらう側が「こういう仕事できるんですが、この価格でやります。いかがですか?」と売り込みをすること。
この需要と供給を理解していない人が意外に多い気がします。
というのも、本当だったらこの需要は10万円の価値があるはずなのに、5万円しか払わない経営者がいたり、
本当だったらこの供給は10万円の価値があるはずなのに、5万円の請求しかしない従業員がいたり。
経営者はなるべく経費を抑えたいので価格を安くする。これはよくわかります。
けど従業員はなるべく充実した生活がしたいので価格を高くする。これは最近あまり聞かないですよね。
人生はお金じゃない。日本の経済は成長していないからしょうがない。体験に価値があるからお金はあまり必要ない。
いろいろな言い訳で「価格を高くすること」をしていない従業員が多い気がします。
商品に「価格」があるように、人の労働にも「価格」があります。
日本の商品が比較的「安い」のと同じように、人の労働も「安い」。
このままずるずると「安い国」になっていくのはどうなんだろうな。
と考える朝でした。
それでは良い1日を!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
