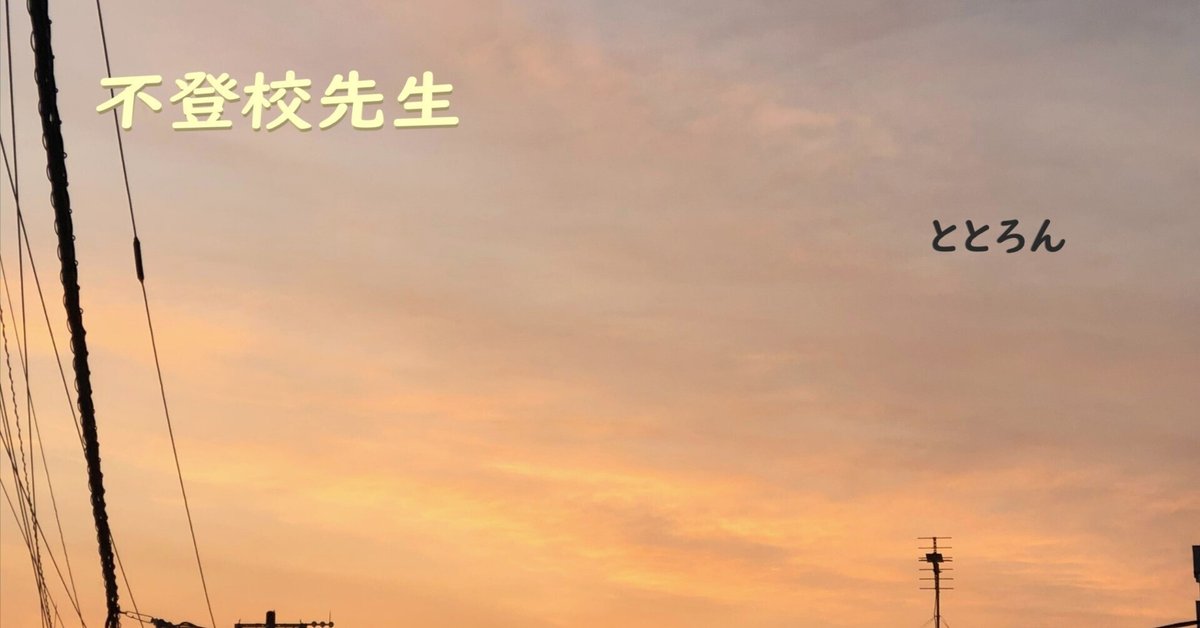
不登校先生 (40)
・退職の理由について記入してください。
『今年度、異動となり○○小学校勤務となりました。異動後の4月10日、帰宅途中に貨物列車に飛び込もうとしてしまいました。異動先の職場でのストレスで心が限界を超えてると判断し、翌日赴任校の校長に相談のうえ、4月12日に心療内科に診察に行きました。うつ病との診断が下り、翌4月13日より、病休を取得の上、自宅にて投薬と療養で回復に努めてまいりました。しかし、病休も上限の90日となり、未だ回復には至っていません。非正規の育休代替での加配であることから、この先休職等で赴任校に欠員の状態を作ってしまうことも考慮し、一度療養に専念するため、退職させていただきたく退職願を出させていただきました。』
A4の用紙の3分の1くらいのスペースに、ぎっしりとなってしまった。
・・・・・・・・・・
考えてしまったのは、二つの考え方がせめぎ合っていたからだった。
「たかだか講師一人の退職理由など、だれも興味がないだろうから、
ささっと、当たり障りなく簡潔に書いておけ」
という考え方が一つ。
「いや、年度途中になぜ退職願を出すことになったかの理由を、把握しておきたい人は必ずいる。だからきちんと伝えよう。自分に何が起こって退職に至ったかを、なるべく正確に。」
というもう一つの考え方。
結果としてぼくは後者の考え方を選んで、
なぜ退職に至ったかを順を追って、
なるべく詳細に報告するように、退職願に書いた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
もはや当たり前問題になってしまいすぎて、
国も自治体も教育委員会も抜本的な解決策も打ち出さない
学校の現場の問題がある。それは常時人手不足問題。
この15年働いていても、その深刻さは肌で感じてきた。
現場で働きだした15年前、一番最初の仕事の時も、
大学時代のゼミの教授から
「実は研究に協力してもらっている学校が、担任の先生が入院されて休まれていて、その代わりの先生を委員会にお願いしているのだけど、もう1か月誰も来なくて、そこで働いてみませんか?」
という、まさに人づてに誰かいないか、という流れで働き始めた。
その後も、現場を経験する中で毎年見てきた、関わってきた、
「欠員をどう補充するか問題」
自分自身、常勤の担任外で加配をされた年はすべて、
年度途中から担任として、休まれた先生の代替で教室を受け持った。
もはやその深刻さは到底「親方日の丸」とは言えない有様だ。
例えば、妊娠を報告して、次年度には産休に入るのが確定している方を、
4月の校内人事で、担任に据える。途中でおやすみが確定している中でも、
人員の加配がギリギリなので、担任に据えざる得ない。母体にも胎児にも
負担は大きいにもかかわらず、そういう校内人事をせざる得ない。
その上でいよいよ、その方が産前休暇に入るとなっても、
代替教員は来ない。当たり前のように。担任不在にはできないので、
校内の担任外の先生に声がかかる。しかし、再任用や非常勤には契約上
お願いすることはできない。結果、教務主任や管理職が担任代替になり、
学校全体の仕事が回らなくなる。機能不全に陥りかねないギリギリの状態。
そんな現場が、どこの現場でも見られる状態なのが、今の学校の現状だ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そんな問題がある中で、じゃあ何が現場で大事なのか。それは、
「スタメンが充実した気持ちとコンディションで、全員完走できる」
ように支え合って協力し合うことだと感じている。
全国的に政治が、本腰いれて問題として取り上げて、
抜本的に人員加配の見直しなどがなされない限り、
現状で出来る働き方の姿勢は、協力・支え合い・思いやり。しかない。
お互いがお互いに無理が過ぎていないか、声を掛け合い助け合い、
みんなで子どもを見ていく姿勢が本当に大事になっていく。
だが、僕は今年その逆の状態になり病んだ。
そういう現場があちこちに存在するのも、
教員不足過労働から派生しているように感じる。
先生たちに、余裕がないのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
せめて人事担当のこの退職願を受理した人だけでも、
この講師が、なぜ退職するに至ったのかについて、確認した時に、
現場に巣食う問題があるなと感じてくれるように。
きちんと書いておこうと思った。
それがどの程度役に立つかはわからないけど、
しっかりと伝えるつもりで書き残そうと思った。
↓次話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
