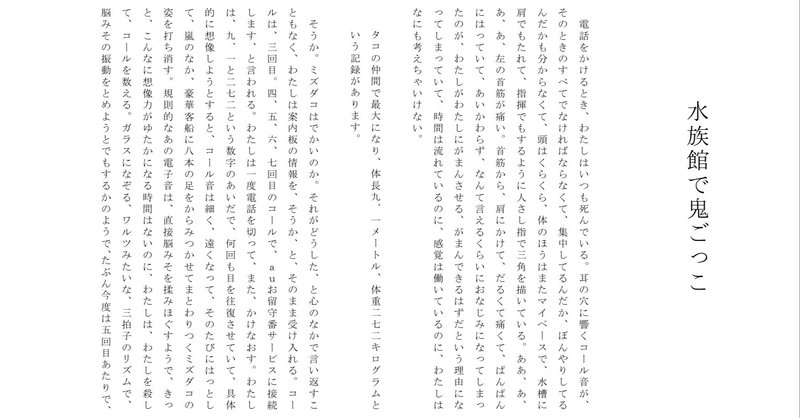
水族館で鬼ごっこ 全8回
電話をかけるとき、わたしはいつも死んでいる。耳の穴に響くコール音が、そのときのすべてでなければならなくて、集中してるんだか、ぼんやりしてるんだかも分からなくて、頭はくらくら、体のほうはまたマイペースで、水槽に肩でもたれて、指揮でもするように人さし指で三角を描いている。ああ、あ、あ、あ、左の首筋が痛い。首筋から、肩にかけて、だるくて痛くて、ぱんぱんにはっていて、あいかわらず、なんて言えるくらいにおなじみになってしまったのが、わたしがわたしにがまんさせる、がまんできるはずだという理由になってしまっていて、時間は流れているのに、感覚は働いているのに、わたしはなにも考えちゃいけない。
タコの仲間で最大になり、体長九.一メートル、体重二七二キログラムという記録があります。
そうか。ミズダコはでかいのか。それがどうした、と心のなかで言い返すこともなく、わたしは案内板の情報を、そうか、と、そのまま受け入れる。コールは、三回目。四、五、六、七回目のコールで、auお留守番サービスに接続します、と言われる。わたしは一度電話を切って、また、かけなおす。わたしは、九.一と二七二という数字のあいだで、何回も目を往復させていて、具体的に想像しようとすると、コール音は細く、遠くなって、そのたびにはっとして、嵐のなか、豪華客船に八本の足をからみつかせてまとわりつくミズダコの姿を打ち消す。規則的なあの電子音は、直接脳みそを揉みほぐすようで、きっと、こんなに想像力がゆたかになる時間はないのに、わたしは、わたしを殺して、コールを数える。ガラスになぞる、ワルツみたいな、三拍子のリズムで、脳みその振動をとめようとでもするかのようで、たぶん今度は五回目あたりで、セミの、もしもし、の声を聞く。
「あ、出た」
「出たよ。なに」
「なにしてた。いそがしかった」
「ちょうど携帯を見ようとしてた」
「いそがしいの」
「いそがしいと言えば、まあ」
「そっか」
水槽のガラスに、ゆっくり、上半身を転がす。携帯を持っているほうの腕で、体をささえ、ミズダコがぐったりしているのがまともに視界に入る。
寿命は約四年で、雌雄ともに繁殖を終えるとすぐに死んでしまいます。
そうか、と胸のなかでつぶやいたものの、体長、体重以上にぴんとこない。
マダコにくらべて、肉が水っぽく、これが名前の由来になっています。
「いま、バイト終わった」
「おつかれ」
「うん」
ミズダコの説明はここまでで、その下は世界地図、赤く色がついているのは生息している場所にちがいなく、日本からアメリカあたりまで、ぐるっと太平洋を囲んでいる。話題を探して、はあ、とか、ううん、とかうなっているうちに、わたしの目は体長、体重にもどっている。
タコの仲間で最大になり、体長九.一メートル、体重二七二キログラムという記録があります。寿命は約四年で、雌雄ともに繁殖を終えるとすぐに死んでしまいます。マダコにくらべて、肉が水っぽく、これが名前の由来になっています。
話題がないから、反射的に、セミに読み上げてやろうと、あ、あ、あ。でも、やめた。この説明だけで、分かった気になられるのがいやだった。よりによって、こんな特徴を選んでミズダコの全部にする、それが、ちょっと変な気もして、読めば読むほど微妙な文章なのに、妙に印象的で、ひょっとすると感動的なような気がして、よけいにおかしかった。せつないのだ、ミズダコの運命が。繁殖、なんて生物学的に書かれているのがまだしもで、繁殖を終えて、死んで、食べられて、マダコとくらべて肉が水っぽいと言われるのが、ミズダコなのだと思うと。
「つかれた」
「おつかれ」
「そうじゃなくて、つかれてんの。肩、痛いんだよ。首も。ふしぶしが痛い。風邪かもしんない」
吐き気もした。わたしの口が、ミズダコを食うと勘ちがいしているのか、ねばねばする唾液を無意味に生産している。くさくて、すっぱくて、わたしはもうミズダコの味を知っているようなものだと思う。
「早く帰れよ」
「帰るよ」
「なんだよ」
「いま、水族館にいる」
「なに。どこの」
「池袋」
「ああ」
「いま、リニューアルするから休館中なんだけど、かわりに、なんか、小さいのがあるの。五〇〇円で入れて、まあ、五分でまわれちゃうけど、気軽でいいよね。最近、バイトの帰りにけっこう来る。九時くらいまででしょ。閉館寸前で、人もいなくて、すごい落ち着く。いいよ。おすすめ。池袋で買いものとかするときは、来るといいよ。リニューアルオープンは、夏あたりでしょ。そのときまで」
まるでアリバイづくりのためのような電話で、実際、出ることなんて期待していないのに毎日毎日、欠かさず電話をかけて、本当にそれは、あんたのことを一日一回は考えたよ、というアリバイづくりに似ているのかもしれず、電話に出られてしまって、かえってこまっているわたしがいる。電話を切るタイミングを探している。ひまになったら、五〇〇円にぎりしめて一緒に来よう、夏になったら、リニューアルした本館に行ってみよう、そのあたりが話の流れとして、終わりにふさわしい気がした。ミズダコのつかれたピンクは、口唇の粘膜に似ていた。携帯を耳に押しつけ、ひび割れた口に近づけているセミの顔が、別に、ふつうに電話しているだけなのだけれど、生々しく目の先に浮かんだ。ぼそぼそ耳うちするミズダコのピンクをはらいのけるように、わたしは、ひまになったら、か、夏になったら、を言って、電話を終わらせた。
ミズダコは、頭の下に足をしいて、水の循環に体をなびかせている。なにかの意思で動いているようには見えなかった。なかなか離れられなかったのは、別にかわいくもないし、おもしろいからでもなくて、なにをおもしろがればいいんだか分からなかったからで、
日本の太平洋岸にのみ分布する世界最大のカニで、ハサミ脚を広げると三メートルを越え、五.八メートルの個体も確認されています。
水深二〇〇メートルから五〇〇メートル付近に多く生息し、十二月から三月の産卵期になると、産卵のため水深三〇メートルの浅瀬に移動してきます。
中央・南アメリカ大陸の熱帯雨林などに生息しており、全長は三メートル以上になる大型のヘビです。名前の「コンストリクター」とは、しめつける、という意味で、エサとなる鳥類や哺乳類などをしめつけ、窒息させてから丸呑みにします。
無毒ですが、大型になり、力も強いので、国が定めている「特定動物」になっています。
タカアシガニ、ボア・コンストリクターと、少しずつ出口へ近づいていって、いちいち、今日はやけに気になり、立ちどまってひと通り観察しないと、通りすぎることができなかった。あまりにも、おもしろくなさすぎて、
ケープペンギンは、アフリカ大陸に生息する唯一のペンギンで、砂地に掘った穴や木の根もと、岩場のすきま、民家の軒下などに巣をつくります。夫婦交代で卵をあたため、子育ても協力して行ないます。夫婦の絆はとても強く、何年も同じ相手と同じ場所で営巣すると言われています。
そのケープペンギンまで到達して、わたしは動物をながめているのだということに、あらためて気づき、こいつらはただひたすら生きているだけなのだ、と、しみじみする。まわり道しないで最短距離で生きているから、別にわたしが見ているからといって、わたしに愛想をふりまく必要はなくて、じっと動かないでいるというのが、動物にとっては基本の状態にちがいなく、そうしてエネルギーを温存しておくのがぜったいにただしい。首をまわすと、骨が鳴った。プールの端で、ケープペンギンは、夫婦ならんで立っている。なにもする必要がないのだ。
「死んでるのか」
爪の先で、ガラスをたたいた。わたしを敵だとは考えもしないようで、あいかわらず、立っている。
携帯で写真をとる。メールで送ろうとしたけれど、いよいよアリバイづくりのようで、やめた。券売所をはさんだ、ふたつの通路の、ボールペン、ぬいぐるみ、キーホルダー、シール、パズル、トランプ、メモ帳、おみやげのならんだ左のほうが出口で、窓口からブラウスに紺のベストを着た女の子に、頭を下げられる。わたしより年下かもしれないその女の子は、ひとりきりで閉館ぎりぎりまでいたわたしを気持ち悪い女だとも思わず、思っていたのかもしれないけれど、バイトにはとてもできないようなにこやかな笑顔で、
「ありがとうございました」
と、わたしを送り出す。
さっそく消灯、カギをかけるような気配を背中に感じる。足をひきずるように歩きながら、わたしはボア・コンストリクター、ケープペンギン、と口のなかで繰り返しつぶやいている。帰りの電車まで、この名前を覚えていられるかどうか、分からない。でも、明日まで忘れなかったら、永遠に覚えている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
