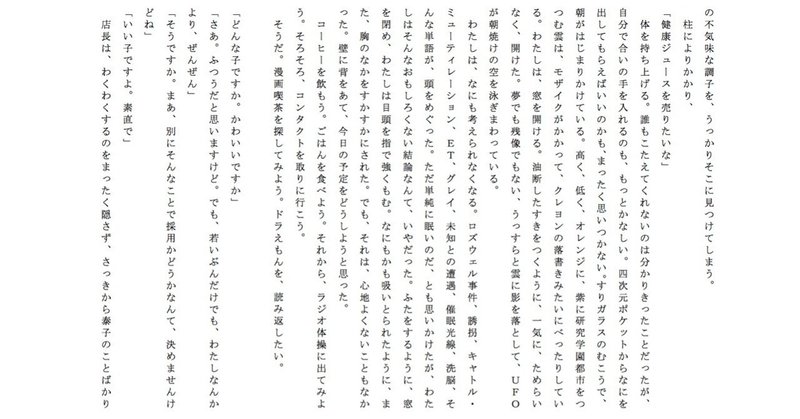
落下傘ノスタルヂア(9)
「どんな子ですか。かわいいですか」
「さあ。ふつうだと思いますけど。でも、若いぶんだけでも、わたしなんかより、ぜんぜん」
「そうですか。まあ、別にそんなことで採用かどうかなんて、決めませんけどね」
「いい子ですよ。素直で」
店長は、わくわくするのをまったく隠さず、さっきから泰子のことばかり言っている。自転車をあいだにはさんで、なにか聞こうとするたびに、こちらへにゅっと首を伸ばしてくる。
「そんなにいい子だったら、本当にうちのバイトにしちゃいますよ」
「どうぞ。おねがいします」
「ちょうど、バイトがひとり、やめたいとか言ってました。この前、うちに来たでしょ。あのとき、顔は見たと思うんですけど、覚えてないかな」
「覚えてないですね」
「一週間とか、二週間じゃないですよ。最低、一ヶ月くらいはもうシフト組んじゃいますよ。だいじょうぶなんですか」
「だいじょうぶですよ。一ヶ月では、ちょっともう開店できそうにないので。うちの泰子、どうか、つかってやってください」
「はあ。それは、こっちは正直、助かりますけどね。でも、だいじょうぶっていうか」
「ええ、たしかに、だいじょうぶでもないんですけど」
大学の敷地を左手に見て、わたしと店長は、並木道をてくてく歩いている。あまりにも立派すぎる並木は、おたがいに枝をからみ合わせ、一定の距離をとって立ってはいても、ほとんど林のなかにでも入ったように、漏れ落ちる光は細くたよりなく、まばらだった。店長にすずしくていいと言うと、夕方から夜は暗くていけない、と強く反対される。関東ローム層は酸性で、本当はこんなに木が成長するはずはなかった。人の背丈よりは高くならない計算だった。だから、調子に乗って、大学のなかも木でいっぱいにしたが、どこで計算が狂ったのか、見てのとおりのありさまになったのである。店長は、こんなことを生物資源学科の学生に聞いたという。
「未来都市なのに」
と、思わず、わたしは口に出していた。
「え」
「ちがった。未来都市じゃないや、研究学園都市なのに。自然がいっぱいでいいですね。わたしの田舎よりすごいですよ」
店長はうなずき、まったく自然の力は、人間にははかり知れないですね、と結んだ。この感想だけは、ぼくが思ったことですよ、とわざわざ断った。
いつか奈津美とふたりで飲んでいるときに、水商売におけるいやな客の分類、というのを講義された。奈津美がまっさきにあげたのは、からみかた、返事のしかたにこまる客、だった。なにかタイプの名前をつけていたが、それは忘れた。うまい対応のしかたもおそわったはずだが、いま、急には思い出せず、はあ、としか言えなかった。
「この前の、続きなんですけど」
うまいことを言ったつもりの店長は、わたしがどう処理しようか迷っているのを見てとり、あわてて話題を変えようとする。
「さしつかえなかったら、でいいんですけど、リストラされたというのは。いや、本当に、別にどうでもいいんですが」
「いいですよ、そんなに恐縮されなくても。ええと、テレビの制作会社にいまして。学校の先生のコネでねじこんでもらえたんですよ」
「なるほど。テレビの制作会社」
「毎日文化祭みたいで、たのしかったですね。文化祭はすぐ終わりますけど、会社はすぐに次のイベントの準備になりますよね。正確には、毎日が文化祭の準備というか。やっぱり、一番たのしいのは、そういう時間ですよ。だから、たのしかったんですよ、本当に」
「なるほどね」
興味がないなら聞かなければいいのに、とも思ったが、一度話しはじめたからには、いやでも聞いてもらう。
「たぶん、それなりにうまくやっていけてたと思うんですよ。好きでしたから、そういうイベントが。少なくとも、大きな失敗もしなかったし。でも、なぜか、リストラされちゃったんですよ。不思議でしたね。ええと、上司がいましてね。わたし、けっこう、なぜか、おっさんにもてるんですけど、だいぶ、気に入ってもらえてたみたいですけど、ある日、急に呼び出されて。それでまあ、やめろ、と。びっくりしましたよ、正直。その理由もまた、わけが分からなくて。おまえは、もっと別にやりたいことがあるはずだ、だから、首にしてやる、そんなことを言われましたね。なんでしょうね、いったい。はあ、って。でも、頭にきましたね。また新しいイベントだとばかり思ってて、なんの期待も、不安もなくて、業務連絡が事務的にされるだけだろうというくらいの、なんの覚悟もない状態でした。その上司の言葉を、どんなふうに受け取ったのかは、よく覚えていません。冗談きついよ、と思ったのか、なんという勝手なことを言う人だ、とまじめに思ったのか。とにかく、気がついたときは、会社の玄関、出てましたね」
ひと息ついて、店長をうかがう。奥に入っていくほど、並木の成長は原始のように凶悪さを増し、縦横に伸ばした根っこが、歩道の石畳を無残に波打たせている。店長は自転車のハンドルをかたく握りしめ、悪路の上でなんとか操縦を続けることで精一杯、という感じ。蝉の声も、夕立のように粒があらく、ずっしりとした重みを持ちはじめる。いよいよ聞いていないな、と確信するが、続きはそのほうが話しやすくていい。
「わたしの上司が言ったことは、いまだに謎のようです。別にやりたいことがある、らしいんですけど。やっぱり、わたしは、自分でそう信じているほど有能ではなかったか、本当のことを言ってもらったほうがよかった、とも思いました。わたしのことをちゃんと見抜いていた、と納得することは、なかなかできませんでした。なにしろ本人にその自覚がないので、そうだ、と言えばそうだし、いやそうじゃない、と打ち消そうとすれば、それも簡単なことですから。まじめに反省してみたこともありますが、よっぽど頭をからっぽにして駆けずりまわっていたらしくて、やってきたことは多いわりに、たのしかったわりに、そこになにかの思い入れがあったわけじゃなかったんですね。自分がそういうふうにあやふやだから、上司の、あのきっぱりしたリストラ宣言のほうが、信用できるような気がして。それなら、といちおうそっちを信用することに決めたあとは、早かったです。もともと生きていくだけなら、なにをやったって生きていける、って、やけくその気持ちがありましたので、わたしのやりたいことというのをじっくり探してやろうと」
思いました、と店長の鼓膜を指ではじくようなイメージで、短く切って言い、終わりました、ということを強調する。はっとして、店長はこちらに顔をむける。と、油断した瞬間に、歩道の割れ目へ前輪をつっこみ、あやうく転びかける。照れ隠しに、わざとおおげさな声を上げ、わたしに笑いかける。目は必死だった。わたしに笑いを誘っているのだと、はっきり分かる。おもしろくもなんともなかったが、そういう店長の存在が、できの悪い弟のような、いとおしいものにも見え、期待されたのとはたぶん別の笑いを、ふともらす。
安心したついでに、気を許したらしく、店長はそれからよくしゃべった。たぶん、照れ隠しの余波でもあった。昨日見たテレビ番組とか、最近おもしろかった漫画とか、まったく分からないなりに、それでも、ちゃんと聞いてあげる。グラウンドで、サッカーしている。授業のようでもなく、かなり本格的な雰囲気だった。すごい有名な選手が入学してきたらしいと、山本か佐藤に聞いたが、まったく知らない名前で、記憶になんの手がかりも残っていない。このなかにいるのだろうかと、横目でちらちらグラウンドを見やるが、誰がうまいかなんて、サッカーのルールすらあいまいにしか知らないのに、分かるはずがなかった。テニスコートのむこうに、コロシアム風の唐突な建築物がある。その有名な選手が来るというので急いでつくったという、サッカー部の練習施設だと思う。それも、山本か佐藤が言っていた。
「いま何時ですかね」
と言いながら、自分で時間を確認する。四時半か、と店長に聞こえるようにつぶやいた。そのつもりはなかったのに、店長の話は断ち切られる。語尾をとりつくろおうとあせるのが、ちょっと気の毒なくらいだった。
「まずいな。そろそろ、やっちゃんもこっちにむかってるかもしれない。せっかく来てもらえるのに、出張面接してもらえるのに、行きちがいになったら、いけませんね」
「急いだほうがいいですか」
「まあ、気持ち急ぎますか。もうすぐなんですよね、その公民館」
「もうすぐですよ。本当にすぐ」
並木道はいつのまに大学をはなれたのか、まっすぐ百メートルくらい先のコンクリート建てがそれだと、店長は指をさす。まだまだ夏の日は空の高いところにいるが、射しこむ光にはそれなりの角度がある。並木のあいだに頭を出し、ぎらぎら照り返す窓ガラスが、少し目に痛かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
