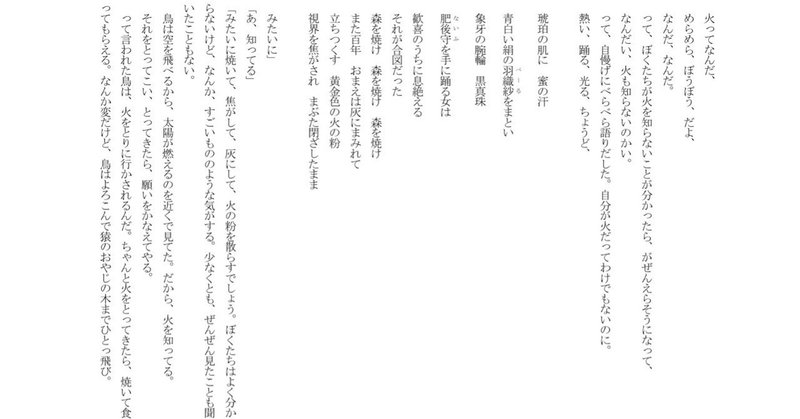
銀匙騎士(すぷーんないと) (30)
「みたいに焼いて、焦がして、灰にして、火の粉を散らすでしょう。ぼくたちはよく分からないけど、なんか、すごいもののような気がする。少なくとも、ぜんぜん見たことも聞いたこともない。
鳥は空を飛べるから、太陽が燃えるのを近くで見てた。だから、火を知ってる。
それをとってこい、とってきたら、願いをかなえてやる。
って言われた鳥は、火をとりに行かされるんだ。ちゃんと火をとってきたら、焼いて食ってもらえる。なんか変だけど、鳥はよろこんで猿のおやじの木までひとっ飛び。
猿のおやじは、ぼりぼり股をかきむしっていた。鳥は馬鹿だから、
火をちょうだい。
なんて、そのまま、唐突に言った。
誰だ、おまえ。
って、当然、猿のおやじのほうは聞くでしょう。
鳥だよ、
なんの鳥だ、
きれいでしょう、歌はあんまりうまくない、
なんの用だ、
火がほしい、
はいそうですか、とやれるものか、阿呆が、
でも、くれないと、こまる、
わしにはどうでもいいことだ、
火がないと、生で食われてしまう。
って、鳥は泣きごとをほざくけど、猿のおやじには通じない。
やかましい、勝手にしろ。火は大事にしまってあるんだ。貴様のようなやつのためにわざわざ出すものか。
って、猿のおやじはごろ寝。
寝ながら、股をかいてる。
鳥は、もうちょっと話を聞けよ、と猿のおやじをゆさぶるでしょう。くちばしでつんつんしても、いびきはぐうぐう、よだれはだらだら、で、股をぼりぼりでしょう。手枕がはずれて、べたっとなって、ぼりぼりのほうの手も枝にひっかかって、それでも、ぼりぼり、ぼりぼり、ぼりぼり、ぼりぼり、してたら、ぱちぱち、ぱちぱち、めらめら燃えだした。
木のなかに火をかくしていたのさ。いや、ぽっかり、洞窟みたいな木のうろじゃない。木のなかって、血と肉と骨、木そのもののなかに染みついて、流れてるんだか、埋められてるんだか、浮かんでるんだか、沈んでるんだか、たぶん、溶岩みたいな樹液がどろどろ。
だから木は、いまでも猿の手のかたちの焦げめが枝の付け根に残っているんだよ。
鳥は、口のなかにその火を入れて、木から、猿のおやじを起こさないように、こそこそ羽ばたいて夜明けの村(あいる)へ。
猿のおやじは、でも、気づいた。火にひもをつけて耳環にひもをむすんでたから、耳たぶがつねられたみたいになって、いたたたた。
くそが、盗人、ぶち殺してくれるわ。
って、鳥を追いかける。
鳥は飛んでいるから、猿なんかに追いかけっこで負けないと思ってたけど、口のなかが熱い。舌が燃えて、もう、だめだ。火を吐き出して、墜落した。二千歩ぶんくらいしか進めなかった。そのときから、鳥は胸がいぶされて灰白黒だんだらの模様になってしまったし、
あっちち、あっち、水かけ、水浴び、さまして、ひやせ、裏の泉は蛙が押しかけ行列だ。
って鳴くようになったし、
ぼくたちは、火種が大きくなって、火の頭がゆらゆらするのを、鳥の舌が風にそよぐ、って言うようになった」
「鳥ってなんだよ。そんな鳴きかたの鳥がいるか」
「いるよ。村(あいる)に」
「鳥って、やっぱり、それしかいないのか」
「いない」
「ふーん」
「鳥の落とした火を拾ったのが鼠で、こいつはしっぽでくるっと巻いて、ちょろちょろ走った。でも、しっぽが熱い。焼き切れて、火がこぼれた。やっぱり二千歩しか進まなかった。
次に拾ったのは、犬。犬はちょっとかしこいから、木の棒をくわえて、その先っぽに火を乗せる。だけど火はどんどん燃えるから、歯にしみる。三千歩で、鼻がかわいてたおれてしまったんだ。
最後の千歩までぼくたちは出迎えに来てたから、火をぼろ布にくるんでふところに入れた。心臓に毛が生えているおっさんだったから、肺にも毛が生えてたし、胃腸もじょうぶだったから、胸のなかはそれほど熱くなかった。猿のおやじが息を切らして、
それは、わしのものだぞ、くそが、
拾ったものは、おれのものだ、
ひどいやつだ。ようし、くれてやる。わしの火はまだ払底しておらん、
じゃあ、いいじゃないか。けちけちしやがって、
腹が立つ。ああ、くれてやる。くれてやるとも。そのかわり、火の稲蝗(いなご)の群を送りこんで、噛ませて、毎日きさまの村(あいる)の子供を五人、風邪をひかせる。火を手ばなさなかったばっかりに、頭がかっかして額が燃えるぞ。九十日に一度、雨のように炎を降らせて、十人焼き殺す。じじいは麻粿(おもち)でのどをつまらせ、ばばあはなんにもないところですべってころばせる。人は百年しか生きれないようにして、死んだら二度とよみがえらない、息をとめたらわしが灰にするから、
やってみろ、おれたちはこれから春だけじゃなく、年中、結婚式をあげて子供をつくらせる。毎年毎年、百人、人が増えるんだ。
ってわけよ」
「なにが」
「それから、風邪をひいたら熱が出るし、人は千年生きられなくなったし、死んでもたまに復活したりしなくなったし、炎が降ることもあるかもしれないし、おじいさんとおばあさんは死にやすい。死体を火で焼くことになって、いつでも子供は生まれて、どんどんぼくたちは多くなった、ってわけよ」
「ふーん」
「えっ」
「なんだよ」
「なんだっけ」
「なにが」
「なんの話だったっけ」
「おれに聞くなよ」
「あっ、だから、ぼくのうちから八千歩のところに木があった、って話じゃないか」
「そうだな」
「たくさん歩いて、そうだな、一万歩くらい歩いたあと、うしろを見たら木が燃えていたよ。
針槐みたいに火の粉がふさになって、満開の花ざかりみたいだった。黄金色の火の粉、ってこういうことか、と思った。視界を焦がされるとも思った。灰にまみれて立ちつくしはしなかった。あと、まぶたを閉じてる場合でもなかった。
ああ、本当に火をかくし持ってたんだな、ってなんか感動した。金貨をばらまいてるようにも見えたから、けちけちしててもいざというときにはふとっ腹なんだな、って。
目が乾燥したみたいで、はっとしたよ。一回立ちどまってしまったから、それからどこへ行けばいいのか分からなくなっちゃった。うちにいれば、旦那さまや奥さまやお嬢さまがいて、どうすればいいか言ってくれるけど、じじいもばばあも屋敷を出るときには横と前にいたけど、いつのまにかはぐれた。ふたりとも、彗星か流星、流星群みたいに頭の上を飛んでいく矢の音にびくびくしてたな。
ぼくは、これが火の稲蝗(いなご)で、炎の雨だと思ったよ。おはなしでうそだってずっと本気にしてなかったけど、うそのなかにも本当のことはあるかもしれないし、まるまる全部が実は本当のことでした、みたいなことだって、もしかして。
そうそう、じじいとばばあに聞いて見たかったんだ。どう思うかって。安稜(あろん)は、どう思う」
「たまたまだと思う」
「やっぱり」
「おまえが本当のことだと思うのは、いいよ」
「ありがと」
「ぼやっとしてんなあ。よくつかまって殺されなかったな」
「ぼくも不思議だ。妹とふたりきりだから、ぼくのほうが年上だから、そうするか決めなきゃいけないだろ、ほかにもっと年上とかえらい人とかいないんだから。妹はしっかりしてるんだ。ぼくがまごまごしていると、早く手足を動かしなさい、って。あてはなくても、とにかく考える前に一歩でも遠くに行かなきゃ。おかげで助かった」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
