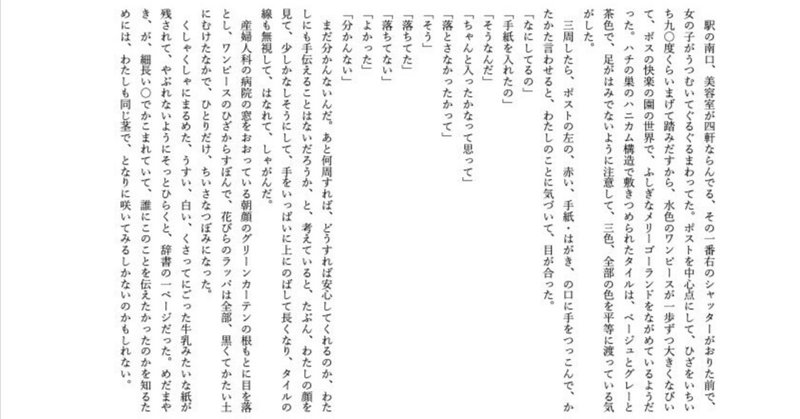
口語散文集 3
朝顔通信
駅の南口、美容室が四軒ならんでる、その一番右のシャッターがおりた前で、女の子がうつむいてぐるぐるまわってた。ポストを中心点にして、ひざをいちいち九〇度くらいまげて踏みだすから、水色のワンピースが一歩ずつ大きくなびいて、ボスの快楽の園の世界で、ふしぎなメリーゴーランドをながめているようだった。ハチの巣のハニカム構造で敷きつめられたタイルは、ベージュとグレーと茶色で、足がはみでないように注意して、三色、全部の色を平等に渡っている気がした。
三周したら、ポストの左の、赤い、手紙・はがき、の口に手をつっこんで、かたかた言わせると、わたしのことに気づいて、目が合った。
「なにしてるの」
「手紙を入れたの」
「そうなんだ」
「ちゃんと入ったかなって思って」
「落とさなかったかって」
「そう」
「落ちてた」
「落ちてない」
「よかった」
「分かんない」
まだ分かんないんだ。あと何周すれば、どうすれば安心してくれるのか、わたしにも手伝えることはないだろうか、と、考えていると、たぶん、わたしの顔を見て、少しかなしそうにして、手をいっぱいに上にのばして長くなり、タイルの線も無視して、はなれて、しゃがんだ。
産婦人科の病院の窓をおおっている朝顔のグリーンカーテンの根もとに目を落とし、ワンピースのひざからすぼんで、花びらのラッパは全部、黒くてかたい土にむけたなかで、ひとりだけ、ちいさなつぼみになった。
くしゃくしゃにまるめた、うすい、白い、くさってにごった牛乳みたいな紙が残されて、やぶれないようにそっとひらくと、辞書の一ページだった。めだまやき、が、細長い○でかこまれていて、誰にこのことを伝えたかったのかを知るためには、わたしも同じ茎で、となりに咲いてみるしかないのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
