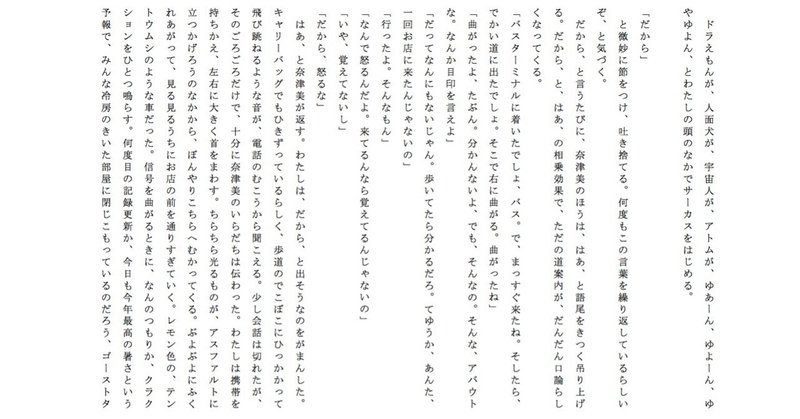
落下傘ノスタルヂア(14)終
「だから」
と微妙に節をつけ、吐き捨てる。何度もこの言葉を繰り返しているらしいぞ、と気づく。
だから、と言うたびに、奈津美のほうは、はあ、と語尾をきつく吊り上げる。だから、と、はあ、の相乗効果で、ただの道案内が、だんだん口論らしくなってくる。
「バスターミナルに着いたでしょ、バス。で、まっすぐ来たね。そしたら、でかい道に出たでしょ。そこで右に曲がる。曲がったね」
「曲がったよ、たぶん。分かんないよ、でも、そんなの。そんな、アバウトな。なんか目印を言えよ」
「だってなんにもないじゃん。歩いてたら分かるだろ。てゆうか、あんた、一回お店に来たんじゃないの」
「行ったよ。そんなもん」
「なんで怒るんだよ。来てるんなら覚えてるんじゃないの」
「いや、覚えてないし」
「だから、怒るな」
はあ、と奈津美が返す。わたしは、だから、と出そうなのをがまんした。キャリーバッグでもひきずっているらしく、歩道のでこぼこにひっかかって飛び跳ねるような音が、電話のむこうから聞こえる。少し会話は切れたが、そのごろごろだけで、十分に奈津美のいらだちは伝わった。わたしは携帯を持ちかえ、左右に大きく首をまわす。ちらちら光るものが、アスファルトに立つかげろうのなかから、ぼんやりこちらへむかってくる。ぶよぶよにふくれあがって、見る見るうちにお店の前を通りすぎていく。レモン色の、テントウムシのような車だった。信号を曲がるときに、なんのつもりか、クラクションをひとつ鳴らす。何度目の記録更新か、今日も今年最高の暑さという予報で、みんな冷房のきいた部屋に閉じこもっているのだろう、ゴーストタウンのような、研究学園都市の片隅に、妙にとぼけてそれは響きわたる。アマゾンあたりにでもいるかもしれない、原色の、ぎらぎらした鳥の鳴き声にも似ている。
ひさしぶりに会うんだから、と、なんとなくちゃんとした服を選んだ。わざわざリクルートスーツをひっぱり出したわけでもなく、いちおう襟のあるシャツを着たくらいだったが、それでもわたしにはけっこうな努力だった。人は見た目が九割、とは、奈津美がよく言っていた。なにしろ、ひさしぶりだった。ひとりで、それなりにがんばっていたのを、ぱっと見たときの印象で誤解されるのはしゃくだった。しかし、早くもわたしの汗と、この湿気とで、しっとりとくずれはじめている。
「なにか見える」
「砂漠みたいですけど。てゆうか、アメリカか。畑と田んぼばっかり。しいて言うなら、聞いたことない名前のコンビニを、さっき見た」
「黄色い、変な車が通らなかった」
「なに、その目印」
「見てないならいい。いざとなったら、人に聞きなさい。田舎の人は親切かもよ。ちなみに、わたしはひとりだったけど、ぜんぜん迷わなかったからね」
「イグアナ」
「じゃあ、もうちょっとがんばってみなさい」
なかに入ればすずしいだろうと無意識に期待していたようで、かえって外よりも蒸している店内に、がっかりして、力が抜ける。一度に毛穴がゆるみ、どっと汗が吹き出す。リモコンの温度設定を十六度にして、運転/停止、を親指でぐっと押しつぶす。
「来ませんか」
泰子が、かき氷を切りくずしながら、目だけこちらにむける。マッターホルン、などと言ってはしゃいでいたのが、いまは三原山くらいになっている。赤いいちごのシロップは異様に高かったが、それだけにどろっとしていて、色も濃い。ほとんどジャムに近い。あとで分かったが、うすめてつかうタイプのものだった。密度のある、溶岩のようなあまったるさに、わたしは頂上をすくったくらいで、胸焼けを起こした。残りは全部、泰子にあげた。泰子の舌は、感覚は、もう馬鹿になっているにちがいない。エアコンも止めたくなるわけだった。
「来ないね。お姉ちゃん、本当にどうしようもないね。方向音痴、じゃないんだな、駅の出口も確認しないで、勘だけで進むからね。遅刻しても会えれば、まあいいほう」
「そんなとこもありますね」
右手は休みなく口へ運びながら、泰子は、テーブルに乗せたままの携帯を左手で器用にいじっている。姉に電話をかけたのだった。よう、と軽くあいさつし、うん、うん、うん、と頭を振って、とめどなくあいづちを続ける。足を引きずるようにして奥へ行くわたしに、泰子は目でなにをするのかと問いかけるようだった。シャツをつまんで、着がえる、と示したつもりだが、通じたかどうかは分からない。
わたしはシャツもパンツも脱ぎ捨て、洗濯もののコーナーにしているダンボールへ投げこむ。引越しのときに片づけたものが、最近目のつくところへ侵出しはじめてきた。ダンボール、養生テープ、すずらんテープ、引越しグッズはなにしろ便利で、あればなにかにつかえてしまう。すこぶる機能的なのだが、見ようによってはだらしない。しかし、それならそれで、ありのままをさらけ出さなければひきょうだ、ということにして、いつものスエットに手を伸ばす。よじれかけた下っ腹に、ふと体を硬直させ、おそるおそる、指でつまんでみる。あいかわらずたるんではいたが、心なしか、多少はましになった気もしないではない。こんなところにかろうじて残っている女の子っぽさに、安心するような、恥ずかしいような、いまさらなような気がして、さっさと着こんでわたしの目から隠してしまう。泰子と奈津美の話は順調に脱線していったらしく、ちゃらちゃらした声で、姉となかよくさえずっている。
スーパー、本屋、ファミレス、回転ずし、本屋、クリーニング屋。関係ない世間話の合間に、奈津美の見たものを、泰子がちょくちょく声に出して聞き返す。畑と田んぼをようやく抜けて、奈津美は、こちらに近づきつつある。あじさい、と泰子がぽつりとつぶやく。わたしのたどっていた地図が、とたんに狂う。あじさい、と泰子は、なおも言い聞かせるように繰り返す。どこかにあじさいの咲く家はあったかな、と頭のなかの地図をもう一度見なおすが、考えてみれば、もうそんな季節ではなかった。
「氷、まだある、やっちゃん」
泰子が電話を切ったのを見はからって、わたしは立ちあがった。
「氷ですか」
サンダルをつっかけ、カウンターに寄りかかる。泰子は、シンクに皿を置いていた。
「奈津美、もう来るんでしょ。暑い思いしてるだろうから、あいつにもつくってやろうかと」
「一気に全部やっちゃいましたけど。さあ、次にできるのは、何時間かかるかな」
冷凍庫を開け、泰子が顔を入れた。まだうすく表面が凍っただけだ、と報告する。
「そうか。いずれ、製氷機、入れなきゃな。まあ、さしあたり、あの容器、なんて言うんだ、氷つくるやつ、何個かほしいな。あれだけ売ってるもんかね」
「見たことないです」
「だって、全部つかって、ひとりと半人前くらいでしょ。ええと、山本、佐藤、あと、バンドの三人でしょ、店長でしょ、わたしと、やっちゃんと、あと、まあ奈津美もか。山本と佐藤には、知り合いつれてきてもいいって言っちゃった」
「やめますか」
「せっかくもらったのに。せっかくだから、かき氷パーティーしたいじゃない。あずきとかさ、練乳とか、抹茶とか、いろいろこれから用意する予定だったのに」
昨日、泰子がバイト中に、これは、と思った。ずっと目をつけておいて、バイトが終わったあと、店長にねだったのだという。タケコプターをまわして氷をけずる仕組みになっている、そのドラえもんのかき氷機は、わたしと泰子に背をむけ、いまも満面の笑みで入口のほうへ愛想をふりまいている。奈津美が来るのを、待ちかまえている。
「じゃあ、花火だけで。けっこうありますけど。初給料で、コンビニの花火全部買い占めたので」
テーブルに立てかけてあった紙ぶくろを、ひょいと持ち上げてみせる。わたしはあらためてあきれつつ、半分くらいは出してやるべきだろうな、と思う。
「あ、コンビニで買うか。氷」
「はあ」
「まあいいや」
わたしは泰子と一緒に、お店の前に出る。
「お姉ちゃん、ちゃんとお金つくったんですか」
「半分、だってさ」
「ふうん。だいじょうぶなんですか」
「だいじょうぶじゃないと思うよ。さしあたり、ふたりでバイトかな。企画書もなおしながら、残り半分、なんとか投資してもらえるようにもするし。やっちゃんは、なに話してたの。たのしそうだったじゃん」
「たのしそうでしたかね。ふつうですよ」
泰子は鼻歌まじりでそう言っていることに、たぶん気づいていない。眠った空気は、くすぐられて、ほんの少しだけ、ゆらゆら、ふるえる。青い、風の筋がゆっくりとすれちがい、こすれ合い、切れ切れに耳もとでなにかをささやく。奈津美は、まだ来ない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
