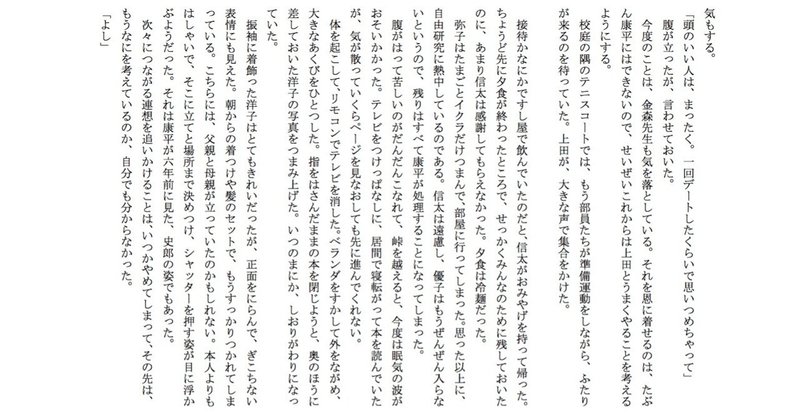
百年の日(14)
接待かなにかですし屋で飲んでいたのだと、信太がおみやげを持って帰った。ちょうど先に夕食が終わったところで、せっかくみんなのために残しておいたのに、あまり信太は感謝してもらえなかった。夕食は冷麺だった。
弥子はたまごとイクラだけつまんで、部屋に行ってしまった。思った以上に、自由研究に熱中しているのである。信太は遠慮し、優子はもうぜんぜん入らないというので、残りはすべて康平が処理することになってしまった。
腹がはって苦しいのがだんだんこなれて、峠を越えると、今度は眠気の波がおそいかかった。テレビをつけっぱなしに、居間で寝転がって本を読んでいたが、気が散っていくらページを見なおしても先に進んでくれない。
体を起こして、リモコンでテレビを消した。ベランダをすかして外をながめ、大きなあくびをひとつした。指をはさんだままの本を閉じようと、奥のほうに差しておいた洋子の写真をつまみ上げた。いつのまにか、しおりがわりになっていた。
振袖に着飾った洋子はとてもきれいだったが、正面をにらんで、ぎこちない表情にも見えた。朝からの着つけや髪のセットで、もうすっかりつかれてしまっている。こちらには、父親と母親が立っていたのかもしれない。本人よりもはしゃいで、そこに立てと場所まで決めつけ、シャッターを押す姿が目に浮かぶようだった。それは康平が六年前に見た、史郎の姿でもあった。
次々につながる連想を追いかけることは、いつかやめてしまって、その先は、もうなにを考えているのか、自分でも分からなかった。
「よし」
と景気をつけて立ち上がったのも、なんのかけ声なのか、はっきりしない。それでも信太と優子の寝室のふすまに手をかけたときには、なにを言おうとしているのか、迷うことはなかった。自分の思いつきにたぶらかされて、他愛なく康平の声は上ずっていた。
「優ちゃん」
しかしいささか尻すぼみではあった。語尾を飲みこみ、のどをつまらせたかのように、息がとまった。
信太と優子が口唇をかさねていた。むこうも一瞬遅れてとりつくろってくれたが、もうどうしようもなかった。
「あ、ごめん」
「うん。なに」
優子だけは、案外恬淡としていた。
「ええと、なんだっけ」
「どうしたの」
「そうだ。明日また、ついでがあるからおやじに会いに行こうと思うんだけど、どう」
「どうって」
「一緒に行かないか」
「明日か。明日は」
と信太に目くばせをして、
「明日は、だめだね」
早く席をはずしたくてじりじりしていた信太が、やっと口を開き、
「それはいいね、お義父さんのところか」
おおい弥子、と声を上げながら、寝室を出ていった。
「弥子、おじさんが、おじいさんのところに行くんだって」
「ふうん」
「連れてってもらえよ」
「うん」
そんなやりとりが、むこうで聞こえた。
「まいったな。まあ、いいけどね」
じゃまをした罰だと観念した。
「ごめんごめん」
と優子は言った。
「いやこちらこそ」
「で、なんの話だっけ」
「おやじに会いに行く」
もっといいことだったような気がしたが、こう言ってしまえば、なんでもなかった。
「そう、それで、伝言とか」
「伝言か」
少しもったいぶって、にやにやしながら、
「あるよ」
と言った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
