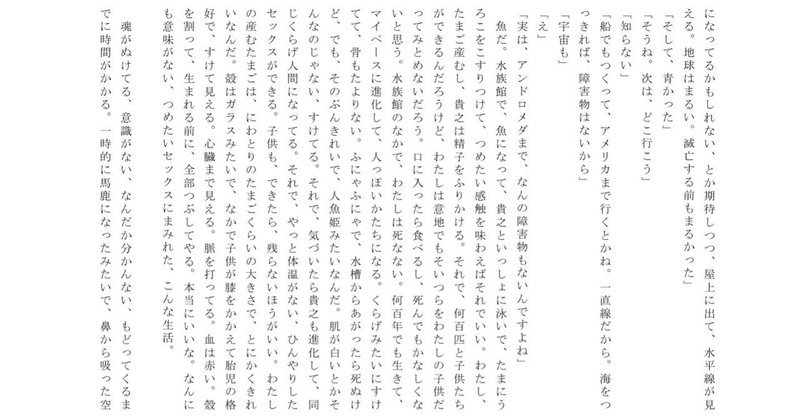
水族館物語(8)終
魂がぬけてる、意識がない、なんだか分かんない、もどってくるまでに時間がかかる。一時的に馬鹿になったみたいで、鼻から吸った空気が、耳から出ていく。からっぽの筒になって、ここはどこなんだか、本当に分かんない。ああ、学校だ、学校だ、学校だけど、むきだしの学校が気をぬいてわたしに本当の姿を見せていて、机とかいすの足に、いちいち長い影がのびていて、つめたい内蔵みたい。そろそろ脳みそがあたたまってくる、ここは学校で、教室で、わたしにはやることがあるのでした。修学旅行の朝みたいに、からっぽにする睡眠は、変な雰囲気の夢がつまっている、しばらくはこれがつづく、つづいたっていいけど、ぼおっとして、夕日の気配が校庭にかかって、窓がぴしりと鳴って、それだけで泣きそうなくらいに、からっぽのわたしはいま、いろんなものが反響して、それがまた教室じゅうに広がるみたいで、こんな、こんな不安なわたしは、いまからどうやって。こわいよ。ひびくんだ。息をはいても、吸いたくない、どくん、どくん、どくん、どくん、どくん、どくん。
来る。ぺたぺた、スリッパの音をさせて。濃い肌色のリノリウムの廊下、金の字で来客用とか書いてあって、茶色のスリッパ、足をひきずりながら歩く先生はポケットに手を入れて、猫背で、だから、わたしはすっと背筋をのばして、ちょっとでも大きくなろうと思って、待ちかまえる。
「いた」
「ええ」
「待った」
「別に。寝てました。夢見るくらい、ぐっすり寝てましたよ」
「どんな夢」
「なんか、知らない人がいっぱい出てきたのは覚えてるんですけど、雰囲気。にぎやかな」
「そう。よく、いねむりしてた」
「そんなことないと思いますけどね」
「うん。たぶん、一回か二回。印象に残ってるってだけのような気もする」
「先生」
「うん」
「なに、かぶってるんですか」
「おまえこそ」
先生、教壇にあがって、黒板にすがる。わたしは、正面の机に腰かけた。
「奈津実がくれた。バリ島に行ったときのおみやげだって。いらないって言ったけど、おもしろいからもらっといた。あまいにおいがする。なんか、神さまの仮面なんだって」
「わたしも奈津実にもらった」
「なんで、いまかぶってんの」
「先生も」
「おどろくかと思って」
「まあ、わたしも、そう思って」
「気が合うね」
神さまなんだか、悪魔なんだか、びっくりしたみたいにまんまるな目は、たまごのからよりまっ白で、マジックでぬりつぶしたくらいにまっ黒にぎょろぎょろしてて、茶色のひげが、ベルトまでとどく。
「同じやつか。微妙に色ちがいなのかな。おもしろい」
「おもしろいですね」
「ああ」
「なんですか」
「男の神さまと女の神さまか」
いやだな。
神さま。
南の島の神さま。
もう、くじけそうだ。ぜんぜん、顔をかくしてる気がしないんです。なにもかも、わたしをうつしてるみたいで、耳の奥に、びりびりひびくんです。わたしが、ちゃんと息をしてるのが、すごく分かって、それをずっと意識してるのはつらいんです。ほら、もう、どくん、どくん、聞こえてくるのが耳の奥の奥のずっと奥で、ひっくりかえって、ずっと遠い、ずっとずっと近い、わたしにふれてる空気が全部、どくん、どくん、波うってるんです。だって、ばれてるよ。もう、先生、海のなか、波にまきこまれてるじゃないですか。
「で」
「で、って」
「なに」
「もうちょっとしたら、奈津実、来ますよ。なんかつかうものを借りたいって」
「へえ。なんだろ」
「まあ、いろいろ」
「よくやるの、こういうところで、きみたちは演劇の公演。おれはよく分からない。奈津実、がんばってるなあ」
「はあ。そうですね。でも、わたしが、言ったんですね、これやろうって。言ったあとは、奈津実のほうがやる気になって、わたしは置き去りにされたけど」
「ああそう」
「そう、なの」
「きみたちさあ」
きみたち、きみたち、って、やめてくれるか。距離なのか、関係なのか、それは、なんだろう、なにが変わったんだろう。赤の蛍光色のマーカーで線をひいたみたいに、そのことばだけが浮かんで、くっきりと、目を閉じても、耳をふさいでも、指でなぞればそうだと分かる、きみ、ってことばが、ぐにゃぐにゃにひずませて、わたし、なにかに変わっていく。
神さま。
こわいよ、めんどくさいよ、神さま。名前を知らない神さま。
神さま、わたしは、大学受験失敗して、いま浪人生で、勉強してるんです。そんなことはどうでもいい。わたし、どうなるのか、おしえてほしい。そもそも、意志が弱いんです。わたし、自分で言うのもなんですが、もてるんです。かわいい、うん、人なみだと思います、でもうまいんです、なんか、つけこまれるのが。ここから、教室出て、廊下を右に、女子、男子、ってトイレを横切って、階段をおりて、学校を出て、校庭にそって、フェンスに右手をおいて、ぐるっとまわる、裏門があって、じめじめして、濃い緑の、じゅうたんみたいに厚い苔がしきつめられてて、暗い。裏口からトラックが入って、給食室のシャッターのところにつける。
ここは、ひみつの場所でした。
五年生のとき、かっこいい同級生の男の子と、ここで、キスしました。気持ちよかったな、とろんとして、体が重くなって、どんどんまわりの湿気を吸収するスポンジみたい、わたしも、なんか、人っていう苔みたいでした。もう一回やろうか、って、言われて、もう一回やりました。一回って、どこからどこまでなのか、一回目よりずっと長くて、わたしの口唇はよだれでどろどろになってた、わたしは、なんとなく、砂糖とか蜂蜜にまみれたアリを思い出したんです。
それから。それから、フェンスをつたって、反対側の角まで行くと、焼却炉がありました。いまは、もうないんです。ごみを焼いた、そうじのときに、ごみ箱を持っていって、ふたをあけて、ぶすぶす燃えてる、オレンジの舌みたいな火に、投げこむんです。
それがわたしは、好きで。
でも、いつのまにか、つかえなくなってた。
銀がくすんで、こまかい傷で白くなってる、針金でぐるぐる巻きにされた四角い焼却炉が、ぽつんと置いてあるのは、なんか、こわれたロボットがそのまま忘れられて、置き去りにされて、さみしそうにしてる、体育すわりして、まだぜんぜんはたらけるのに、って、泣きそうにしてるのを想像する。子供だから、すごい想像力があるんです。わたしは、さみしい子で、部活も習いごともやってなくて、ただひとりでまっすぐ家に帰るだけの放課後で、でも、ときどきロボットに会いにくるんです。話しかけたりするんです。それで、本当にかわいそうになってきて、わたしは、わたしの知ってる最高の愛情表現をする、キスしたんです。それは、もう、儀式でした。いつでも、焼却炉のロボットに会ったら、キスしてあげる、鉄の、さびた、血の、つんとするにおいがして、わたしはそれがいやだった。でも、やらなきゃいけなかったんです。血のにおいのするロボットを、なぐさめなきゃいけないからです。たりないじゃないですか。キスだけじゃ、だめなんですよ。わたしは、針金をとって、ふたをあけて、なかに入ったんです。目が痛い。すすで、鼻の穴が黒くなるんです。体育すわりして、ぼおっとしてました。
つまんなかった。
それが、ロボットの気持ちなんだと思った。ロボットとひとつになれて、心が通じ合って、つまらないけど、満足だったんです。そこで、ねえ、神さま。
神さま。
神さま。
神さま。先生。神さま、神さま、神さま、わたしのはじめての恋人は、先生だったんです。
「先生」
先生、仮面をとった。ただの先生だった。人間の男が、汗を、ぬぐっていた。
「先生、焼却炉は、なくなったんですね」
「うん」
「四角い空地になって」
「いや、花壇になった。いまは、ひまわりが咲いてるよ」
「うそ」
「うそじゃないけど。きれいだよ」
「あんなところに、きれいな花が咲くわけないじゃないですか」
咲いたとしたら。そうか。きれいかもしれない。まるい、人の顔みたいな、ぼたぼたした、重い、中身のつまった脳みそみたいな、でも黄色い、きれいなひまわりは、元気な、夏の花。
咲いたんだ。
黄色い海です。
「先生。ここまで来てる」
「なにが」
「水」
「へえ」
「駅は、もう水没してた。じとっとしてて、なんか息苦しくて、青黒いのがもやもやしてる。街灯とか、お店のあかりとか、五倍くらい大きく見えて、輪郭が変になってぶよぶよして、気持ち悪かった。歩いてる人は海草みたいじゃないですか。とまってたらサンゴみたいだし。車は回遊魚みたい。カツオとかマグロみたい。たまに、クジラがいる。わたしも小魚みたいに、海草をかきわけて、ふらふら駅に流れ着いたんです。電車の扉が開いて、飲みこまれて、網にかかって引き上げられたみたいに、電車がだんだん遠ざかる。気づいたら、もう水のなかにはいなかった」
わたしの言いたかったことは一割も伝わっていない、と思う。分からないことにはあいづちをうたない、先生は正直だ。泣きながらさまよっていた、体がだるくて、せつなくて、泣いた。そのまま言ったらうっとうしいだろうと、うつくしい表現をしてみたけど、よけいなことだった。
いいんだ。神さま。先生は人間で、わたしは神さまだから、わたしは、いまから、泣いて、泣いて、日本が水没します。いいよね。もう、そうでもしなきゃ、終わらないよ。
もう、わたしは、膝のあたりまで、水につかっている。
どんどん、かたちを変えていって。
「奈津実、来ないね」
先生、なに、笑ってるんですか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
