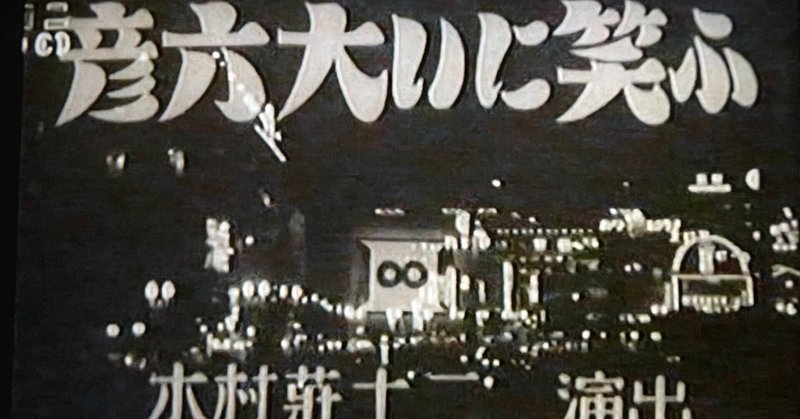
『彦六大いに笑ふ』(1936年11月12日・P.C.L.・木村荘十二)
P.C.L.映画研究。三好十郎原作・脚本『彦六大いに笑ふ』(1936年11月12日・P.C.L.・木村荘十二)を久しぶりにスクリーン投影。これは見事な作品。PCL映画草創期からメイン監督として活躍してきた木村荘十二としてはベスト作品ではないか。戦前、関東大震災後に目覚ましい発展を遂げた新興繁華街・新宿を舞台にした一晩の物語。
タイトルバックは、新宿のネオン。当時としては珍しい、二重露光でロールテロップで、スタッフ、キャストがクレジットされる。ひときわ煌めいているのは、1933(昭和8)年に開店したばかりの新宿伊勢丹。もともと明治時代、今の外神田一丁目に開業した伊勢丹が関東大震災で焼失、翌年には百貨店形式で神田に再建されるが、1930(昭和5)年に新しく新宿へ出店を決定。東京市電気局所有の広大な土地を落札。2階にはアイスケート場を完備するなど昭和のデパート文化を支えることになる。

その伊勢丹のネオンが眩しく煌めく、その反対側、甲州街道に程近い、昔ながらの歓楽地の再開発が進んでいた。資本家の手駒として、力づくで立ち退きを手がけているのが、新興やくざ。不動産や飲食業を経営しながら、土地ブローカーとしても暗躍。「事件屋」と呼ばれた悪どい連中である。
この映画の舞台は、そうした地上げ屋に狙われた繁華街のアミューズメント施設。おそらくは大正時代ぐらいからある老朽化した建物一階はカフェー、二階はビリヤード場。他の店子たちは、おどかされてわずかの金で立ち退きを余儀なくされている。といったこれまでの状況が、登場人物たちの会話で次第に明らかになっていく。
トップシーンは、このビリヤード場・旭亭。新宿の劇場(おそらくムーラン・ルージュ新宿座)がはねて、踊り子・ミル(堤眞佐子)、同僚の踊り子(宮野照子、林喜美子)たちがタップダンスの練習をしている。アコーディオン伴奏をしているのは、劇場の若き学士・修(河村弘二)である。修は窓の下に、怪しい男たちがいるので、気になって、テンポがおそろかになる。ミルはそのことに腹を立てて、修を激しくなじる。気性が激しい娘なのである。


やがてミルと修が恋人同士であること、このビリヤード場がミルの実家で、彼女が娘・千代であることが明らかになっていく。ビリヤード場の奥には、座敷があり、店を任されている年増女性・お辻(英百合子)が、うつ伏せになりだらしない格好をして、踊り子や修たちと会話をしている。が、ミル=千代は、お辻にぞんざいな態度。相当仲が悪いことがわかる。
お辻は、千代の父・政宗彦六(徳川夢声)の愛人で、長年の腐れ縁。浮気性のお辻は、何度も若い男に目をつけて一緒になり、彦六の元を去ってきた。しかし捨てられ、無一文になるとまた舞い戻ってきた。まさに「腐れ縁」である。千代は、女として、娘として、お辻のだらしなさを受け入れることはできない。
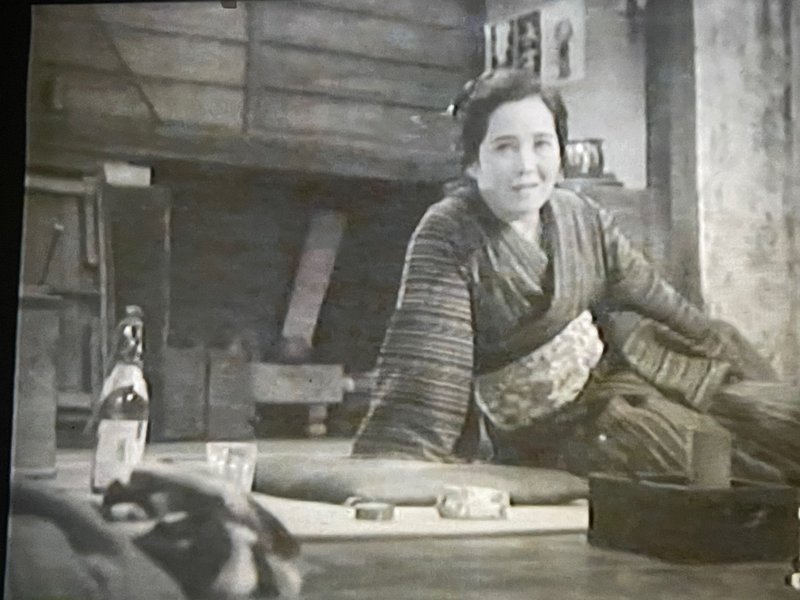
という、この家族の「これまで」が、セリフの端々から観客が窺い知ることができ、いよいよ彦六が登場。五十代後半の彦六は、ごろごろしているうちに病気がちになり、床に臥せっているようだが、これも地上げ屋の立ち退き交渉のための「手」である。お辻が、階下のカフェーに行った隙に、奥から出てきた彦六。娘の恋人である修と酒を酌み交わし、彼が気性の激しい千代に、相応しい相手だと瞬時に見抜いてしまう。彦六はかつて、府中で鳴らした無頼で「自由党」の若い衆として大暴れして投獄されたこともある。
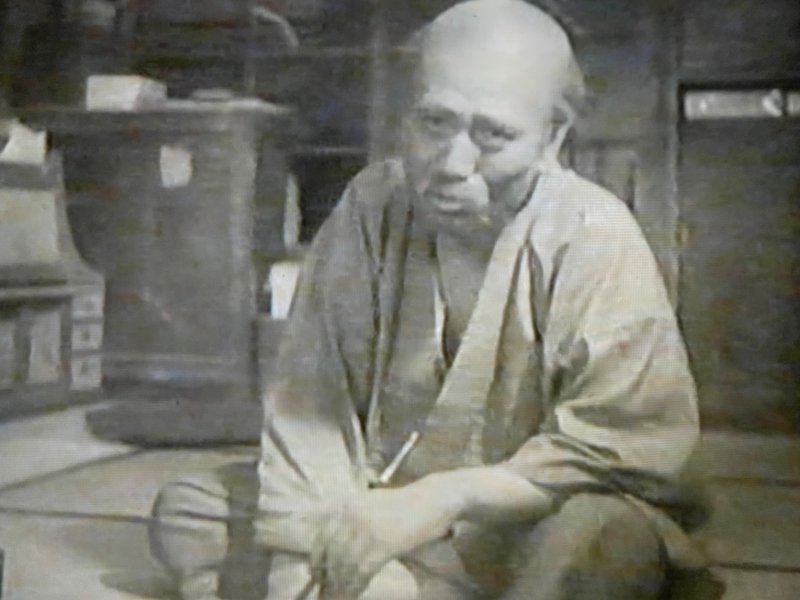
そんな彦六が、酒の肴の「支那そば」を買いに、階下の屋台に行った隙に、やくざたちがビリヤード場に上がり込んで狼藉三昧。店を壊し始め、世帯道具をめちゃくちゃにする。実は、お辻が、階下のカフェーの主人・鉄造(小島洋々)と出来ていて、かつて彦六の世話になった鉄造が裏切って、地上げの元締め・事件屋の白木(小杉義男)からリベートをせしめて、立ち退き幇助をしていたのだ。
そのお辻のずる賢さを見抜いていたのは千代だけじゃなくて、彦六も全てわかっていた。その上で、悠然としている。しかし、やくざたちの狼藉に、彦六が一喝。その迫力に誰もがタジタジとなる。いかに彦六がすごい男だったかが、チラリと垣間見える。
というわけで、徳川夢声。いつもの好々爺の雰囲気なのだけど、時折、無頼の影を匂わせる。その芝居と演出が見事。お辻を演じている英百合子も、戦前から1970年にかけて「東宝映画の母」として、戦前の原節子の母親から「社長シリーズ」の小林桂樹の母親役まで演じてきた「理想のお母さん」女優のイメージが強い。しかし、ここでは身を持ち崩しただらしない女であり、相当のワルでもある。それがまた見事!
で、カフェーの主人・鉄造は、たった一人しかいない女給・おあさ(清川虹子)を手籠にして「新しく出来る飲食店の女給頭にしてやる」と甘言。田舎から出てきて、カフェーの女給に身を持ち崩したおあさは、純情を捧げた鉄造にぞっこん。しかし鉄造とお辻が通じていて、自分が裏切られるのではないかと感じている。というわけで、お辻には敵愾心をむき出しにしている。

後半、地上げ屋たちが実力行使をして、建物をぶち壊していくのだが、その騒音と粉塵のなか、清川虹子と英百合子が壮絶なキャットファイトを繰り広げる。殴り合い、掴み合い、髪の毛を振り乱す二人。清川虹子にしても、それまでの喜劇映画のおかみさんキャラとは真逆の「女の純情」を激しく演じている。おそらく日本映画で、ここまでのキャットファイトは、これが初ではないだろうか。
物語は深夜12時から、朝方5時ぐらいまでの、一晩だけ。鉄造のカフェーには、酔客(三島雅夫!)と、奥の席で黙々と飲んでいる男(丸山定夫)だけ。おあさが、鉄造の浮気をなじって大喧嘩している隙に、酔客はビール瓶を抱えて、無銭飲食で逃げてしまう。おあさが気づいても時すでに遅し。その代金は全ておあさが背負い込むことに。
さて、一人残った男は、おあさの酒の相手をしながら、これまでの経緯。事件屋の白木と、彦六の確執、これからこの店がどうなるかを聞く。その頃、事件屋の白木は、鉄造とお辻を連れて、ビリヤード場へ。彦六に最後通牒を突きつけるためだった。白木はいつもズボンの腹にピストルを忍ばせている男であることも、おあさの話から明かになる。

そこで銃声! 彦一は立ち上がって、二階に行くと。ビリヤード場では、白木と鉄造がビリヤードをして、お辻がカウントをして、何事もなかったのかのようである。しかし、実は修羅場があって、千代が日本刀を振りかざして、白木が発砲していたのである。
さて、二階に現れた彦一は、実は彦六の息子で、千代の兄。若い時に無頼の徒となり、親父と大喧嘩して、行く方しれず。今は府中で家庭を持って、真面目に生きている。子供が生まれたことを父と妹に報告するために、新宿へ戻ってきたのだ。この映画、ここからが見事である。深夜2時すぎに、彦一が現れ、白木たちが一旦引き下がる。そこからの父と息子、兄と妹の再会。バラバラになった家族がリユニオンするのである。彦六は彦一から一緒に暮らそうと誘われ、千代も府中から劇場に通えばいい、と納得。
しかしその前に、落とし前をつけなければならないことがある。白木たちに数百円で立ち退かされた住民たちのために、一銭でも多く取りたい、という思いから彦六は粘っていたのである。聞けばすでに二千五百円も、白木から出させているという。彦六は五千円は吐き出させたいと考えていた。「父っあん、それぐらいでいいだろう?」「ああ、いいだろう」と彦六は、黙って出ていくことにする。

ラストシーン。お辻に三行半をつける彦六。「あたしは一体どうなるんだ?」と荒れるお辻に、ポンと三百円を投げつける。すると、泣きじゃくっていたお辻が必死に金をかき集めて、握りしめる。どこまでも浅ましいのである。
このシーンを三好十郎の原作シナリオから引用する。
お辻 (坐つてゐる)……どうしてくれるんだよ? 皆で寄つてたかつて私に恥ぢを掻かさうつて言ふんだな? よし、なら、死んでやる! 死んでやるとも!(刀をひねくり廻す)
彦六 ……死んで見ろ。昔の縁だ、見届けてやる。死んで見ろ。……おい、どうした?
お辻瞬間キヨトンとするが、不意に刀を放り出して畳に突伏してヒーヒー声を出して泣く。彦一が刀を拾ひ鞘に納めて持つ。
彦六 どうだ、死ぬより金の方がいいだらう。三百円ある筈だ。まあ、達者で暮せよ。
お辻、金を受取り、夢中で勘定し始める。ミルを先頭に、父子三人、扉口の方へ歩いて行く。ミルは「糞でも喰へつ! こんな家!」。彦六は立止つて、お辻や、部屋の中を見廻してゐたが、大声にカラカラ笑ふ。
全てが終わって、彦六、彦一、千代が、着のみ着のままで、新宿駅に向かう。このロケーションが素晴らしい。南口方向に向かって歩くショット。後年「太陽にほえろ!」などで繰り返しこのあたりが出てくるが、戦前の映像、しかもロケーションはおそらくこれが初めてかもしれない。ずっとセット撮影だったので、ラストのロケが効果的。このロケーションは前半、千代が恋人の学士・修を「物騒だから」と、新宿南口まで見送るナイトシーンに呼応している。ほとんどがセット撮影なので、このラストは希望に満ちた開放感を感じさせてくれる。
新興ヤクザVS昔ながらの無頼。おそらく日本映画では初のやくざ映画ではないかと思いつつ、昭和11年のドラマツルギーを堪能した。

P.C.L.を支えた美術の久保一雄のセットデザインも素晴らしく、ビリヤード場とカフェーの空間設計が見事。奥行きのある空間で、映画的な人物の出し入れで濃密なドラマが展開。昭和20年代の黒澤明映画のような、空間と登場人物たちの動き、モンタージュが本当に濃密で、見ていて惚れ惚れする。これは傑作である。
ちなみに八代目・林家正蔵が、その名跡を海老名家に返上した後に、林家彦六を名乗ったのは、この『彦六大いに笑ふ』の徳川夢声にちなんだもの。1936年のキネマ旬報ベストテンで8位となった。
よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。
