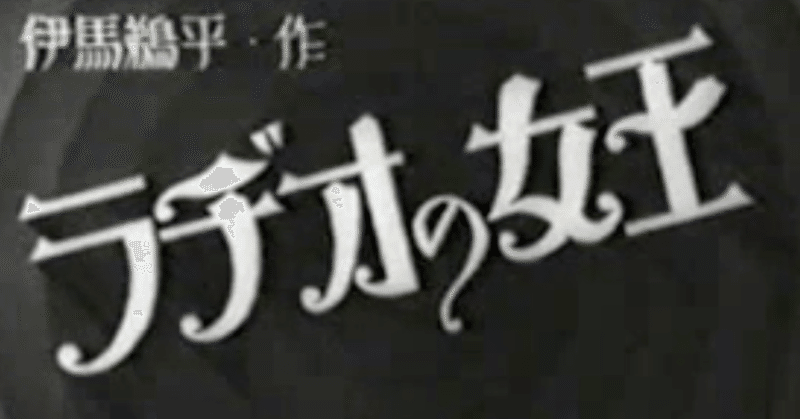
『ラヂオの女王』(一九三五年八月十一日・P.C.L.映画製作所・矢倉茂雄)
『ラヂオの女王』(一九三五年八月十一日・P.C.L.映画製作所・矢倉茂雄)
製作=P.C.L.映画製作所/1935.08.11・日本劇場/八巻・二〇三五m・七四分
【スタッフ】作・伊庭鵜平/監督・矢倉茂雄/脚色・永見隆二/撮影・川口政一/録音・市川網二/装置・北猛夫/現像・小野賢治/編輯・岩下廣一/音楽監督・紙恭輔/演奏・P.C.L.管絃楽團
【キャスト】千葉早智子(見染貴美子)/英百合子(金森夫人)/神田千鶴子(オペレッタの歌手)/堤眞佐子(アナウンサー)/宇留木浩(金森欽吾)/丸山定夫(金森士郎五郎)/丸山章治/岸井明(浪曲師の付人)/生方賢一郎/伊達信/藤原釜足(川村飛行機社員)/笑の王國・専属 古川緑波(大阪堂・見染惣右衛門)、生駒雷遊、横尾泥海男(引き抜きの男)、山野一郎(映画スター)、杉寛、堀井英一、多和利一、鈴木桂介、土屋伍一、花井淳子、三益愛子/東宝専属・谷幹一、森野鍛治哉(詐欺師)/吉本興業専属・石田一松・鶴枝・九官鳥、林家雅子、林家染團治
日本でラジオ放送がスタートしたのは、大正十四年。関東大震災の二年後。高価だった受信機も、昭和に入るとサラリーマンが月賦で買える時代となった。朝にはラジオ体操、昨夜には音楽や演芸番組を楽しんだ。レコード会社は、流行歌のプロモーションにラジオを最大限に活用。映画会社も映画スターを積極的にラジオに出演させた。トーキー時代となり、ラジオと映画の親和性はますます高まった。
この『ラヂオの女王』は、幼稚園の先生・千葉早智子が、映画女優となり、ラジオスターとなっていくシンデレラストーリーに、ラジオ嫌いの飛行機会社の社長・丸山定夫と、ラジオ好きだが吝嗇な老舗薬舗の主人・古川緑波の対立。千葉早智子の恋人で、丸山定夫の息子・宇留木浩の恋の行方が賑やかに展開。モガの「当世娘気質」と「道楽息子」の恋愛を描きつつ、ラジオ・メディアの効用を具体的に見せてくれる。尖端的な娯楽映画でもある。
古川緑波が立ち上げた「笑の王国」のユニット出演で、生駒雷遊、山野一郎、三益愛子たちが次々と出演。ロッパはこの年の六月に、「笑の王国」を脱退。東宝に引き抜かれて七月には古川緑波一座を旗揚げしているので、そのガス抜きも兼ねてのユニット出演だったのかもしれない。また、東京に進出した吉本興業の芸人もフューチャー、翌年からPCLと吉本の本格的な提携がスタートする。
ラジオ局の舞台裏を描くバラエティ映画としては、パラマウントの『ラヂオは笑ふ』(一九三九年)が作られるが、それに先駆けること二年前。監督の矢倉茂雄は、松竹蒲田の出身で、『踊り子日記』(一九三九年)からP.C.L.のモダンなカラーを支えた。本作では、盛りだくさんのエッセンスをテンポ良くまとめ上げ、スピーディなコメディに仕立てている。同時に、ロッパたちが目指した「笑の王国」のアチャラカ芝居のテイストを片鱗とはいえ味わうことが出来る。この時期のP.C.L.映画ではダントツの出来で、昭和一〇年の映画界、演芸界、ラジオ事情が体感できる。
映画はラジオ体操の朝から始まる。さまざまな家庭の様子がラヂオ体操を通して描かれる。サラリーマン(藤原釜足)は子供たちとハツラツと体を動かしている。川村飛行機社長の金森士郎五郎(丸山定夫)は、まだベッドで寝ていて、隣のラジオがうるさいとオカンムリ。「あなたもたまには早起きをしてラジオ体操でもやってご覧なさい」と、夫人(英百合子)に布団を剥がされる。「ならお前やれ、お前この頃少し痩せておるぞ」。早速ラジオ体操の効用が説かれる。ここで丸山定夫がラジオ嫌いであることが強調される。
一方、薬舗・大阪堂の見染惣兵衛(古川緑波)は、大のラジオ好き、使用人、家族を集めて張り切ってラジオ体操に勤しんでいる。娘・貴美子(千葉早智子)は、そんな父親に辟易している。ラジオ体操が終わると、大阪堂の訓話が始まる。昨日は二宮金次郎、今日は「アメリカの大金持ちロックフェラーいう人の話したるよって、みんなよう聞くんやで」。うんざりする使用人たち。これはロッパお得意の「ガラマサどん」の展開。
ロックフェラーは失業者から、働いて、働いて大金持ちになったと得意げな大阪堂。こういうわからずやをやらせたらロッパは天下一品。「節約・貯金・お金が大好きにならなあかん」「ほんまにお金に惚れこまないかん。男がホンマに惚れこんでいたら、なんぼでも靡いてきよる」と大阪商人らしいところを見せる。このロジックは、「社長シリーズ」第一作『へそくり社長』(一九五六年・東宝・千葉泰樹)の先代社長の社訓でもある。そういえば『へそくり社長』に古川緑波も出演していた。
「何事も目的を決めたら、狙いを定めて」とロッパがカメラ目線で言うと、隣家の金森士郎五郎が、庭先で弓矢を射るシーンに繋いでいる。堅物の親父さん、飛行機のパイロットを目指している大学生の倅・欽吾(宇留木浩)に「ちとムッソリーニあたりを手本にするといい」と、ムッソリーニの人物伝を語り出す。
親父の言葉を遮るように、欽吾は「昨夜の話、ダメでしょうか?」と切り出す。大阪堂の娘・貴美子と結婚したいという希望は、頑固親父によって見事に粉砕される。「あんなガリガリ親父の娘なんて、絶対ならん!」
モダンガールの貴美子は、幼稚園の先生。やはり父・惣兵衛に「ねえ、お父さん、昨夜の話なんだけど」と隣の家の欽吾との結婚を持ち出す。「あんな古臭い、頑固親父の息子なんぞ、あかん言うたらあかん」とケンもほろろ。
前途多難の恋人たち。「このままでいくと、私、あの薬剤師の奥さんにされちゃうわよ」。惣兵衛は自分の甥、つまり貴美子の従兄弟・久一と結婚させようと決めていた。そこで貴美子「いっそ逃げ出して、二人きりの世界を作らない」。昭和十年の女の子としては尖端的である。「つまりかけ落ちのことだろ?」「つまり新しい言葉でいえば…」。親父に似て、保守的な欽吾は「すぐ新聞に出ちゃうから」いやだと拒否。この頃、かけ落ちはスキャンダルで、新聞ダネになっていた。脛齧りの欽吾は生活費の心配をしているが、貴美子は「あんたはずいぶん実利的ね」。そこで貴美子は、これからお互いの親に気に入られるように運動しよう「一種のデモってわけよ」と提案。
何か良い方法はないかと、ベンチに座って考えることに。触れ合う手と手。「貴美ちゃん、僕の手を握ってもいいよ」と今度は欽吾が尖端的なことを言う。当時としては、相当なエロ描写である。
ここから先は
¥ 200
よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。
