
『新・忍びの者』(1963年12月28日・大映京都・森一生)
今回のカツライスは森一生監督二本立。まず市川雷蔵のシリーズ第3作『新・忍びの者』(1963年)。左翼のセシル・B・デミル、山本薩夫監督の娯楽映画作家としての手腕が堪能できた。しかし山本薩夫監督は「忍びの者」が巻き起こした忍者ブームで、忍者ごっこをした子供が亡くなったことに責任を感じて自ら降板。そこで大映京都のベテラン、森一生が引き継いでの忍者スペクタクルとなった。脚本は第一作からの高岩肇。
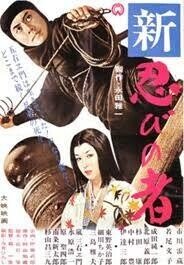
昭和33(1958)年、山田風太郎が「甲賀忍法帖」を発表。たちまち「忍法帖ブーム」が出版界を席巻。最初は大人のエンタテインメントだったが、昭和34(1959)年、白戸三平が貸本劇画「忍者武芸帳 影丸伝」が刊行され、小中学生の男の子たちも熱中した。特に「影丸伝」は、永禄年間から本能寺の変、天正末年までの支配者層と、農民や領民たちの間の一揆や、戦乱を背景にした「歴史の中の忍者たち」を描いていた。さらに昭和36(1961)年、横山光輝が「少年サンデー」に連載した「伊賀の影丸」が少年たちに空前の忍者ブームの火種となる。
そうしたブームの最中、戦前から作家、前衛芸術家、映画美術、舞台演出を手がけてきた作家・村山知義が、昭和35(1960)年11月から「赤旗日曜版」に連載開始した「忍びの者」(〜1962年5月)を、山本薩夫監督が、大映の永田雅一に映画化を薦めたことで、このシリーズがスタートした。これまで「忍術映画」は、サイレント時代から、映画ならではのトリックを売り物にひとジャンルを作ってきたが、山本薩夫の『忍びの者』は、巻物をくわえてドロン!の忍術ではなく、あくまでも科学的なバックボーンがある特殊技能としての忍者のリアルな物語として作られた。支配する側と支配される側の対立という点では、白戸三平の「忍者武芸帳」シリーズと同じアプローチである。というわけで、小説、漫画を中心とした「忍者ブーム」にさらに拍車をかけたのが、市川雷蔵の「忍び者」シリーズだった。

さて『新・忍びの者』は、前作のラスト、石川五右衛門(雷蔵)が、京都三条河原で釜茹でにされるところで「完」だった。そして今回は「この日― 豊臣秀吉の暗殺に こと破れた石川五右衛門は、京、三条河原に於いて、釜煎りの極刑に処せられた。」とアバンタイトルで字幕スーパーが出る。
三条河原に集まった野次馬の中に、徳川家康の命で動いている服部半蔵(伊達三郎)がいて、次のカットでバックショットの五右衛門が釜へと連行される。ここで半蔵が、他の罪人を身代わりにして、五右衛門を救出。そこから物語が始まる。「五右衛門は生きていた!」。このオープニングは、この映画の3年後に公開される『007は二度死ぬ』(1967年・英・ルイス・ギルバート)の先取りでもある。
関白の地位を嫡男・秀次(成田純一郎)に譲り、太閤となった秀吉(東野英治郎)は、自らを暗殺しに来た、雑賀衆の忍びの者・石川五右衛門処刑して一安心していた。しかし五右衛門は、憎っくき、妻子の敵である秀吉を暗殺すべく、また自分の存在をアピールするために大泥棒として暗躍。大名から奪った金を、庶民にばら撒いていた。ここで「大泥棒・石川五右衛門」伝説がヴィジュアル化される。その辺りは、眺めていて楽しい。
「金が必要なら用意する」と服部半蔵が嗜めるが、五右衛門は自ら「生きている」ことをアピールしていく。大映京都のバイプレイヤー、いつもは悪役が多い、伊達三郎の服部半蔵がなかなかいい。雷蔵の好敵手であり盟友、という感じなのである。前作『続・忍びの者』のティーザー・ポスターで天知茂がクレジットされていたが、おそらくは服部半蔵を演じる予定だったのだろう。何かの事情で天知茂が出演できなくなり、伊達三郎が演じたものと思われる。それほど「良い役」なのである。
さて、五右衛門は雑賀衆の仲間、名張の犬八(杉田康)と共に、あの手この手。秀吉は淀君(若尾文子)との間に、秀頼が生まれ、世継ぎにしようと目論んでいた。しかし北政所(細川ちか子)、嫡男・秀次はそれを承服できない。折しも秀吉は、朝鮮、明国への出兵を開始するが。「天正末年、秀吉は、朝鮮討伐を布告し、各大名に兵員・武器・弾薬・食糧、更には輸送船の提供を、強制的に割り当てた」のである。「既に江戸に移され、一面葦の生い茂った湿地帯に営々として国作りに没頭していた家康のもとにも出兵の要請が届いた」。
今回の家康は、永井智雄から三島雅夫へ。さらに老獪のタヌキぶりに磨きがかかっている。もちろん家康は、江戸整備を理由に出兵を断る。朝鮮討伐で秀吉の評判が悪くなるかと、五右衛門も家康も思うが、秀吉の討伐は破竹の勢いで初動は成功する。映画は、秀吉の晩年の史実を描きつつ、例によって忍者・五右衛門が暗躍する。
家康は、服部半蔵を使って、五右衛門の復讐心を利用、秀吉暗殺、豊臣家崩壊を間接的に仕掛ける。秀吉が明国へまで出兵したのは、幼い秀頼に全ての権力を移譲するつもりだったのである。50代にして出来た秀頼を可愛がるあまりに、周囲には不協和音が高まっていく。五右衛門は、犬八とともに、秀吉不在の屋敷に忍びこみ、秀頼と淀君を亡き者にして、秀吉に自分と同じ苦しみを味合わせようとするが失敗。
しかし、五右衛門は屈せずに秀吉暗殺の一念で、生命を掛けてあの手この手を駆使していく。五右衛門が秀吉に送った手紙の文面である。「猿め! 朝鮮は負け戦だぞ 信頼していた武将は背を向けている。民百姓の塗炭の苦しみを知れ やがてお前も 業火の苦しみを知る時が来る」。
やがて「破竹の快進撃も限界に達し、朝鮮戦線は膠着状態が来た。朝鮮は明国を通じて和平交渉を申し入れ、それを機に秀吉は、名護屋をひきあげ新築なった伏見城に帰還した。」ここから秀吉の落日が始まる。秀吉の不在中、秀次は大名たちに軍資金を乱発して、それは回収できたものの、五右衛門と犬八が聚楽第へ忍びこみ、千両箱を奪い、秀次は窮地に陥る。秀吉の怒りを買って、切腹を命ぜられ、文禄四年7月15日、高野山で切腹。いわば謀殺されてしまう。
こうして事は、五右衛門の思い通りに展開していく。それは家康が仕掛けたことでもあるが、五右衛門はそれを知りながら、お互いの利害が一致したまでと嘯く。「秀吉の死後―老せずして王道権を握った家康は、実質上天下をその掌中に握った」のである。とにかくスピーディな展開、奇想天外なアクション。そして歴史の中の石川五右衛門の暗躍が、何よりも観客を楽しませてくれる。娯楽映画の面白さが詰まった佳作!
よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。
