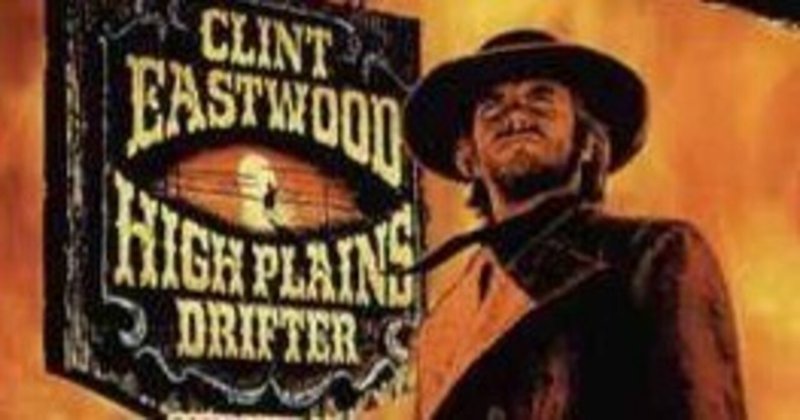
『荒野のストレンジャー』(1973年・ユニバーサル・クリント・イーストウッド)
6月9日(木)娯楽映画研究所シアターでは、クリント・イーストウッド監督”High Plains Drifter”『荒野のストレンジャー』(1973年・ユニバーサル)を久しぶりにスクリーン投影。僕が持っているDVDは20年以上前のもので、4:3のレターボックス収録なので画質が悪く、16:9のスクリーン投影してもザラザラの映像なので、観そびれていた。アマプラで配信されていたマスターもさほど良くはないけど、1970年代のフィルムの質感が懐かしく堪能した。

カリフォルニア州の湖、モノ・レイクでロケーションした湖畔の小さな町・ラーゴに、ふらりと現れた”名無し”のストレンジャー(イーストウッド)。いきなり、三人のならず者・ビル、トミー、フレッドを射殺するオープニングシークエンス。クライマックスのような一瞬のガンファイト。これぞイーストウッド!という感じの構図で、床屋を舞台に悪漢どもをぶちのめす。その爽快さ!
このラーゴという町は、鉱山会社とそこの雇用によって持っていたが、一年前に、保安官が無法者たちによって鞭のリンチで殺されていた。それをみてみぬふりをしていた住人たち。彼らは何かを隠している。
さて、その無法者たちが出所してくることになり、町への復讐を恐れた住人たちは、冒頭の三人のならず者を用心棒として雇ったものの、彼らはやりたい放題。住人たちも手を焼いていたところへストレンジャーがやってきて殺してしまう。しかし、刑務所から三人の無法者が出所するのは翌日。町の人々は、ストレンジャーを新たな用心棒として雇って、三人の無法者に備えることにするが…
イーストウッドのキャラクターは、セルジオ・レオーネの”名無し三部作”『荒野の用心棒』(1964年)、『夕陽のガンマン』(1965年)、『続・夕陽のガンマン 地獄の決斗』(1966年)の延長にある。しかしこのストレンジャー、単なる西部劇ヒーローではなく、この世のものとも、あの世のものともわからない「ゴーストライダー」的なのである。
「用心棒が、町の人たちのために、悪漢たちをやっつける」という西部劇のフォーマットに、本当に狡猾で悪いのは「傍観者」の住人たちかも知れない。という裏テーマを忍ばせておいて、クライマックスに近づくにつれて「善良な人々の仮面」が剥がされていく。
『七人の侍』(1954年・東宝・黒澤明)のように住人たちに武装をさせて、敵との闘いのシミュレーションをする。ストレンジャーは町を「真っ赤なペンキ」で塗れと命じ、町の入り口にある墓場に「地獄の入り口」と看板を出す。この異常さ、異様さは、初見の時に戸惑った。しかしラストにその意味が、なるほど、なるほどとなる。
三人の無法者が町へ現れ、町の人々を次々と殺していく。応戦する人々をよそに、ストレンジャーはその場を立ち去ってしまう。その違和感と、冷徹さ。最後の最後には戻ってきて、無法者を倒すのだけど、ストレンジャーが彼らを倒すのは、町のためではなく、非業の死を遂げた保安官のためだったことが、ここではっきりとわかる。
前半からストレンジャーが見る「悪夢」がインサートされる。鞭で打たれて、全身が傷だらけになって瀕死の状態となる。それが鞭で殺された保安官と、次第にリンクしていくことで「勧善懲悪の悪党退治の物語」から「殺されれた保安官の報復」に転じていく。
しかもストレンジャーは、この世のものか、あの世からの使者なのか、観客にもわからなくなってくる。ラスト、保安官の墓標にその名前が刻まれたことを見届け、馬上のストレンジャーが去っていく。それがふっと陽炎のように消えて、エンドマークとなる。
ストレンジャーは、殺された保安官の霊が復讐のためにあの世から蘇ったとも受け取れるし、保安官の家族ともとれる。「無念」を晴らすための戦いであることが、クライマックス、炎上する町のなかにすっくと立つストレンジャーの姿(これがかっこいい)で明らかとなる。
わが「大菩薩峠」の机竜之介のように、幽明の境を彷徨うストレンジャーの描写。日曜洋画劇場で初見の時には「え? 消えたの?」と驚いたが、ファンタジーとして観ると、ああ、保安官はこれで成仏(昇天)したんだなと得心。
よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。
