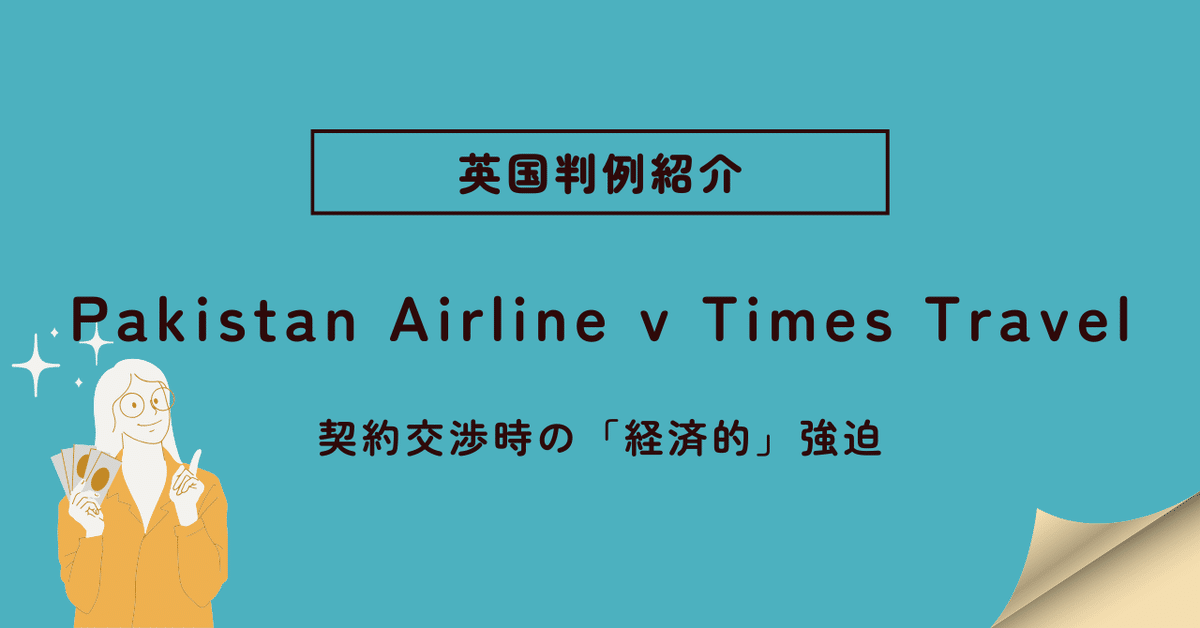
【英国判例紹介】Pakistan Airline v Times Travel ー契約交渉時の「経済的」強迫ー
こんにちは。
お読みいただきありがとうございます。
今回ご紹介するのは、Pakistan Airline v Times Travel事件(*1)です。
今回の判例は、契約法における強迫(duress)に関する近年の判例で、最も重要なものです。
いつもは、ぼくが個人的に興味を持った判例を紹介することが多いので、あまり実務とは関係ないものも多いのですが、今回は、ちょっと関係するんじゃないかと思っています。イギリス企業と契約交渉をされる方は、頭の片隅に置いておいてもいいかもしれません。
なお、このエントリーは、法律事務所のニューズレターなどとは異なり、分かりやすさを重視したため、正確性を犠牲しているところがあります。ご了承ください。
前提知識:強迫(duress)とは?
本件の概要に入る前に、英国の契約法における強迫について解説します。
強迫とは、「一方当事者による不当な圧力や強制を伴うもので、他方当事者を契約に誘引し、その結果、他方当事者の同意を無効にするもの」などと言われています(*2)。
日本の民法における「強迫」(96条)と似たものと理解してもらえれば大丈夫かなと思います。
強迫について規定する制定法はなく、強迫による契約の無効の主張は、もっぱらコモン・ロー上認められてきたものです。
事案の概要
パキスタン航空(*3)(被上告人)は、イギリスの小規模な旅行代理店であるタイムス・トラベル社(上告人)に対して、英国ーパキスタンの直行便のチケットを販売していました。
当事者間で紛争が発生したため、上告人が未払代金の支払いを求めたところ、被上告人は、上告人へのチケットの割当てを5分の1に減らした上で、上告人に対して、未払代金の放棄と新たな代理店契約の締結を迫りました。
上告人は、このまま十分なチケットの割り当てが行われない状況が続けば廃業に追い込まれる状況にあったため、やむなく未払代金の放棄と新契約の締結に同意しました。
その後、上告人は、被上告人に対して、未払代金の支払いと新契約の無効を主張して、訴訟を提起します。
原審では上告人が勝利したものの、控訴審ではそれがひっくり返ったため、上告人が上告を行いました。
争点:どのような場合に「経済的」強迫が成立のか?
本件は強迫の典型的事例とは異なる
ぼくが大学1回生のときに民法総則の講義で習った強迫の事例は、「この契約書にサインしないとお前をボコボコにするぞ」と言われて恐怖から契約を締結した、みたいなものでした。強迫の手段が不法(unlawful)である場合ですね。
本件は、そういう事例ではありません。パキスタン航空は、ビジネス交渉の一環で、タイムス・トラベルに未払金の放棄と新契約の締結を迫っているわけです。このような交渉が違法かと言われると難しいです。少なくとも英国法では、合法(lawful)な手段と分類されています。
英国法では、このような合法的な圧力行使による強迫を、「legitimate duress」(合法的強迫)と呼んでいます。また、合法的強迫は、多くの場合、本件のようなビジネス交渉の場で問題となるため、「economic duress」(経済的強迫)と呼ばれることもあります。
パキスタン航空は未払金の支払義務が無いと信じていた
彼らは、一貫して、タイム・トラベルに対する未払金の義務が無いことについて、善意であったと主張しています。
パキスタン航空の善意は、原審及び控訴審のいずれでも認定されています。
派生的な争点として、このような強迫をした側の認識がどのような意味を持つのかについても、当事者間で主張が対立していました。
裁判所の判断
最高裁判所は、上告を棄却しました。
タイムス・トラベルの敗訴です。
最高裁判所は、次のように判示しました。
① 英国法上、経済的強迫を含む、合法的強迫は存在する。
② 経済的強迫が成立するためには、以下(i)~(iii)の事実が必要である。
(i) 一方当事者による不当(illegitimate)な圧力の存在、
(ii) これにより他方当事者が契約を締結したこと、及び、
(iii) 他方当事者には、圧力に屈する以外に合理的な選択肢がなかったこと
③ 圧力の不当性は、要求の理由に着目すべきである。
④ 商業的な利己心は、一般的に正当化される。
つまるところ、経済的強迫の主張は、認められることがあるものの、その範囲は極めて限定的であるということです。
結論としては、タイムス・トラベルの主張は認められなかったのですが、その理由付けは、多数派と少数派で異なります。
少数派の意見を書いたBurrows卿は、次のような趣旨を述べています。
請求権の放棄の要求については、これが悪意で行われたことを立証しなければならない。
この考えは、「パキスタン航空は、未払金の支払義務について善意であったため、その放棄の要求は不当な圧力に当たらない」という結論を導きます。逆にいえば、Burrows卿は、もし悪意で請求権の放棄の要求を行った場合には、合法的強迫が成立するようにも考えているようにも読めます。
これに対して、多数派は、悪意で行う請求権の放棄の要求が合法的強迫になるというのであれば、望まない契約の不確実性を巻き起こすとして、Burrows卿の見解に反対しています。
考察
バーゲニングパワーの単なる主張が不当な圧力になり得るという命題には何の根拠もない
これは、多数派のBurrows卿の見解に対する批判です。また、権利放棄の要求は、契約締結の前提条件として、相手方に金銭を要求するのと変わらないとも言っています。「なんか問題ある?」と言いたいのでしょう。
多数派は、もし、契約交渉における圧力の行使により契約が解除されるというのであれば、それは、契約上の信義則(general principle of contractual good faith)や交渉力不均衡の法理(doctrine of imbalance of bargaining power)を認めるに等しく、英国法ではこれらの原則は認められていない、と言っています。
もし、このような原則が認められてしまうと、せっかく当事者の合意によって定めた契約が、当事者の予期しないところでひっくり返ってしまい、不確実性が生じるということですね。
不確実性(uncertainty)に親を殺された英国法
これまでも何度か触れていますが、英国法は、当事者の合意を尊重し、これを損なうような不確実性を、蛇蝎のごとく嫌います。
その背景には、成文法ではなく先例法に基づいた法体系を構築してきたことが関係しているんじゃないかと思っています(またどこかで書きたい)。
いずれにしても、本判決によって、有効な契約上の合意に基づく主張や、交渉力を背景にした圧力が、経済的強迫に該当する可能性は限定されることになりました。
契約交渉の担当者が気を付けるべきこと
日本企業(又は在英日系企業)側で英国企業と交渉する場面を考えてみると、こちらは国際的な企業(又は英国に拠点をおける企業)ということになるので、対等な立場であるか、こちらが強い立場にあることが多いのではないでしょうか。
そうなると、本件は、契約交渉の担当者にとっては心強い判例になるんじゃないかと思います。
もっとも、今回の判決は、経済的強迫となるような圧力の範囲を明確に示したものではありません。よくある結論ですが、今後の行方を注視する必要がありそうですね。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
【注釈】
*1 Pakistan International Airline Corp v Times Travel (UK) Ltd [2021] UKSC 40
*2 この定義は、O’Sullivan, "The Law of Contract (10th Edn)" (OUP), 279頁から取ってきています。
*3 パキスタン航空はいわゆるナショナル・フラッグ・キャリアで、英国ーパキスタンの唯一の直行便を運営しているようです。
免責事項:
このnoteは、ぼくの個人的な意見を述べるものであり、ぼくの所属先の意見を代表するものではありません。また、法律上その他のアドバイスを目的としたものでもありません。noteの作成・管理には配慮をしていますが、その内容に関する正確性および完全性については、保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
X(Twitter)もやっています。
こちらから、フォローお願いします!
英国法の重要な判例、興味深い判例を紹介しています。
よければ、ご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
