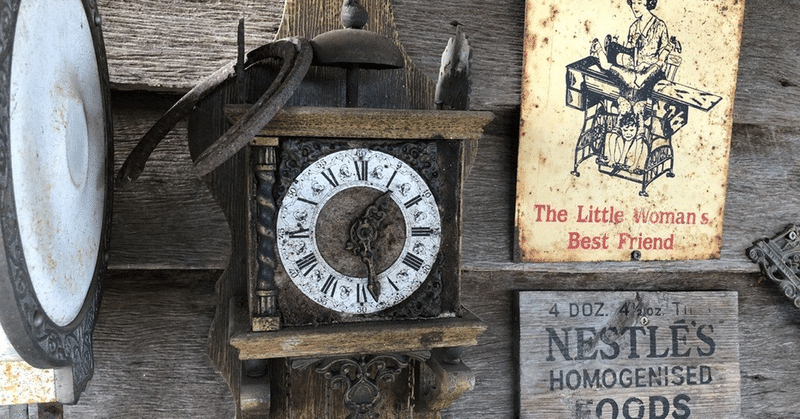
個別指導バイト完全攻略ガイド【3-4】誰でもできる褒め方の方法論
授業に緩急をつけるのに効果的な「褒める」という行為について。
多くの新人バイトの学生さんから質問を受けるので、褒め方の方法論を解説したいと思います。
「褒める」のミッションについて
「褒める」という行為に限りませんが、何かを本当の意味で使いこなせるようになるには、まずその行為のミッションを定義づけする必要があります。
そもそも「褒める」って行為のミッションは何なのでしょう?
僕は「褒める」という行為のミッションを「目の前の生徒が勉強に対して前向きになる」と定義づけています。
「目の前の生徒が勉強に対して前向きになる」、その目的を達成するための手段としてあるのが「褒める」というカード。
まずはここの認識を持つことが大切です。

「褒め」とは「称賛+肯定」でできている
では、次に具体的に褒めるという行為についてですが、僕は「褒める」という行為を、「褒める=称賛と肯定」と定義づけて使っています。
褒めるのが苦手、褒めているのになんとなく子供たちの伝わっていない、または伝わってはいるが具体的な変化や成長にまでつながらない。
こういった状況は「称賛」と「肯定」の二つを明確に意識することで、改善されます。

「称賛」とは目的達成時の褒め、「肯定」とは日ごろの所作やちょっとした部分に対する褒めの事をさし、それぞれ前者は勉強に対するやる気をたきつける事、後者は勉強に対して前向きになることを目的としています。
「肯定」により勉強に対する苦手意識を払しょくし、「称賛」により少しずつやる気にさせて得点につなげることが、僕が目指す「褒め」の手順です。
称賛型の褒めについて
ここからはそれぞれの褒め方の手順について具体的に説明します。
称賛型の褒め方のポイントは次の三つ。
①あらかじめ明確な数値目標で示してあること
②背伸びして頑張ればギリ超えられる数値であること
③達成のための具体的手順が決まっていること
この3つが満たされていない場合、称賛型の褒めは十分に機能しません。
たとえば、テストの点数が良かった時に褒めるという人が多いと思いますが、僕の称賛型の褒めの定義では、試験語にいい点数だから褒めるというのでは不十分で、称賛型の褒めを機能させるのならば、必ず事前に目標点数を設定しておかなければなりません。
漠然と「いい点数だった」→「だから褒められた」では、その場の「嬉しい」という気持ちの創出で終わってしまい、その後のやる気の持続まで落とし込むことが困難になるからです。
「具体的な手順を知った→スモールステップで頑張った→だから目標を突破できた」という一連の過程を称賛することで、それが次の行動のモチベーションになる。
これが称賛型の褒め方のロジックです。
肯定型の褒めについて
次に肯定型の褒めについてです。
肯定型の褒めの目標は通常授業の中で細かな部分を肯定してあげることで、勉強に対して前向きな姿勢にしてあげることが目的です。
肯定型のポイントは次の3つ。
①解釈を変えてあげる
②細かな変化を言語化してあげる
③あなたを受け入れるという安全基地になること
勉強が苦手な子の中には自分が勉強ができないことに後ろめたさのようなものを抱いている子が少なくありません。
そうした子の肯定感をあげてあげるための着眼点が①と②で、それに対して心を開いてもらう前提条件が③の関係づくりです。
解釈というのはその子がネガティブに受け止めていることをポジティブに捉えなおしてあげる肯定方法です。
たとえば「50点しか取れへんかった」という生徒さんがいるなら「50点も取れている」という方向にするみたいな形。
細かな変化を言語化してあげるというのは勉強姿勢や計算過程、入室時間など、少しでもプラスになる部分があったら、それらをしっかり言葉にして「いいね」と伝えてあげること。
これにより、自分の授業という勉強空間そのものがその子にとって心地よいものになるように導くわけです。
そして①と②をしていると、少しずつ「この先生は自分を受け止めてくれる」という信頼関係の構築につながります。
そうした安全基地としての関係性を積むのが③
なわけです。
褒める回数を増やすための方法論
さて、以上で褒め方についてみてきましたが、褒めるという行為には種類と共に頻度が大切になってきます。
皆さんは自分が褒めている回数を数えたことがありますか?
僕は新人バイトの子の研修をする場合、事前に褒めの回数を確認するわけですが、授業がうまい子は圧倒的に褒める頻度が多いことに気づきます。
自分の褒めの回数を数値化して少しずつ増やしていけばそれに近づけるわけですが、バイトの子を見ていると、そもそも褒める言葉を見つけるのが苦手というような子も畳みかけます。
「褒める手数を増やすにはどうしたらよいか」という課題にぶつかるわけです。
これを改善するための僕の方法論が次の公式です。
褒める回数=事象の解像度×解釈の数
褒めるのが苦手な人は十中八九、目の前の出来事に対する注目が薄いか、起こった出来事の受け止め方のパリエーションが少ないかのいずれか。
ここを意識することで褒める回数は増やすことができるわけです。

事象の解像度とは、物事をどれだけ細かく見ているかという部分のこと。
たとえば音楽を聴くときに何となくノリのいい曲くらいで聞いている人と、この歌詞のあのフレーズがいいなと聞いている人では気づきの数が違います。
褒めるのが苦手ということは、現象を前者で受け止めているということです。
例えば、生徒さんの鉛筆の持ち方のクセ、字、姿勢(のめりこみ具合)というようなものに意識を向けられれば、そこに変化が起きたときに気づくことができます。
この変化の気づきは細かく見ているほど多くなるわけです。(そして「変化」さえあれば解釈で褒めることにつなげられる)
解釈の数とは、一つの出来事に対して何パターンの受け止め方ができるかということ。
例えばある生徒さんが的外れな解答をしたときに、「それは違う」と受け止めるのか、「それは違う」に加えて「勇気はすごい!」や「ほんまおもろいな」といった他の受け止め方のバリエーションがあるかということです。
仮に生じた現象の50%を褒める要素と受け止めてアウトプットすることができれば、事象の解像度の2分の1が褒めるタイミングとして機能するようになります。
褒める回数を「事象の解像度×解釈の数」の面積と考えるとき、その両者を意識しつつ伸ばせばいいわけです。
(理想的な褒めの回数に関してのロジックも自分なりにありますが、ここはその教室の色にもよるので割愛します)
今回は自分が「褒める」ということに対して心がけている姿勢を以前バイトの子に話したときのものを文章にしてみました。
需要があれば他の内容も少しずつまとめてみたいなと思うので、よかったらいいね、フォロー宜しくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
