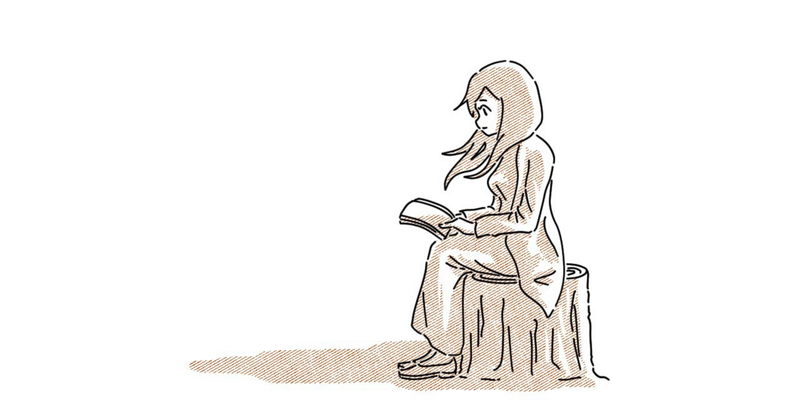
1年目講師向け成績が出るまでの保護者の方との信頼関係の作り方
僕たちが直面する悩みの一つに成績の変化が表れるまでに保護者の方のご理解を得るというというのがあるように思います。
僕たち大人が勉強の構造を分解すると、①苦手分野を見つけ出し、②適切な対策を行えばいいと考えがちで、そのためにKPIを定め、最適な教材と指導を行えばそのミッションは達成できる、と。
もちろん、それを実践するのは子供たちですし、そう簡単にはいきません。
無茶な課題感を設定すれば子供たちに学びそのものに対するトラウマや苦手意識を植え付けかねないし、下手をすれば子どもたちが壊れてしまう。
僕たちは普段その辺を加味しながら指導に当たるわけですが、なかなかその辺の理解が得られないことも少なくありません。
3ステップの変化を用意する
そんな不安をケアしつつ、保護者の方との信頼関係を構築しつつ成績を伸ばしていくための方法論として、僕は短期、中期、長期の変化の指標に次の3つの報告点を用意しています。
短期:物理的な変化の報告
中期:スモールステップの変化の報告
長期:成績と学習姿勢の報告
それぞれ目に見えた変化を予め用意しておくことで、ご家庭との合意形成をしつつ、長期的視座の指導に持っていくために僕はこの辺をかなり意識しています。
短期変化:物理的な変化の報告
ここに関しては指導開始時から3ヶ月程度を見たものになります。
例えば指導開始時のノートの取り方、机上の文房具の配置、鉛筆を持つ癖など、これから受験勉強を始めるにあたって長期的に治しておいた方がいい部分の指摘と修正がここに当たります。(上に挙げた例は中学受験で4年生を想定しました)
例えば、まだ体が小さい小学4年生にとっては、見開きでA3のテキストとB4のノートを広げることですら一動作あたりに負荷があります。
利き腕や姿勢に合わせて机の上の配置をコーディネートする事で勉強から意識が離れる要因を取り除くことにつながる。
僕の場合、こういった観点から初回の授業内でいくつかの項目(下にまとめたいと思います)を確認して、保護者の方に伝え、それをどういう意図でどういった方向に修正するかというご提案をするという形をとります。
こうした部分は本人のやる気等に関係ないため、比較的変化が現れやすくなります。
その変化を見て指導効果を実感していただくというのが僕の考える短期指標の目的です。
初回授業で確認する一例
①机の上の配置
②利き腕と鉛筆の持ち方
③字の大きさとバランス
④文章を読む時の視線移動
⑤プリントのしまい方
⑥資格優位が聴覚優位か
⑦帰納と演繹のどちらが向いているか
中期変化:スモールステップの報告
短期の変化に続いて3ヶ月から半年の指導の実感を得てもらうため、僕は授業にスモールステップが実感できる次の3つの小テストを導入しています。
①授業開始時に行う前回内容を確認するプレテスト
②授業後に行う授業内容の復習のポストテスト
③漢字テスト
もちろん内容定着はそれぞれのテストの目的ののひとつなのですが、それと同時に、半年程度でこれを突破できるという自信をつけてもらうことを、もうひとつ大きな目的地しています。
3つのなかで1番達成しやすいのは授業開始時のプレテスト。
こちらは前の授業の終わりに行った③のテスト内容と類似にしており、それさえ勉強しておけば取れる内容にしています。
少しの見直しで得点できるテストを導入する事で、a.授業前に前回内容を復習するという習慣づけ、b.テストで合格できるというモチベーション喚起、c.今回の単元へのスムーズな導入を目的としており、そこでの点数が上がる事や振り返りの習慣がつくことがこのテストのご家庭への報告ポイントとなります。
これに慣れてきたら次に点数を満たしてもらいたいのがポストテストです。
こちらは授業内容から出題するテストにしてあり、授業を聞いていたかの確認を意図したテストにしています。
半年までの目標はスムーズに満点が取れること。
しっかりと理解できていたという自信づけと、要点の刷り込みなどを目的としています。
最後が漢字テストなのですが、こちらは半年スパンで漢字テストに合格できる勉強量の「相場観」を掴んでもらうことを目的に、予めその趣旨を保護者の方に伝えるようにしています。
具体的には漢字の練習量の把握と事前にご家庭で練習できる漢字の小テストの配布という形をとるのですが、これで講師と本人と保護者の3者で、半年くらいでどれくらいの勉強量で漢字が定着するかの分量を握ることを重視しています。
無理なく毎週3者で試行錯誤する部分でコミュニケーションをとることで結果を実感してもらう仕組みにしています。
以上が中期の変化について僕が取り入れているシステムです。
春(中学入試なら2月)からの指導の場合、ここまでである程度の信頼関係と数字的な変化を積み上げて夏期講習というイメージです。
長期変化:成績の変化の報告
上ふたつで僕は早い段階で信頼関係を構築するように心掛けているのですが、どこまで行っても僕たちがしっかり見なければならないのはこの長期変化です。
ここには①成績の変化と②学習姿勢の変化の二つが該当すると思います。
①に関しては中学入試であればどこまでも月々の模試の結果、中学生以降であれば内申点、定期テスト、模試の3点あたりでしょう。
ここに関して僕は各要素(知識分野・読解分野など)に分けて、どこをどういう筋道で伸ばすというプランを事前にお伝えするようにしています。
漠然とした点数だけで把握されてしまうと、思わぬ不安や漠然とした先入観に振り回されることもあるので、基本的には「○○のパーセンテージがどう変化した」というものをベースに話せる準備をしていきます。
②に関して、僕はいわゆる「授業力」というものはここに該当するのかなあと考えています。
これはa.授業に対する生徒さんの印象、b.ご家庭での課題への向き合い方、c.家庭でどれだけ授業の話が出るかなどがここに当てはまるかと思いますし、それぞれで意図的に行っていることもあるのですが、それは個別指導の作り方の
授業意図編の時に書きたいと思います。
おわりに
もちろん短期、中期、長期のものはそれぞれその場で終わりではなく、こうしたものを螺旋状に積み上げていくイメージです。
こうした仕組みを一旦作っておいて、それらを日々の授業で全基準満たしながら進めていけば、ご家庭の不満は基本的には生じづらくなるというのが僕の方法論です。
(もちろんこんなものベテラン講師の方なら当然と思われるかと思いますが、今回はあくまで一年目の人orバイト講師を想定していますので...)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
