
2023-11-01: 『東京ヒゴロ』と創作者の壮年期について
10月30日に松本大洋先生の連載作『東京ヒゴロ』全3巻が完結した。
隔月刊である『ビッグコミックオリジナル増刊』上で2019年から連載されていた、漫画家と編集者を中心とした日常の物語だ。
私は連載開始当初から、各所で「この漫画はすごい!」と言い続けてきた。身辺の漫画家、アニメ関係者、編集者の方々は異口同音に「確かに面白い」と評価する一方で、「この面白さは、漫画家や編集者以外に伝わる面白さなのだろうか?」という疑義もしばしば呈していた。
たしかに、『東京ヒゴロ』は同様に漫画家を主人公に据えた『バクマン。』(大場つぐみ・小畑健)や『吼えろペン』(島本和彦)、『かくしごと』(久米田康治)のような、ある種戯画化され読者向けの演出を施された作品群とは作風を異にする。
もしかすると、あなたも本作を読んで「話の筋は追えるが、”喰らった”と言えるほど刺さりはしなかった」と感じるかもしれない。
なので、私は本作になぜ『喰らった』のかを、ここに書き残しておこうと思う。ああ、そういう読み方、感じ方もあるのかな、と思っていただければ幸いだ。
漫画家という残酷な職業について
本作は群像劇の形式をとる。
主人公格である漫画家・編集者たちの作品を通じた縦糸の物語に、ゲストキャラクターとなる人物たちによる横糸の物語が交錯していく。
冒頭のあらすじを簡単にまとめる。
ベテラン編集者・塩澤は大手出版社である「小学社」を退職し独立する。
新卒時から漫画愛に溢れた塩澤は、自身が手掛けた漫画雑誌『夜』の商業的失敗に対し責任を取る形で職を辞し、「自らの理想とする漫画雑誌」創刊に奔走しはじめる……という筋書きだ。
塩澤は、かつて辛苦を共にしたベテラン漫画家や引退漫画家たちに連絡を取り、彼らの元へ足を運ぶ。
そこには成功者の姿があれば、他方で跳ぶことすらできなかった者の背中もある。
運良く成功者側に立てた者であっても、生き馬の目を抜くような業界である。プレイヤーであり続ける以上、「あがり」は存在しないのだ。
盤石なキャリアを築いた後も、常に若手を警戒し対抗心を燃やしていた手塚治虫先生のスタンスは「大人げない」と一蹴できるものではなく、そこには「神」すら脅かす業界の残酷さを滲ませる。

残酷と書いたが、実際に漫画家稼業の残酷さを描いた作品がある。
それが永島慎二先生の『漫画家残酷物語』だ。

1952年にデビューした永島先生は本作や『フーテン』で後進に多大な影響を与えるとともに、青年漫画の発展に寄与した。
会話劇的な作風は脱・手塚的(親・つげ的)であり、各話で画風を変える取り組みなどは岡田史子先生などに強い影響をもたらしている。
私見では、『東京ヒゴロ』は令和の『漫画家残酷物語』である。
『漫画家残酷物語』は、政府が経済白書において「もはや戦後ではない」と脱復興時代を宣言し、岩戸景気を背景とした社会発展の中で漫画に取り組む、若い都市生活者らのスケッチである。
『漫画家残酷物語』第1話『うすのろ』は、『東京ヒゴロ』の縮図的掌篇だ。
5人の漫画少年が一様に都会で漫画による立身出世を夢見るも、現実の厳しさに蝕まれていき、失意のうちに夭逝する者、所帯を持ち漫画から離れる者、いつ漫画による生活が行き詰まるか怯えて暮らす者など様々な生き様を晒す。
こうして、彼等の青春の日は過ぎて、一人一人がまた、新たな人生に足を踏み入れて生きることにとらわれ多くを忘れていった。
『うすのろ』には、商業的に成功できなかった漫画家のキャリア類型がカタログのように並ぶ。
『フーテン』同様、そこには高度成長期における都市生活者の哀歌が漂うが、令和の時代においてもこの稼業の本質的な恐怖や敗残の形は維持されている。
漫画家とは残酷である。最も残酷なのは、『漫画家残酷物語』を読んでなお、あだち勉・充先生ら、多くの若き漫画家志望者がこの修羅の門を潜っていったことである。
さて、令和の『東京ヒゴロ』はどうか。
漫画家と編集者
『東京ヒゴロ』が『漫画家残酷物語』と異なる点として、前者は「編集者の物語」でもある。
編集者を主題とした漫画として、松本大洋先生の仮想敵的好敵手であった土田世紀先生の『編集王』や、先日完結した松田奈緒子先生による『重版出来!』がある。
『編集王』も『重版出来!』も、型破りな新人編集者が障害に対峙し乗り越えていくストーリーだ。
他方、『東京ヒゴロ』の編集者に型破りな新人は登場しない。そこには普通の社会人による、普通の生活と静かな挫折・失意が横たわる。
誰よりも漫画を愛する編集者・塩澤は、漫画家から愛され同業者から敵意をないまぜにした畏敬の念を示されている。以下は、塩澤が芽の出ない新人作家・青木のネームをチェックするシーンである。

このようなネームチェックは業界のあらゆる場所で日々行われている。
ネームチェックとは、漫画家と編集者との間で最も重要となるコミュニケーションであり、かつ中間成果物であるネームが「商品」になるかどうかを判断する「命がけの飛躍」的瞬間だ。
ある意味残酷な瞬間であるが、クオリティコントロールが要求される商業漫画である以上このプロセスは基本的に不可欠である。
ちなみに、本文中特別の説明なく言及される「語り」とは以下のような演出を指す。
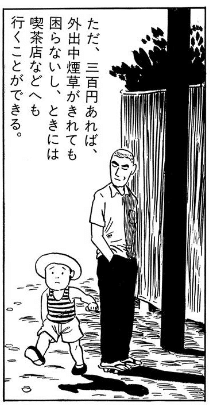
編集者である塩澤は、漫画家やその成果物に対してコメント・フィードバックを行えるが、本質的には「待つ」ことしかできない。
『東京ヒゴロ』は全編を通じて、塩澤ら編集者が「待つ」描写が非常に多い。
一方、編集者らを待たせる「漫画家」たちの姿にも照明が当たっていく。
漫画家たち
『東京ヒゴロ』にはさまざまな漫画家が登場する。
彼らの中には、キャラクターとして極端に戯画化された「漫画家」は、基本的に登場しない。例外として、新人作家・青木のキャラクターはかなり強烈であるが、『Sunny』の春男や『ピンポン』のペコなど、松本漫画の物語推進を担う破天荒な人物の類型だ。

ここでは、主人公格である3人の漫画家を取り上げたい。
彼らは、キャリアとしての漫画家の3つの状態を表現し、各々固有の課題に衝突している。
みやざき長作
長作は行き詰まったベテラン漫画家である。
長年の交流がある塩澤からは、表面的な技巧に走り輝きを失った漫画を描いていると涙ながらに酷評されている。
長作には離婚した妻と娘がおり、両者との関係は良好といえるものの、円満な家庭を育むことには失敗している。
さらに、久米田先生の言う「落ち着いた感じ」の現状を生み出している自身の成果物品質にも苛立ちをつのらせており、家庭と仕事両面におけるミドルエイジクライシスに直面している。
長作がどのように自分自身を恢復していくかが、本作の大きな物語の一つである。

青木収
青木は「今一つ吹っ切れない」新人作家である。
漫画を愛しているものの、ねじれた愛し方と本人の面倒な気質から社会人としては破綻しており、塩澤の後任編集者・林との関係を劣悪化している。
彼は「漫画かくあるべき」「漫画で成功すれば理想的な世界が待っている」というようなバイアスで自縛しており、長作同様、青木がどのように彼自身の殻を脱却し、作家として立脚していくかが本作の主要な物語となっている。

青木の心理的危機は、「到達した場所が想像していたものと違った」という自らの理想に裏切られる形で到来する。
オーバーワークと社会的成功とは、青木に人間としての成長と過度のストレスを与え、彼はメンタルダウンに向かっていく。
客観的に見れば社会的成功の絶頂にいる青木が、実際には判断能力を喪失し、生活者として創作をしていくことの本質的な恐ろしさに気づく展開は、一度ヒット作を打ったり、メディアミックスで世の中に知られた作家にとって経験的に理解できるところではないだろうか。
BUMP OF CHICKENの楽曲に『乗車券』という曲がある。
「乗車券」を持って他人を蹴落としながら「バス」に乗った男が、「バス」の行き先に気づいて途中下車を願うも、もはや「バス」は男のために停まってはくれないという歌詞だ。
あぁ 見逃してくれ 解らないまま乗ってたんだ
俺一人 降ろす為 停まってくれる筈もねえ
商業的な仕事は成功と同時に規模が大きくなり、ステークホルダの数も増えていく。
そこには社会的な責任が発生し、ある日突然「止めたいです」では済まない。
最早自力では止めることができない連載はハムスターの回し車のように速度を上げ、漫画家の体力・気力・意欲を残酷に奪いにかかる。
この状態でなお漫画を書き続けられるかどうかが、プロとアマの境界線になるのかもしれない。
草刈時生
草刈は長作の漫画スタジオの一員であり、自身は連載を持っていない職業アシスタント(プロアシ)だ。2人は師弟関係にある。
草刈の漫画技術は非常に高いものらしく、長作の担当編集も草刈に高い信頼を置いている。また、基本的に他人を見下す傾向がある青木が、塩澤以外に敬意を払っている人物が草刈である。
青木は、草刈が自作に対してどんな評価をしているか、随所で気にかけている描写がある。ここからも、草刈が表面的な作画技術のみならず、青木に刺さるような漫画を描いてきた実績があることがわかる。
長作はしばしば草刈に対して、自身のネームを切ってくるように指導しているが、草刈には暖簾に腕押しである。
草刈は、自宅の机に向かうが、真っ白なネーム用紙を前に手が動かない。

彼は本作の傍観者であり、精神的師弟関係にあり、第一線のプレイヤーである長作と青木の2者を一歩引いた目で見ている。
草刈自身も漫画の実力者でありながら、彼は商業漫画家に必要な要素が、自身から既に喪われてしまったと感じている。
ギリギリの状況下で心身ともにすり減らし、プライベートも破綻させていく長作と青木に対し、デザイナーの彼女と同棲し円満な関係を築いている草刈は、彼らの領域で切磋琢磨できないと確信し始めている。
漫画という仕事に関わることと、「創作者であること」との間には残酷なクレバスが穿たれている。
創作者であるということは「工芸」「芸術」を生業とすることであり、そこでは科学的・工学的な方法論、高度な再現性や決定論的な世界とは異なる、一回性・非方法論的な領域との格闘を回避できない。
草刈は、眼前で燃え盛る我が家を眺め、ただその圧倒的な火力の暴力性に呆然とする家主の気持ちなのではないか。
象徴・隠喩について
『東京ヒゴロ』にはいくつかの象徴・隠喩が登場する。
それは、各巻の表紙に描かれている鳥・リンゴ・傘だ。
鳥
塩澤は一羽の文鳥を飼育している。
この文鳥と塩澤とは自在に会話でき、文鳥の存在は本作における最大のファンタジーとなっている。
文鳥のセリフは塩澤の妄想という表現では描かれておらず、『東京ヒゴロ』内では当然のように文鳥が発話する。
しかし、なぜ喋る文鳥が必要なのか。
塩澤は編集者でありながら、創作者の世界へ片足を踏み込んでいるためだ。
その世界は換言すれば狂気的かつ霊的な世界であり、ネームの霊感をユニコーンとして幻視する老作家や、夢の中で架空の少年と凧揚げをしてしまう青木のように、現実へ浸潤し混ざり合っている。

喋る文鳥の存在は、塩澤の狂気性を表現している。
文鳥と会話する塩澤は「普通の」編集者ではない。
そして、人間に迎合し飼い慣らされた文鳥は、編集者としての塩澤の一部分であり、その外在化であると言えるだろう。
リンゴ
リンゴは2巻で登場する。
雨の中で取り落としたリンゴを拾う草刈。
彼は長作のために購入したリンゴを、夕立が降り注ぐ路上で丸齧りする。
このリンゴは『創世記』の禁断の果実の隠喩だ。
これを口にした草刈は無知を喪失したアダムとイブのように、決定的な契機を迎える。それがどのような結末に至るかは、ぜひ3巻を読んで確認して欲しい。

傘
傘と風雨は本作において反復される象徴である。
第1話で、退職直後の塩澤は手持ちのこうもり傘を風で飛ばされ、紛失している。必然的に塩澤は風雨に晒されることになるわけだが、これは大手出版社を辞めて独立した塩澤の置かれた厳しい状況を暗喩している。

小学社時代、塩澤は人気作家・立花の原稿を受け取り、原稿に自身の傘を被せ、深夜雨の中を印刷所へ駆けた。原稿の締め切りとは換言すれば「印刷所が待機できる限界」であり、これを破れば原稿の後工程に進めなくなるため、紙・電子問わず原稿は落ちる。
塩澤は漫画のためであれば、風雨の中に喜んで身を投げられる人物であるということも、本作序盤で示されている。ここに、塩澤のタフさが認められる。
他方、作家を守るための傘が吹き飛ばされる描写は、出版不況の中独立した塩澤の理想論では現実的に作家を食べさせられない、庇護する力がないという象徴でもある。
終わりに
沈丁花の話など、まだまだ本作について語りたいことはあるが、まずは本作未読の方たちにぜひご一読いただきたいと思っている。
私が本作に”喰らった”理由は、何よりも私が現在進行系でこの「まんが道」を歩いているからであり、何人もの「長作さん」や「青木くん」、「草刈さん」らを見聞きしてきたからだ。
『東京ヒゴロ』を読むとき、『漫画家残酷物語』を読んでいるときに感じる哀愁や恐怖と同じものを私は感じる。
しかしながら、一言で言ってしまえば、本作はシンプルな「ワンスアゲイン」ものとも言える。
ぜひこの曲を聴きながら、雨の日に読んでもらいたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
