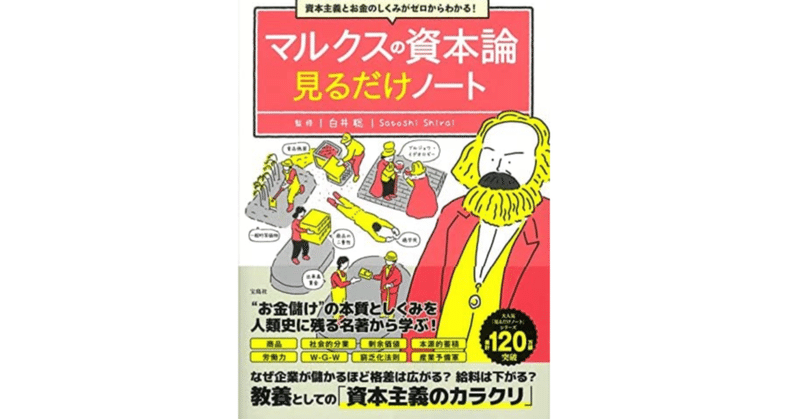
マルクスの資本論見るだけノート
地球のみなさん、資本主義と民主主義社会の中で懸命に生きるみなさん、こんにちは!
偏差値50に届くよう日々積み上げをしている偏差値48の成田悠輔です。
今回は、マルクスの資本論について学びたいと思いましたが、流石に原作を読んだりするのはハードルが高いと思いましたので、有効活用をさせていただいております。累計120万部を突破しました大人気「見るだけノート」シリーズよりマルクスの資本論をお届けしたいと思います。
思想史家、政治学者、京都精華大学教員 白井 聡 さん 監修のとてもわかりやすい、偏差値が低くてもわかる、楽しくわかる本となっております。
1.『資本論』を知ることで、あなたの常識が180度変わる
高校や大学を卒業したらどこかの企業に入り、給料をもらって生活をする。
また、入った企業のために身を粉にして働くことが正しい行いとされ、時間外勤務や休日出勤も厭わないという人も少なからずいると思います。
でも、自分で興した会社ならまだしも、そこまで会社に義理立てする必要はあるのでしょうか?
今からおよそ150年前、「労働者が身を粉にして働くのが正しいことなのか?」と世の中に訴えたのが「マルクスの資本論」です。
労働とはどういうことなのか?
資本主義社会とは何なのか?
「資本論」を読み終えたときあなたの中で何かが変わるはずです。
カール・マルクス
1818年、ドイツ生まれのマルクス。大学卒業後、記者として痛烈な政治批判を行い数々の地で国外への追放を命じられます。
それでも経済学の研究に没頭し、現在でも愛読されている「資本論」を執筆します。

2.資本主義社会は商品と労働で溢れている
資本主義経済の解明は商品を知ることから始まる
マルクスは世の中に溢れる商品の数々を、資本主義経済を構成する主要な要素とみなしました。
資本主義経済下の世の中では、すべての富が商品化されるということです。
これが「資本論」の出発点となります。
マルクスは、商品を分析することが資本主義社会を知るための第一歩であると主張しました。
労働力もまた商品である
賃労働を行うとき、労働者は自分の労働力を商品として資本家に売っていることになります。
労働力も商品である以上、値段が付きます。いわゆる賃金の多寡です。
優れた人材は使用価値が大きく、使用価値が低い労働は、低い値段がつけられます。
↓
労働力も売買される商品
3.商品から誕生した貨幣

布や塩が貨幣のはじまりだった
物と物の交換で成り立っていた時代では、どんな商品とも交換することができるのも貨幣の代わりでした。
貨幣として優位な地位を確立したのは金
その後、貨幣の役割を担うようになったのは金や銀でした。
マルクスは「貨幣形態は、本来一般的等価物の社会的機能に適する商品である」と定義し、大きさに関わらず質が同一であり、量も表しやすく分割や合体が容易であった金や銀が該当すると述べました。
↓
資本主義社会がはじまった
なぜ人は金を欲しがるのか?
お金がたまれば欲しいものがたくさん買え、できることも増えます。だから人はお金を欲しがるのです。
貨幣のもう一つの機能は、価値の保存です。だから貨幣はため込まれる。
貨幣によって価値を保存できるから、多くの人は「貨幣はいくらあってもいい」という気持ちになります。
より多くの金を良くすることをマルクスは「黄金欲」といいました。
貨幣があれば何でもできる!!!
↓
だから人はお金を欲しがる
4.貨幣から誕生した増殖を止められない資本
資本家は資本の人格化
なぜ、資本家は容赦なく労働者を搾取したり、儲けの為に環境を破壊したりするのか?
初めは目標があり、そこに向かっていても、お金が儲かるようになると、真の目的が目標達成からお金儲けに変化してしまう強烈な傾向が資本主義社会にはあります。
↓
いつの間にかお金儲けが目的になる
資本家が労働者を雇うのは剰余価値を得るため
資本家は何のために労働者を雇い商品の生産をおこなうのでしょうか?
1つ目は「使用価値」と「交換価値」を兼ね備えた商品を生産することでより多くの貨幣を得るためです。
2つ目は使用価値と交換価値に加えて「剰余価値」を獲得できる商品を生産するためです。
資本家は、自分で商品をつかうことでもなく、慈善事業することでもなく、利益が出ることを望みます。
資本主義社会において生産過程=価値増殖過程となっていったのです。
剰余価値を得たいがために労働者は搾取される
資本家は、商品を生産するために購入した労働力を給料分以上に働かせます。剰余価値を生み出すためです。
資本家は労働者と10時間労働の契約を結び、給料の半分以上の労働者の働きで生み出された価値を資本家のものにするのです。
労働力の価値<労働生産物の価値という不等式が剰余価値の生産の源泉です。
資本家は労働者を平等だと都合よく考える
マルクスは、労働者の運命を「打ちのめされるほかに、何も期待できないと」語りました。
資本家は労働力によって生み出される剰余価値を、自分の才覚と機械によって生み出されていると捉えがちです。
マルクスは、労働力に関しては不等価交換が行われていると分析しました。
資本家には、剰余価値が労働者の搾取によって生み出されているという認識がまったくなく、ただ労働力と貨幣を等価交換しているだけという認識なのです。
5.資本による労働者の搾取
生産物を所有することができない労働者
マルクスは、労働者の働き方には2つのことが課せられると指摘しました。
それは、「管理」と「所有関係」です。
労働時間中は資本家の管理に従わざるえません。
↓
労働者は常に監視されている
マルクスは「生産物は資本家の所有物であり、労働者の所有物ではない」とも述べています。
生産物を実際に作るのは労働者ですが、生産された商品はあくまで資本家の所有物であり、労働者の所有物にはなりません。
資本は労働者の体の成長や発達までも奪う
過酷な労働を強いられた子供たちは、健康維持が難しいだけでなく、身体の発達にまで影響を及ぼすほどになりました。
マルクスは、満足な教育も受け入れられない子供たちが、夜間労働に駆り出され満足に休息も与えられないといった事例を挙げて「資本は、身体の成長、発達、および健康維持のための時間を強奪する」と指摘しました。
マルクスが生きた時代の資本家が労働者に要求していた労働時間は、1日24時間のうちからわずかな休息時間を差し引いたものでした。
資本家には子供を含む労働者の衰弱・奇形化に直結するような労働を強いていることについて恥じることもありませんでした。
↓
資本家に罪の意識は存在しない

6.資本は労働者だけでなく社会全体と自然からも搾取する
「あとは野となれ山となれ!」が資本家の標語
資本家は労働者の健康や寿命に気を配ることはありません。
資本主義の発達に伴い、労働者の酷使が深刻になりました。
特にイギリスでは人材の消耗が激しく、平均寿命は20歳に満たなかったそうです。
↓
資本家は今を乗り切れればそれでいい
なぜ、資本主義は生産力を飛躍的に増大させたか
どうしても制限されてしまう絶対的剰余価値ではなく、相対的剰余価値の増大をめざして生産力アップへ。
必要労働時間を以下に短縮できるかを考え、工夫することにより剰余の領域を増やすというやり方で得られるものが相対的剰余価値なのです。
↓
相対的剰余価値の増加が資本主義社会のカギ
機械化は、女性や児童に労働をさせる
機械によって女性や児童も仕事ができるようになることで、労働者人口は増加し、賃金も低下へ。
マルクスは、「機械は、搾取の拡大を可能にするために、初めから使われていた」と説いています。
↓
女性や児童も労働が可能に
労働人口の増加で賃金低下
失業者が増えるほど資本家はよろこぶ
失業者が増えれば、増えるほど、産業予備軍の存在が賃金引き上げを制止してくれます。
産業予備軍とは、失業もしくは半失業状態にあって、就業の機会を待つ労働者のことを指します。
罪は機械そのものになく資本家の使い方にある
機械に問題があるのではなく、資本家による資本主義的な技術利用の問題なのだとマルクスは説いたのです。
”刃物で首を切ったからと言って、刃物が悪いわけではない。食卓において包丁は役立ち、外科手術においてメスは役立つ。”
この主張は、刃物を機械に置き換えても同じ事がいえることでしょう。
↓
益となるか害となるかは使い方による
7.資本主義の不合理な構造
大勢の労働者が一緒に働く協業がはじまった
資本主義社会では大規模な工場などがつくられて、大勢の人々が同じ場所で働くようになりました。
マルクスは、たくさんの労働者が同じ生産過程、または関連した複数の生産過程において計画的に協力して働くことを協業と呼びました。
仲間と一緒に働くことでお互いに協力し合ったり、競争心を刺激されたりして、単独で働く以上の力を発揮できるのです。
↓
協業によって人々は力を発揮する
協業で利益を得るのは労働者ではなく資本家
人々の団結力にマルクスはも注目していました。10人が協業したとき、その団結力で10人以上の力が発揮されると考えたのです。
収益が増えても、企業が労働者に支払う給料の金額は以前と同じままです。そのため、資本家はより大きな利益を得るのです。
↓
協業で増えた利益は資本家のもの
単純作業が増えると労働力の価値が低下する
資本主義社会においては分業が増えて、作業は単純化します。
誰でもできる作業なので、賃金が低下してしまうのです。
↓
賃金が高い熟練労働者は仕事を失う
頭が資本主義に侵され資本家の代弁者となる
資本家にとって都合にいいことだらけの資本主義社会。その最たるものがブルジョワ・イデオロギーです。
ブルジョワジーとは有産階級を指す言葉で、わかりやすく言えば資本家です。
資本家が持つ財産は雪だるま式に増えることはあっても、労働者の給料が雪だるま式に増えることはありません。
生まれた時から資本主義社会で育った労働者にとって、こうした資本家の支配は今や当たり前のものとなっています。
↓
資本家の代弁者となる労働者

8.資本主義の行く末は革命である
資本間競争と資本の集中
1つの巨大企業の陰には数多くの倒産した企業があり、ひと握りの資本家による独占が進んでいきます。
マルクスは「常に一人の資本家が多くの資本家を滅ぼす」といっていますが、これまで数多くの資本家や企業が誕生しては、競走に敗れて姿を消していきました。
いくつもあった様々な企業も、生存競争の果てに吸収・合併や倒産などを繰り返し、やがて最終的には1つの巨大な企業が生き残ります。
この過程を独占資本の形成といいます。
マルクスは100年以上前に巨大独占企業の出現を予見していたのです。
↓
世界的独占企業
資本主義の危機
資本主義社会において、恐慌は不可避的現象であるとマルクスは考えました。
マルクスは恐慌の根本原因を、利益を増やそうとする資本家が労働者を低い賃金で働かせることにあると考えました。
↓
恐慌の原因は資本家のせい?
資本主義の最後を告げる鐘が鳴る
資本と労働者の間に格差が広がっていくとプロレタリア革命(※)が起こるとマルクスは考えました。
※プロレタリア革命:プロレタリアート(労働者階級)が農民をはじめとする勤労人民を指導して、ブルジョア(中産階級)の政治権力を打倒し、プロレタリアート独裁を樹立し、資本主義社会から社会主義社会を目指す革命を指すマルクス主義の用語。
資本が少数の資本家に蓄積するとともに労働者階級の窮乏も蓄積され、格差が広がっていきます。
その結果、資本主義的私有の最後を告げる鐘が鳴り、民衆が立ち上がり、少数の独占資本から富を奪い返し、労働者中心の社会が実現するというのです。
↓
資本主義の最期

終わりに
『資本論』第1巻が発刊されたのは1867年のこと。
明治、大正、昭和へと時代が下るにつれて飛躍的に資本主義社会を発展させた日本ですが、マルクスが指摘していたにもかかわらず、長時間労働や過労死問題など、労働に関するさまざまな問題を抱えたまま現在に至っています。
大切なのは「問題を解決すること」ではなく、「問題に気づく」ということです。
少なくともマルクスの「資本論」を知ったあなたなら、売り上げを重視するあまり病気になるまで働いたり、仕事上のストレスで自殺してしまった利子なはずです。
ともあれ、資本主義社会は万能ではなく、矛盾を抱えているんだよということがわかるだけで、生きやすい人生になるのではないでしょうか?
仕事で悩みを抱えてしまった時、どうしようもなく行き詰まってしまった時、是非ともマルクスの資本論を思い出してください。
必ず、あなたを救ってくれることでしょう。
著者 白井聡
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
